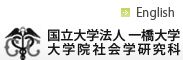研究交流部門
公開レクチャー・シリーズ参加記
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第62回(2025年5月29日)
Fierce Desires: Telling Stories about Sexuality in America
講師:Rebecca Davisさん(デラウェア大学歴史学科教授)
司会: 田中亜以子さん(一橋大学大学院社会学研究科・講師)
参加記
第62回CGraSS公開レクチャーは、デラウェア大学歴史学科教授のレベッカ・L・デイヴィス先生を講師に迎えて開催された。デイヴィス先生は、アメリカにおけるジェンダーやセクシュアリティ、宗教をめぐる歴史に関して幅広く研究をされており、多数の著書・共著書をお持ちである。今回のレクチャーでは、2024年にW. W. Norton社から刊行された近著Fierce Desires: A New History of Sex and Sexuality in Americaの内容に基づいてご講演いただいた。
本講演は、日本のアメリカ学会およびアメリカのOrganization of American Historians(OAH)の後援を受けた。これは、今回のデイヴィス先生の来日が、アメリカ学会とOAHが提携して実施している短期滞在プログラムによるものだったことに関係している。当該プログラムでは、毎年アメリカから研究者を招聘し、アメリカ学会年次大会での発表に加え、2週間の滞在期間中に日本国内の大学で複数回の講演を行っていただくことになっている。今年度は私がこのプログラムのホスト校担当者としてデイヴィス先生をお迎えすることになったため、私の母校である一橋大学のCGraSSでも講演をお願いする運びとなった。
1980年代以降、アメリカではセクシュアリティの歴史を専門とする学会やジャーナルが相次いで創設され、学問分野として発展していった。この草創期にあたる1988年には、アメリカにおけるセクシュアリティの通史を描いた初の概説書であるジョン・デミリオとエステル・B・フリードマン著Intimate Matters: A History of Sexuality in Americaが刊行されている。同書はこれまでに二度の改訂を経て、現在も広く読まれ続けている。以後約30年にわたり、膨大な研究が発表され分野は大きく拡張したが、新たな研究で得られた知見を加え、全体を概観するような概説書は現れなかった。そうした状況のなかで出版されたデイヴィス先生のFierce Desiresは、Intimate Matters以降初めて、アメリカにおけるセクシュアリティ全般の通史に挑んだ野心的な著作であるといえる。
レクチャーでは、ピューリタン(清教徒)などから想起される一般的なイメージに反して、初期アメリカではジェンダーやセクシュアリティに関する取り締まりは比較的緩やかで、寛容な態度が長く続いたことがまず指摘された。しかし、1873年の猥褻物取締法(その成立に尽力したアンソニー・コムストックにちなみ、「コムストック法」と呼ばれている)の制定を皮切りに、連邦政府が人々のセクシュアリティを積極的に規制するようになっていった状況が論じられた。さらに、こうした政府の介入に対して市民たちがどのように抵抗し、性の解放を訴えていったのか、また、その運動に対抗する新たな動きが1960年代末以降にどのように展開していったのか、という点にも議論が及んだ。
続く質疑応答では、フロアから様々な問いが投げかけられた。著書において、なぜ網羅的な叙述ではなく、特定の個人の物語に焦点を当てるという語りのスタイルを選んだのか。アメリカのセクシュアリティのどういった側面が「アメリカ的」だといえるのか。セクシュアリティ史研究における今後の課題は何か。今日のアメリカにおいて、トランスジェンダー、とりわけトランスジェンダーの子どもをめぐる対応が、なぜ主要な争点となっているのか。こうした多様な論点をめぐり、活発な議論が展開された。
2024年11月のアメリカ大統領選挙を見据え、Fierce Desiresはその直前の9月に刊行された。ドナルド・トランプが大統領に再選されれば、アメリカにおけるジェンダーやセクシュアリティをめぐる状況が大幅に悪化する危険があるという危機感のもと、一般読者にも手に取りやすい通史を出版し、議論を広く喚起する意図があったと伺った。
大統領選の結果、第二期トランプ政権が誕生し、その不安は現実のものとなった。この点はレクチャーの終盤でも取り上げられた。2025年1月の就任直後に出された大統領令では、連邦政府は男性と女性という二つの性別のみを認めること、さらに、社会的・文化的な構築物としての「ジェンダー」ではなく生物学的性差を指す「セックス」という用語を使用することを命じている。実際に、連邦関連機関のウェブページからは「ジェンダー」の表記が消え、LGBTQ+の歴史を扱ったページも削除された。こうした状況は、歴史的記録の保存という観点からも非常に由々しき問題である。さらに、中絶へのアクセスはもちろん、避妊の権利さえも先行きが不透明である。女性の生殖に関する権利やLGBTQ+の権利がすでに制限されつつある現状は、アメリカがいまだにコムストックの時代の延長線上にあることを突き付けている。このような時代状況において開催されたデイヴィス先生のレクチャーは、まさに大きな今日的意義を持つものであったといえる。
私は学部3年生時から大学院の博士課程の途中でアメリカに留学するまで貴堂嘉之先生のゼミに所属しており、私が修士課程に在籍していた時期である2007年にCGraSSが設置された。当時、レクチャー・シリーズで様々な分野における最新のジェンダー研究を学べることを毎回楽しみにしていたのを覚えている。留学先のデラウェア大学の博論指導教官であったデイヴィス先生を一橋にお招きし、CGraSSでの講演を実現できたことは私自身にとっても大変感慨深い出来事だった。
また、当日レクチャーに参加してくださった院生のみなさんの熱心さや質問・コメントの鋭さにも大きな刺激を得た。一橋で若い世代の研究者たちが育っていることが頼もしく感じられた。この貴重な場を提供してくださった貴堂先生、田中亜以子先生、牧田義也先生には心より感謝申し上げたい。
(白百合女子大学 文学部英語英文学科准教授 箕輪理美)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第61回(2024年6月28日)
ブックトーク:「戦争ごっこ」の近現代史——児童文化と軍事思想
講師:サビーネ・フリューシュトゥックさん(カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授)
司会: 田中亜以子さん(一橋大学大学院社会学研究科・講師)
参加記
第61回CGraSS公開レクチャー・シリーズは「ブックトーク:「戦争ごっこ」の近現代史——児童文化と軍事思想」と題し、カリフォルニア大学サンタバーバラ校のサビーネ・フリューシュトゥック(Sabine Frühstück)氏にオンライン上でご講演いただいた。フリューシュトゥック氏は近現代日本文化研究がご専門で、ご著書にはUneasy Warriors: Gender, Memory and Popular Culture in the Japanese Army (University of California Press, 2007)やRecreating Japanese Men (University of California Press, 2011)などがある。いずれも『不安な兵士たち』(原書房、2008)や『日本人の「男らしさ」』(明石書店、2013)として邦訳され、日本でも多く読まれている。
今回の講演では昨年、『「戦争ごっこ」の近現代史——児童文化と軍事思想』(人文書院、2023)として邦訳されたご著書の内容に基づき、近現代日本における子どもたちの「戦争ごっこ」を題材に子どもに関するイメージが帝国日本の軍国主義や戦後日本における平和主義に利用されてきたことが論じられた。フリューシュトゥック氏は子どもや兵士の表象に関して、19世紀後半から21世紀に至るまでのさまざまな資料を提示しながら講演されており、子どもと軍隊や戦争との結びつきが視覚的にも明らかにされていた。以下、本講演の内容を三つの点から紹介する。
(1)子どものイメージとその軍事利用
従来の子どもと戦争・軍隊に関する研究も大きく以下の三つの議論に焦点を当ててきた。つまり①子どもは戦争の被害者か加害者か、という議論、②近代戦争における子どもに関するプロパガンダとその評価、そして③子どもと軍隊および戦争の間の微妙な関係が終戦直後に消滅すること、という三点である。しかしフリューシュトゥック氏によれば、本書の目的はこうした研究史に対し、日本における子どもと戦争に関する議論に変化をもたらすため、全く別の視点を提示することにあるという。
そもそも近代国家建設以来、日本の軍隊と教育制度は子どもを絶えず再定義してきた。教育の専門家たちは古くから子どもの健康や発達、権利、そして子どもと大人や青年期の関係を研究し続け、また明治政府の学制と徴兵令は幼年期と戦争、子どもと軍事というかつては別々に考えられていた領域を長年にわたって結びつけてきた。特に1945年に第二次世界大戦が終わるまで、子どもは国家の大規模な暴力を正当化するために利用されてきた。「純粋で弱く、政治的に左右されない存在」としての子どもイメージの動員によって、大人を戦争に動員することが図られたのである。そのなかで、あるときには「子どもは誰もがすでに兵士なのだ」とされ、別の文脈では「子どもは生まれながらに平和をもたらすもの」とされた。
こうした背景から、フリューシュトゥック氏は本書で以下の三点を主張する。つまり、①子どもが傷つきやすく、無邪気で道徳的に純粋だという考え方は、近代の戦争に関する態度に重大な政治的影響を及ぼしたイデオロギーの産物であるということ、②こうした考え方は近代日本の軍国主義に利用され、逆説的に1945年以降の平和主義にも継続的に利用されてきたということ、そして③プロパガンダや教化は権威主義的な戦時体制の専売特許ではないということである。特に帝国日本では、上述のような近代的な子ども観が権威主義的で帝国主義的な政治体制や商業主義に利用され、「子どもはつねにすでに兵士であり、かつ生得的に純真で道徳的に純粋な脆い生き物」とみなされて帝国建設と戦争遂行の中心に据えられた。こうして子どもに対する感情的・倫理的な反応が戦略的に形成され、利用されてきたのである。これは一方では子どもを教化・犠牲化・抑圧するための出版物や玩具という形で、また他方では戦争ごっこという形で立ち現れた。しかしながら、1945年以降は、民主化しつつあった国家や企業において、近代の子どもと幼年期への見方が平和のために一新され、今度は自衛隊とその活動を正当化するのに利用されたのであった。
(2)子どもたちの戦争ごっこと大人の認識
本書前半部では、日本の子どもたちの戦争ごっこをめぐる表象や言説が詳しく分析されている。19世紀後半から1945年以降へと、大人たちは戦争ごっこに対する見方や認識を頻繁に変化させてきた。最初に幼年期の専門家たちがごっこ遊びの教育的価値について論じ始めたのは19世紀末であった。これが20世紀になると遊びを通じて学ぶことが子どもたちの喜びと大人の生活の準備につながるという観念が一般的になる。ここでは子どもの遊び心は自然と戦争ごっこに向かうものとされた。この延長線上として、戦争ごっこが多くの子どもに受け入れられるのと同様、戦争を受け入れることは人間の本質に深く根ざしているのだと主張するため、近代的な子ども観が無理やりに利用された。こうした中で、戦争ごっこの危険性を危惧する大人もいれば、中には規範や大人の管理を拒否する手に負えない子どもを訓練する方法として戦争ごっこを歓迎する大人もいた。後者のような人々は子どもが健康で社会的な大人になるため、また特に少年であれば兵士になるために彼らのエネルギーを方向づける上で、戦争ごっこが適していると考えていたのである。フリューシュトゥック氏によればこの時期はある種の節目にあたり、日本の軍事組織と国家が子どもを管理し、何が子どもの成長を導くべきかを決定することに最も深く関わった瞬間であったという。
こうした戦争ごっこに関する言説の歴史的変遷を分析する上で、フリューシュトゥック氏は幕末から第二次世界大戦後までの期間における事例を用いて実証的に議論を進めている。幕末の戦争ごっこの事例では、「日本軍」チームと「アメリカ軍」チームの戦いが過熱した結果、「日本軍」のリーダーだった少年が「アメリカ軍」のリーダーを殺害するに至った。それでも奉行所は「日本軍」の少年が日本の敵国、アメリカを打ち負かしたと捉え、加害児童に同情的な判決を下したという。一方、西南戦争期の新聞を見ると、1877年には戦争ごっこの危険性を指摘され、止めさせたいと書かれている。しかし日清・日露戦争期に入ると、軍事教練とともに戦争ごっこが教育の場に浸透していった。フリューシュトゥック氏は特にジョルジュ・ビゴーの風刺画や子ども向け雑誌の図像資料などを豊富に用いて、当時の戦争ごっこの様子を示していた。しかしながら戦後の占領期には、またもや戦争ごっこは否定的に捉えられる。1955年の新聞に載った「こどもたちが立派な人間に成長するような平和な明るい遊びを教える努力と指導が、大人たちの責任である」という投書が、このことをよく物語っている。こうして、さまざまな出版物に戦争ごっこの表象が現れており、時代によってその捉え方も変化していたことが明らかにされた。
(3)子どもの表象と兵士の表象
本書後半では、戦争ごっこの表象から兵士の表象へと分析の対象が移される。なぜなら、兵士のすぐそばに子どもを配置した図像が多く見られるように、子どものイメージと兵士のイメージは密接に結びついているからである。20世紀初頭の子ども向け製品や子どもの描いた絵をみると、そこには子ども文化の商業化がはっきりと現れている。この時期には子どものイメージが軍国主義の中で頻繁に用いられ、これに対応するように兵士は子どもの救済者、もしくは子どもの遊び相手になる幼児化された存在として表象されるようになる。つまり、戦争という近代の大規模な国家暴力と、傷つきやすさ・無邪気さ・純粋さ・道徳的権威という子どもに想定された特性との間の矛盾が表象の次元で無効化され、子どもと軍隊や兵士のつながりが視覚的に明示されたのである。
フリューシュトゥック氏はこうした子どもに与えられた特性を「感情資本(emotional capital)」という概念を用いて分析する。「感情資本」とは、子ども自身や子どものもの、そして子どもらしさと紐付けられた特性から生まれる資本を指す。この感情資本は軍国主義の中において菓子の広告から戦場における写真に至るまで、多くの表象の中で利用された。家の外でぶつかり合う戦争は、兵士と子どもを商業主義の中で表象することによって、家の中に持ち込まれたのである。
このように帝国日本では「傷つきやすく無邪気で純粋な幼年期」という子どものイメージが軍国主義的に利用されてきた。しかし、1950年代に連合国の占領が終わり、自衛隊が発足すると、子どものイメージは自衛隊の任務を正当化するために違った形で再利用されるようになる。そして21世紀に入ると、子どもや子ども文化がますます自衛隊に道徳的な権威を提供するようになってきた。自衛隊の広報資料は自衛隊の活動が厳密な意味で人道主義的であることを、子どもを利用して強調している。今日、世界的に見られる兵士のすぐそばに子どもを配置するような表象は、戦争と平和の境界をなくして軍事的暴力と非戦闘的軍事作戦との区別を曖昧にするために利用されている。この結果、暴力・破壊と救助・平和構築に関する認識および両者の区別は混乱したものになっている。こうした状況を、フリューシュトゥック氏は「比喩的な子どもの再動員」と表現する。つまり、現実における動員と異なって、子どものイメージに言及することで子どもを軍事的に利用しているのである。
しかし、日本の自衛隊における「比喩的な子どもの動員」には独自の特徴がある。たとえば自衛隊の募集ポスターで女性隊員二人がランドセルに類似した鞄を背負って小学生のような姿で描かれているなど、日本の自衛隊は子どもを少女としてジェンダー化し、少女を性的対象化して表象することによって、自衛隊の仕事が楽しく暴力的でないことをアピールしているのだ。本来「感情資本」の議論では子どものイメージを特定のジェンダーと結びつけることは想定されていない。にもかかわらず、現代日本の自衛隊ではポピュラーカルチャーの影響を強く受けて、子どもや兵士の姿を少女化・性的対象化しているのである。
世界的に見れば、各国の軍事組織は子どものイメージを使って国家の大規模な暴力を人道主義的な努力として描こうとしている。そして戦争の正当性や必要性、不可避性を確認するために戦争を承認し、子どもと幼年期を生まれつき自然で普遍的なものとする近代的観念を再強化してきた。そうして世界中の軍隊で作られた子どものイメージやレトリックは、戦争と平和を道徳的で感傷的なものにするため、子どもを利用してきたのである。これらの表象は軍隊の広報活動やメディアで取り上げられることで、軍事活動とそれ以外のものの境界を曖昧にし、戦争を人道主義的な任務に見えるように幼児化し、不可避で継続的な人間の活動に変えている。「比喩的な子どもの動員」により、最終的には平和の価値が矮小化され、平和の達成が不可能にさえなってしまうのではないかと、フリューシュトゥック氏は危機感を表して講演を閉じた。
以下、筆者によるコメント。フリューシュトゥック氏は19世紀末から20世紀半ばまでの日本の資料を豊富に提示された上、日本語で講演してくださった。こうしてアメリカ合衆国を拠点とする研究者が日本に向けて投げかける問いは、日本社会に暮らす私たちがあまり注目してこなかった状況に再検討を促すものであった。たとえばフリューシュトゥック氏が講演の中で示したうち特に印象的だった資料に、防衛省制作の広報アニメーション「ボーエもんの防衛だもん〜よくわかる自衛隊〜」というものがあった(2015年に公開され、今でも防衛省のYouTubeチャンネルで視聴可能である)。フリューシュトゥック氏が指摘するように、ここでは自衛隊の任務が「本質的に人道的で平和的」であることを強調するため、子どもや子どものようなキャラクターが利用されている。そして、多産の礼賛や国防と家庭内での役割を結びつけるような発言(「子どもたちのために日本を守り抜く」など)といった保守的な言説が顕著に示されている。このような自衛隊のリクルーティングにおける思想的な実態は一般社会に現れにくく、軍事的な領域に積極的に関与しない限り見えにくい部分であろう。こうした日本の現状を歴史から照射する研究は非常に勇気がいるように思える。しかし、フリューシュトゥック氏はこのような研究を現代における平和への危機感と使命感に基づいて進められている。こうした姿勢はかつて本研究所でも講演を行なった、シンシア・エンロー氏が言うところのフェミニスト的好奇心(feminist curiosity)に近いものがあると、筆者には感じられた。エンロー氏によれば、フェミニスト的好奇心とは「みんなが当たり前だと思っていることに疑問をさしはさむ」という「政治的な行為」を通じて、「女性たちの置かれた状況、女性同士の関係、女性と男性の関係について探求する」営みである(エンロー:2004年、3-4頁)。フリューシュトゥック氏の研究も、まさにこうした営みに類するものである。つまり、日本社会の中で自明視された子供と軍隊、自衛隊の女性表象などに切り込む研究によって、政治的な問いが提起されている。こうした点にこそ、フリューシュトゥック氏の研究の大きな意義があるのではないかと考えた。
参考文献
〈国際ジェンダー研究〉編集委員会編、シンシア・エンロー著『シリーズ〈国際ジェンダー研究〉③ フェミニズムで探る軍事化と国際政治』御茶の水書房、2004年。
(一橋大学社会学研究科 修士課程 内川創達)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第60回(2024年5月29日)
新自由主義社会におけるケア 女性間の経験の共通性・格差・連続性
講師:山根純佳さん(実践女子大学 人間社会学部 教授)
司会: 佐藤文香さん(一橋大学大学院社会学研究科 教授)
参加記
第60回CGraSS 公開レクチャー、山根純佳さんによる「新自由主義社会におけるケア 女性間の経験の共通性・連続性・格差」は、一橋大学キャンパスで対面開催された。新型コロナがインフルエンザと同様の扱いになりひさしぶりに対面で開催された会場には多くの来場者があり、あらかじめ準備された座席だけでは足りず椅子を補充したのちに始まった。
山根純佳さんは2000年、ワーカーズ・コレクティブの共同研究に上野千鶴子さんと共に参加し、2011年東日本大震災の発災時は赴任先の山形大学で「原発事故による「母子避難」問題とその支援—山形県における避難者調査のデータから」(山形大学人文学部 2013)を執筆なさった。2023年には「新自由主義とケア労働」(大原社会問題研究所雑誌 771号 2023年1月号)を発表、介護保険のヘルパー国家賠償訴訟の証人尋問で介護保険制度の問題点を意見陳述した。2024年の7月には、山根さんが第6章「ケアの再公共化とフェミニズムの政治—福祉国家・ケア・新自由主義」を執筆なさった書籍(『挑戦するフェミニズム-ネオリベラリズムとグローバリゼーションを超えて』有斐閣)が刊行予定だ。
今回山根さんの講義をはじめて聞かせていただくことをとても楽しみにしていた。レクチャーの内容のすべてを紹介することは難しいので、わたしが特に引きこまれた論点について感想を交えながらご紹介したい。
◯「ケアをめぐるジェンダー規範」は「女性の経験」として、いまなお残されている 「うまくやらない」女性を非難する社会」
第2波フェミニズムは、私的領域において不可視化されてきた女性の無償労働(再生産労働、ケア労働)が、女性抑圧の物質的基盤であることを明らかにした。その後、女性の労働力化がすすみ、女性が家事と仕事を両立できるように国家は政策整備を進め、移住者へのアウトソーシングが可能になった。ケアの社会化や市場化は進み、女性の選択肢は増えて「女性間の差異」は広がり「格差」が生じたといわれている。
しかし、「女性ならケアできるはず、女性ならケアしているはず、男性はケアできなくて当然」といった「ケアをめぐるジェンダー規範」はいまだに女性に共通する経験として強固に残っている、と山根さんは指摘した。
良妻賢母や銃後の母、介護する嫁といった、無償で働く女性ケア要員は、近代国民国家の成立には必要不可欠だった。無償で働くケア要員女性たちをほめたたえる社会の裏側には、「うまくやらない」女性を非難する社会が存在している。放射能汚染を恐れて福島から他県に母子避難した母親や、子どもを産まない女性をあしざまに言う社会は、ジェンダー規範を逸脱している人を非難してよいとみなしている。
◯ケア・エシックス、ケアの道徳的価値は、ケアの「うまくいかなさ」を説明しない
山根さんの研究は、ケア・エシックスの方法論や、ケアの道徳的価値からはアプローチしない。その理由について山根さんは、ケアの道徳的価値はなぜケアが「うまくいかない」のかを説明していないから、とおっしゃった。この指摘にわたしは驚いた。というのは、わたしは子育て中、いつも貧血で、息切れがして、思考力は落ち、元気すぎる子どもを制御するばかりで、子育てがうまくいかないもどかしさを言語化できなかった。そして1日1日をこなすように生き、子育てに悩み落ち込んだ時には、思いやりや優しさを思い出す本をながめ、ほんわかした癒しムードに一時ひたり、よい母親になる気持ちを盛り上げリセットしていたように思う。「うまくいかない」原因を子どもにフォーカスし虐待しないよう、耐え忍び、気を紛らわし、道徳心を呼びさます、そんな対処しかできていなかった。
しかし山根さんは、ケア責任に由来する葛藤状況を「道徳的な個人」の物語に還元する限り、「ケアする人を追い詰める規範や、必要な資源は特定できない」し、「社会のどこを変えるべきなのかは明らかにならない」とおっしゃる。
そうだよ。ケアがうまくいかなかった原因は、わたしのせいだけじゃない。産んで育ててニコニコしてろ、イライラしないで働いて、ワンオペ育児うまくいかなくても、気分リセット!いい母演じろ!の対処法では、もはやケア責任に由来する葛藤状況は乗り越えられない。何がどこに必要なのか、社会のどこを変えればよいのか。
◯新自由主義とケアの危機 ケア責任と、ケア責任を果たせない罪悪感を、もたないですんでいる自由な男性の存在
新自由主義のもとで福祉国家はケアの供給を縮小した。ケアは市場化され公的な責任は縮小された。この論点についてフェミニズムではどのように議論されてきたのか、振り返りの時をわたしたちは迎えているようだ。新自由主義とケアの危機については、上野千鶴子さん、江原由美子さんの新刊で触れられているとのことなので、そちらを読んでみようと思う。
そしてもう一つ、以下の重要な論点がある。なぜ男性はケア責任や罪悪感から自由でいられるのか。女性たちは「女性ならできるはず、母親ならできるはず」と「ケアをめぐるジェンダー規範」を押し付けられているのに。
個人的な話になるが、子育て中は自ら「ジェンダー規範」にハマっていたわたしはその後目覚め、いわゆる “嫁介護” をすることはお断りした。夫の母と仲が悪かったということではなく、夫や夫の兄は正規雇用、わたしはフリーランス職の身分であることを理由に、“嫁介護” を請け負うのは違うと考えていた。ケアをめぐり思案し、人として成長する、その貴重な経験を、男性だからといってしないですまさないでほしい。ケア責任者として、ケアの大変さ、うまくいかなさ、もどかしさ、人に伝わらない困難さを、男性が経験すると、どのようなことが彼らの口から語られるのか聞いてみたい。わたしが「女性の経験」を男性に伝えようとした時には、言葉を尽くしても届かない、まるで糠に釘のようなやるせなさが残った。「男性のケア経験」はどのように言語化され、女性に届くのだろうか。わたしはまず身近なところでケアをめぐる「男性の経験」を聞きとってみようと思う。
◯ニーズと資源の配分 ケアをめぐる権力と不平等
「ニーズと資源の配分 ケアをめぐる権力と不平等」で思い出したことがある。日本ではコロナ禍、大規模な介護事業所は訪問看護を次々に打ち切った。それを肩代わりし、感染リスクの高い利用者のケアを押し付けられる形で担ったのは、民間の小規模な訪問介護事業所だった。それに加えいったい何の差別かと怒りが湧くのだが、厚労省は大規模な介護事業所の職員たちにはワクチンの早期接種を優先したのに対して、小規模事業所の職員たちには優先枠を設けなかった。小規模事業所の職員たちは一般市民と同時期までワクチン接種を待たされたというのだ。これはまさしくケアをめぐる権力と不平等ではないだろうか。
また、障害児をケアする高齢の母親、子育て中のシングルマザーたち、発達障害の子を育てる母親への研究者によるインタビューからは、言ってもわかってもらえないからと諦めてしまう母親たちの絶望が伝わってくる。ふと、むかし子どもが通っていた保育園の親仲間のことを思い出した。若くして病気で亡くなった方もいた。シングルで障害児を育てていた人、こどもが発達障害かもしれないと療育をすすめられ戸惑っていた人、モラハラ夫から逃げ離婚を選んだ人。彼女たちは今どうしているだろう。わたしは彼女たちの話を聞くことしかできなかった。彼女たちのニーズは承認され、資源は十分に再分配されただろうか。資源の少ない女性たちのニーズが無視され、女性たちの間が断絶されていいわけがない。
◯ニーズ解釈をめぐる政治と権力 研究者の責任
最後に山根さんは、研究者は何を論じるかではなく、どのように論じるべきかが大切なのだとおっしゃった。
研究者は「学識経験者」として政策に対して発言力を持つ。ニーズ解釈の政治に参加する研究者の責任について山根さんは語られた。今回教室でともにレクチャーを聞いた学生さんたちの中から、ニーズ解釈の政治に参加する「学識経験者」が生まれるかもしれない。そう思うとワクワクする。わたしのような一般市民にとっては、学者や研究者がケアワークの大変さを言語化し可視化してくださるのはとてもありがたいことなのだ。
レクチャー終了後は知り合いと場所を移してグラスを傾けながらケアについて感想を語り合えたのも、リアル開催ならではの良い時間となった。
公開レクチャーをご準備くださった山根純佳さんとCGraSS関係者の皆さまに、心からの感謝を申し上げたい。ありがとうございました。
(WAN ウイメンズアクションネットワーク 鳩たけこ)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第59回(2023年12月23日)
Slavery and Gender in Nineteenth Century Brazil(19世紀ブラジルの奴隷制とジェンダー)
講師:Maria Helena Pereira Toledo Machadoさん(サンパウロ大学歴史学部・教授)
司会: 貴堂嘉之さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
第59回CGraSS公開レクチャー・シリーズでは、「19世紀ブラジルの奴隷制とジェンダー Slavery and Gender in Nineteenth Brazil」と題し、ブラジルから来日された、サンパウロ大学歴史学部教授のマリア・エレーナさんにご講演いただいた。エレーナ氏はブラジル・アメリカ大陸の奴隷制の社会史がご専門で、奴隷化された女性のライフストーリーを扱った今年刊行予定の著書Geminiana and Her Children. A History of Slavery and Death: Maternity and Childhood in 19th Century Brazil(Bazar do Tempo, 2024)や、編著Brazil through the Eyes of William James(Harvard University Press, 2006)のほか、Crime e Escravidão. Trabalho, Luta e Resistência nas Lavouras Paulistas. 1830-1888(2014)など多数のポルトガル語の著書がある。
ブラジルは大西洋奴隷貿易の地域別統計では最多の奴隷制を受け入れ、南北アメリカ大陸で最後まで奴隷制度が残った国であり、奴隷制研究ではきわめて重要な研究対象である。本講演では、ブラジル奴隷制研究をけん引する専門家のエレーナ氏にブラジルでの最新動向や、奴隷化された人々(enslaved people)の家族や女性、再生産などジェンダーの視点から奴隷制の社会史を論じていただいた。
今回の講演では、今年刊行予定の著書Geminiana and Her Children. A History of Slavery and Death: Maternity and Childhood in 19th Century Brazil(Bazar do Tempo, 2024, in press)の内容をもとに、奴隷化された母親とその子どもたちの社会史が紹介された。エレーナ氏は、1876年に自由身分となった、奴隷化された女性Geminianaと、奴隷制社会で無残な死に追いやられた娘と息子のライフストーリーを、800ページにおよぶ刑事事件としての資料と家族関連の補完資料から解き明かし、黒人女性たちの歴史的主体を浮かび上がらせた。本研究は、沈黙させられてきた人々の世界を警察関連資料から解き明かし、奴隷制研究において長らく軽視されてきたジェンダーの視点からの新たな展望への道筋を開いたものである。本講演で紹介された研究内容を、以下4部に分けて紹介する。
(1)奴隷制下で「母親であること」
「奴隷制の永続を考える上で、『母親であること』(motherhood)の重要性を理解するのは難しくないことだが、ブラジルの学者たちがこの事実を認識するのには非常に長い時間がかかった」。エレーナ氏は冒頭、ブラジルの大西洋奴隷制研究における「奴隷化された母親」や「黒人女性」がこれまで「奴隷化された人々」というカテゴリーに一括りにされ、ジェンダーの視点が反映されていなかったことを言及した。その上で、奴隷化された女性にとって、妻であり母であることはかなりの困難を伴うものであったと続けた。奴隷制下での妊娠、出産、授乳、育児などの身体的健康へのリスクに加え、結婚と出産は、女性が「二重のシフト」を行い、奴隷商人と夫の「二重の服従」に苛まれることも意味する。そのため、奴隷制において「母親であること」や母親が果たした役割に焦点を当てるためには、奴隷化された男性と女性が異なる場所から奴隷制を経験し、異なるレベルの抑圧と苦痛を受けたという事実を考慮しなければならないと、エレーナ氏は研究の意義を強調した。
大西洋奴隷貿易でアフリカ大陸から南北アメリカ大陸へ強制連行された1200万人の約4割の480万人がブラジルへ渡った。ブラジル社会の奴隷制廃止は南北アメリカで最も遅い1888年で、400年近く奴隷制が存続したことになる。それが故に、奴隷制は今日のブラジル国内の不平等や人種差別にもつながっているという。
Geminianaのライフストーリーに入る前に、エレーナ氏は大西洋奴隷社会全体での大原則「partus sequitur ventrem」(生まれるものは子宮に従う)を説明した。これは古代ローマ法から継承された揺るぎない不変の原則で、奴隷化された女性の身体が奴隷制の核心をなしていた。この原則によって、奴隷制社会は奴隷化された女性を「人間の生産者」と「人間以外の資本の生産者」という二重の役割に置くことで、奴隷化された女性の身体の中心性を強調することとなった。また、奴隷主は常に富を生み出すための戦略に「生殖」(Reproduction)を織り込んでいたという。
「奴隷化された女性たちは、奴隷制下でどのようにして『母親であろうとした』のだろうか?」。この問いに答え、奴隷化された女性を歴史的主体として浮かび上がらせようとしても、アーカイブや史料が「沈黙」しており、多くの制約があるため、これに答えることは非常に難しいと、エレーナ氏は語った。
以上のような背景から、1876年に自由身分となり、娘と息子を無残な死に追いやられた女性Geminianaのライフストーリーは、語る価値があるという。エレーナ氏は刑事記録の資料や家族関連の補完資料から、Geminianaの「歴史的主体」を浮かび上げ、これまで沈黙させられてきた人々の世界を、本研究によって明らかにしていった。
(2)Geminianaに起きた無残な事件と刑事記録文書
Geminianaは1840年ごろに生まれ、ブラジル全土で最も暴力的な奴隷制度を築いていたマラニョン州内陸部のサトウキビ工場で育った。先住民を捕らえ、奴隷として拘束されたアフリカ人が働く巨大な製糖工場を設立して富を築いたアイルランド系家族、ベルフォール家で奴隷とされた。母親のSimpliciaと妹と、奴隷にされた100人ほどの人々とともに暮らしていたが、ベルフォール家の娘の一人が結婚した時、Geminianaは奴隷主家族によって、娘の「持参金」の一部として新婚夫婦に差し出された。
Geminianaはその後、2人の娘と2人の息子を出産したが、娘の1人は幼くして亡くなった。ブラジルの奴隷制社会では1869 年まで、15歳未満の母子を別々に売買することが可能だった。1871年の自由子宮法(Free Womb Law)は、奴隷化された女性から生まれた子供を解放し、8歳から21歳までは奴隷商人または国の保護下に置くと法律であったため、再び母子を分離させ、母親は子供を奴隷主の手中に置き去りにせざるを得なかった。多くの母親にとって、この法律は別離の苦痛と苦悩をもたらした。
奴隷主が亡くなった後、奴隷主家族の遺産は親戚の手に渡った。そして親戚は1876年、奴隷化された人々の一部を売却することを決め、サン・ルイス市場に査定に出し、リストに載せた。そのリストの中にはGeminianaと3人の子供も含まれていた。彼女がどのようにしてお金を調達したかを説明する記録がないが、Geminianaは裁判所に代金を預けることができ、彼女自身の奴隷解放を可能にさせた。しかし、Geminianaは3人の子供を奴隷として残さなければならず、娘Isaura(12歳)は、サン・ルイスの裕福な家に売られた。息子Inocencio(8歳)と Jacinto(6歳)は数カ月間売りに出された後、残酷な奴隷商人の手に渡された。そして、数カ月経った後に拷問され、殺されてしまった。
Geminianaがどれほど心を痛めたかは分からない。奴隷にされた女性とその家族の人生を研究する場合、記録文書がないことはよくあることで、史料の中の「影として残ること」があまりに多い。しかし、この無残な事件の場合は非常に珍しく、事件後に800ページにも及んで記入された刑事記録が残されていた。そしてその記録文書は、2人の死に直面した母親のGeminianaと祖母Simpliciaの感情や反応について、いくつかの手がかりを与えることになる。さらに残された史料には、奴隷制度下の人種差別的な社会で最も貧しかった層であるGeminianaが、子供たちの殺害に対してどのように抗議し、地元で力を持つ家族の権力にいかに挑戦したかを示してくれるというのだ。
(3)息子の死への抗議
Geminianaは息子たちの死をどのように知り、いかに抗議したのだろうか。
1876年、Geminianaは自身の奴隷解放後に雇われ労働者として生計を立てていた。ある日、子供用の小さなサイズの棺桶を運ぶ4人の男たちに出会った。男たちは喪主で、奴隷化された人々だった。Geminianaは男たちにどこから来たのかを訪ね、すぐにそれが息子Inocencio(8歳)であることが分かった。Geminianaは喪主に棺桶を開けるように頼み、一度は拒まれたが、「生前息子を見ることを拒否されたのだから、死後も拒否されたくない」と抗議し、棺桶を開けた。死んだInocencioの姿を見て、Geminianaと祖母Simpliciaは絶望の淵に立たされた。Inocencioの体には手首に縄で縛られたような火傷の痕があり、鞭打ちや殴打の傷跡、腕や背中、膝に多くの損傷が見られた。
しかし、奴隷主家族はこの「不都合」を葬り去ろうとしていた。奴隷主家族は奴隷化された少年の死を隠蔽されるべき厄介ごとの一つに過ぎないと思っていたのだ。
Inocencioの死後、奴隷主家族は医師を呼び、彼が自然死したことを証明する死亡診断書を書かせた。医師も隠蔽に加担し、非倫理的な処置を行った。奴隷主家族は使用人を呼び出し、形式的な儀式だけを許可し、人目を避けて午前6時に、鍵のかかった棺桶に入れ、急いで埋葬するように指示した。Inocencioと一緒にこの奴隷主家族のもとに売られたJacinto(6歳)は、実はInocencioの少し前にすでに謎の死を遂げていた。奴隷主家族は短期間のうちに自分の家で2人の奴隷の子供が死んだことで、何か影響が出ないかを心配していた。しかし、莫大な綿花プランテーションで得た富は、2人の奴隷の少年の死よりも何倍も重く、幼い2人の命は全く持って軽視されていたといえる。
息子Inocencioの死後、少年の不審な死と凶悪な事件に噂で広がり、医師と薬剤師による検視が行われた。墓地の小部屋に群衆が詰めかけ、上流階級の加害者に対して奴隷化された人々が憤慨。加害者は残虐行為を隠蔽することが不可能となった。
(4)「沈黙させられた者」の声や感情
エレーナ氏は最後に、このように残された資料を通じて、刑事記録と形式的な言葉、法的手続きの下に隠された母親の声や感情、母親が子供たちを失うことにどのように向き合っていたかについて垣間見ることができると話した。この事件が公式文書に記録されていることで、通常は歴史的資料が否定していることを想像し、推測することができるようになる。GeminianaやSimpliciaの経験を通じて、その他の「沈黙させられた者」たちの声や感情、そして卑劣な人生についても思いをはせ、想像できるようになるとし、講演を閉じた。
(5)論点整理
講演後、司会の貴堂先生より論点整理がなされた。第一に、奴隷にされた人々(男性、女性、子ども)の社会史、沈黙させられてきた人々の世界を警察関連資料から解き明かし、黒人女性たちの歴史的主体を浮かび上がらせる(=奴隷制社会での抵抗の諸相)ため、長らく軽視されてきたジェンダーの視点からの新たな研究展望が見られたことが指摘された。
第二に、奴隷化された女性の抑圧と、母性(motherhood)への着目だ。結婚と生殖という「二重のシフト」、奴隷商人と夫との「二重の服従」、奴隷制下での妊娠、出産、授乳、育児は、奴隷にされた男性とは異なるレベルでの抑圧と苦痛をもたらすということを、改めて強調した。さらに大西洋奴隷社会全体での大原則「partus sequitur ventrem」(生まれるものは子宮に従う)は、北米植民地のヴァージニアでも1662年に同様の原則ができ、のちにすべての植民地へ拡大。奴隷の子は奴隷、異人種間結婚でのジェンダー非対称な罰則であったと説明された。
第三に、Geminianaのライフストーリーが描かれた意義についても評価がなされた。母親であった一人の女性の物語を800ページにおよぶ刑事事件としての資料と家族関連の補完資料から描き、奴隷制解体期のブラジル社会やマラニョン州の奴隷制の暴力性についても明らかにされたとした。さらに、Geminianaが息子の死に抗議し、棺の鍵を開け遺体の検証をしたことを明記したことで、Geminianaを「歴史的主体」として浮かび上がらせ、反対に息子の死の「不都合」を葬り去ろうとした奴隷主家族や隠ぺいに加担した医師が対極に描かれていると、解説した。
参加後記
エレーナ氏は従来の奴隷制研究にジェンダーの視点から風穴を開け、長らく軽視されてきた女性や母親の経験を「母性、母親であること」(motherhood)という言葉を使いながら、明らかにした。講演でエレーナ氏が残した以下の言葉が印象深かった。
「私たちは過去を調査する際、推測、共感、想像のテクニックを用いることができるし、また用いるべきである。史料を丹念に調査することで、恐ろしい奴隷制度に囚われていた人々の人生を再構築し、人々の伝記を歴史的な物語の中心に据え、私たちの現在をよりよく伝えることができるようになる。奴隷にされた女性とその家族の人生を研究する場合、記録文書がないことはよくあることだ」。
「記録文書に残されていない」「史料が限られている」という壁は、奴隷化された人々のような被支配者側の視点が、いかに公式の文書上で「存在しないもの」とされてきたのかを表している。社会史学者の役割は「存在しないもの」と扱われてきた人々の歴史的主体をいかにして浮かび上がらせるかであり、その際にジェンダーの視点は欠くことができないものである。エレーナ氏の講演を通じ、研究者として被支配者側の視点に立とうとする姿勢や、限られた史料をもとに「推測、共感、想像」することの価値や意味を学んだ。エレーナ氏の研究成果からは、研究者自らが「史料がないから」と被支配者側の視点に立った研究に挑戦せず、確かに過去に存在したはずの人々を、公式文書が沈黙してきたと同等に「存在しないもの」として扱ってしまっていいのか、と問いかけがなされたように感じた。 奴隷制研究においては、黒人女性の歴史的主体を浮かび上がらせること自体が、歴史学や従来の研究への「抵抗の諸相」であるとも言えるのかもしれない。シス男性の視点で語られてきた奴隷制史を「再構築」していくエレーナ氏の研究の実践に、多くの学びと刺激をいただいた。
(吉田梨乃)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第58回(2023年12月15日)
〈教師の人生〉とジェンダーはどのような関係にあるのか?
講師:寺町晋哉さん(宮崎公立大学人文学部・准教授)
司会: 山田哲也さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
第 58 回 CGraSS 公開レクチャー・シリーズは、「<教師の⼈⽣>とジェンダーはどのような関係にあるのか?」と題し、宮崎公⽴⼤学⼈⽂学部・准教授の寺町晋哉さんにご講演いただいた。寺町さんのご専⾨は教師教育学・教育社会学であり、ご著書に『<教師の⼈⽣>と 向き合うジェンダー教育実践』(晃洋書房、2021 年)、編著書に『現場から変える!教師の働き⽅』(⼤⽉書店、2023 年)などがある。
今回の講演では、『<教師の⼈⽣>と向き合うジェンダー教育実践』の内容をもとに、ジェンダー教育実践を進めることの意義と難しさ、今後の展望についてご報告いただいた。以下では、講演の内容を4部に分けて紹介する。
(1)<教師>とジェンダー教育実践
講演の冒頭では、学校教育が、ジェンダーを再⽣産する装置となっていることが指摘された。具体的には、持ち物や整列の仕⽅、教員にどう呼ばれるかなど、⽬に⾒えない「隠れたカリキュラム」の形で⽣徒にジェンダー規範が伝達されており、そこには教員⾃⾝のジェンダー・ステレオタイプが影響していることが挙げられる。
ジェンダーの課題に対抗するジェンダー教育実践は、①「フォーマルかインフォーマルか」 (学校レベルで組織的・制度的に⾏われているのか、教師個⼈の判断で⾏われているのか) ②「ジェンダーにセンシティブか否か」(学校や⽣徒、教師の中に存在するジェンダーに敏感か否か)という指標で4つに類型化される。この類型によると、「フォーマル×ジェンダーにセンシティブでない」教育は形式化されており、誰でも実践しやすいのに対して、「インフォーマル×ジェンダーにセンシティブ」な教育では、教師個⼈の価値観が反映されやすい。
ここで寺町さんは、<教師>=1⼈の⼈間としての教師、であることに⽬を向ける。⼀⼈ひとりの教師は、それまでの⼈⽣からそれぞれの価値観を持って教壇に⽴っており、教師⾃⾝もジェンダーから⾃由ではない。<教師>によっては、ジェンダー教育実践が⼤きな葛藤 や⼼理的負担を伴う可能性がある。ジェンダーにセンシティブであること、⾃⾝のジェンダー・バイアスに⾃覚的であることを、どこまで<教師>に求められるだろうか。
(2)ジェンダー教育実践を進める難しさ
「センシティブである」教育実践は、<教師>個⼈の対応に依存してしまう。ジェンダーを学んだことのない<教師>も多いため、ジェンダーに問題意識を持っている<教師>と共に、教師集団で連携して実践を⾏うことが有効だと考えられる。
しかし、教師集団での実践にもまた難しさがある。まず、ジェンダーについては教育課程で正式に位置付けられていないため、「数ある問題の中から、なぜジェンダーを取り上げるのか」という合意形成が必要になることが挙げられる。次に、男性中⼼の学校⽂化の中で、⼥性教員がリーダーシップを発揮するのが難しく、男⼥間の⼒関係について問うような教育実践が難しいという課題がある。加えて、同僚<教師>に対してセンシティブであることを求めるのは、同僚<教師>の価値観に踏み込むことになるため困難である。これらの難しさを踏まえると、<教師>集団によるジェンダー教育実践では、「フォーマル×センシティブでない」パッケージ化されたもの(「市の冊⼦」のような外部教材を利⽤するなど)が⾏いやすい。パッケージ化された実践は、<教師>個⼈の価値観が問われないため、教師の⼼ 理的負担が少ないというメリットがある⼀⽅で、デメリットとしては、実践が⽬的化し、⽬の前の⼦どもたちの実態から離れてしまうリスクもある。
(3)ジェンダー教育実践の今後の展望
寺町さんは、ジェンダー教育実践を進めていく上で、次のことが必要になると指摘する。 ①<教師>も⼦どもたちも、それぞれジェンダー化された⼈⽣を歩んでいる(価値観に限界がある)ことを前提にすること。②⽬の前にいる⼦どもたちを中⼼に据えることで、<教師 >集団でジェンダーの課題に対する⽬線を揃えること。③⼦どもたちとの具体的なやりとりからジェンダー・バイアスを振り返り・共有すること。④個々の学校・⼦どもたちの実情 に即して、ジェンダー教育実践の必要性を考えること。これらを意識することで、⼀⼈ひとりの<教師>たちが連携したジェンダー教育実践が可能になる。
(4)研究の課題とこれから
最後に、上記の研究では<教師>と教育実践の関係は検討してきたが、<教師の⼈⽣>そのものは分析してこなかったことを指摘し、今後は社会との関係性の中で、「どうしてそのような教師になっていったのか」を明らかにする必要があると振り返り、講演を締められた。
以下、参加記の筆者によるコメントである。
講演を受けて特に印象に残ったのは、⾃⾝の価値観を問われると負担の⼤きい<教師>もいるため、「フォーマル×センシティブでない」ジェンダー教育実践がなされることがある、という点である。ジェンダーをめぐる課題について、「⾃分はどう考えているか」を⽣徒に語ることは、プライベートを曝け出すことになるため、抵抗のある教員がいることはよく理解できる。しかし⼀⽅で、⽣徒が期待しているのは「先⽣はどう考えているのか」という顔の⾒える答えなのではないか、という思いもある。今回も、寺町さんがご⾃⾝の失敗談と反省も交えつつお話しくださったことで、研究者の⽅も試⾏錯誤の中で絶えず実践を重ねていることがわかり、未熟な筆者も勇気をいただけた。<教師>である以上、必ずしも「模範的」な返答ができるとは限らないが、むしろその不完全さが⽣徒の考えを刺激することもあるだろう。
今回の講演で、個⼈の価値観がとりわけ強く反映されるジェンダーというテーマについて、<教師>たちが共通認識をつくることの難しさと、その意義の⼤きさを再確認することができた。筆者は教員志望なのだが、1⼈の等⾝⼤の<教師>として、同僚や先輩、(気が早いが)後輩<教師>たちと、どのように連帯していけばよいのか、これからも考え続けたい。
( ⼀橋⼤学社会学部 堀江絢⾹)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第57回(2023年10月4日)
敗戦・被占領と性暴力―日本(内地)と「満洲」(外地)で同時展開の「性接待」
講師:平井和子さん(一橋大学ジェンダー社会科学研究センター・客員研究員)
司会: 貴堂嘉之さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
第57回CGraSS公開レクチャー・シリーズでは、「敗戦・被占領と性暴力―日本(内地)と「満洲」(外地)で同時展開の『性接待』」と題し、一橋大学ジェンダー社会科学研究センター客員研究員の平井和子氏にご講演いただいた。平井氏は近現代日本女性史・ジェンダー史がご専門で、今夏刊行された新著『占領下の女性たち――日本と満洲の性暴力・性売買・「親密な交際」』(岩波書店、2023年)のほか、『日本占領とジェンダー ――米軍・売買春と日本女性たち』(有志舎、2014年)や、上野千鶴子・蘭信三・平井和子編『戦争と性暴力の比較史へ向けて』(岩波書店、2018年)などの業績がある。
今回の講演では、「性接待」という用語に顕著に現れる、占領軍「慰安所」・RAA(特殊慰安施設協会)・満洲引揚げという「未曽有の国難」に女性が「性の防波堤」として差し出されてきた歴史が紹介された。歴史学において長らく注目されずにいたこのような性暴力の実態と複層性を、平井氏は綿密な資料分析とオーラル・ヒストリーの収集によって明らかにした。根強い「自発性神話」さえも突き崩す鮮やかな研究成果を惜しみなく披露してくださった講演を、以下では大きく4部に分けて紹介する。
Ⅰ. 新著紹介と問題提起
まず冒頭では、新著の各章紹介と共に、ようやく近年、軍事占領に伴う性暴力の社会問題化や問い直しが行なわれ始めたことの経緯と意義が話された。平井氏は、「なぜ、占領軍「慰安所」や、「満洲引揚げ」時の性暴力の社会問題化が遅れてきたのか?」と問い、日本占領が「良き占領」であったとする日米で共有された認識や、その認識にジェンダー・セクシュアリティ視点が欠如していることが、社会問題化への壁となってきたと指摘する。つまり、①「性」を些末なことと見なしてきた歴史学のメインストリームにおけるジェンダー認識、②性売買に携わる女性にたいする研究者自身の<上から目線>のセクシュアリティ認識、さらに③犠牲者意識ナショナリズムとも通じる「強姦神話」など、被害者の「発話の正統性」を決定する当該社会側の認識が、壁やブレーキとなってきたのである。これら3点のうち、新著のテーマに繋がる③を平井氏はとくに強調した。佐藤文香氏による「受難物語におけるレイプ/売春/恋愛のグラデーション」図式(2018)を下敷きにして、圧倒的非対称な構造的暴力のなかでもひとりの個人が発揮するエイジェンシーと、そうしたエイジェンシー発揮に伴って生じるレイプ/売春/恋愛間のグラデーションを「見逃さず、敬意を持って」新著に書き留めたとのことであった。このエイジェンシーとグラデーションの視点は、(以後の講演中に紹介される)「慰安所」内部での遊興の様子を捉えたプライベート写真の受け止め方、また紛争地における性暴力の存在とエイジェンシーの関係など、本講演の最後に行なわれた質疑応答でも議論となった。
Ⅱ. 日本(内地)における、日米合作の性売買・性暴力の実態――旧くて新しい史料「エゴ・ドキュメント」で明らかになるもの――
続いて、①敗戦の数日後から早々に、東久邇宮内閣発案により占領軍向け性接待施設が「絶対必要ナリ」と全国的に設置展開されていくさま、②設置された「慰安所」やRAAで働く女性の募集時に露わになる、男性リーダーたちの「護るべき女性」と「差し出す女性」の二分化発想、③そうした施設の実質的運営を左右した、占領軍主導の徹底的な性病管理政策やMPによる秩序維持、④RAAのオフリミット(立入禁止)化によって働く女性が街頭へあふれ出て「パンパン」となったこと、の4点に触れながら、占領期日本における対占領軍性売買・性暴力が事実上日米合作で成立していたことが解説された。
上記③の「MPによる秩序維持」では、平井氏の今般の研究成果と新規性が示された。それは、当時のRAAや「慰安所」の内部を撮影した貴重な個人所蔵写真を特別に入手したことによって、従前は活字で認識するだけであったMPによる秩序維持の様子が、実際に画像として確認できたということである。本講演では、RAA入口を警備するMPを写した当該1枚のほか、「慰安所」ダンスホールで遊興する若い米兵と日本女性らの一団を写した1枚の、計2枚が参加者へ紹介された。これらの写真は、元陸軍通信隊公式カメラマンが当時の占領軍兵士のプライベートを写した複数のオフショットの一部で、現在は写し手の孫娘にあたるオランダ在住女性の手元にあるとのことであった。所有者の女性は、本講演での写真の公開を平井氏へ許可する際、現代の日本の人たちがこうした性暴力の一端を捉えた写真をどのように受け止めるのか、ぜひ感想を知りたいとおっしゃっていたそうである(寄せられた参加者の感想は、講演最後の質疑応答にて共有された)。こうした写真と併せて、米兵男女から性暴力を受けたとみられる「マスコット・ボーイ」や「ハウス・ボーイ」の存在、RAAがGI(米兵)に与えた影響の聴き取りなど、「個」への着目による新しい知見の掘り起こし事例も紹介された。
Ⅲ. 満洲(外地)における性暴力の実態 ――「自発性神話」を解体する力を秘めたオーラル・ヒストリー――
講演の話題は、内地日本から目を転じて外地満洲へと移る。まず、(長野県)満蒙開拓団員家族の帰還率が、応召者・義勇隊らに比べ30%程度も低いという明確なジェンダーギャップの事実が示された。その背景に、敗戦直後の痛ましい経験が窺える。痛ましい経験に想起される満洲での性暴力「性接待」は、近年(とくに黒川開拓団の)女性たちが長年の沈黙を破り、ソ連兵への「少女」の差し出し事例を語るようになったことから世間の耳目を集めている。しかし平井氏は、この注目の一方で、元「慰安婦」すなわち性売買経験者らが初期の「性接待」に同行していたことが最近見落されるようになっていると指摘する。この指摘によって我々は、女性が団のために「自発的に」名乗り出て接待へ臨んだ、と美談化されがちな事例へ目を向けることが可能となる。そしてその着目は、とりわけ当事者以外によって記憶・記録されるあまたの「自発性神話」の突き崩しへ道をひらくことに繋がってゆく。公的な記録と、人びとの証言が一致するからと言って、それが歴史的事実とは限らない。オーラル・ヒストリーは、文献と一致する証言が出てくることによってそれを歴史的事実と認定してしまう「危うさ」を持っているが、同時に「自発性神話」に基づく記憶の定着と継承を解体する突破口・糸口となるのもまた、当事者(やその近親者)による証言である。こうした証言を語らしめる場となり得るのが、オーラル・ヒストリーの持つ「強さ」であると平井氏は言う。
講演冒頭の新著紹介において平井氏は、「戦争にまつわる国家や共同体の集合的記憶が、犠牲になった被害者の受難物語の域を脱しない限り、「パンパン」や 、満洲引揚げで「自ら」性の防波堤になったとされる売買春女性たち、そして日本人慰安婦たちは、語り出すことができない」と喝破したうえで、新著に込めた「語りの正統性の序列から外れ、スティグマを負ったうえに、「自己責任」として語る場をどこにも与えられなかった女性たちの姿を見逃さないぞ、という意識」を語っている。 講演ではほかにも、満洲時代「子ども」だった女性の証言が貴重な音声(「ロモーズの歌」歌声)とともに紹介されたり、当事者証言から窺える性暴力被害の多様性の事例として、ソ連の女性兵士から日本兵へ、また引揚げ船中で米兵から、といったケースも明らかにされた。『戦争は女の顔をしていない』(岩波文庫、2016年)で500人に聴き取りを行なったアレクシエーヴィチ氏でさえ女性から男性への性暴力加害事例は拾えなかったとのことで、平井氏の紹介事例の貴重さが示された一方、抑圧性の影響(語れないのかもしれない)も示唆された。なお、この「性暴力被害の多様性」について、男性から男性への性暴力事例が出てきていないのでは、とのちの質疑応答で指摘があった。なぜ事例がないのかここで明確な答えを出すことはできないが、語られることと語られないことを分けるものを問いつつ今後検討する余地が大いにあることが確認・共有された。
Ⅳ. 質疑応答
質疑応答では、先に示した話題のほか、「慰安所」内部写真への参加者の感想(戸惑い)や、貸間提供家族の「パンパン」にたいする見方に関する質問などが挙がった。加えて、差し出された女性の社会階層が幅広かった可能性や、満洲における性接待には「占領-被占領」だけでなく日本人内部の「軍隊-非軍隊」という構図も存在したという補足情報が近接領域の研究者から寄せられ、複雑な関係性を読み込むためのさらなる視点が参加者へ共有された。
この場を借りて筆者も、「慰安所」内部写真、とくに遊興の様子を写したものに衝撃を受け、心に揺さぶりをかけられたことを告白したい。20人ほどの若い男女が遊興する様子は率直に楽しそうであったし、写真から「性暴力」の「加害者」「被害者」性をひと目で見て取ることができるかと問われれば、難しいと答えざるを得ない。しかし、当人たちが笑顔を見せていれば不問にされるような関係性ではない構造が彼らの背後にあるのも確かである。眉をひそめて見るべきか、目を細めて見るべきか。グラデーション性の議論の肝であり理解の眼目である、この「あわい」のあり様をうまく自分が処理できなければ、壁を作って向き合わずにいたかつての研究者たちの轍を踏みかねない、という恐ろしさを突きつけられた感じがした。どう受け止めるかは「難しい」とご本人でさえ何度も仰っていたが、この難しさを御しながら新著を刊行された平井氏の成果は、たいへんなものであると改めて実感する。長年の沈黙を経て経験を語り始めるという動きは、開拓団のみならず、戦争孤児、戦争花嫁などにも近年見られるものである。また、占領期に米軍関係者によって撮影された個人所蔵写真の「発見」も、今後さらに増えていくだろう。信じられてきた既存の「レガシー」的な神話の数々を、後年の証言によっていかに解体するか。「新しく」出て来た写真をどう理解し位置づけるか。占領期を研究する筆者の目下の関心事へ、平井氏の新著と講演が一つの道筋を示してくれた思いがした。
(一橋大学社会学研究科 修士課程 吉川史恵)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第56回(2023年6月30日)
西洋ジェンダー史とアグノトロジー
講師:弓削尚子さん(早稲田大学法学学術院・教授)
司会: 貴堂嘉之さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
第56回CGraSS公開レクチャー・シリーズは、「西洋ジェンダー史とアグノトロジー」と題し、早稲田大学法学学術院・教授の弓削尚子さんにご講演いただいた。弓削さんのご専門はドイツ史、ジェンダー史研究であり、ご著書に『はじめての西洋ジェンダー史――家族史からグローバル・ヒストリーまで』(山川出版社、2021年)、共編書に『論点・ジェンダー史学』(ミネルヴァ書房、2023年)などがある。
今回の講演では、『はじめての西洋ジェンダー史―家族史からグローバル・ヒストリーまで』のコンセプトと、本書で掘り下げることができなかった「アグノトロジー」の観点と強制収容所の女性同性愛者の掘り起こし(クィア・ヒストリー)を中心にご報告いただいた。
はじめに
1. 『はじめての西洋ジェンダー史』
『はじめての西洋ジェンダー史』は、日本人研究者が著したジェンダー史の数少ない入門書である。近代歴史学では、ジェンダー化された公私二元論をもとにする男性の公的領域(政治や経済、戦争)が対象とされ、歴史家とは男性であり、近代歴史学とは「男たちの学問」であった。こうした西洋・白人・ミドルクラス・異性愛男性が牽引してきた歴史学が意識的、無意識的に創り出した「無知」に向き合うもの、それがジェンダー史である。
男性中心の近代歴史学/ナショナル・ヒストリーが創り出した「無知」に向き合うためには、アグノトロジーの概念が有効である。「アグノトロジー」(無知学Agnotology)とは、ある社会的、政治的、経済的、文化的文脈の中で、抹殺・忘失されることになった知識の研究のことである。アグノトロジーは、アメリカの科学史家のロバート・N・プロクターとロンダ・シービンガーが作った造語である。(青土社『現代思想』2023年6月号では、「無知学/アグノトロジーとは何か――科学・権力・社会」という題で特集が組まれた)
2. クィア・ヒストリーとアグノトロジー
報告では、ジェンダー史は、近代歴史学の創り出した「無知」に向き合ってきたものの、「無知」に向き合うと新たな「無知」が生まれることもあるのではないかとの問いが出された。上述の書籍では、男性同性愛者には触れたが、女性同性愛者について掘り下げることができなかった、ゆえに、報告ではナチスの強制収容所の女性同性愛者についての「無知」が取りあげられた。
2023年に開催されたドイツ連邦議会におけるナチス犠牲者追悼の式典では、はじめてセクシャル・マイノリティの犠牲者が追悼された。式典は、強制収容所に送られた男性同性愛者のカール・ゴラート(1912-2003年)とユダヤ人で女性同性愛者とされるマリー・ピュンヤー(1904-1942年)の生涯が紹介されて話題になった。強制収容所の犠牲者のなかでも、同性愛者は「忘れられた犠牲者」とされ、男性同性愛者だけではなく、女性同性愛者も追悼された。ここで男性/女性とつけたことには意味がある。これまでナチス政権下での同性愛者の強制収容所での裁判記録・経験・記憶が明らかにしてきたのはもっぱら「男性同性愛者」であった。「同性愛者」カテゴリーにおいても、「国民」や「市民」と同じように男性のみに光が当てられていたのではないか。
ドイツ近代史における女性同性愛者は、ジェンダー秩序のなかで女性が私的領域に置かれたがゆえに不可視化されてきた。だが、20世紀初頭に女性同性愛も刑法の処罰対象にすべきという刑法改正の議論があった。さらに1920年代の女性の政治的権利の議論が盛んであった時代に、女性同性愛は公序良俗を脅かすものであり、異性愛女性をその誘惑から守る必要があるとの議論も行われるようになった。そして、1933年以降のナチス政権下では、ジェンダー秩序が強化され、「民族共同体」を守るための刑法のあり方が議論された。ヒトラーは男性同性愛者を処罰する刑法175条を徹底化することを公約に掲げ、何万人もの同性愛者と見なされた人びとを強制収容所に送った。女性同性愛も刑罰の対象にすべきか諮問委員会で議論されたが、大半の委員が反対した。女性同性愛は、男性同性愛ほど人口政策上の危険を与えないとされたからである。一方で、刑法175条に女性同性愛を含むべきという少数派は、ナチス・イデオロギーに基づいており、女性同性愛は「民族共同体」を脅かす存在、「人種の退化」の危惧、女性たちの妻・母という「自然の定め」に反すると考えた。ナチス政権で厳格化された刑法175条は、これまで通り男性同性愛のみを対象にした(猥褻行為、公安侵害、売春を取り締まる他のドイツ刑法に違反したとして女性同性愛者が対象になったケースがある)。刑法そのものが男性のセクシュアリティを中心とし、女性のセクシュアリティを無化する。つまり、公的領域における女性のセクシュアリティを不可視化していた。
もう一つ、女性同性愛を不可視化してきた要因に史料の不在がある。1936年設置の同性愛・中絶闘争帝国中央本部では、約10万人が「同性愛」の嫌疑をかけられたとされるものの、史料が消失してしまっている。他方、人種政策局では、1938年から女性同性愛者の名前と住所のリストが作成されていたことが研究で明らかになっている。ただし、収容所入所において女性同性愛者であることは、単独の理由ではなく、あくまで二次的な理由の一つであり、「政治犯」や「反社会的分子」などの複合的な理由で入所させられていた。つまり、ナチスによるレズビアン抑圧は「インターセクショナルな形態 」であったとも言われている。
さらに、女性同性愛者の可視化には、後世の人びとによる「想起の文化」が関係する。1980年代末以降、同性愛者の犠牲者たちの記念碑が建てられていく。2008年にベルリンに建てられた「ナチスに迫害された同性愛者の記念碑」は、元々ナチ下で刑法175条に違反し迫害されたゲイ男性のために造られた記念碑であったが、女性同性愛者を無視しているという批判の声が上がり、連邦議会は過去だけではなく現在の注意喚起のためにゲイとレズビアンの両方に捧げるものへと変更した。刑法175条の対象外のレズビアン女性を含めたことで、元々の設置目的とは矛盾を抱えた 記念碑になった。その後も、2011年にミュンヘン市議会はゲイとレズビアンのための記念碑建立を決定した(2017年完成)。記念碑の説明文には、「ピンクのトライアングルは、ゲイが強制収容所で身につけなければならなかったもの」、「黒のトライアングルは、レズビアンの抑圧の印」と書かれている(収容所で「女性同性愛者」が黒のトライアングルを身につけさせられたことはなかった)。レズビアンは「迫害」ではなく、「抑圧」と表現されていることも重要である。さらに、女性同性愛者の「想起の文化」は、ラーフェンスブリック収容所跡地(最大の女性収容所)の記念碑設置において、レズビアンらの運動団体と財団が一時対立し、「女性同性愛者」という理由のみで入所・迫害はなかったことから歴史家からの批判があり物議を醸すこともあった。
おわりに 歴史学にアグノトロジーの観点は有効か?
最後に、弓削さんからいくつか問いが投げかけられた。アグノトロジーは、「想起の文化」と相性がよいと思われる。想起することで何が、なぜ無知とされてしまったのかを考えることができる。一方で、レズビアンの史料上の痕跡が可視化・想起されることに対してではなく 、彼女たちは不可視のままを望んでいたのではないかという問いや、レズビアンが「模範的な女性像」の「仮面をつけた時代」でもあったのではないかという当時の文脈を重視したナチス期同性愛の歴史家たちの指摘がある。 弓削さんは誰がその「仮面」を外すのだろかと問いかける。
そして、弓削さんは「歴史家のアウンティング?」と疑問符をつけた最後の問いかけをした。アウンティングとは、本人のセクシュアリティを本人の同意なく第三者に暴露する行為である。死者のプライバシーや「死者の人格保護」は法的に問題ないが 、死者であればアウンティングにあたるような行為をしても許されるのだろうか。弓削さんは前述したナチス犠牲者追悼の公的な場でマリー・ピュンヤーをレズビアンであると紹介していたことに逡巡した。ピュンヤーは当時の医師に「レズビアン」と診断されていたが、本人が語っているわけではないからである。この逡巡が起きるのは、歴史家自身が生きる社会がシスジェンダーの異性愛を規範とし、クィアの人びとへの認識と偏見のある社会だからだろうかと弓削さんは問う。昨年亡くなったマルゴット・ホイマン(1928-2022年)は、ホロコーストのサバイバーで、戦後に「ユダヤ人でレズビアン」のポジショナリティを引き受けている。彼女は自らのセクシュアリティを公表しているため、ピュンヤーの状況とは異なっている。
結びに、弓削さんはクィア・ヒストリーの難しさと新たな「無知」の創出、死者の人格保護の問題、「歴史家の倫理」に言及し、考えていきたいと語った。
以下、参加記の筆者によるコメント。
筆者は、高校生の頃、古代ギリシアの哲学者ソクラテスの「無知の知」を学び、この標語に大変感動した記憶がある。私にとって歴史を学ぶことは、自分の知らないことを知っていく営みであり、大変面白かった。だが、そんな「学校で教えられる歴史」にも、「無知」があったことに気づいたのは、残念ながら卒業後であった。世間では「何も知らないほうが幸せだ」と言われることがある。私にとってジェンダー学を学ぶことは、自分と社会の「無知」や「不知」に気がつくことである。そして、その度に社会に裏切られたようにひどく傷つく。知らなかったほうが幸せだったのかもしれない。しかし、私は知らないほうがよかったとは思わない。むしろ、自分の「無知」や「不知」で他人を傷つけているのであれば、ジェンダー学を学ぶことで負う傷は必要な痛みだと思う。
歴史家によるアウンティングの問題は、そもそもアウンティングが成立するのかという問題がある 。生きている人間のセクシュアリティは、他人が勝手に判定してはならない。だが、亡くなった人間は亡くなっているから良いのだろうか。亡くなった人間が隠そうとしたセクシュアリティを、第三者である歴史家が学問の意義や社会の貢献というもっともらしい理由で公開していいのだろうか。この問いは、引き続き考えていきたい。
歴史家によるアウンティングの指摘は、歴史家による「無知」を露呈しているのかもしれない。一方で、セクシュアリティの枠組みやアウンティングの概念は、現代的な考え方であり、単純に過去を当てはめることはできない。この議論は、アウティングが自死に繋がった事件の起きた一橋では、とりわけ重く受け止める必要があろう。
参考文献
弓削尚子, 2021年, 『はじめての西洋ジェンダー史――家族史からグローバル・ヒストリーまで』山川出版社.
弓削尚子, 2023年, 「強制収容所の女性同性愛者を掘り起こすこと――クィア・ヒストリーとアグノトロジー」『現代思想 2023年6月号』青土社, 119-129.
(一橋大学社会学研究科 博士課程 樋浦ゆりあ)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第55回(2022年11月30日)
ルッキズムとジェンダー——フェミニズム/ジェンダー研究における外見/美
講師:西倉実季さん(東京理科大学教養教育研究院・准教授)
司会: 佐藤文香さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
第55回CGraSS公開レクチャー・シリーズは、「ルッキズムとジェンダー——フェミニズム/ジェンダー研究における外見/美」と題し、東京理科大学教養教育研究院・准教授の西倉実季さんにご講演いただいた。西倉さんのご専門は社会学、ライフストーリー研究であり、ご著書に『顔にあざのある女性たち——「問題経験の語り」の社会学』(生活書院、2009年)、共著書に『「社会」を扱う新たなモード——「障害の社会モデル」の使い方』(生活書院、2022年)などがある。
本公演のテーマであるルッキズムに関しては、2010年代以降、社会的にも学術的にも関心が高まっている。しかし、ルッキズム概念は定義が曖昧なまま濫用されており、論点は錯綜している。さらにそこで展開される議論においては、1980年代終盤から90年代序盤のミスコン論争でフェミニズムが解決したはずの争点が再浮上しているようにみえる。西倉さんはルッキズム概念をめぐる現状を以上のように診断し、フェミニズムの文脈に立ち返り、その貢献と残された課題を確認することを通して、混迷状態にあるルッキズムをめぐる議論を整理するための視座を提示してくださった。以下では、西倉さんのご講演内容を振り返った上で、感想を述べる。
⑴「ルッキズム」とは何か
本講演は三部構成からなる。第一部では、ルッキズム概念の学術的バックグラウンドが確認された。ルッキズム概念は、主に2000年代以降、職場の差別を問題化する概念として使用されてきた。代表的研究としては、Daniel HamermeshとJeff Biddleによる"Beauty and the Labor Market" (The American Economic Review, 1994)が挙げられる。この研究は、外見が良い人ほど収入が高いことを実証的に示し、それを「ビューティー・プレミアム」として名付けた。ルッキズムに言及する研究の多くがHamermeshとBiddleの議論に言及しており、ルッキズムは雇用や労働における不平等・格差に関する問題として注目されるようになった。
フェミニズムの立場からルッキズムを正面から論じた研究としては、Lynn S. ChancerによるReconcilable Differences: Confronting Beauty, Pornography, and the Future of Feminism(University of California Press, 1998)が紹介された。フェミニストで社会学者であるChancerは、「美しくあれ」という社会からの圧力をルッキズムとして定義し、この現象は単に個人的な問題ではなく、Émile Durkheimのいう「社会的事実」に相当することを指摘している。さらにChancerは、ジェンダーの視点を持ち込むことによって、ルッキズムをジェンダー非対称的な現象として——すなわち、女性により深刻な影響をもたらす現象として——位置付けた。
⑵フェミニズムはルッキズムをどう論じてきたか
では、フェミニズムにおいてルッキズムはいかに論じられてきたのだろうか。第二部では、第一部で紹介されたChancerの議論が詳細に紐解かれる。Chancerは、フェミニズムがある一定の成果を達成した一方で、外見をめぐる女性の状況はむしろ悪化していると分析し、過去のフェミニズムの歴史を振り返ることを通してルッキズムの乗り越えをはかろうとする。Chancer以前の議論は、ルッキズムがフェミニズムのバックラッシュとして登場し、女性の社会進出を妨げるために利用されていることを明らかにしてきた。Chancerはこのような指摘を高く評価する一方で、フェミニズムはバックラッシュを悪化させた社会経済的状況を論じてこなかったとし、以下のような見立てを示す。すなわち、グローバル資本主義下において人々の生活が不安定となるなかで、ダイエットやエクササイズを通して自らの身体をコントロールできることに喜びが見出された結果、バックラッシュの打撃は深刻なものになってしまったと、Chancerは分析した。
さらにChancerは、フェミニズムにおける「美」をめぐる論争の歴史を整理した上で、1990年代当時を「美をめぐる論争の段階」として位置付ける。この段階においては、美容行為を女性の従属的な地位を表すものとして捉える立場と、女性の選択や主体性の表現として捉える立場との間で、議論は平行線を辿ることになる。Chancerはこのような議論の構造を、社会学における「構造」対「エイジェンシー」問題の一バージョンとして捉え、このような二項対立的な議論のあり方は、フェミニスト同士の対立を煽るのみならず、美の問題を脱政治化させると危惧する。そこでChancerは、これらの立場の違いを「調停可能な差異reconcilable differences」として捉えることを提起する。
⑶ルッキズムをめぐる今後の論点
第三部では、Chancerの議論を踏まえ、ルッキズム概念をめぐって今後考えるべき課題が提示された。以下、四点に要約して示したい。第一に、ルッキズムと性差別の関係性を考える必要性が提起された。西倉さんは、性別に回収されない問題や不当感があるからこそ、人々の間でルッキズム概念が必要とされてきたのではないかと指摘し、性差別に還元されないルッキズムのありようを検討する方向性を示した。
第二に、フェミニズムの議論から継承すべき問いとして、「なぜ今ルッキズムなのか」という論点に立ち返る必要がある。西倉さんは、自分自身を投資の対象として「価値」を高めることが要請される新自由主義的な状況や、進行しつつあるセクシュアライゼーションを、議論のための糸口として提示した。
第三に、新自由主義的見方を内面化している研究者たちによる、外見の経済主義的見方の問題点を考える必要がある。西倉さんは二つの問題点を挙げている。まず、経済主義的見方において、「美」の問題は「個人の努力によって解決可能なもの」として「個人化」される恐れがある。社会的に理想とされる「美」に到達することは、単に個人の努力の問題に回収されず、さまざまな特権性(白人性、若さ、社会階層など)が関係していることに注意を払うべきだと、西倉さんは強調した。つぎに、「美」の追求には時間、金銭、労力を要するのみならず、健康面でのリスクをともなうほか、摂食障害やうつなどの精神的問題が引き起こされることもある。このように、「美」の獲得のために女性たちが払ってきた代償を見逃すことはできない。
最後に、Chancerの指摘した「構造」対「エイジェンシー」という二項対立の議論構造の隘路を縫うために、差別をされている側に焦点をあて、その人々の経験を分析する方向性が示された。そのさい、フェミニスト現象学の議論を引きながら、経験に着目することの意義が確認された。
以下、本講演の感想を述べる。西倉さんのご講演は、ルッキズムの概念の現在および学術的バックグラウンドを丁寧に読み解き、またフェミニズムの議論に立ち返ることによって、今後論じるべき点を明確に示してくだった。フェミニズムの立場から「美」を論じることを目指してきた筆者にとって、西倉さんのご研究は「バイブル」であり、数々のご論考にいつもエンパワーされてきた。そのため今回CGraSSでご講演を拝聴することができ、本当に嬉しかった。 ルッキズムをめぐる議論において、フェミニズムがミスコン論争で解決したはずの論点が繰り返されているように見えるというご指摘は、フェミニストとして重く受け止めるべき点だと考えた。私たちは今一度、ミスコン論争や「美」をめぐる議論において、フェミニズムが指摘してきたことを再確認する必要があるという西倉さんの主張に、強く同意する。Chancerが言うように、過去のフェミニズムの成果を無視してしまえば、また一から議論を構築する必要があり、それはフェミニズムにとって不幸なことであるに違いない。
ご講演において特に印象に残ったのは、質疑応答のさいに西倉さんがおっしゃった、ルッキズムによって差別を受けている人々の経験に着目する意義である。西倉さんは、差別を受けている人こそ、当該の社会構造や規範に対して違和感を持つだろうという想定のもとで、以下のように述べた。現状のルッキズムに違和感を持つことなく、うまく適用している人々の経験においては、構造に対しての疑問や個人の応答的な実践を見出すことは難しい。よって、社会構造に対峙して生きざるを得ない人々に目を向け、構造に対する彼ら彼女らの「応答」に着目することで、構造のありようやその変容可能性を捉えることができるのではないかと、西倉さんはおっしゃった。ご指摘のとおり、構造に対して違和感を持つ人々の経験に着目することによってこそ、さまざまな応答可能性を見出すことができるため、そのような人々の経験を記述することは重要であると考える。
このような西倉さんのお考えを聞く中で、筆者の研究対象とする美容産業従事者の経験に着目することは、いかなる意味を持つのかについて、今一度考える必要があると考えた。フェミニズムにおいて美容産業従事者は長らく、「女性は美しくあるべきだ」という「美の神話」のエージェントとして捉えられてきた。このような議論において従事者たちは、西倉さんのお言葉を借りれば、「現状のルッキズムに違和感を持つことなく、うまく適用している人々」として想定されている。しかし、実際に調査をしてみると、美容産業におけるコンプレックスを煽るような販売戦略や、売り上げを最重要視する商業主義に対して違和感を持つ従事者も少なからず存在することがわかった。このような違和感をどのように位置付けることができるのか、また、違和感を持つ従事者のみならず、構造のなかでうまく適用している従事者の経験は、フェミニズムの立場からどのように論じることができるのだろうか。これらの点について、今後考察を深めていきたい。
西倉さんのご講演は、多くのインスピレーションを与えてくださった。筆者も西倉さんのように、「美」を論じるフェミニズムの発展に寄与できるよう精進していきたいと、思いを強くした。
(一橋大学社会学研究科 博士課程 永山理穂)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第54回(2022年10月14日)
難民とセクシュアリティーアメリカにおける性的マイノリティの包摂と排除
講師:工藤晴子さん(神戸大学大学院国際文化学研究科・講師)
司会: 飯尾真貴子さん(一橋大学大学院社会学研究科講師)
参加記
第54回CGraSS公開レクチャー・シリーズでは、「難民とセクシュアリティ ―アメリカにおける性的マイノリティの包摂と排除―」と題し、工藤晴子さんにご講演いただいた。工藤さんは、修士号取得後、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)エジプトおよびトルコ事務所にて、性とジェンダーに基づく暴力の予防や対応を中心とした難民支援に携わった経歴をお持ちの他、一橋大学で博士過程を卒業し、現在は神戸大学大学院国際文化学研究科にて講師としてご活躍されている。
工藤さんの問いの原点となったのは、人の移動とセクシュアリティの関係性について、セクシュアリティの規範が国境管理、移民・難民政策と歴史、政治とどのように関わり、それらを難民の人々がどのように経験・認識しているのかという点である。これらを解き明かすために、工藤さんはアメリカ合衆国を事例に調査を行ったが、その理由としては主に2点挙げられていた。1点目は外交政策と難⺠政策のなかで性的マイノリティの人々の保護という問題が、どのように構築されてきたのかを理解し、その枠組みと言説のなかに、包摂される人々、取りこぼされる人々、排除の対象となる人々が存在することを考察することだった。そして2点目には難⺠の人たちが移動の過程をどのように経験し、認識し、語るのかを理解するという目的を挙げていた。さらに、工藤さんは上記の研究を行う上で難民・強制移動研究およびクィア移住研究の2つのアプローチを併用する。難民・強制移動研究、およびクィア移住研究それぞれの研究において限定的にしか行われていない議論があり、この2つの領域をまたがるような研究にしたいという思いがあったからだそうだ。
本講演では、まず性的マイノリティの難民をめぐる国際規範の変化とアメリカ合衆国における国境管理の特徴を概観した後に、セクシュアリティの規範が国境管理と難民の双方に与えた影響について、幅広く学んだ。以下では、工藤さんのご講演内容を振り返った上で、私の所感を述べる。
■近年の性的マイノリティの難民をめぐる状況
講演の冒頭では、日本における性的マイノリティの難民をめぐる状況について、タンザニアから日本に逃れ、現在難民申請中の同性愛カップルに関する記事が共有された。日本では2018年と2020年に計3名の同性愛者に対して難民認定がおりているが、そもそも全体の難民認定率が諸外国に比べ極めて低いことが各国際機関等から度々指摘されている上に、やはり同性愛者の難民申請に関してはさらにハードルが高い事実は変わっていないようだ。
このような性的マイノリティの難民はここ数年で出現したわけではなく、以前から存在していたという前提のもと、工藤さんは、性的マイノリティが難民条約(「1951年難民の地位に関する条約」および「1967年難民の地位に関する議定書」)における条約上の難民として国際的に認知されるようになったのは90年代以降であると指摘する。特に2000年代以降は、UNHCR(国連難⺠高等弁務官事務所)による『国際的保護に関するガイドライン第1号:難⺠の地位に関する1951年条約第1条(A) 2および/または1967年議定書におけるジェンダーに関連する迫害』や2008年『性的指向とジェンダー・アイデンティティに関する難⺠の主張についてのガイダンスノート』などを契機して、「LGBTQ+難民」の保護が国際的な優先課題であるとする指針が確立されていったという。
■アメリカにおける国境管理の特徴
キャナデイ(2009)の分析に依拠し、工藤さんは、ホモセクシュアリティが、アメリカにおける入国管理のなかで定義し直され、望ましくない「非市民」を見つけ出し、区別し、排除・追放のツールとして用いられてきた証左を提示してくださった。例えば、19世紀の終わり頃まで遡ると、1891年に導入された不道徳行為の罪についての条項と、公的扶助条項にもとづいて、特に男性同性愛者の実質的な排除が開始されたことが分かっている。この公的扶助条項は、入国しても自立が見込めず公的支援の対象として国家の負担になるとみなされる者や、貧困ゆえに罪を犯すおそれがあるとされる者の入国を制限、拒否することを目的としたものだ。こうしたロジックはその後使われなくなるものの、1917年移民法や1952年の移民国籍法(INA)では、「精神障害」「精神異常人格」という言説が排除に用いられることとなった。この頃から、公衆衛生局が同性愛者の外国人の医療検査を担うこととなり、これは体制は1965年移民法後も維持された。70年代にかけては、ゲイ・レズビアンの権利運動の影響を受け、各州で同性愛行為の非犯罪化が進み、1990年にやっと移民法から同性愛者の入国禁止が取り除かれたという。
また、20世紀後半はアメリカへ第三国定住を希望する難民と、米国境および国内で庇護を希望する難民の受け入れの姿勢に明らかな違いが生まれるようになった時期でもある。例えば、第三国定住者に関しては「国際社会の負担の共有」という国際的規範のもと、事前に難民を何人受け入れるかなどの管理を徹底した上で、アメリカは世界一第三国定住受け入れが多い国として名を上げた。しかしながら、もう一方の庇護希望者に関してはいつどのような難民が何人来るのかなどの予測がつかない上に、難民の送還を禁止するノン・ルフルマン原則が適応されるため、管理が困難である。そのため後者は安全保障対策としての国境管理政策の中に組み込まれ、狭き門となっていったという。
■外交問題から国内安全保障の問題へ
第三国定住と庇護が明確に区別された事例として、工藤さんは1980年のマリエル・ボートリフト事件を挙げる。これは、キューバのマリエル港からアメリカ・フロリダへと大量のキューバ人の到来した事件を指し、半年でおよそ12万5千人という大規模な数の難民が押し寄せたことで知られる。実はそれまでアメリカは、冷戦イデオロギー対立を背景にした外交的戦略のもと、積極的に中産階級の反共産主義的イデオロギーを持つキューバ難民を受け入れていた。しかしこの事件によって米国に流入したキューバ人には、貧困層、受刑者、病人、売春婦、同性愛者などが多く、それ以前に米国に難民として逃れたキューバ人とは全く異なる存在として見なされた。この事件は、アメリカで初めて性的マイノリティの存在が可視化された出来事だったと工藤さんは指摘すると同時に、アメリカ合衆国の庇護申請者の管理が、冷戦イデオロギー対立を背景とした難⺠の外交問題から、国内問題としての安全保障の問題に変化したというギブニー(2004)の指摘を踏襲する。
こうして「望ましくない」難民としてスティグマ化された、「ホモセクシュアル・マリエルズ」だったが、後にゲイ男性の難民が起こした裁判(「トボソ-アルフォンソ事件」裁判)を契機として、性的マイノリティは難民条約が規定するところの「特定の社会的集団の構成員」であるとして認められるようになる。この裁判はアメリカの性的マイノリティの難民認定における基盤となった重要な判例となった。
■LGBT権利のチャンピオン・アメリカ?
オバマ政権下にあった2010年以降は、LGBTの権利を国際的な問題として認識し、外交や政策に組み込まれる形であらゆる声明が発表され始める。例えば、当時国務長官を務めていたヒラリー・クリントンは、自身のスピーチで、「ゲイの権利は人権であり、人権はゲイの権利である」と言い、注目を集めたという。しかしながら、LGBTの人々の権利が国内で発信される場合には、アメリカの先進性のナラティヴが表れていることがある。それが顕著に露呈したのが、当時副大統領だったジョー・バイデンが行ったスピーチだ。彼は難民の地位と庇護希望者を含めた、LGBTの人々への緊急支援を訴えかけつつも、他国を「ホモフォビック」として表現したという。
このように、進歩的な人権のモデルを後進的な国々に広める責任がある、という人権外交の枠組みのなかで「LGBT難⺠と庇護希望者」の保護は語られるようになった。工藤さんは、ここでは、管理が困難でノン・ルフルマン原則の国際法と倫理的制限を受ける難⺠認定申請の手続きの一部を、国家の特定の移⺠の制限のための政策のなかに位置づけるという、庇護のポリティクス(Gibney 2014)が踏襲されていると鋭く指摘する。なぜなら、上記のように第三国定住と庇護によるLGBT難⺠ の受け入れを並列に語る陰で、あくまでもラテンアメリカ諸国出身の移⺠に対する国境管理の厳格化が緩められることはなく、むしろ性的マイノリティの難⺠の庇護へのアクセスを妨げていたと言えるからだそうだ。
■フィールド調査1)難民の移動の経験
上記の先行研究をふまえて、工藤さんは、ニューヨーク州ニューヨーク市と、カリフォルニア州サンフランシスコ・ベイエリアの二つの都市地域で2009年から2014年の間に断続的にフィールドワークを行っている。それぞれの拠点では、研究に関連する団体で実際に支援活動に携わりながら調査を実施したという。
調査結果では、2つの都市の支援団体の特徴の違い、調査協力者の来歴や背景の違いが目立ったものの、一つの国のなかで難⺠認定申請の過程が画一的に理解でき、経験されるものではないという発見があったそうだ。具体的には、調査対象者たちが難民申請者に「なっていく」過程には少なくとも3つのパターンが存在するという。それは、(1)アメリカに入国する前から準備を行う難民申請計画型、(2)何らかのビザで入国した後に機会を見つけて行う難民申請機会発見型、そして(3)正規の入国審査を経ずに入国した後、地位の正規化の手段として行う「移民」移動型である。工藤さん曰く、調査対象者は主体的かつ戦略的に状況に応じて移動や難民申請に関連する選択や意思決定を行う。この過程を正しく解釈するためには、対象者を庇護-移住ネクサス(人の移動を相互排他的な移民/難民のカテゴリーではなく、連続体として捉えるための概念)のなかで理解することが重要であると工藤さんは強調する。
■フィールド調査2)難民の語りの構築
難⺠の語りとは、語り手、聴き手、書き手の相互行為から生み出され、習得されるものであるとされる。聞き取り調査では、こうした語りのパターンの地域と経験による違いが描き出された。具体的には、ニューヨークでの調査では、対象者らはゲイやレズビアンとしての本質主義的なアイデンティティや権利という概念を習得し、主体的にパフォームすることが明らかにされている一方で、ベイエリアでの調査では、地域性として「非正規移⺠」としての移動のプロセスや排除を経験するメキシコ出身者が多く、彼・彼女らは性的マイノリティゆえの暴力やレイプの被害によってトラウマ化された身体を動員していたという。
また、こうした語りの構築の過程で、難⺠には、寛容な庇護国アメリカの先進性に対して、自身の出身国をホモフォビックで後進的な存在として描くというコロニアルな語りが要求される。自身の語りを、庇護審査官などの意思決定者にとって「理解可能」にし、制度からの期待や要求に沿って構築することによって、いち早く難民の地位の獲得に近づくことができるからだ。しかしながら、自分の出身国を後進的に語ることで人種差別および帝国主義的言説に加担せざるを得ないという葛藤は、難民自身にももちろん存在する。しかし、工藤さんがもう一歩踏み込んで着目するのは、そうした言説に見られる「自由で寛容」なはずの庇護国アメリカ社会のなかにも、人種、国籍、階級と交差する他者化の問題が存在していることである。講演の中では、実際の聞き取り調査で得た証言を引用しながら、LGBTのコミュニティ内部でも、人種や法的地位によって境界線が引かれている事実について説明があった。こうして工藤さんは、聞き取り調査を通して能動的な語り手としての難⺠と、難⺠カテゴリーと移⺠カテゴリーの間を生きる人々の存在、 そしてかれらを取り巻く複層的な差別・排除の存在を明らかにした。
■今後の課題
工藤さんは、最後に本講演の内容をまとめた上で、今後の課題について言及した。1点目は、特にトランプ政権下の庇護空間の縮小、第三国定住の減少・保留などを中心とした2014年以降の状況についてのアップデートの必要性である。2点目は、第三国定住における「LGBTIQ+難⺠」、地方自治体とNGO、宗教団体の役割を明らかにすること。そして3点目に、女性やトランスジェンダーの人々の経験へのアプローチを再検討することを挙げ、講演は結びを迎えた。
■質疑応答
講演後の質疑応答では、日本という文脈でクィア移住研究や性的マイノリティの難民について考える際に重要なことを尋ねる質問があった。工藤さんは、前置きとして日本では認定者、申請者ともに少ない上に、個人情報の扱いが重要になっているので、研究の対象として設定するのは非常に難しいと述べ、広く移民難民を捉えることが大切であるとご回答なさっていた。例えば、ご自身が日本の入国管理局収容所で出会った性的マイノリティのお話に触れながら、「難民に限らず、彼・彼女らの経験に注目して、可視化していくことは重要だと思う」と述べた。
また、別の質問で「語りの構築」と、それがはらむ「そうだ難民しよう」といった難民バッシング等の悪用の可能性について尋ねられた工藤さんは、質問者が抱く危惧に関して難民に関する議論に悪用されかねないのは確かにありうると同意しつつ、ここでもなお、移民や難民を区切らずにより広い概念として捉える重要性を強調した。第一に、難民認定を申請する人々は最初につながった支援団体と、迫害に関してどんなストーリーを提示できるのかを構築する作業に着手するが、実はこの時点で既にスクリーニングは始まっている。そのため、虚偽の申請は非常にハードルが高い。また、ご著書にも記述があるが、彼・彼女らがどのような状況で語っているのかということを見落とすことはできない。特に難民を受け入れる西欧諸国においては、難民審査がそもそも「難民であること」よりも、「偽装の難民ではない」ことを試す場になっているという傾向にあり、難民の経験についての語りは重要な陳述として批判的な検討と審査にかけられるという(工藤 2022:148)。これらを踏まえた上で、工藤さんは質問者に対して、難民とされる人々が申請の過程で選択的に語るという行為は、決して嘘をついているわけではなく、偽装難民であると思われないためのアプローチであると応答した。つまり、難民の「語りの構築」を考える際に、当事者を広義の意味合いで捉えることによって、国家の限定的かつ恣意的な「難民」の定義から取りこぼされ、「偽装」のレッテルを貼られてしまう人々にもスポットライトを当てることができるということだろう。
総じて、私は工藤さんの課題意識や研究の目的全体に大変共感した。特に、強く感じたのは、工藤さんも何度か強調しておっしゃっていたように、「難民」「移民」そして「庇護-移住ネクサス」の定義を改めて広く捉え直す必要性である。私は、修士課程という短い期間ではあるが、工藤さんの研究に依拠しつつ、日本にフィールドを定めて移民・難民の人々が経験するセクシュアリティおよびジェンダーの管理に着目する研究がしたいと考えている。しかしアメリカ合衆国と異なる多くの点の1つとして、日本には、本講演でも説明のあった「庇護-移住ネクサス」に当たる人々が多いということが挙げられる。
特に、条約難民の定義に当てはまる人ですら、日本のあまりにも低い難民認定数から、あえて難民申請は出さずに在留特別許可が出るのをひたすら待つ人も少なくないと予測することが可能だ。そのため、彼・彼女らを日本の入国管理制度が定義づけるような窮屈な「難民」の概念に囚われずに捉えることが欠かせないと言える。
また、難民認定取得のためのプロセスで、難民申請者はコロニアルなまなざしで出身国を語ることを求められることについて、申請者自身のナショナル・アイデンティティと、現在難民申請中の〇〇としての私、というアイデンティティの衝突に光を当てる作業の重要性を感じた。例えば愛する故郷で内戦や虐殺が起き、避難を余儀なくされた場合、当事者は出身国の情勢が1日でも早く落ち着き、平和な母国へと戻ることを願うはずだ。しかしそうならないうちは、母国で起きている重大な人権侵害を嘆きつつも、逃れた先の国で難民申請をするにあたり、国に帰れない、あるいは帰りたくない理由を語る必要がある。なぜなら工藤さん曰く、「難民は制度的に語ることを求められる存在」だからだ。この点に関しては、工藤さんもご著書で言及しており(工藤 2022:194)、事前にご著書を読んでいたことでさらに理解が深まったと考える。さらに気になる点としては、語ることを許される難民・移民と、入管収容所などの施設にいて語ることを許されない人々の間で、「葛藤」の度合いや言語化にどのような違いが見られるのかということである。私は難民や移民の被収容経験に注目したいと考えているので、自分自身の今後の研究にとっても非常に示唆に富むご講演だった。
(一橋大学大学院社会学研究科 修士課程ZOLJALALIAN NARIN)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第53回(2022年5月13日)
民主主義の場としての家族――国家中心的政治像の再検討
講師:田村哲樹さん(名古屋大学大学院法学研究科・教授)
司会: 佐藤文香さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
第53回CGraSS公開レクチャー・シリーズでは、「民主主義の場としての家族」と題し、名古屋大学大学院法学研究科教授の田村哲樹氏(専門:政治学・政治理論)にご講演いただいた。今回の講演に関連する主な業績として、『熟議民主主義の困難——その乗り越え方の政治理論的考察』(2017,ナカニシヤ出版)や『日常生活と政治——国家中心的政治像の再検討』(編著,2019,岩波書店)などがある。
田村氏は政治を国家と同一視する見方には批判的な立場をとられており、本講演では、民主主義を国家・政府に関わるもののみとして捉えるのではなく、国家・政府の対極に位置付けられてきた「家族」もまた民主主義の場として捉えうるという提案がなされた。
本講演は、「はじめに.政治学が『家族』を『民主主義の場』として語るとはどういうことか?」、「1.なぜ民主主義が重要なのか?」、「2.『家族における民主主義』はうまくいくのか?」、「3.どこまでが『家族』か?」といった4パートにより構成された。順に要点を整理する。
はじめに.政治学が「家族」を「民主主義の場」として語るとはどういうことか?
まず、政治学者にとっての「政治」「民主主義」「家族」とはどのようなものかご説明をいただいた。これまで、政治学者にとって「政治」は国家/政府で(それに関わって)行われることであり、「民主主義」はこの意味での「政治」の一つの形態であると考えられてきた。そして、「家族」そのものを「政治」「民主主義」の場としてみなす研究はあまりなかったという。しかし、このような政治学の研究の潮流に対して、田村氏は次のようなご指摘をされた。いわく、「政治」がある範囲の人々の間で発生する紛争を解決すること、つまり集合決定の作成とするならば、それは国家/政府に限らず「家族」にもこの意味での「政治」はあり得るのではないか、ということである。本講演はこのような視点に依拠する。
1.なぜ民主主義が重要なのか?
それでは、どのような意味において民主主義は重要であると考えられるのだろうか。田村氏は民主主義の正当化には内在的正当化と道具的正当化という考え方があるとし、特に講演では後者について「家族における民主主義」に焦点をあてて解説された。
道具的正当化とは、「家族における民主主義」は、民主主義の結果として何らかの価値・「良いもの」を実現するがゆえに望ましい、とする立場である。ここで実現が目指されるものとして、「正しいcorrect」決定の作成、「別の可能性alternative」の提供、「正統性legitimacy」、「機能」による正当化(機能的正当化)の四つが紹介された。なかでも、田村氏はとりわけ機能的正当化を支持するという。機能的正当化とは、「家族における民主主義」によって、家族メンバーの間に不可避的に発生する紛争を解決するという機能が果たされるがゆえに望ましいということである。
2.「家族における民主主義」はうまくいくのか?
ここで、「家族における民主主義」はうまくいくのか、という問いを検討するうえで、「家族における民主主義」を困難にするような二つの想定しうる問題点を考える必要がある。以下で、二つの問題点とそれらに対する田村氏の応答を順に確認する。
第一の問題点は、参加者の「政治的」平等の確保が難しいということである。これは、民主主義は「政治的」(≠「経済的」「社会的」)平等が前提とされるが、相対的に非公開的で非制度的な「家族」においてはそのような平等の確保が難しいということである。田村氏は、これに対して、「対抗的」なコミュニケーションの習得や政治的平等の前提としての経済的不平等の実現、「退出」オプションの実質的保障、「子ども」の参加能力の再検討が解消につながると主張する。
第二の問題点は、「家族における民主主義」の無力性/無効性である。すなわち、家族における紛争や問題の原因は、家族の「外部」に求められるべきであって、「家族」という単位では解決できないのではないかということである。事実、妻と夫の発言力の格差は、経済格差に(も)由来しているのであり、その格差は国家レベル/社会構造の問題であるため家族のみでは解決できないのである。しかし、田村氏は構造決定論的な家族観に疑問を呈するかたちで応答する。つまり、マクロな「構造」のみが「家族」のあり方を規定するわけではないという主張である。むしろ上記のような構造決定論的な見解では、よりミクロな対抗の契機を不可視化してしまうという懸念から、非構造決定論的な家族観への転換を示す。
以上のことより、想定される主な二つの問題点を乗り越えることによって「家族における民主主義」は十分達成されうるし、家族における意思決定が「民主主義的」な形でおこなわれることが望ましいと語られた。
3.どこまでが「家族」か?
最後に、「家族における民主主義」を論じるにあたって、田村氏がどこまでを「家族」として捉えているのか話された。重要な点は、田村氏は「典型的な家族」のみを対象としているのではないことである。また、「家族」の具体的な形態や構成員の属性/背景に関わらず、「家族」内における意思決定には「民主主義」が望ましいのではないかという主張である。
上記のことを前提としたうえで、「民主主義の場としての家族」の境界線(外縁)について「熟議システム論」を援用して説明された。注目すべきは、熟議システム論を用いることで国家/政府のみに限定するのではない「小規模」な熟議システムのあり方や「家族」概念の拡張に可能性を見出すことができるということである。これについて、講演では、家事・育児役割にストレスを感じる女性(妻)が「家族」外部の「子育てグループ」内の女性と意見を交流するなかで、性別役割分業が問題であると考えるようになり、夫に伝えたところ夫婦間での家事・育児分担のあり方が変化したという(架空の)事例で具体的に説明された。つまり、この事例でいう「子育てグループ」は、「熟議システムとしての家族」の「公共空間」にあたり、「家族」の外縁を拡張したものとして捉えることができるということである。
そして、上記の視点を発展的に応用することで「国家」もまた「熟議システムとしての家族」の構成要素として捉え直すことができるのではないかという提案が最後になされた。換言するとこのような捉え直しにより、国家/政府が意思決定の中心であるという旧来の政治観の転換につながりうるということである。
田村氏による「家族」という場に「民主主義」の可能性を見出す提案は、依然として田村氏が想定するように「家族」の枠組みやあり方をめぐる観点から批判がおこなわれうるだろう。しかし、おそらく田村氏は「家族」という集団に強く固執しているというよりも、これまで学術領域や社会の認識として「政治」や「民主主義」の場としてみなされず、さらには「私的領域」として社会/政治から切り離されてきたような場/集団として「家族」が位置付けられてきたことを抜本的に批判する試みを目指しているのではないだろうか。すなわち、「家族における民主主義」の可能性を議論することは、既存の政治と国家を同一視する見方を見直し、人びとの様々な生活のレベルでの意思決定を「政治」的にとらえることにつながりうるのではないだろうかと私は考える。そして、そこにフェミニズムやクィア研究、社会学と政治学の結節点があるといえるだろう。今後は、政治学に留まらず、社会学による社会調査などによって田村氏の主張を検証し、裏付けや乗り越えていくことによる議論の深化が期待される。
(一橋大学大学院社会学研究科 修士課程 内田賢)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第52回(2021年12月3日)
日本の台湾認識とジェンダー
講師:洪郁如さん(一橋大学大学院社会学研究科・教授)
司会: 貴堂嘉之さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
第52回CGraSS公開レクチャー・シリーズでは、「日本の台湾認識とジェンダー」というタイトルで、一橋大学大学院社会学研究科教授の洪郁如氏にご講演いただいた。洪氏の専門は近現代台湾史であり、主な業績としては『近代台湾女性史-日本の植民統治と「新女性」の誕生』(勁草書房、2001年)、『誰の日本時代-ジェンダー・階層・帝国の台湾史』(法政大学出版局、2021年)などがある。『近代台湾女性史-日本の植民統治と「新女性」の誕生』は、植民地化の台湾女性、特に読み書きの教育を受けた「新女性」の存在に焦点を当て、その形成過程や社会的位相について論じた著作である。一方、最新刊の『誰の日本時代-ジェンダー・階層・帝国の台湾史』は、学校教育から排除された人々や農村漁村の住民、都市部の労働者階層など、今まで光の当たらなかった人々それぞれにとっての「日本時代」を問い直そうとする著作である。特に、「親日台湾」というような台湾認識をもとにした従来の歴史像に、女性史や家族史の立場から一石を投じようとする研究となっている。
本講演では、この『誰の日本時代-ジェンダー・階層・帝国の台湾史』の内容をもとにしながら、日本の台湾認識とジェンダーの視角から見えてくる従来の歴史の語りの問題点をご報告いただいた。以下、本講演の要旨と私自身の所感を述べる。
①「日本時代」を考える
はじめに、「日本時代」という言葉についてご解説いただいた。これは時期としていえば、いうまでもなく1895年から1945年まで日本が台湾を植民地支配していた時期のことである。ただし、かつての台湾では「日本占拠時代」、略して「日拠時代」という言葉を使っていた。これは日本の台湾植民地支配の非合法性、不当性が強調されている表現である。しかし、台湾の民主化以降、台湾の歴史学界ではこの不法性を強調する「占拠」ではなく「日本統治時代」という言葉を使おうとする共通認識が形成された。一方、台湾語話者の大多数の民衆は、修飾語の何もない「日本時代」という言葉を使っている。この「日本時代」という表現については、一部の研究者から「統治」という言葉が抜けることで、植民地統治という事実に目をそらすことにつながるのではないかと危惧する声もあるという。洪氏もこの危惧については理解しながらも、台湾民衆層の生活経験に基づいた言葉として「日本時代」を選んだと述べられた。同時に、洪氏は日本社会において「日本統治時代」という言葉が使われる際には、植民地支配に対する批判的な視点が失われており、むしろ日本の台湾植民地支配によって「近代化」がもたらされたというような意味になっているとして、歴史学界として看過できない問題であると指摘した。
②日本の台湾認識の変遷-日台の歴史記憶の非対称性と偏在性
次に、日本の台湾認識の流れを見ながら、日台の歴史記憶の非対称性をめぐる問題についてご解説いただいた。まず、台湾における「日本時代」の歴史研究では、日本の研究成果も参照されるのに対し、日本の台湾研究においては、台湾での歴史研究の成果が反映されていないという問題について言及された。また、日本の戦後の進歩的な知識人も台湾について語ることはなく、1972年の日中国交正常化以降はこうした傾向が一層鮮明になったそうである。その際、日本の台湾認識は、植民地台湾から蒋介石政権の中華民国という認識へと移行しており、台湾の問題は日本とは関係がないという姿勢にもなっていったと洪氏は指摘する。つまり、戦後日本の台湾の記憶は終戦直後台湾から引き揚げた日本人引揚者に限られたものだったのである。
③日本語世代の歴史経験と語りへの依存性の問題
しかし、1980年代後半の台湾民主化が、日本における台湾の「再発見」に大きな影響を与えることになる。特に、日本語が流暢で発信力もある李登輝が初の台湾出身の中華民国総統になったことや、1994年の司馬遼太郎『台湾紀行』の出版、日本のマスコミによる日本語の話せる台湾人へのインタビューなどを通して、「親日台湾」というイメージが形成されていったという。また、同時に民主主義の成熟している台湾というイメージも形成されていった。しかし、依然として日本が台湾を植民地支配していた時期についての認識については更新されておらず、むしろ、日本人の台湾における現地体験で「親日台湾」というイメージが強化されることもあると洪氏は指摘した。
④日本語世代というツールの限界性
ここでは、台湾の「日本時代」に関わる集合的記憶の再生産・再構築の問題に注目した。まず、洪氏は歴史研究のもととなる史料の形成過程について言及した。史料には、日本という植民地権力側の史料と日本語教育を受けさせられた台湾人側の史料があるが、そこには必然的に植民地「日本語教育」にゆかりのある人々を中心に歴史記述が形成されるという限界性がある。しかし、今までこの問題はあまり意識されてこなかったという。また、日本のマスコミが日本語教育を受けた台湾人の言説を採用する際の選別や台湾人本人が語る際の意志など、複合的な問題にも気を付ける必要性を洪氏は指摘した。さらに、世代間の差異の問題もあり、李登輝総統以後の世代とその前の世代とでは、歴史記憶の様相が異なっていることにも注意をする必要があるという。
⑤かつての非識字者層は今日の台湾市民社会の母体
ここで洪氏は、近現代台湾研究は長い間、非識字者層に着目してこなかったと指摘し、非識字者層を歴史において社会の底辺層や例外的な人々と捉えることに異議を唱えた。なぜなら、かつての非識字者層は「日本時代」の台湾民衆層の大半を占め、彼らを出自に持つ人々は戦後台湾市民社会を構成する主体だからだという。そのため、非識字者層の人々がどのように「日本時代」を経験し、感じてきたのか、そして戦後はどのように記憶してきたのか、という問題は日本の台湾認識を考えるうえで重要である。しかし、かつての非識字者層は植民地支配終了後においても当然ながら文字として記録を残すのが難しかったため、洪氏は歴史研究者として方法論的な壁にぶつかったそうである。そのため、『誰の日本時代-ジェンダー・階層・帝国の台湾史』は、洪氏の方法論的な試みの著作でもあったと述べられた。
また、洪氏は非識字者層とその家族の歴史記憶の断絶と衰退の問題についても言及され、実際の聴き取り調査でも、本人の親や祖父母が植民地受益層から排除されていた人々にもかかわらず、本人の歴史記憶は教育受益者の言説や植民地支配による「近代化」の言説を肯定的に踏襲したようなものになっているケースが多いと述べられた。
⑥植民地記憶と歴史記述の問いかけ―ジェンダーの視点から
ここからは、ジェンダーの問題が、識字をめぐる植民地経験やその歴史記述を規定しているという問題についてご解説いただいた。こうした問題を考えるうえで、読み書き能力の需要が高まるという時代の変化があったことを確認しておく必要があるという。「日本時代」以前は、人々は特に読み書きを身に付ける必要はなかったが、「日本時代」になると政治環境の変化や産業の変化に伴って、識字が社会的地位の上昇に大きく関係してくるようになり、識字への欲求が台湾内部で高まったのである。ここで留意しなくてはいけないのは、「識字」とは字の読み書きという意味に留まらないということである。ここでの「識字」とは漢文の書写に加え、日本語、基礎的な算術、新たな知識などを指す。しかし、多くの台湾民衆はこうした教育を受けることが難しかった。たとえば、台湾の伝統的な漢学塾は日本の植民地当局の圧力により崩壊し、日本の設けた近代学校における教育を受けられる人々も限られていた。
⑦ライフヒストリーのなかの読み書き(教育)の意味
そんな教育における階層の不平等があるなか、ジェンダーの不平等の問題により女性はより教育を受けることが難しかった。ただ、ここで注目すべきなのは簡易国語講習所においては、男子より女子の比率の方が2~3倍高かったということである。簡易国語教習所とは、修業年限1~4年、夜間に2~3時間の授業を行う常設の簡易初等教育機構である国語講習所とは異なり、修業期間は3~6ヶ月、夜間2~3時間、合計60日以上の授業を行うより簡易的な教育機関のことである(ただし、民衆側は両者とも「国語講習所」と認識)。
洪氏は、女子が国語講習所に通うことの背景としてまず、学校数も公学校より多く、通学距離も近いうえ、授業時間も短いため、家庭への負担が少なかったことをあげた。つまり、家父長権力と女性の妥協点として簡易国語講習所が選ばれていたのである。台湾総督府はこれをもって、同化政策がうまくいっていることの証拠として教育の普及ぶりを自画自賛したが、学習者の観点から見れば、彼女たちが国語講習所に通おうとした主な要因は、彼女たちの教育・識字への渇望であったことを洪氏は指摘した。しかし、彼女たちは短い国語講習所の授業が終わってしまえば、その後は自学自習をするしかなく、満足に国語講習所に通えないケースさえあった。
⑧自学自習の道と「断片化された学習形態」
洪氏はこうした彼女たちの学習形態を「断片化された学習形態」と呼ぶ。そしてその特徴は学習時間と空間の非連続性にあるという。洪氏はここで、のちに台湾共産党の創設者となった謝雪紅(1901~1970)の回想録を引用しながら、近代教育から排除された女性の学習経験の事例を紹介した。たとえば、謝雪紅は幼いころは日本人の子守りをしながら、簡単な日本語を教えてもらい、地面に枝で文字を書いて勉強していたという。また、就職後は新聞の切れ端を使い、人に聞きながら文字を覚えたという。こうした近代教育から排除された人々の学習方法は体系化されておらず、学習内容も日本語や漢文、古典文学、雑学など混沌としていた。さらに自学自習の場合、実際の会話により話す・聞く能力は比較的伸びても、読み・書き能力を伸ばすことは難しかった。
⑨彼女たちの「日本時代」
そんな謝雪紅にとっての識字は一体どのような意味を持っていたのか。洪氏によれば、謝雪紅が自身の断片化してしまった言語能力に困惑していたという。そして、本来近代の学知は植民地の苦悩の根源を解釈し、植民地権力に抵抗するための武器であったが、謝雪紅にとっては学知以前の識字の時点から大きな壁があったということを意識しなければいけないと洪氏は強調された。
次に、洪氏本人の家族史、特に農民の娘として生まれた洪氏の母方の祖母の経験についてもご紹介いただいた。洪氏によると、洪氏の祖母は識字の意欲が高かったという。そんな祖母が自学自習を始めたのは還暦を迎えた1985年頃からであり、自分の力で生きていきたいとおもちゃ屋さんの経営を始め、経営のために字や数字を学ぶようになったそうである。洪氏自身も学生時代、祖母のたどたどしい数字や領収書に書く自分の名前を見ており、あとから考えると胸が痛くなると述べられた。洪氏の祖母は洪氏のいとこが小学校から持って帰ってきた勉強道具を使いながら、文字を自力で学んだという。
⑩「日本時代」を語るまで
次に、洪氏は謝雪紅と洪氏の祖母が「日本時代」を語るようになるまでは長い道のりがあったと述べられた。たとえば、謝雪紅が自らの一生を再解釈できるようになったのは、1960年代に入ってからであったという。しかし、謝雪紅の「日本時代」についての語りは淡々としており、自伝のなかでも「日本帝国主義者が収奪した植民地台湾人民の血と汗と金によって、普通の日本人職員があのような豪華な生活を送ることができたことは、当時の私は知る由もなかった」という部分が最も植民地批判が現れている部分だと解説された。
また、洪氏の祖母については、洪氏が中国研究をしている日本人の親友を台湾に連れていった際の話をご紹介いただいた。洪氏の親友は洪氏の祖母に会った際、祖母に植民地支配について謝ったという。しかし祖母の反応は特になく、その代わりに自分の顔を指しながら、「鼻、目、耳、口」とゆっくり言葉を発したそうである。これは祖母が知っている日本語を使った精一杯の歓迎の気持ちであり、洪氏にとっては様々なことを考えさせられる瞬間だと述べられた。
洪氏はこうした「日本時代」の歴史記憶の存在は忘れてはならず、ジェンダーと階層の不平等が残した影響は、今に至って、戦後台湾の「日本時代」の言説のあり方、そして日本の台湾認識まで大きく規定していると指摘した。
⑪「台湾近代化の父」とされる日本人たち
ご報告の最後では、帝国書院の中学校歴史教科書における台湾記述をご紹介いただいた。洪氏が示したのは、台湾において烏山頭ダムをつくった総督府の技術官僚である八田與一が紹介されている部分である。洪氏によれば、八田は教育現場で有名な人物であり、八田の墓は台湾修学旅行の目的地として指定されているという。つまり、八田は「台湾近代化の父」の一人として教えられているのである。洪氏は最後に、こうした現象について、台湾の「日本時代」/日本の「台湾時代」を語る際、私たちはどう向き合い、どう考えたらいいのかという問題提起でご講演を締めくくられた。
質疑応答ではいくつかの質問がなされたが、最後に貴堂嘉之先生がなされた『誰の日本時代-ジェンダー・階層・帝国の台湾史』において「和解」にはどのような意味が込められているのかという質問と洪氏の答えが印象的だったので紹介したい。洪氏によると、台湾はそもそも東アジアにおける「和解」についての議論の対象から長い間外されていたと指摘する。つまり、台湾の「和解」の問題は不可視化されていたのである。そのうえで、洪氏は「和解」の仕方の可能性について、それは謝罪するかしないかの問題ではなく、知ることであると指摘する。洪氏は最後に、知ることはすべての歴史記憶に対する誠実な第一歩ではないかと考えていると述べられた。
おわりに、私自身の洪氏のご講演を聞いての簡単なコメントをしたい。本講演では、序盤に日本社会における「親日台湾」というイメージの形成について述べられていたが、朝鮮近現代史を専攻する私としては「反日韓国」という日本社会の韓国(朝鮮)に対するイメージの問題を想起せずにはいられなかった。ここで私が着目するべきだと感じたのは、日本社会において台湾と韓国(朝鮮)は一見正反対のイメージを持たれていながら、どちらも植民地支配の歴史についての認識が更新されていないという共通の問題である。また、講演では、日本人の台湾現地経験によって「親日台湾」というイメージが強化され、植民地支配の歴史の不可視化につながるということが指摘されていたが、それは近年の日本人の韓国に対する認識の問題を考えてみても同様の問題があろう。たとえば、韓国に旅行した際に現地の韓国人の温かい対応を受けて、「反日ではなかった」と安心したという日本人の声も聞くが、これは「反日」という本来韓国から日本に対する正当な批判を不可視化しているという意味で、まさに現地体験が植民地支配の認識の不更新につながっているケースだといえるだろう。こうしたことを考えると、「親日」「反日」とは植民地支配認識の欠落に基づく表裏一体のものであり、日本にとって友好的か友好的でないかという基準で相手をジャッジする日本中心的な一種の植民地主義のあらわれなのではないかと改めて思わされた。
また、講演の中心的な内容である非識字者層の経験とジェンダーについては、洪氏がこうした非識字者層を社会の底辺としてではなく、戦後の台湾市民社会の母体として捉えることで、戦後の語りまで射程に入れて一人ひとりの感情を描き出そうとしている点が印象的であった。私の研究対象地域である朝鮮でも、台湾と同じく多くの民衆は教育の機会から排除されていた。そして民族だけではなく階層やジェンダーの要因が民衆の教育経験を規定しており、朝鮮人女性は朝鮮人男性よりも教育から疎外されていた。私自身、こうした植民地権力の朝鮮人に対する教育排除の実態に着目しがちであったが、洪氏のご講演を受けて同時にそうした非識字者層の個別具体的な教育疎外の経験とその後の人生についても着目していくことが植民地支配を経験した一人ひとりの感情に迫ることにつながるのではないかと感じさせれた。その際に問題となるのは、やはり非識字者層の声は史料として残りづらいということであるが、その意味で洪氏の研究は文字を残せない民衆の経験をいかに描くかという歴史学の古典的な問いに対する一つの実践例だと思う。私自身も朝鮮における非識字者層、特に女性の経験をいかにあぶりだしていけるのか、今後の勉強・研究のなかで模索していきたい。
(一橋大学社会学部 熊野功英)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第51回(2021年11月24日)
離婚後の子の監護のあり方とジェンダー
講師:千田有紀さん(武蔵大学社会学部・教授)
司会: 貴堂嘉之さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
第51回CGraSS公開レクチャー・シリーズでは、「離婚後の子の監護のあり方とジェンダー」と題し、武蔵大学社会学部教授の千田有紀さんにご講演いただいた。
千田さんは、近年、法学者や弁護士、全国的運動組織、議員連盟等によって活発に論じられている共同親権問題について、ジェンダー研究者・家族社会学者としての知見に基づき、主にDV、虐待による家族紛争の事例の調査・研究を通して重要な指摘をおこなっている。今回のご講演の内容に関する主要なご著書として、『離婚後の子の監護と面会交流——子どもの心身の健康な発達のために』『離婚後の共同親権とはなにか——子どもの視点から考える』『離婚後の子どもをどう守るか——「子どもの利益」と「親の利益」』(すべて共著)がある。
本講演では、共同親権と子の監護の背景にある構造的な問題について、国内外の事例を取り入れながら、ジェンダーの視点からの鋭いメスを入れてくださった。講演の内容のメインポイントは、司法における形式的平等の理念によって生じる問題、裁判所や社会におけるDVへの無理解、虐待や共同親権における母親への社会の厳しい評価やバッシング、そして裁判所による離婚後の「理想的な親子のあり方」の措定の問題についてであった。以下に、まず千田さんのご講演内容の要点を順に述べる。
裁判所は「男女平等」で「公平」な機関なのか?
千田さんは、裁判所は「男女平等」で「公平」な機関なのかを問うことから講演を始められた。裁判所は「形式的平等」や「中立性」を装っているものの、実際には家父長制が根強い日本社会において例外的存在ではない。 このため、日本社会における離婚後の子の監護をめぐる問題は、男女の非対称な現状を踏まえて慎重に対応しなければ、「子どもの利益」を守ることができないだけではなく、DV被害者の女性や子どもたちの生命が危ぶまれる最悪の事態を招きかねないという点が考慮されなければならないのである。
裁判所による「理想的な家族像」に基づいた介入
家庭裁判所は、「特定のライフスタイル」を理想とし、家族に介入している。裁判所が「あるべき家族像」を掲げ家族へ介入するといった権力の家族への介入は、1980年にジャック・ドンズロによって指摘されている。ドンズロは、国家が近代家族に介入・規制する管理装置としての「保護複合体」の存在を指摘した。裁判所・社会事業・精神分析などの「保護複合体」の諸制度が、子どもを「守る」ために家族に介入するのである。前近代では多くの子どもが捨てられていたが、近代国民国家が形成されていくにしたがって、子どもが亡くなっていくのはもったいないというまなざしの出現がある。子どもは将来の「国民」を構成するものであって、国力を成すものであると考えられるようになり、まさにフーコーの言う「個別的かつ全体的に」といった国家による「国民=人口」の管理がおこなわれるようになったのである。子どもの保護がおこなわれるようになるが、「保護」は介入と表裏一体であり、保護複合体の諸制度が、「理想的な家族像」を掲げ、家族へ介入していくという権力の働きが問題化されるようになった。裁判所はまさにその保護複合体の頂点を成している。
他方で戦後の日本の家族について考えてみると、戦前に比べ戦後では、家族に法は積極的に介入しないことが「民主化」であると考えられた。なぜなら戦前の家父長制を反省することが戦後の社会科学の前提だったわけであり、戦争責任は家父長制的な家族を形成したことにあると考えられたからである。そのため、家父長制から民主制へ移行し、家族は家制度から米国的な民主的な家族、つまり「近代家族」にならなくてはならないと、戦後の社会科学では考えられるようになった。そして法が家族に介入しないことが社会や家族の民主化であると認識されるようになったのである。
家族に介入しないといっても、近代国民国家における家族は国家によって形成されている側面があり、実際には家族に介入している。しかし、あたかも家族に介入しないという「民主化」が目指されることによって、家族における暴力や虐待に法は介入せず、そうした問題はブラックボックス化されてしまった。例えば、DVについても「民事不介入」という取り決めが行われてしまったのである。
近代家族とジェンダー:「形式的平等」による問題が生じる歴史的背景
戦後の日本の家族制度と法の関係において、戦後強くなったのは「妻の座」であり、法は実質的に結婚した専業主婦女性を保護し、それ以外は排除してきた。そうした近代家族を前提とする「平等」が問題とされ、それが女性解放だと言われたのが、日本の戦後であると千田さんは指摘する。このように戦後は、近代家族の保護、近代家族における女性の保護が展開されていった。
では、近代家族とジェンダーの関係はどのようなものになっているのだろうか。千田さんは近代家族を「政治的・経済的単位である私的領域であり、夫が稼ぎ手であり妻が家事に責任をもつという性別役割分業が成立しており、ある種の規範のセット(『ロマンティックラヴ』、『母性』、『家庭』イデオロギー)を伴う」と定義する。こうした定義によって女性は社会のなかで弱い立場に置かれている。実際に現代の日本社会では、第一子出産のために半数近くの女性が離職し、女性の6割は無職になっている。なぜなら女性は出産・育児・介護など「家族のために」離職するからである。加えて女性の過半数は非正規雇用であり、家事育児のほとんどを女性が担っている。
平成16年に厚生年金保険法が改正され、平成19年より、公的年金の基礎部分が分割されるようになり、離婚後の女性の貧困の緩和が実施された。しかし、ここには近代家族を前提とした改革のパラドックスが存在する。女性が働き、男性が働きもせず家事育児をしない夫婦の場合、女性は財産分与や年金分割によって生活の基盤を奪われる。つまり性別役割分業を前提としている制度であるため、実際には夫が家事育児もせず、稼がなかった場合において、女性側が離婚後に元夫に支払い続けることを命じられるのだ。女性が担わされてきた家事・育児に対する賃金は支払われることはないが、「形式的平等」のもと、離婚後は「平等な負担」が求められる。しかし、現実には女性は労働市場で不利な状況に置かれ、男女間のれっきとした賃金格差が存在し、ケア役割を果たさない女性へのサンクション(制裁)を受ける。一方それに対して男性は労働市場での優位性を保持したまま、離婚後も女性から収入を得る続ことが可能になる。このように、性規範や賃金格差などの不均衡で不平等な社会システムが温存されている状態で、性別非関与で形式的な「平等」を法規範が適用されることには問題がある。この場合、リベラリズムの論理が差別的状況の継続や搾取を促し、不平等を隠ぺいし、さらなる不平等を作り出してしまうのである。
離婚後の家族をめぐる新しい動き
このような離婚後の子どもの監護のめぐる問題について社会学的視点から研究はほとんどなされてこなかった。このため、現状を把握するエビデンスがないままに、リベラリズムなどの理念によって、離婚後の子どもをめぐる法改正が議論されている状況が続いている。
離婚後の子をめぐる法改正を整理すると、まず大きな影響があったものとして2012年の766条の民法改正がある。この改正をきっかけに裁判所は「原則面会交流」へと舵を切った。さらに離婚後の親権をめぐっては、父母のDVは「夫婦間の問題」として不問とされ、子への虐待認定は困難を極め、子どもの意思を反映しない判例が下されるようになった。 特に憂慮すべきなのは、子の親権をめぐる裁判において、DVへの無理解が浮き彫りになっている点である。DV被害を受けた女性たちは、裁判で、「自分の恨みつらみは忘れて、子どものために何とかしろ」と助言されることが少なくない。厚生労働章の委託事業所が作成したパンフレットには、「DVは親の一方が被害者だと思われがちですが、子どもにとっては、両親とも加害者です」と明記されている。男性から女性へ行われる暴力が圧倒的に多く、また被害も深刻であることを考慮すると、司法の側(家庭裁判所)にDVの無理解があることは明らかである。主たる監護者になることが多いDV「被害者」である母親が、「加害者」として表象されることは重大な問題である。
母親としての責任という重圧の増加
こうした裁判所によるDVへの無理解は、子への虐待に関する裁判において、女性に対する非常に厳しい判決につながってしまう。母親の責任がことさら大きく問題視され、DV被害者であるにもかかわらず子どもを守らなかったことの非難の対象となる。実際に、米国ではDV被害者である母親が、面前DVなどから「子どもを保護できなかった加害者」であるとみなされるといった問題が深刻化している。判例のなかには、DV加害者である夫の子への虐待に対する懲役が2年にであったのに対して、「きちんと暴力に介入しなかった」罪として母親に対する懲役が30年であったケースもある。こうした判例の原因には、家庭裁判所の裁判官たちのガイドラインに、DVへの配慮がなかった点が指摘される。夫から殴られている女性は、養育パートナーとして位置づけられ、子どもが面前DVに晒されているのに止められなかった場合には、「虐待の加害者」とされるのである。こうした事例は、日本でも野田判決や目黒判決にみられる。子への虐待をめぐっては、社会や裁判所は、母親に対して非常に厳しく、加害者は父親でもあっても虐待は母親の責任であるとされるのである。
両親との面会交流や共同監護の問題点:共同親権は男女共同参画なのか
海外の共同親権運動は、男性権利回復運動と呼ばれており、往々にして「女ばかりが得をしている」という反フェミニズム運動的性格を伴う。運動の多くは男性たちによって行われており、彼らは男女に「平等な権利」を訴えている自分たちこそが「真のフェミニスト」であると主張する。こうした父権運動が生じた要因の一つには、父親への養育費の厳しい取り立てへのバックラッシュがあるといわれている。
共同親権は家父長制的性格と脱性別化を内包している。海外では父親に家父長としての地位を保持させ、父親への「対等の権利賦与」と「子育ての分担」という理念から、共同親権などに関する法改正が行われている。さらに、父親が親権を持たない場合も、父親に面会交流の権利を無制限に与えるがために、親権をもつ母親が自分や子どもを顧慮する権利が制限されるという状況が生じている。千田さんは、このような状況について、マーサ・A・ファインマンのポスト平等主義の議論を援用しながら、リベラルフェミニズムの持っていたジェンダー中立性のレトリックの盗用がおこなわれていると指摘する。養育費の取り立てが法令で厳しく定められたことがきっかけで、父親団体が生まれ、性差に関係なく「男女平等」に扱うというリベラリズムのジェンダー中立性のレトリックが巧みに用いられた結果として、親権をめぐる裁判におけるジェンダーの考慮が禁じられるようになった。
***********(以下、コメント)
千田さんはご講演の最後に、DV夫と妻子との間における共同親権や面会交流をめぐる問題を描いた映画『ジュリアン』を紹介された。講演では詳細についてうかがう時間はなかったが、ご論考「共同親権は何を引き起こすのか?——映画『ジュリアン』を手掛かりにして」(『離婚後の共同親権とはなにか——子どもの視点から考える』)から学ぶことができる。(たとえ暴力的なDV夫だとしても)離婚後も父親に会うことが子どもにとって良いこととする裁判所が措定していること、また子どもや母親の「証言」は聞き取られないか、父親に有利な「証言」に歪めて解釈する裁判の実態やプロセスなどの、共同親権をめぐって妻子が直面する問題が詳細に描かれている。「形式的平等」の理念や離婚後の「理想的な家族像」を裁判所が追求することによって、暴力的な夫に「平等に」親権を与えてしまっている。これは、裁判所が主張するように本当に「子どものため」になっているのだろうか。DV被害者である母親は本当に「加害者」なのか。これらを考えるための手がかりとして、妻子の身に実際何が生じているのかについて把握する必要があるのではないかと千田さんは述べる。これまで、ジェンダー不平等の問題や妻子の現状を考慮しないで、理念や理想を掲げて共同親権をめぐる議論が進んできたことにより、もっとも弱い立場の人びとが置き去りにされてきたと言わざるを得ないのである。
講演後の質疑応答では、共同親権を社会学で問うことの意味について質問があった。千田さんは、法規範が社会システムにどのような影響を与えるのかを検討することが社会学の役割の一つなのではないかと回答した。つまり共同親権を法律の問題として片づけるのではなく、法律のもとで制定される制度が社会に与える影響を検討し、実際に何が起きているかについて弱者の視点から把握することが、社会学アプローチによって可能になるのである。特定の法理念や制度によって、実際の社会において何が生じており、そしてそれらは「誰のための」ものになっているのかを、声が反映されにくい人々に寄り添って、常に問い直していかなくてはならないということを本講演から学ぶことができた。
(一橋大学大学院社会学研究科 修士課程 土屋匠平)
参考文献
千田有紀「家族紛争と司法の役割——社会学の立場から」『離婚後の子の監護と面会交流——子どもの心身の健康な発達のために』(梶村太市・長谷川京子・吉田容子編)日本評論社(2018)
————「共同親権は何を引き起こすのか?——映画『ジュリアン』を手掛かりにして」『離婚後の共同親権とはなにか——子どもの視点から考える』(梶村太市・長谷川京子・吉田容子編)日本評論社(2019)
————「DV、虐待事件から考える『子どもの利益』と『親の利益』」『離婚後の子どもをどう守るか——「子どもの利益」と「親の利益」』(梶村太市・長谷川京子・吉田容子編)日本評論社(2020)
上野千鶴子「共同親権の罠——ポスト平等主義のフェミニズム法理論から」『離婚後の子どもをどう守るか』同上。
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第50回(2021年10月6日)
「性愛規範と最小結婚―シェアハウス研究との接点から―」
講師:久保田裕之さん(日本大学文理学部・教授)
司会: 田中亜以子さん(一橋大学大学院社会学研究科講師)
参加記
第50回CGraSS公開レクチャーシリーズでは、「性愛規範と最小結婚―シェアハウス研究との接点から―」と題し、日本大学文理学部教授の久保田裕之氏にご講演いただいた。久保田氏は、エリザベス・ブレイク(以下:ブレイク)の著書『最小の結婚』の監訳者である。久保田氏には、自身のシェアハウス研究(以下:シェア研究)をご紹介いただき、そこから得られた知見を踏まえたうえで『最小の結婚』における核となる議論について、ご報告いただいた。
本講演は、「序:シェア研究と非性愛関係への着目」、「議論の準備:性の法/ケアの法/共同性の法」、「『狭義のケア』と結婚の再編(M. Fineman)」、「『広義のケア』と最小結婚(E. Brake)」、「Brakeが関わる倫理学的な仕事」という5つの部分により構成されている。
1シェア研究と非性愛関係への着目
はじめに、久保田氏は自身のシェアハウス経験を通して、共同生活における構造的利点への気づきから、シェア研究に携わったきっかけと経緯および、研究を進めていくにつれ、日本社会における婚姻や家族に関する根強い規範的想定に直面することについて述べられた。根強い規範として、「家族中心主義」、「性愛中心主義」を挙げられ、久保田氏はこれらに向き合いながら、非性愛的関係について深く探究することで、理論的土台を整えていかれた。
2議論の準備:性の法/ケアの法/共同性の法
「結婚」を通して成人間のケア関係が形成されており、それによって成人間、ほとんどの場合は二人、一男一女がケア関係を形成する仕組みがある種、社会的規範として存在する。しかし同時に「結婚」というシステムに参入するにはジェンダー、セクシュアリティ、性関係、ときには人種というさまざまな要因から生じる制限により排除や社会的不正義がうまれる。結婚以外の方法で生きることは可能になるだろうか。こうした問題意識をもち、久保田氏はまず「標準(完全)パッケージとしての家族」という概念を取り上げた。「標準(完全)パッケージとしての家族」には、「ロマンティック・ラブ・コンプレックス(恋愛的愛の複合体)の歴史性」が含意されていることに留意すべきである。つまり、何をもって「家族」が構成されるかは、不変的でなく、歴史的偶発的である。『最小の結婚』の序章でも、アメリカ社会の文脈から婚姻史が論じられ、宗教、人種とのかかわりについての概説が書かれていた。また、日本の婚姻・家族法でもこのような恋愛的愛の複合体が想定されている。例えば性関係の法では異性であること、ケア関係の法では嫡出・出産・認知による親の権利義務、共同生活関係の法では同姓であることが規定される側面から見出される。
続いて、『最小の結婚』に関する議論に入る前に「ケア」という用語的使い方に言及され、『最小の結婚』を読む上で「ケア」概念に留意すべき重要な点が解説された。「ケア」には「狭義のケア」と「広義のケア」が含まれており、「狭義のケア」は「世話」、つまり他人に依存しないと生きられない状態の相手に対するケアのことを指すのに対し、「広義のケア」は「対等な人間関係における配慮や気遣い全般」を意味している。「狭義のケア」は主にフェミニスト法学、倫理学で論じられているが、他方で「広義のケア」は教育学、看護学の領域で広く捉えられ、研究されている。久保田氏は『最小の結婚』において著者ブレイクは議論を展開する際に想定している「ケア」のレベルは後者の「広義のケア」であることに注意深く把握する必要があると述べた。
3「狭義のケア」と結婚の再編
ここからは、既に言及された「狭義のケア」と「広義のケア」の詳細、それぞれが「結婚」の議論にどのようにかかわっているかについてご解説いただいた。まず「狭義のケア」を論じるために、フェミニスト法学者であるマーサ・A・ファインマン(以下:ファインマン)による著書“The Neutered Mother, the Sexual Family”(1996)(邦訳:『家族、積みすぎた方舟』)が取り上げられた。ファインマンは「依存」をフェミニスト的視点から考え、理論化を試みた。ファインマンによると「依存」は二種類に分類される。一人では生きられない状態の「不可避の依存」と、不可避の依存をケアするために経済的依存状態に陥る「派生的依存」である。「不可避の依存」は人間の宿命とも言えるものであるのに対し、「派生的依存」は社会的に作られるものである。ファインマンの考えでは従来の性関係を支える「結婚」の体制は、もはや「不可避の依存」および「派生的依存」を支えるのに十分に機能していない。そこで提案されたのは法的婚姻の廃棄であり、法的保護の単位は直接「依存―ケア関係」になり、「依存をケアするあらゆる関係」を保護の対象にすることである。すなわち「不可避の依存」は、あるいは先述した「狭義の依存」と言っても良いが、直接的に社会全体による支援を受ける必要があるということになる(政府によるケア支援の正当化)。だが一方、ファインマンは成人間のケア、つまり「広義の依存」を議論の射程外にしたところは、『最小の結婚』におけるブレイクの議論の前提と顕著に違いが見られる点と言える。ファインマンは成人間のケア、成人同士の関係を自由にすると主張するのに対してブレイクは成人間のケア関係を元に最小結婚を構想したのである。久保田氏はファインマンの主張に対して、「家族と同視されてきた共同生活関係」などの例に挙げ、「性愛関係を含む成人間の関係一切を私的自治に放逐してかまわないのか?」と異議を唱えた。
4『広義のケア』と最小結婚
以上のように、ファインマンによる「狭義のケア」をめぐる「結婚」の構想に関する議論を踏まえたうえで、次に「広義のケア」に着眼したブレイクの『最小の結婚』の内容に入った。本書の問いは、①「現行の婚姻制度は正義にかなったものか?」および②「正義にかなった婚姻とはどのようなものか?」という2点である。①「現行の婚姻制度は正義にかなったものか?」に対し、結婚の道徳哲学、とりわけ「性愛規範性」(amato-normativity)概念を把握することが重要であった。「性愛規範性」は、「異性愛規範性」(hetero-normativity)を念頭に作られ、中心的で一対一の恋愛関係性こそが人間にとって正常であり普遍的に共有されるもの(普遍性の想定)、そしてそれが他の形の関係よりも優先して目指されるべきである(優先性の想定)ということに基づいている。「性愛規範性」は、必ずしも成長や徳をもたらすとは限らないのに加え、有害をもたらす場合(例えば結婚や恋愛内部の暴力)やそれを不可視化させてしまう場合があること(本書3章参照)から、正義にかなうとはいけないにもかかわらず、不合理に正当化され続けてきた。そこでブレイクは「最小結婚」の構想に至り、「最小結婚のみが婚姻制度と政治的リベラリズムを両立させる」ことができると主張する。「最小結婚」とは、ケアの関係性について制約を設けないものであり、「国家は結婚に伴う権利を互恵的で完全なものとして取り交わすことを求めることは許されず、非対称で分割されたものとしてでなければならない」(Brake2012=2019:269)と定められる。ここでケア関係は繰り返し指摘されたように「広義のケア」を指しており、また、子育ては別制度として、結婚から切り離されるべきものとされる。すなわちブレイクの議論における肝心なところは、結婚に付与される経済的利益の正当性をなくし、その際に「地位の任意指定」(self-designation of status)によって「結婚」でしか得られなかったケアに関わる権利を、合理的な範囲で対象、人数を問わず自由に分割して取り結ぶことや取り消すことを可能にしようとするところにある。
続いて、よく見られるブレイクへの批判として、「最小結婚」はなぜ「結婚」という名称を使用しつづけ、「結婚」を手放さないのかというものがあることに言及された。ブレイクはこれに関して「政府の修復的責任」として、結婚のあり方の修復的作業として「民営でなく国家関与が必要であるため、結婚の廃止ではなく改革こそ平等なシティズンシップの促進につながる」と述べているという。また、久保田氏自身は疑問として、ブレイクの構想において「広義のケア」が想定される一方で、「狭義のケア」をどのように保障するのか不透明である点を挙げられた。
最後に、より多方面からブレイクの主張を紹介するため、久保田氏はブレイクの他の倫理学的業績を紹介された。ブレイクによる「生殖倫理」領域における「意思」説とは、生物学的に母であることと倫理的、法的に親であることを切断する主張であるという。
講演を通して改めて本書があぶり出そうとしている、性愛規範性、現行の婚姻制度の正当性を懐疑的に検討し、かつ緻密な論理展開を通して、モノガミーな性愛的関係性が当たり前とみなされる社会規範がどれだけ根強く存在し、かつさまざまな周縁化と排除をうんでいることについて理解が深まった。本書を読むことで、婚姻制度によって構造的不平等が温存されることを認識し、反婚視座を打ち出すクィア研究における批判的視点を再確認することができた。また本書には、「正義にかなった婚姻」という問題提起を通して、「不正義」に満ちた現行の婚姻制度を問い直す・撹乱する点に重要な意義がある。しかし一方、クィア研究では婚姻制度そのものの解体に焦点が当てられるのに対し、講演でも触れられた本書において「婚姻」の枠組みが保持されている理由を、まだ不勉強ではあるがより一層検討する必要があるように感じた。クィア研究で目指されるものと本書との接続をいかに捉えるか、今後勉強を進めながら考えていきたい。
(一橋大学大学院修士課程 孟令斉)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第49回(2021年7月21日)
〈ヤンチャな子ら〉の大人への移行と男性性
講師:知念渉さん(神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部・講師)
司会: 山田哲也さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
第49回CGraSS公開レクチャーは、「〈ヤンチャな子ら〉の大人への移行と男性性」と題し神田外語大学講師の知念渉氏にご講演いただいた。
知念氏は、2009年~2012年までの間に、大阪府にある公立X高校で、教師や他の生徒たちから〈ヤンチャな子ら〉と呼ばれる生徒たちを対象として参与観察を行った。今回のレクチャーでは、この調査分析をまとめた博士論文をもとに出版され話題となった知念氏の著書『〈ヤンチャな子ら〉のエスノグラフィー』を、「大人への移行と男性性」という2つのテーマで再構成してご講演いただいた。
1.英語圏における労働者階級の男性性に関する経験的研究
知念氏の研究は、イギリスの社会学者ポール・ウィリスに強く影響を受けている。「〈ヤンチャな子ら〉の大人への移行と男性性」についてレクチャーをはじめる前に、ウィリスとそれ以降の英語圏における労働者階の男性性に関する研究動向についてご紹介いただいた。
ウィリスの研究は、労働者階級の生徒たちのなかでも反学校文化を身につけた〈野郎ども〉のもつ女性差別や〈耳穴っこ〉と呼ばれる同性たちへの優越感が描かれ、1970年代のイギリスの労働者階級男性の文化を分析した男性性研究として評価できるものである。この後、イギリスは脱工業化という変遷をたどり、〈野郎ども〉の就くような肉体労働は大幅に縮小され、サービス産業化が進んでいった。ウィリスは、これ以降〈野郎ども〉の労働者階級の文化もまた衰退していくであろうと予見していた。
英語圏では、労働者階級男性の文化とは別に、「男性性の理論化」という大きな仕事が、1980年代にオーストラリアの社会学者ロバート・W・コンネルによってなされた。コンネルは、男性性の複数性と階層性をモデル化した理論を提唱した。複数の男性を従えかつ女性を支配する「ヘゲモニックな男性性」を文化的に最も優位な男性性として、それ以下に「共謀的な男性性」「従属的な男性性」を位置づけた。また、人種や階級と交差するかたちで生み出される男性性を「周辺化された男性性」と呼ぶ。
コンネルの「ヘゲモニックな男性性」についてはさまざまな議論があるものの、英語圏では、ウィリスの『ハマータウンの野郎ども』にコンネルの理論を組み合わせるようなかたちで、さまざまな研究が蓄積されてきた。労働者階級男性の男性性は典型的に表象されてきたが、産業構造の変容を受けた2000年代の研究では、男性性がどのように再編されているのか、極端に表象されてきた男性性とは矛盾するような実践が行われている実態や、そもそも〈野郎ども〉こそ労働者階級男性の中ではマイノリティではないか、など、その再編のあり方が盛んに論じられている。
2.日本の若者研究と男性性研究
日本における「ヘゲモニックな男性性」は、サラリーマンとして表象されてきた。ポストバブル経済の不安定化に伴い、「オタク」や「草食系男子」といった「新しい」男性性が構築されているのではないかという議論もあるが、R.ダスグプタは、サラリーマンは1950年代、60年代のように、社会経済的理想像になりつつある一方で、新自由主義の中で個人化・流動化し、より「自由な」像に再編されていることを指摘している。サラリーマンという男性性の形式は、外圧や論争を受けて変化しているかもしれないが、コアのイデオロギーの前提(労働、異性愛的な再生産の主体)は変わっていない。
日本の「周辺化された男性性」については、労働者階級男性はキャリアよりもいわゆる「手に職」を重視する、脱工業化によって職人や匠にもスピードが重視され彼らの仕事の中身が再編されている、どんな職業に就くのかが自分が何者であるのか「男らしく」あれるのかという問いに結びつき日常的な消費へつながる、といった分析がある。
日本の「周辺化された男性性」の分析は、「サラリーマン的な男性性」といかなる関係にあるのかという点で議論の余地を残した状態にある。よって、知念氏は、英語圏の男性性研究を参照しながら、日本の男性たちの性内分化に焦点を当てること、男性も「ジェンダー化された存在」であることに留意し、〈ヤンチャな子ら〉の実践のなかにある「男性」としてのアイデンティティを分析してゆくことになった。
3.〈ヤンチャな子ら〉の男性性
知念氏は調査を行う中で、〈ヤンチャな子ら〉は自らを〈ヤンチャな子ら〉と自称することはほぼなかったが、自分たち以外の生徒たちを男女問わず〈インキャラ〉と呼び、攻撃・嘲笑することが多々あることに気づいたという。
この〈インキャラ〉という解釈枠組みが、適用場面にどのように組み込まれているのかを分析する際、リチャード・ホーソンによる男性性の三原理に依拠した。ホーソンは、コンネルのジェンダー構造モデルを手がかりにして、西洋社会を中心とした男性性の支配構造は「大黒柱の原理」「異性愛の原理」「攻撃性の原理」の3つに支えられているとした。
そもそも〈ヤンチャな子ら〉が教師や他の生徒からそう呼ばれるのは暴力的な逸脱行為や非行を意味する〈ヤンチャ〉な行動をとるためであるが、彼らは日常的に〈ヤンチャ〉をするわけではない。そこで、日常の中では〈インキャラ〉という言葉を用いることで、自分たちが〈ヤンチャ〉であることを表明し互いの立ち位置を確認し合っている。
しかし、すべての〈ヤンチャな子ら〉が、仲間外の生徒たちを〈インキャラ〉と呼んで「異性愛の原理」や「攻撃性の原理」にもとづく実践を行うというわけでもない。特に、学年進行にともない、他者を〈インキャラ〉と呼んであからさまに攻撃したり嘲笑することは「子ども」だとみなされるようになっていった。肯定的に評価されてきた〈ヤンチャ〉な行為へ異議申し立てを行ったのは〈ヤンチャな子ら〉内部でも一目置かれた生徒だったのに対し、〈ヤンチャな子ら〉内部において周辺的な地位にあった生徒は積極的に〈インキャラ〉を攻撃・嘲笑することで自らを〈ヤンチャな子ら〉内部に位置づけなくてはならなかった。〈ヤンチャな子ら〉は外見などのスタイルをある程度共有しているため一つの集団としてみなすことができる一方で、高校入学以前の〈ヤンチャ〉経歴の違いによって、内部に階層性が生じているのである。
ヤンチャな子ら〉の男性性の再定義は、「攻撃性の原理」より「大黒柱の原理」が強調されるようになっただけでなく、カネの甲斐性で他の男をひれ伏すといった意味も含まれており、金を稼ぐことそのものが「男らしさ」の象徴であるといった段階への移行であるとみることができる。
『ハマータウンの野郎ども』では工場労働がホワイトカラー職に対して「男らしさ」の点で優越すると〈野郎ども〉から語られたのに対して、〈ヤンチャな子ら〉からはサラリーマンに対する忌避感や批判はみられなかった。〈ヤンチャな子ら〉にとってサラリーマンはかなり遠い存在であり、〈野郎ども〉の発したような批判は生まれさえしないのである。
〈ヤンチャな子ら〉の男性性の中核は異性愛・大黒柱を中核としている点では「サラリーマン的な男性性」と同様であるが、「良いお父さん」像は中流階級のそれよりも強いのではないかと考えることができる。特に、〈ヤンチャな子ら〉の中でも両親の離別を経験したり、定位家族の不安定を経験している生徒からは、自身の親を反面教師にした「理想の家族」や「怖いけどやさしい父親」像が語られている。
4.打越の研究からみる沖縄の建設業の男性たち
知念氏のもともとの関心は、脱工業化した時代の若者・男性性はどのようになっているかというものであった。しかし、特定の仕事が地域の産業として結びつかない調査地であったためか、高校を経由した調査であったためか、男性性と特定の職業との結びつきという問いは『〈ヤンチャな子ら〉のエスノグラフィー』時点では不明瞭なままとなった。こうした男性性の地域差を考慮する場合の例として、打越正行著『ヤンキーと地元』が紹介された。このエスノグラフィーの中で打越氏は、沖縄県のヤンキーや暴走族の若者たちを2007年~2017年の10年にわたって調査し、その若者たちの大半が過酷な生活を送る過程を描写している。
ここで知念氏は、打越氏が彼らの仕事や生活の過酷さについて産業構造の変動とあわせて分析している点を取り上げる。沖縄県の産業構造は2013年時点で第二次産業の占める割合が全国平均26.1%に対して沖縄県14.1%と極めて小さく、この点で非常に特徴的であるといえる。労働者階級男性にとって工場労働が安定的な仕事として想定されるが、沖縄県の男性たちにはこの選択肢はほぼ存在せず、これによって沖縄県の労働者階級男性に特有のしんどさが生み出される。日本においては1990年代以降から脱工業化の影響が現れているが、サービス産業の比重の増加率には地域差がある。したがって、脱工業化して以降の日本の労働者階級男性の男性性について分析を試みる際には、よりミクロなレベルでの地域性を考慮する必要があるといえる。
5.日本の脱産業化における男性性の変容(≒ジェンダー関係)を捉えるには?
レクチャーの最後は、知念氏の今後の展望についてお話いただいた。
知念氏は現在、打越正行氏と尾川満広氏の協力を得ながら「産業構造の変容がトランジッション経験に与える影響の地域差」の研究を構想している。1970年~2020年の50年間における産業構造の変動を市町村レベルで分析し、その変動のあり方によって地域を分類して典型的な地域を複数選定する。1990年を境にしてバブル経済以前と以後に分けてそれぞれの時期に移行を果たした男女へインタビューを行い、それぞれの地域の性役割分業(労働・家族・生活の営まれ方)の変動と世代間葛藤を明らかにしたいと思っている。これによって男性性、パートナーとどのような性役割分業を営んでいるのか、その営みが産業構造とどのように結びついているのかを描くことで、ホーソンの男性性の三原理よりもさらに細かな次元で男性性を分析することを構想しているという。
知念氏が男性性概念によってアプローチを試みるのは、労働者階級男性を取り巻く世界を理解するためにはその背後で彼らを支える女性たちとの関係もまた理解する必要があるからだという。男性を対象とした研究を人間一般の研究として扱ってしまうことは、社会を理解するうえで決定的な見落としを起こす。そうした危機感が、調査対象は何であるか、どのようになっていて、背景はどのようであるかという知念氏の丁寧な事例分析につながっている。
質疑応答が交わされる中で印象深かったのは「ひとつの生徒集団に着目した研究をやれば後続する人たちがもっと広い研究をやってくれるかなと思って、あくまで(〈ヤンチャな子ら〉という)ひとつの集団に絞ったところもある」という知念氏の言葉である。今回知念氏には「大人への移行と男性性」をテーマにレクチャーしていただいたが、『〈ヤンチャな子ら〉のエスノグラフィー』には学校文化、貧困、家族、労働市場への移行、社会関係といったさまざまなテーマが含まれており、読み手の関心に応じたさまざまな受け取り方が可能である。知念氏の言葉から、エスノグラフィックな研究へ憧れて大学院に進学した者として、先達に鼓舞されたような気分を味わった。
私は、これまでジェンダーにまつわる諸問題に関心がありながらも、積極的に学んだり何か具体的な行動を起こすということはしてこなかった。一方で、私個人がジェンダー視点に乏しいことで、研究を行う過程で、調査対象をも巻き込んで何か差別的な「決めつけ」に加担してしまうのではないかという不安を感じていた。特に、大学院進学後の講義やその中での議論から、私がこれまで経験させてもらったインタビューや調査の中で、私のジェンダー視点の不足によって見落としてしまったことの多さを痛感するようになった。そうした反省があって参加した知念氏によるレクチャーは、様相を変えながらも私たちの人生に巧みについて回る「女らしさ」や「男らしさ」について深く考える機会に、そして、今後私が研究を進めていくうえでの重要な指針を得る機会となった。
(一橋大学大学院 社会学研究科 修士課程 松木るい)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第48回(2021年4月28日)
「なぜ包茎は恥ずかしいのか――男性間支配と女性差別を架橋する歴史社会学」
講師:澁谷知美さん(東京経済大学全学共通教育センター・准教授)
司会: 佐藤文香さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
第48回CGraSS公開レクチャー・シリーズは、「なぜ包茎は恥ずかしいのか――男性間支配と女性差別を架橋する歴史社会学」と題し、東京経済大学全学共通教育センター・准教授の澁谷知美氏にご講演いただいた。澁谷氏は、『日本の童貞』(文藝春秋, 2003年。2015年に河出書房新社から文庫化)や『立身出世と下半身――男子学生の性的身体の管理の歴史』(洛北出版, 2013年)などの著作がある、男性のセクシュアリティの歴史を専門とする社会学者である。
本講演では、なぜ「包茎」が「恥ずかしいもの」とされてきたのかを、江戸後期から現代まで、医学書から週刊誌まで、膨大な資料群の分析から迫った労作である『日本の包茎――男の体の200年史』(筑摩書房, 2021年)の内容をもとにご報告いただいた。以下では、レクチャーの内容をかいつまんでご紹介したい。
「包茎だと女にモテない」、「包茎は男として半人前」――実は多数派でありながら、包茎を「恥ずかしいもの」とする語りは、あたかもそれが「当たり前」であるかのように多くみられる。しかし、包茎手術で名を馳せた高須克弥氏による次の発言は、包茎であることによる「恥の感覚」が作られたものであることを端的に物語っている。
僕が包茎ビジネスを始めるまでは日本人は包茎に興味がなかった。僕、ドイツに留学してたこともあってユダヤ人の友人が多いんだけど、みんな割礼してるのね。……日本人は割礼してないわけだから、日本人口の半分、5,000万人が割礼すれば、これはビッグマーケットになると思ってね。雑誌の記事で女のコに「包茎の男って不潔で早くてダサい!」「包茎治さなきゃ、私たちは相手にしないよ!」って言わせて土壌を作ったんですよ。……まるで「義務教育を受けてなければ国民ではない」みたいなね。そういった常識を捏造できたのも幸せだなあって(笑)。(『週刊プレイボーイ』2007年6月11日、81~82ページ。『日本の包茎』15ページから再引用)
これをふまえ、澁谷氏は「歴史的にどのようにして恥の感覚が形成されたのか」というリサーチ・クエスチョンを掲げた。これに答えるため、先ほども書いたように膨大な資料群を分析しているが、紙幅の都合もあるから、ここでは戦後の分析に限って記述しよう。戦前の言説の分析から、澁谷氏は市井の男性たちによってなんとなく了解され、受け継がれてきた包茎にたいする恥の感覚を「土着の恥ずかしさ」と呼び、1980年代に美容整形医が作りだした恥の感覚を「捏造された恥ずかしさ」と呼んで区別する。
1980年代以降の記事には、それまで見られなかった「女の意見」が掲載されるようになった。「包茎ってキライ!」、「包茎は不潔!」という女性たちの意見は、時代を経るにつれて過激さを増してゆく。しかし、「女の意見」を掲載したのは、ほとんど男性が占めている雑誌の編集部であることを忘れてはならない。しかも、不潔な陰茎はたしかに嫌われるかもしれないが、包茎=不潔ではないし、実際の女性は包茎をそこまで気にしていないのであるから、この「女の意見」はリアルな女性の存在が反映されたのではなく、男性が作りあげたものなのである。つまり、このような言説によって成り立つ包茎ビジネスとは、端的に「男が男から金を巻き上げるシステム」にほかならないのだ。
さらに、「女の意見」だけでなく「男の視線」も語られていた。トイレや銭湯で陰茎を見る/見られること、そして陰茎の大きさや包茎であるかどうかによって一喜一憂することが「あるあるネタ」として描かれる。その視線や評価のなかで「包茎は男にあらず」と男性から指摘されることは、男性にとって恐ろしいことである。なぜなら、同性から認められてこそ、男の値打ちが決まるからだ。そこでは、「男ではない」とされる包茎男性が下位に置かれ、「真の男」である非包茎(=露茎)男性が上位に置かれるという、「よりよいペニス競争」をめぐる男性間のヒエラルキー構造ができあがっている。
このように、包茎を忌み嫌うものの実在はしない「女の意見」、そして「男の視線」や男性間のペニス競争から生じる男性のヒエラルキー構造をあばき出したことが、包茎をめぐる言説分析の成果である。そしてその分析を受け、澁谷氏は冒頭の問にたいして、ずっと以前からあった「土着の恥ずかしさ」が、1980年代以降に医師や出版社が雑誌メディア上であおることで形成された「作られた恥ずかしさ」へと変容した、と答えている。「土着の恥ずかしさ」とは異なり、「作られた恥ずかしさ」には作為性がある。そしてそれは、女性に嫌われ、男性に軽んじられるという「他者にバカにされる恐怖」とイコールになったのであった。
これだけでも十分に面白いが、澁谷氏はさらに、そこから示唆される理論を抽出している。本講演の副題でもある、男性間支配と女性差別のメカニズムである。端的に述べれば、それは「〈フィクションとしての女性の目〉を用いた男性間支配が、女性にたいする男性の敵愾心を涵養し、女性への攻撃を正当化することで、ジェンダー不平等に関与する」というものである。どういう事態なのか、以下で確認しよう。
〈フィクションとしての女性の目〉は、ハゲ男性の経験をインタビュー調査から分析した須長史生氏が考案した概念で、「ハゲると女性にもてない」といった形でハゲ男性をおとしめるものであり、実際の女性による意見ではなく、根拠にもとづかない(須長 1999: 167)。包茎男性をめぐる言説にあらわれた「包茎は不潔」、「包茎はキライ」という「女の意見」は、根拠を問われないまま流通する点で、まさしく〈フィクションとしての女性の目〉である。
澁谷氏の分析は、「女の意見」が〈フィクションとしての女性の目〉と一致することの指摘にとどまらない。さらに、「女の意見」が男性によって男性に用いられた点で、医師と患者の支配、つまり男性による男性の支配に用いられていたのである。そしてこの〈フィクションとしての女性の目〉を、男性性研究における「ジェンダー平等の正当化に利用される女性像」概念※と接続することで、それがいかに不平等なジェンダー関係に関係しているのかをあばき出す。つまり、「『包茎ってキライ、フケツ』と吐き捨てる女性像」が「よくある女性のあり方」として認識されれば、包茎男性を迫害するのが女性であるというリアリティが強固になる(くり返すが、これは実際の女性の声ではなく、医師や編集部の男性が吹聴していたものである)。この女性像が男性の女性にたいする敵愾心をあおり立てることで「男が生きづらい世の中を作ってるのは女である」女性憎悪(ミソジニー)を再生産し、強化する。
このような「男性の『生きづらさ』言説」の根底には、女性を所有できないことで同性から男として認められない恐怖がある。「包茎ってキライ」という〈フィクションとしての女性の目〉があるからこそ、女性を所有できない男性は「自分がモテない(=女性をモノにできない)のは、女のせいだ」とお門違いの憎悪を(それを作り上げた男性にではなく)女性に向けてしまう。そのため、「女持ち」男性がそうでない男性を劣位に置くヒエラルキー構造や支配関係は温存され続ける。
さらに澁谷氏は、この構造は「包茎」を「ハゲ」や「チビ」、「デブ」、「ブサイク」などに置き換えても変わらないであろうことを指摘する。けっきょく、「男の生きづらさ」なるものは、男性が女性を所有できず、それゆえに同性から認められないことに由来するのではないかと指摘している。
この互換性の高さについて聞いたとき、私にも思い当たる節があった。修士課程の研究で性暴力をめぐる言説を分析した私は、加害者を他者化する言説のなかに、「加害者はレイプで童貞を捨てた!」とわざわざ童貞であったことに言及したり、「加害者はモテなかったから性欲がたまって性暴力を起こしたのだ」と性暴力の原因を「モテないこと」に求めたりする語りと同時に、「自分たち(男性)はレイプなんかせずに、女のコを口説かなくては」という語りを発見した。そこでは、性暴力の原因を加害者の「モテないこと」と「性欲」に還元しつつ、加害者と異なる自分たちを女性との関係を持てる存在であると提示する――その「性欲」も、加害者の異常なそれとは異なると恣意的な線引きを行う――という、「女性を所有できるかどうか」を基準とする男性間のヒエラルキー構造が存在していた、と分析した。これはけっきょく、「包茎」を「モテ」に置き換えたのであるから、澁谷氏のいう互換性の高さを例証しているといえる。
レクチャーを終え、私はこの互換性の高さの解体について澁谷氏に質問してみた。「たとえ『包茎の恥ずかしさ』が消えたとしても、それがハゲやチビなどに置き換わり、結局は男性間支配・ジェンダー不平等が維持・再生産されていくことも考えられるが、これを打破するには一体どうすればよいのか」――実に漠然とした答えづらい質問である。しかし、澁谷氏は真摯に応答してくださった。本講演では「包茎」という現象から男性間支配や女性差別を考えたが、この大きなテーマについてはむしろみんなで考えたい、と。男性として生まれ育ち、種々の特権を享受してきた男性のひとりとして、一朝一夕ではとても答えられない大きな問いに、真正面から向き合っていきたい。本講演は、その思いを新たにする機会となった。
※提唱者のR・W・コンネルは、この女性性を「emphasized femininity」と名づけ、日本語訳では「強調/誇張された女性性」の言葉も用いられるが、平山亮氏はそれがジェンダー関係に与える影響を考慮し、ジェンダー不平等の「正当化に利用される女性像」と意訳することをすすめている(平山 2019: 49)。
【参考文献】
平山亮,2019,「『男性性による抑圧』と『男性性からの解放』で終わらない男性性研究へ」『女性学』日本女性学会,27: 42-56.
須長史生,1999,『ハゲを生きる――外見と男らしさの社会学』勁草書房.
(一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了生 前之園和喜)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第47回(2019年7月3日)
「「サムライファンタジー」と「子供扱い」――日本文化を利用した在日米兵の軍事的男性性」
講師:カール・ゲイブリエルソンさん(カリフォルニア大学サンタバーバラ校東アジア言語・文化研究学科博士課程)
司会:佐藤文香さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
第47回CGraSS公開レクチャーシリーズは、「『サムライファンタジー』と『子ども扱い』 ―日本文化を利用した在日米兵の軍事的男性性」と題し、カリフォルニア大学サンタバーバラ校東アジア言語・文化研究学科博士後期課程在籍の、カール・ゲイブリエルソン氏にご講演いただいた。ゲイブリエルソン氏は在日米軍基地を通して行われる日米文化交流を研究テーマとされ、2018年度国際交流基金日本研究フェローとして、名桜大学(沖縄県名護市)総合研究所の共同研究員としてもご活躍中である。
本講演では、米軍のよく使うという「在日米兵は現代のサムライ」という表現に端を発し、男性性の頂点に君臨しようとする「サムライファンタジー」と駐留先での「子ども扱い」への反発が、いずれも日本文化を利用した在日米兵の軍事的男性性の発現であることを、ご自身の在日米軍基地でのフィールドワークをもとにご報告いただいた。
ゲイブリエルソン氏は、2017年から本州と沖縄にある米軍基地周辺でフィールドワークを行なっている。最初に訪れたのは、横田基地で行われている日本文化教育イベントだ。イベントでは基地の設備の紹介からお箸の使い方のデモンストレーションまで行われる。その際、オリエンテーションの途中で教室に入ってきた司令官が挨拶がわりに「Samurai warriors swift to fight!(サムライ兵士は速やかに戦う)」というスローガンを述べ、兵士たちも同じようにスローガンを唱える。一方、その夜同じ教室で行われた日本文化を紹介するコースでは、米兵は日本の子ども用おもちゃでお寿司のグミを作っていた。
この日ゲイブリエルソン氏は、朝は「サムライ兵士は速やかに戦う」と叫び、夜にはお寿司のグミを作る在日米兵のギャップに驚いたという。これが、本公演でゲイブリエルソン氏が指摘する、米軍の日本文化の扱い方についての大きな矛盾である、「サムライファンタジー」と「子ども扱い」の出発点だ。
そもそも軍事組織とは国家で認められた暴力を行使するために存在する。暴力とは物理的な暴力だけでなく、「抑止力」としての象徴的な暴力も含む。軍人とは国家の暴力を指導して、暴力を行使し、さらに暴力をうける役割を持つ。その軍人が国家のために人を殺し、殺されることが成り立つよう、各国の軍事組織は男性性イデオロギーを利用している。
とりわけアメリカ国内では、暴力を過度にする「軍事的男性性」は、軍人だけではなく多くの一般市民にも影響を及ぼしており、さらに現在150ヵ国以上に兵士を配備することで、その影響は国外にも及んでいるという。中でも多くの米兵が配置されているのが日本だ。そして、日本に暮らす10万人以上の米兵のほぼ全員が、カルチャーショックを軽減するために日本文化のオリエンテーションを受けている。
しかし米軍が新人兵士に教える日本のイメージは、米軍からの偏ったジェンダー的視点を多分に含んでいるという。それは「二つのイメージ」に分けることができる。一つは、米軍が兵士の男性性を維持するために使う「サムライファンタジー」。そしてもう一方が、その男性性が維持できない時に使う「日本人から子ども扱いされているというファンタジー」だ。この二つのイメージは基地周辺の日米交流、アメリカ国内での人種・他国文化にかんする意識、日本文化の定義にまで影響を及ぼしているとゲイブリエルソン氏は述べる。
講演では四つのセクションに分け詳細なご報告があった。①在日米軍の構造とジェンダーイデオロギーについて、②米軍の「サムライファンタジー」・米軍が想像する日本の男性性について、③現在「日本のサムライ」とされている米兵がなぜ軍隊から「子ども扱い」されるのか、④軍事的男性性が作り上げた「サムライファンタジー」と「子ども扱い」の矛盾による、日本とアメリカの社会に対する影響、以上の四つだ。以下では、各セクションを振り返っていこうと思う。
①在日米軍の構造とジェンダーイデオロギーについて
米軍兵士は日本に配備される時に必ず日本文化にかんするオリエンテーションを受ける。このオリエンテーションは彼らにとって日本のイメージを作る上では重要な現場となっているが、例えば海軍での日本文化オリエンテーションは「ソフト・セッション」と呼ばれ、戦闘任務である「ハード・セッション」と対置されている様子が観察されたそうだ。つまり、文化教育を「ソフト=女性的」とみなしていると捉えうるとゲイブリエルソン氏は述べる。これがさらに、欧米各国からアジア各国が「女性的」とみなされ、西洋と東洋を正反対のものとして対置するオリエンタリズム(Edward Said:1973)とも重なり合う。
このように「ハードセッション=男性的」「ソフトセッション=女性的」とする米軍兵士による男性性と女性性の対置は、軍事的男性性を作り上げる上で非常に効果的である。ゲイブリエルソン氏はArron Belkin(2012)を援用し、軍事的男性性にとって基礎的な要素となるのは「矛盾」であるという。これは決して女性性を「拒否」するものではない。軍事的男性性を作り上げる際、司令官は兵士に対し理想的な男性性のイメージを押し付けながら、その理想的なイメージと正反対の行動を命じ、兵士の心の中に「矛盾」を生み出す。常に「矛盾」を抱えさせ続けることで兵士には混乱が生じるが、この混乱こそを利用して、兵士の命令に対する抵抗感を抑制するのだという。
そこで鍵となるのが「スケープゴーティング」だ。自分に男性性が足りないと感じる兵士は、その原因を組織の矛盾や自分自身の問題と切り離し、軍事的男性性の理想的なイメージに合わないイメージ、つまり女性、LGBTQ、他人種や他国籍の人などに責任転嫁するよう訓練されている。
米軍は兵士に対し、あらゆる「矛盾」を押し付ける。例えば、兵士は紳士的でありながら、動物的な強い性欲の持ち主でなければならないと教え込まれる。明らかな矛盾だ。この矛盾したイメージを抱えきれないとき、兵士は、「この矛盾を抱えきれないのは女性のせいだ」とスケープゴーティングする。生じた矛盾による混乱や不安を自分から切り離し、他者のせいだと責任転嫁することを訓練されることは、戦地で敵を殺さねばならないときに生じる自分の中の混乱や不安を切り離すことにも役立つのだという。つまり、スケープゴーティングは結果的に兵士の暴力性を強めると言える。それゆえに、軍事組織にとって非常に便利なツールとなるのである。
氏の報告された「サムライファンタジー」と「子ども扱い」は、在日米軍の抱える「矛盾」そのものだ。それでは兵士たちはこの矛盾をどのように乗り越えていくのかが、以下のセクションでは述べられる。
②米軍の「サムライファンタジー」・米軍が想像する日本の男性性について
在日米軍は「サムライ兵士は速やかに戦う」というスローガンから、ホームページに掲げられたロゴデザインまで、いたるところで「サムライ」のイメージを用いている。米軍のイメージによれば、「サムライ」は最強の兵士であり、かつての日本の男性性の頂点に立っている。そして現在、日本の男性性の頂点に立っているのは、「現代のサムライ」である米兵しかいないというファンタジーが練り上げられている。このファンタジーには、「日本には兵士が必要である」という前提で米兵の配備を正当化したり、また現代の日本人の男性性を否定したりする意味合いも含まれている。これは、最強の「サムライ」として男性性の頂点に立つ米兵に対し、尊敬の念を抱くことを期待させる効果さえあるという。
日本の男性性の頂点に立つ「サムライ」としての米兵の語りとして、印象的なのは装備品に関するものだった。米軍基地で行われるフェスティバルでは、米軍と自衛隊の装備品がそれぞれ展示されている。その中でゲイブリエルソン氏が話を聞いた米兵は、油やサビでボロボロに汚れた米軍の中型戦車を指差し「もっとベストな大きいやつもあるけどね」と言う一方、自衛隊の中型戦車に対して「自衛隊の装備品は汚れてもないし臭くもないね」と笑う。これは、「日本の装備品は戦場で使われたことがない」という裏返しの意味で捉えられる。Belkinによれば、装備品の汚さもまた、米軍の持つ理想的な男性性のイメージの一つとして上げられる。ゲイブリエルソン氏がここで感じ取ったのは、米兵は装備品の汚さなどのあらゆる手段で「自分たちは自衛隊よりも上だ」と伝えようとしているのだろう、ということだ。
③現在「日本のサムライ」とされている米兵がなぜ軍隊から「子ども扱い」されるのか
このように、米兵は「サムライファンタジー」を通して日本の男性性の頂点に立とうとする様相が見られる。しかし、彼らはそうした扱いとは矛盾するような「子ども扱い」を感じることがある。自らを「サムライ」と呼称する、最強の兵士たる米兵が「子ども扱い」されているとはどういうことか? そこには、またしても軍事的男性性を練り上げるスケープゴーティングが隠れていたり、米軍が兵士を「子どもらしく」見せようとするPR戦略が隠れていたりする。
在日米軍基地には厳しい行動制限があり、例えば夜中一時の門限があること、運転免許を取れないこと、一人で基地の外に出ることができないことなどが挙げられる。こうした厳しいルールに対し、「自分たちが子ども扱いされている」と不満に感じる米兵は少なくない。もちろんこのルールは米軍により設けられたものだが、実際には米兵がこれを地元の日本人のせいにすることもままある。これもまた、Belkinの述べるスケープゴーティングだ。米兵は、自分たちが所属する組織そのものが自分たちを「子ども扱い」しているということを否定するために、全く関係のない日本人や日本の文化に責任転嫁する。米兵の存在に対して神経質な振る舞いをする日本人が周りにいることで、自分たちは行動制限がかけられるのだ、と信じている米兵は少なくないのだという。日本人は国防の意識が低く、感情的、神経質、非合理的であるというイメージが共有されている。こうしたイメージは米軍の理想とする軍事的男性性のイメージとは異なり、非男性的だ。これは、「日本人とはまともに話し合いができない」と、日本人の声を無視する口実にもなる。
こうした非男性的なイメージは、なにも米兵同士のインフォーマルな噂話にとどまるものではない。米海兵隊員にむけた新人オリエンテーションには、「日本の文化は子どもっぽく非男性的である」という印象を与えかねない内容が盛り込まれている。オリエンテーションにおいて米兵は「なぜ自分たちは仕事でこんな小学生のような遊びをしているのか」と、つまり自分たちが子ども扱いされているような矛盾を覚え、男性性に不安を感じるものの、米兵はそれに対し「日本の文化は子どもらしいから仕方がない」とスケープゴーティングすることもあるという。
また一方で、在日米軍はPR作戦の一つとして「自己幼児化」をとっている。自己幼児化とは、軍隊や兵士のイメージをあえて子どもっぽくすることだ。Sabine Frühstückによれば、米軍はこの戦略を日本の自衛隊から学んだという。自衛隊が自己幼児化に取り組むのには二つの理由がある。一つに、自衛隊を子どもらしく見せれば旧日本軍の暴力的イメージから離れることができ、国民の支援をより得やすくなる。さらに若年層にも直接アピールし、次世代の支援も得やすくすると考えられている。自己幼児化の例として、ゲイブリエルソン氏は在日米軍が安保50周年の記念として作った『わたしたちの同盟 ―永続的パートナーシップ』という漫画のカットを提示してくださった。カットの中では、沖縄各所に配置された飛行場やキャンプが、それぞれ二頭身のアメリカ人キャラクターに擬人化して紹介される。こうしたキャラクター化を通して、自衛隊の自己幼児化と同じように米軍を可愛く子どもらしく見せることも、子どもにアピールすることも可能になる上に、漫画が子ども向けということを言い訳に、敗戦の歴史や基地建設の問題など政治的に“都合の悪いこと”を避けることも可能になる。
見方によっては米兵がまた日本文化の中で子ども扱いされているようにも見えるが、『わたしたちの同盟 ―永続的パートナーシップ』は国際政治のわからない日本人女性に対し、アメリカ人男性が同盟のことを教えるという構図になっており、ここにオリエンタリズムから作られるアジアへのジェンダー的視点や、日本人は政治が理解できないというスケープゴーティングのようなイメージを読み取ることもできると述べる。
他にも、在日米軍のホームページやSNSなどを見ると、第二セクションでも出てきたフェスティバルなどの写真から兵士が子どもを相手にしている様子も見ることができ、これもPRのための自己幼児化と言うことができる。フェスティバルは米兵から見ると、遊びやレジャーを通して地元の人々とつながる手段と考えられており、同時に、軍隊や軍事化を子どもの頃から生活の一部として正常化する効果もあるとゲイブリエルソン氏は述べる。
このように、米軍の日本文化の利用の仕方は米兵の男らしさと子ども扱いをうまく使い分けている。在日米軍は「サムライ」という言葉を利用することで兵士の暴力的な仕事と日本文化とのつながりを作り上げ、さらには男らしさを強調するオリエンタルな「サムライ」というファンタジーによって、日本国内での兵士の活動に特別な意味を持たせる。そして同時に、日本文化を子どもっぽく伝えることによって、在日米兵に課される厳しいルールや、PRのために兵士を子ども扱いすることの原因が「日本文化から」発生しているものだと錯覚させ、そうすることで米軍組織自体が兵士からの批判から逃れることが可能になる。このように米軍は「サムライファンタジー」と「子ども扱い」という矛盾したイメージを戦略的に利用し、兵士の男性性を維持するのだという。
④軍事的男性性が作り上げた「サムライファンタジー」と「子ども扱い」の矛盾による、日本とアメリカの社会に対する影響
第4セクションでは、これまでのセクションでご報告された米兵の思想が、日本文化の定義にまで影響与えていることを指摘された。ゲイブリエルソン氏は、米軍基地周辺に住んでいる地元の人たちが、米軍の軍事的男性性によって自分たちの文化の定義にまで影響を受けていたと述べる。例えば島根県益田市の「七尾まつり」には岩国基地の米兵がよく参加しており、まつりの中で米兵がサムライに変身するという催しがなされる。この催しに対して、米兵がサムライの仮装で行進したことに益田市民が感動したという感想が地元コミュニティから寄せられているそうだ。しかし当然ながら、本来の日本の「侍」には、米軍式の行進が求められているはずはない。それでも米軍の「サムライ」の仮装や行進というパフォーマンスが地元コミュニティから評価されるというのは、米兵が想像した「サムライ」の動き方が認められたというようにも解釈できる。このようにして、益田市民の「侍」の定義が、米兵のサムライファンタジーに少しずつ近づいているとも言える、と氏は分析する。
しかしながら、米兵はこのような自分たちの影響力に自覚的でいるのだろうか? 氏が次に出された、在日米軍による地元の人たちへの英会話教室の例を聞くと、そこには無邪気に帝国主義をちらつかせる米兵の姿が垣間見える。ここでは、沖縄の「ウチナーグチ」を「方言」と言って教材に用いる米兵の話が紹介された。沖縄の人々にとって、沖縄の言葉は自らのアイデンティティと関わる重要な要素だ。例えば、自分たちを先住民族として認識されたい人にとって、ウチナーグチは「方言」ではなく、内地である日本との違いを強調する言語である。そこには、先住民族の土地の権利を用い、米軍が使っている土地を取り戻す運動の意味合いも込められているという。そんな「ウチナーグチ」を米兵が「方言だ」と宣言することは、沖縄の人々のアイデンティティの定義を指摘するようなことでもあり、反基地運動の否定にも繋がりうる。
講師である米兵が「ウチナーグチ」を「方言」として地元の人に教えようとすることや、アイデンティティの政治を意識せず発言することから、彼が沖縄への理解や敬意よりも、自分自身の居心地の良さ優先していることが窺えるとゲイブリエルソン氏は述べる。
日本での任務が終了すると、ほとんどの在日米軍は帰国し、配備先で身についた日本文化に関する知識やイメージを自国に持ち帰る。サムライと呼ばれた経験、米軍や日本人から子ども扱いされた経験、もしくは子どもらしく行動するよう命じられた経験。そこで抱えた矛盾を解消するために、日本は「非男性的で子どもっぽい国だ」とスケープゴーティングした経験を、米兵は自国に持ち帰り、周囲の人々に伝えるだろう。彼らは日本文化などについて語ることのできる人々の中でも筆頭となるだろうし、場合によってはアメリカ国内での日本文化教育や、日米関係のポリシーに関わる役割につくのだという。結果的に、在日米軍基地で行われる日本文化教育は、アメリカ人の日本へのイメージ、アメリカ人の人種とジェンダーへの意識の構成にまで繋がりうる。グローバル化組織である米軍では、男性性のイデオロギーは兵士の暴力性を上げる効果以外にも、配備を受ける国の文化や政治にまで変化を起こす効果すら持ちうるのだと述べられ、講演は幕を閉じた。
ゲイブリエルソン氏は講演の冒頭で、毎年数万人が米軍基地の中で日本文化教育を受けていれば、アメリカ全体の日本やアジアへの理解の仕方に大きく影響を及ぼすだろうが、その際米軍基地を通して、より現実に即した情報を尊敬を込めて伝えれば、日本文化に対する誤解やステレオタイプを大幅に減らすことができるかもしれないと述べていた。在日米兵が必ず受ける場当たり的なオリエンテーションからは、「現実に即した」日本文化を伝えようという気概は感じられず、現時点ではかなりの誤解が持ち帰られているのだろうということは想像に難くない。しかしオリエンテーションのクオリティ以上に問題なのは、日本文化を子どもっぽく感じさせ兵士の男性性をヒエラルキーの上位に置くことで、異国の軍事組織内で米兵が感じる様々な不全感を解消させようとする軍事組織の戦略そのものだ。軍事的男性性とはなんと複雑に練磨されるのだろうと驚くばかりだった。日本文化をスケープゴート化することで軍事組織内での兵士の矛盾を解消させるばかりでなく、「萌え絵」の漫画イラストなどを通して自己幼児化することで、軍事組織自体をソフトに見せる。日本文化が利用されていることにすら気づかせず、違和感なく受け入れさせるにとどまらず、「七尾まつり」の例のようにサムライのイメージを一部上書きする。報告を拝聴したのち、ここまで複雑なやり方で軍事化が進んでいるのかと鳥肌がたった。また個人的には、自分自身「萌えミリタリー」や「戦争ごっこ」などの日本のミリタリー・カルチャーを調べる身として、報告にあったような異文化のジェンダー化や他者化、軍事化は、よっぽど意識しないと気付かないほど透明化して生活に染み込んでいると感じる。その様相は複雑すぎて、ゲイブリエルソン氏の取り組まれるような、軍事組織やそれを取り巻く周囲の人々に肉薄する丹念なフィールドワークがあってこそようやく浮かび上がってくるのだと痛感し、気持ちの奮い立つ講演だった。
(一橋大学大学院 社会学研究科 博士後期課程 関根里奈子)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第46回(2019年5月24日)
「占領期神戸・エゴ・ドキュメントとしての女性軍属の手紙を読む」
講師:長志珠絵さん(神戸大学大学院国際文化学研究科教授)
司会:貴堂嘉之さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
第46回CGraSS公開レクチャー・シリーズは、「占領期神戸・エゴ・ドキュメントとしての女性軍属の手紙を読む」と題し、神戸大学の長志珠絵氏にご講演いただいた。長氏は、『占領期・占領空間と戦争の記憶』(有志舎, 2013年)や『歴史を読み替える—ジェンダーから見た日本史』(共編著, 大月書店, 2015年)などの著作がある日本近現代史を専門とする歴史家である。
本講演では、神戸基地の実態と変遷を明らかにするために、神戸基地の監察総監大佐スタッフであった女性軍属エリザベス・ライアンのエゴ・ドキュメント(家族友人に当てた手紙)を分析する研究についてお話いただいた。本参加記では、報告のキーポイントであった「エゴ・ドキュメント」に焦点をあてて、長氏の報告内容と現代歴史学の潮流について述べたいと思う。
講演の主題である神戸基地は、当時の全国紙の記事においても多数取り上げられており可視化された存在であったが、その輪郭は未だ不明瞭であり、兵庫県軍政部との関係性も曖昧に捉えられていた。しかし、今回の長氏の研究によって、神戸基地は占領軍ではなく米軍の一機関であり、非常時の治安関係だけなく「接収」をめぐる占領軍側の窓口としても機能しており、兵庫県軍政部とは異なる組織であったことが明らかにされた。また、戦後のある段階において、神戸基地に課された任務は大きく変転しており、神戸基地(Kobe Base)からキャンプ神戸(Camp Kobe)へと組織変更されていく。その背景には、朝鮮戦争が大きな要因として存在していたと長氏は指摘する。
行政文書だけでは可視化できない神戸基地を多角的に明らかにするためのツールとして、長氏は、神戸基地の女性軍属であったエリザベス・ライアンが家族・友人へあてた手紙(エゴ・ドキュメント)に注目した。エリザベス・ライアンは、1947年2月から1948年6月までInspector General(監督総監)のスタッフとして働いており、彼女は1年ほどの日本滞在にも関わらず91通もの手紙を残している。手紙からは、占領軍の女性軍属として彼女が抱えていた思想(朝鮮人に対する偏見、監察総監スタッフとしての使命感、性病に関する軍隊内部の批判, etc)とともに、今まで行政文書では明らかにされてこなかった神戸基地の詳細な内部状況が読み取られる。長氏は、彼女の手紙を分析した後、神戸基地の内部から神戸の占領を再検討することを試みており、最終的には、地域占領として神戸基地の全体像を明らかにし、占領期の米軍自体を問い直すことを目標としている。その際に、個人の語りから地域占領を問い直そうとする研究方法、つまりミクロな世界とマクロな歴史全体を往還する研究方法を採用している。
近年、このようなパーソナル・ナラティブを主要な資料として、従来の占領期の歴史観を問い直した研究に、西川裕子氏の『古都の占領』(平凡社, 2017年)がある。生活史を軸として占領期の京都を描いた『古都の占領』に代表されるように、現在の占領期研究においては、国家間の年表に地域事例を流し込むことなく、地域から全体としての時代像を描きだす試みがなされている。(西川,長, 2018: 2)このようにミクロな歴史に焦点をあて、そこから戦争や占領といった全体史を考える占領期の方法論は、現代歴史学の中心的な主題であり、欧米における歴史学の動向と共振している。
たとえば、従来のアメリカ史学においては、さまざまな学派が存在していたが、現代のアメリカ史学では、多様な人種・エスニシティ・階級・ジェンダー・セクシュアリティの、あらゆる市井の人々がアメリカ史を構成する歴史的主体であると前提とされている点で、伝統的な政治史や法制史の枠組みとは大きく異なっている。(有賀ほか, 2009: 171)このように、地域から全体、個人の語りから全体の歴史へと、ボトムアップで歴史を記述する方法の1つとして、エゴ・ドキュメントに焦点を当てた分析方法が存在する。この方法論については、長谷川貴彦氏の論文「エゴ・ドキュメント論―欧米の歴史学における新潮流―」において詳しい。上記の論文によると、エゴ・ドキュメントを使用する研究は、ヨーロッパでは広く発展しており、日本における歴史研究も、欧米の研究と同時期に発展している。例えば、日本西洋史学会において2012年に「パーソナル・ナラティブの歴史学」、2013年に「市民の自分史」のシンポジウムが開かれた。また、グローバル・ヒストリーのオルタナティブとして、エゴ・ドキュメントから読み取られるミクロな歴史をシティズンシップの観点から読み直し、国境をこえた「共有される歴史」を追求した槇原茂『個人の語りがひらく歴史』(ミネルヴァ書房, 2014年)なども刊行されている。西洋史だけでなく日本史の研究分野においても、「エゴ・ドキュメント」という言葉を用いないものの同様な動向がみられている。
上記のように現代歴史学は、まさに長氏の研究と通底する「顔が見える歴史」を念頭において、エゴ・ドキュメントに代表されるようなボトムアップの歴史研究を重視している。この方法論は、マジョリティがアクターとなっていた伝統的な政治史・経済史を乗り越え、集団としてではなく生身の人間を起点として発展する可能性を保持しているのである。
本講演では、エゴ・ドキュメントを使用する長氏の研究によって神戸占領期における最新の研究動向に関する知見を得られただけでなく、エゴ・ドキュメントについて理解することで自身の専門分野である歴史学の方法論について深く再考する機会となった。
【参考文献】
有賀夏紀ほか, 2009年. 『アメリカ史研究入門』 山川出版社. (第1章)/粟屋利江, 1996年「『サバルタン研究』再考―インド近代へのまなざし−」『創文』(376)/西川裕子 長志珠絵, 2018年「『古都の占領』のから読み取れること」『燎原』(237)/ 長谷川貴彦, 2015年 「エゴ・ドキュメント論:欧米の歴史学における新潮流」『歴史評論』(777)/ 長谷川貴彦, 2010年「物語の復権/主権の復権―ポスト言語論的転回の歴史学―」『思想』(1036)/ 槇原茂編, 2014年. 『個人の語りがひらく歴史』 ミネルヴァ書房. (序章)/ 歴史学研究会編, 2017年. 『第4次現代歴史学の成果と課題』 績文堂出版. (第1章6節)
(一橋大学大学院社会学研究科修士課程 吉田汐里)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第46回(2019年 1月25日)
「うろたえる男たち――女たちの告発に、私たちはいかに応えてきたか/応えるべきか」
講師:平山亮さん(東京都健康長寿医療センター研究所・研究員)
司会:佐藤文香さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
1月25日一橋大学での公開レクチャーのテーマは「うろたえる男たち」。男がうろたえる、心躍る言い回しである。実は、お話が始まる前から私の心の中では拍手喝采である。それは、常日頃男がうろたえる様を見たいと私が思っているからであり、厳然たる男社会の日本で男がうろたえることはそうそう無いからである。その日本社会で男がうろたえている…こんな愉快なことがあるだろうか。さらにテーマは「いかに応えてきたか/応えるべきか」と続く。
早速「うろたえる」を辞書で引いてみた。「思いがけない事に驚き、どうすればよいかが分からず、まごつくこと」とある。男が「思いがけないこと」に「まごつ」いているのである。痛快。
この「思いがけないこと」とは(痴漢が犯罪とみなされ)被害者である女性がそれを告発することであり、それに付随して発生すると男が考える「痴漢の冤罪」リスクのことである。痴漢の冤罪被害を声高に訴える男たち、そこに垣間見える「男」を平山さんはこれまでの男性性についての理論を手掛かりに容赦なく追い詰めていく。冤罪リスクのリアリティがどのように構成され、なぜ男たちが冤罪リスクを訴えなければいけないのか、を一つ一つ外堀を埋めながら緻密に考えていく。
まず、平山さんはHegemonic Masculinity(HM):覇権的男性性の解剖から取り掛かる。そして基本に立ち返って、そもそもこの言葉・概念が提案された本来の目的を果たせない使い方をされていることを導く。不平等なジェンダー関係を正当化してしまい、その相対性が対として持ち出される女性像によって変わってしまう、というこの使われ方の弱点を指摘する。その言葉が使われる文脈の中で強調されている「女性とは」「男性とは」を吟味せずには、ジェンダーの矛盾や不平等は語れないのだ、と。様々にあり得る「女性性」「男性性」の中で、何が持ち出され、それによって何が「仕方ない」(正当化)に結び付けられてしまうのか?
そして、これをわきまえた上で男が「冤罪リスク」という時の現実の構成のされ方をHMの枠組みで考えていく。いかなる文脈なのか?、そこで際立たされている女性像は何か(何が見えなくされているのか)?そして、そこで際立たされた女性像によって男性がいかなる存在として立ち現れてくるのか?、と。鮮やかな手法が、見事だ。
1988年11月4日に起こった「地下鉄御堂筋線事件」を切っ掛けに1994年に「痴漢は犯罪です」というポスターが駅構内に貼られ始めたが、それまで痴漢は犯罪とは言われず、女性たちがその被害者であることも「語るべきではない」ことだった。「犯罪」はおろか「ありふれたこと」だったのである。このポスターを目にした一人は「ついにここまで来たか」と感慨深かったそうだが、「痴漢は犯罪」になったら、今度は「冤罪リスク」の登場である。女性たちが「痴漢」被害を訴えることを、男たちは手をこまねいて見逃したりはしなかったのである。
女性たちは被害を訴えたが、瞬時にそれは「聞き届けられる」ことにすり替えられ、「冤罪リスク」や「ハニートラップ」を男たちが声高に拡散し、痴漢被害が聞き届けられないことが女性が自ら被害を訴えることを抑制させる力(逆向きのエネルギー)になってしまった、と平山さんは説き進める。
ではなぜ、男たちは冤罪リスクを訴えなければいけないのか?そこには、加害者と名指されかねないことへの神経症的恐怖と責任を果たせないことへの恐怖があり、それが容易に攻撃へと変わる。これまで常に「女の上にいる」と社会から下駄を履かせて貰って来た男たちが初めて感じた恐怖、そしてそこから生まれた被害者への攻撃の始まりである。だが、「被害者への攻撃」などそれ自体が犯罪ではないのか?
その攻撃の手段が、「冤罪被害の訴え」なのである。男性たちは本当に責任の取り方が分からないのか、加害者から降りたいと思っているのか、と平山さんは畳み掛ける。
冤罪被害を妄想することと(性暴力)被害当事者であることの間には天と地ほどの差がある。これまで一体どれだけの、夥しい数の女性たちが「魂の殺人」によって自己の尊厳を奪われ、苦しめられてきたことか。一次的な被害だけではない、社会からの数度にわたる「セカンドレイプ」までを受けさせられてきたのだ。堪忍袋の緒が切れた時、「#MeToo」は始まった。
加害者に間違われることは仕事や家庭生活に影響を及ぼし、辛く苦しい…人生そのものがめちゃくちゃになってしまう…と冤罪被害(妄想)を男性が訴える時、そこにあるのは「自分」だけだ。実際に被害を受けた女性への配慮や、自らの「男というもの」についての考察は皆無である。実在する被害者には一片の配慮も無く、今ありもしない被害を男たちは妄想しまくる。車内の痴漢被害について、被害を受けていない女性たちが「痴漢被害に遭ったら…」と言い募ったことがあっただろうか?
多くの男性たちが「やりたい放題お構いなし」で続けてきた性犯罪は不問に付して、実害を受けてもいない冤罪を妄想し、言い募る…ここにある「男性性」もまた、「オレ様自己チュー」以外の何物でもない。問題にすべきは冤罪被害ではなく、この、手の付けられない「オレ様自己チュー」なのではないのか?
なぜ、漸く声を挙げ始めた女性たちを攻撃しなければならないのか?なぜ女性たちの被害の訴えへの応答が加害者の他者化とならずに「冤罪被害」の訴えになり、攻撃の手段になるのか?このねじれ、歪みにこそ、男性性の核心を突くものがあるに違いない…と、平山さんは直感しているように見える。
私たちが抱えているモヤモヤを一掃し、きっちりとした言葉で理詰めに「男たちの冤罪被害」妄想を追い詰め、この平山理論がどうフィニッシュするのか…ゾクゾクするほど楽しみである。
(ウィメンズ アクション ネットワーク(WAN) 永野眞理)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第44回(2019年 1月9日)
「ジェンダー、人種、文化ナショナリズム——外国人の話す日本語におけるジェンダー表現をめぐって」
講師:鈴木聡子さん(マカレスター大学アジア言語文化学部ドゥイット・ウォレス教授)
司会:ソニア・デールさん(一橋大学大学院社会学研究科専任講師)
参加記
外国人が話す日本語、外国人が話すべき日本語、外国人が話すことが出来る日本語はどのようなものとされているのだろうか? 今回の鈴木聡子先生によるCGraSS公開レクチャーでは、1980代以降に書かれた23冊の小説に出てくる外国人(白人や東アジア)男性の登場人物による語りを分析した結果が報告された。そこでは、文化的ナショナリズムと人種決定主義が近年書かれた小説に出てくる外国人男性の語り方の描写に影響していることが示された。これには日本社会の中でも確認されてきた外国人男性が話してもいいとされている日本語とも共通する側面があり、日本社会にこの二つのイデオロギーが根強くみられ、「男性語」こそが日本文化の砦のような役割を果たしているという仮説が提示され興味深い発表となっていた。Q&Aでは社会と小説の中の描写との関係についての議論もあり有意義なディスカッションの場となった。
鈴木先生はこれまでの研究でもテレビや漫画、小説に出てくる外国人女性の語りをとりあげてきた。子どもの本に出てくる吸血鬼のキャラクターが、一般的に西欧人が話すと思われているなまりと文法的に正しくない日本語で話していたのを読んで残念に思ったことがこのテーマ関心を持つようになるきっかけだったという。数十年前までは日本のテレビ番組や小説、漫画などに出てくる外国人の登場人物が使う日本語はたどたどしく、「なになにあるよ」のような差別的にもとらえられる表現が使われることも多かった。しかし、近年日本の小説に出てくる外国人の登場人物は綺麗な日本語を使うのが当たり前になっているという。だが、その登場人物がどのような外国人であるかによって使用する日本語は異なって描写される。豊かな語彙を使った表現、文法が正しい日本語を使っていても、小説の中に出てくる外国人の日本語には、特にジェンダーにおいて、言語的な偏見が確認できることを、鈴木先生は研究で明らかしてきた。今回の発表では日本の小説の外国人男性の登場人物が使用する日本語のジェンダー表現に着目した研究の結果に焦点があてられた。
まずは、先行研究等を参考にしながら、「役割語」について説明した。アニメや漫画の学者が「わしはじゃなあ、このことについては○○のように考えているのじゃ」というような現実世界ではほぼ誰も使わない話し方であっても物語の中でそのキャラクターの役割を示すのが役割語である。そして、ジェンダーにおいても「女性語」や「男性語」といったジェンダーを明確に示し、同時にイデオロギーに基づいた役割語がある。先行研究等を参照しながら、先生は、女性と男性がマスメディアの中で使うべきとされている日本語の表現について説明した。特に女性は「女性語」を話すべきとされ、また方言等を使うべきでないとされるイデオロギーがある。女性は綺麗な日本語、女性らしい日本語を話すべきというイデオロギーがメディアによって再生産されている。しかし、日本の女性は実際に方言や時には特に女子中学生などは「男性語」で話すことさえある。さらに、女らしいとされる「女性語」というのも実は明治時代の女学生が使い始めたもので、当時は下品で女らしくないとされていたものが、のちに新しい女性の言葉として雑誌や小説といったメディアによって再生産されることで広がった。このようにマスメディアを通して言葉の使用が再生産されることが重要であることに気付き、それが鈴木先生に外国人の語りにおいてはどうなのか考えるきっかけとなったという。
外国人女性が話す日本語についてはテレビや小説、または翻訳において様々な先行研究がある。例えば西欧人の女性が話している言語では特に女性語といったものが無い場合でも日本語に訳されるときは女性語に訳される傾向が強いことが確認されてきた。ここにも女性は女性語を話すべきというイデオロギーが見られるという。では、外国人男性が話す日本語についてはどのようなイデオロギーがあって、メディアを通してそれはどのように生産・再生産されてきたのか。小説の中の外国人の登場人物の語りを用いて説明された。
今回の研究では、小説に出てくる外国人男性の登場人物の場合は敬語を使う者と「男性語」を使う者とに分けられる。そしてそれは小説作家が設定した登場人物の「人種」や出身国によって使い分けられていた。いわゆる欧米諸国出身の「白人」の登場人物はほぼすべて敬語で話すのに対し、中国や韓国出身という設定になっている東アジアの外国人男性のキャラクターは男性語で話すこともある。
男言葉を話すことにはどのような意味があるのか?敬語を話すことにはどのような意味があるのか?先行研究などにも示されているように男言葉は「汚い」と思われ、とくに日本語文化の象徴であるとは考えられてはいないという。関西弁や東北弁などの方言においても同じことがいえるが、しかし、同時に文化の裏の側面として実は日本人にしか出来ないもの、砕けた感じのかたり、親近感を持たせるものとして考えられている側面がある。
今回の研究では文化的にも視覚的にも「人種的」にも日本人から遠いと考えられている「白人」には男言葉を使わせない傾向があった。これは、一般社会のなかでの白人の外国人男性の経験で男性語を使った際に周りから注意されとか、使わないようにたしなめられた経験と一致しているという。そしてそれは男言葉が日本人のものであると言う文化的ナショナリズムに基づいていることが伺えると説明された。その反面、視覚的にも日本人に見た目が似ているとされる東アジアの男性は、小説の中でも男性語を話すことが多い。特に、この研究で取り上げられた外国人男性で物語の主人公であった場合は必ず男性語を使う設定になっていた。歴史的にも戦前の日本の帝国時代のイデオロギーにおいても日本人と朝鮮人や台湾人を近い存在とし、文化的に包摂できるものとして考えられてきたことも先行研究で示されている。そして、小説の登場人物である韓国や台湾人、中国人男性に男言葉を使わせることで彼らを日本人に近い存在と位置づけていた。日本人と人種的に近いとされる東アジアの男性に男性語を喋らせることで、本当の日本語は日本人にしか喋ることができないという「人種決定主義」に基づいていることがうかがえるのである。
このような分析を経て、鈴木先生は、作家たちの描く外国人像とその語りの背景には文化的ナショナリズムと人種決定主義といったイデオロギーがあるという仮説を提示した。それは、白人男性には「男性語」をしゃべらせないことで白人を究極の他者として描く一方で、東アジア人男性には、その場面によっては男性語をしゃべらせることで人種・文化的に日本人に近いことを示すイデオロギーを再生産しているという。
この発表は、日本の大阪で生まれ育ち、人生の5分の2ぐらいは日本に住んできた「白人」男性としては大変興味深い話であった。自分は今でも「ハロー」などと英語で話しかけられ、関西弁などを使って返事すると驚かれ、日本語がうまいと褒められる。いっぽう、日本生まれ日本育ちで親が台湾出身の女性の知り合いが、わたしが日本語がうまいと褒められているのを見て「わたしはほめられない」と言ったことがあってその場面全体がとてもおかしいものに思えた。また、私は関西弁を話すし、男性語もつかうが、男性語を使わないようにとたしなめられた経験はほとんどない。それはなまりがあまりないから「勉強中」の外国人ではないと思われているのか、関西育ちといえば「だからか」と納得されているからなのかわからない。しかし、男性語が汚い、乱暴な言葉であると言われたり、考えられたりしているいっぽうで、それが日本の文化的ナショナリズムと人種決定主義の砦になっている可能性があることについて考えさせられ、とても興味深い発表だった。
(一橋大学大学院 社会学研究科 博士後期課程 マキンタヤ スティーブン)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第43回(2018年 9月21日)
「ポストコロニアル世界のイスラームと女性・ジェンダー」
講師:ザフラ・アリさん(ラトガース大学専任講師)
司会:森千香子さん(一橋大学大学院社会学研究科准教授)
参加記
2018年9月21日、一橋大学にてCGraSS(ジェンダー社会学研究センター)と一橋大学国際社会学プログラムの共催により、米ラトガース大学のザフラ・アリさんを招聘し、「ポストコロニアル世界のイスラームと女性・ジェンダー」と題して講演会が開催された。
講師のザフラ・アリさんは現在、ラトガース大学の社会学・人類学セクションで専任講師を務めている。専門はイスラーム世界、中近東、特に現代イラクにおける戦争・紛争下の女性・ジェンダーと政治・運動であり、自身もイラクの出身である。彼女は両親が政治亡命者としてフランスに渡ったことから、幼少期よりフランスで育ち教育を受けた。学生のころからフランスでアンチ・レイシズムの運動に携わり、若干17歳のときにはフランスの著名な社会学者でありフェミニズム理論家のクリスティーヌ・デルフィとともにアンチ・レイシズムを掲げるフェミニスト団体を設立したという経歴を持つ。
筆者は、講演者を宿泊場所から会場までアテンドする役割を引き受けることになり、幸運にも会場までの道中、彼女と個人的に話をすることができた。当日、主催側との連絡に齟齬があったため、約束した時間に遅れて待ち合わせ場所に到着してしまったが、長い時間待たせてしまったにも関わらず、全く気にする素振りも見せずに笑顔で迎えてくれた。彼女は日本を訪れるのは初めてだと言い、長いフライトで疲れているが今日の講演をとても楽しみにしていると快活に語ってくれた。筆者が中東地域に関心があると話すと、今までの彼女のアラブ世界での豊富な経験を語ってくれ、会場までの道中、とても贅沢で充実した時間を過ごすことができた。
筆者の自慢話はここまでとして、本題のザフラ・アリさんの講演の内容に移ろう。講演会の冒頭ではまず、司会の森千香子先生による講演者の紹介が行われた。2003年、フランスでは、公共の場においてイスラーム教徒の女性のスカーフ着用を認めるべきか否かという問題をめぐって激しい議論が毎日のように交わされていた。ザフラ・アリさんはこの、いわゆる「スカーフ論争」をめぐる運動に当時、高校生でありながら参加しており、実際に彼女の活動の様子も収められているドキュメンタリー映画の一部が紹介された。これは質疑応答の際に彼女が語ったことであるが、彼女がアカデミズムの世界に入ろうと決心したのは、自らがアンチ・レイシズム、そしてフェミニズムの運動に携わっていく中で、当事者としてこれらの運動を分析し、自らの声を世界に発信したいと考えたからであったという。彼女はフランスにおいてマイノリティのイスラーム教徒として生活し、さらに故郷のイラクでもフェミニズム運動に携わった経験を持つ。そのような二つの異なる場所での経験から、異なる場所にいる人々がいかにして連帯を形成するのかという理論的問いを、トランスナショナル・フェミニズムの観点から読み解くというのが彼女の研究における中心的な命題である。
講演の冒頭においてはまず、イスラーム教徒の女性について語る際に、そのトピックにおける自明性を脱構築することの必要性が投げかけられた。「イスラーム」とは、その大きな経験、文脈、歴史的また空間的な広がりがあるにも関わらず、イスラームという集団、あるいは概念に要約されてしまいがちである。このことにまず疑問を抱くべきであると講演者は主張する。
エドワード・サイードのオリエンタリズムに代表されるように、イスラームはしばしばポスト・コロニアルな文脈の中で捉えられる。しかし、実際に人々が「イスラーム」という言葉を用いる際、多くの場合、様々に異なる国や地域の事情が均一化され、固定的で単純化されたイメージのもとで用いられてしまう。さらに、イスラームとフェミニズムの関係性のこととなると、さらに事情は複雑になる。イスラームは女性に対して抑圧的であるという固定的なイメージのもとで、イスラームと女性の解放が完全に矛盾する概念であると考える人々もいる。
イスラーム教徒の人々の中には、フェミニズムというタームが西欧化されたもので、そもそもイスラームと繋げてはいけないという考えを持つ人もいる。一方で、宗教そのものがフェミニズムと矛盾しており、世俗的フェミニズムだけが正統なフェミニズムであると主張する人々もいる。これらの異なる立場からなされる主張において共通する問題点は、イスラームをひとつの概念としてまとめ、本質主義的な見方をしてしまっていることである。そこで講演者が主張するのは、「イスラーム」や「フェミニズム」という言葉にこだわらず、その中身に注意を向けなければいけないということである。これらのタームを用いる際に、Islam”s”やFeminism”s”というように、複数形を敢えて用いる必要性を講演者は提唱する。つまり、これらのタームの中に、様々なアプローチや経験、意味があるというところから始めなければならない。
アラブ世界において、「女性の問題(qaḍīyat al-mara’)」は、19世紀および20世紀に西洋の帝国主義の文脈の中で出現した。19世紀から20世紀にかけてアラブ世界は植民地主義と遭遇し、「アラブのめざめ(al-nahḍa)」を経験した。その時代の著名なアラブの思想家であるアフガーニーやムハンマド・アブドゥフは、西洋との遭遇の中で、イスラームを信仰しながら近代化を目指すモデルを模索し、新たな「ムスリム性」について著書を発表した。
アラブ世界においてフェミニズムが語られる際、必ず引用される本に、エジプトの法律家であるカースィム・アミーンによって著された『女性の解放(Taḥrīr al-mara’)』(1899)がある。この本は、ムスリムが多数の国において、女性の権利の議論に関する議論において先進的な役割を果たした。この本の一部は、アミーンと先述のアブドゥフとの会話から構成されている。それはいわば権力のある男性の政治的エリートの視点から執筆されており、当時のアラブ世界における女性が執筆した文章が脇へ追いやられているという問題点が指摘される。当時のイスラーム教徒の女性たちによって書かれた著作は非常にラディカルで、家父長制への疑問を投げかけるものが多くあった。イラクでは女性のフェミニストによって『最初の一歩(Awwal ṭarīq)』という本が出版され、宗教的とも世俗的とも解釈することができない独自のフェミニズム論が提唱されていた。
イラクでは歴史的に様々なフェミニズムの運動が展開されており、それに伴いイラクの知的階層の中ではフェミニズムについて、様々な議論がなされてきた。その議論の内容は多種多様で、イスラームの宗派主義的な議論だけではなく、完全に世俗的な左翼のラディカルな議論もあった。特に、1940年代や50年代のフェミニズムの議論においては宗教は問題視されておらず、女性の平等を考える際にどれだけラディカルであり得るかが焦点となっていた。
1940年および50年代はアラブ世界においては西洋の植民地支配から独立するという時代であり、実際にエジプト、チュニジア、そしてイラクなどの国ではフェミニストの団体が独立運動に関わっていた。しかし多くの場合、これらの国では独立を勝ち取ったころにはフェミニズムの問題は完全にわきへ追いやられてしまった。その結果、当時の多くのアラブ諸国においてはフェミニズムとナショナリズムの間にある種の緊張関係があり、アラブ世界におけるポストコロニアリズム時代のフェミニズムに関しては多くの論文が記されている。
そのようなアラブ諸国における独立後のフェミニズムをめぐる状況の中で、イラクの事例はある意味特殊であり、注目に値する。イラクの女性の地位に関する議論における重要な事例として、1959年に制定されたPersonal Status Code(以下PSC)と呼ばれる法律が挙げられる。イラクの王政を打倒し成立した当時の政権は、イラク共産党の協力のもとで、フェミニズム運動を西洋の植民地主義からの解放の一環として位置づけた。このような共産党の政策のもとで、PSCは市民法として制定された。PSCは女性の権利に関して、シャリーアの思想のもとで、女性の結婚、離婚、相続、親権といった権利を宗教的権利のレジームの枠組みにおいて統制した。
PSCの制定により、イラクにおける女性の地位は著しく改善されたとされる。もちろんこの法律は完全とはいえない。PSCは家父長制の色合いが強く、男性のナショナリストと家父長制の文化を温存し、その中でフェミニズムを擁護するという立場をとっていたが、同法は女性の権利に関して中東アラブ世界において当時最も先進的な法律であった。同法が制定される際、イラク延いてはアラブにおいてはじめての女性の大臣となるナズィーハ・ドゥライミが策定に関わった。彼女はフェミニスト活動家であり、共産主義活動家でもあった。また、同法はスンニとシーアの法的解釈を折衷する形で制定され、その点において双方の教派を統一するものであったと評価されている。同法の重要な条項の中には、相続に関して男女が平等であると定めたものがある。また、男女が合法的に結婚できる年齢を18歳としており、これに反した場合刑罰が科された。また、一夫多妻制も違法とされた。現在のイラク、そしてイラクの派閥主義や女性について理解する際、この法律の時代による変遷と、それについての議論を理解することが重要であると講演者は主張する。
1960年代以来、イラクにおいてはバアス党政権が一貫して政権を握っていたにもかかわらず、70年代には世俗的だった同政権による政策は、80年代、90年代には宗教色を非常に強め、保守化していった。1970年代には、イラクは女性に対して最も充実した教育システムを提供する国家であった。しかし、80年代に入りイラン・イラク戦争がはじまると、当時のバアス党政権は女性に対する問題に対してより保守的な方針に転換し、「良いイラク人女性は子どもを最低5人は産む」というようなナラティブに変更した。
90年代に湾岸戦争がはじまると、政府は「信仰キャンペーン」を打ち立て、社会のイスラーム化を促した。例えばイラクの国旗にアラビア語で記された「神は偉大なり」という文字も、90年代に制定されたものである。このような状況の中でPSCは改革の対象となり、女性の身体に対するコントロールを一層強めていった。
2003年のアメリカによるイラク侵攻と支配のもとで、イラクの社会は大きな転換期を迎えた。アメリカの侵攻後数か月後にはPSCが議論の的となり、アメリカ主導のイラクの新政権はPSCを人種および宗派によって異なる個別の法律へと改定し、宗派・部族のアイデンティティをもとにするシステムが成立し、人種差別が制度化された。その結果、イラク社会において暴力や貧困が広がり、イラク社会が宗教的、あるいは非宗教的な側面においても保守化が進んだと講演者は主張する。
このような米軍主導のイラク新政権の方針は、アメリカの多文化主義的な価値観を反映したものと解釈できるが、それは実際のイラクの歴史・社会的な文脈を考慮せずアメリカ的な人種・文化・宗派的なイメージを押し付けるものであったと講演者は主張する。イラクでもともと人種や宗派間の差別や対立が全くなかったわけではないが、それまでのイラクにおいて、市民は法の下に平等が保障されており、人々の属性にもとづくシステムは存在しなかった。その結果として、米国主導の政治的エリートによって、もともとあったイラクの統一性が完全に破壊され、そのような伝統は崩壊した。
そのような流れの中で、2014年には政治指導者によってPSCに代わる形でジャアファリ―法(Ja‘fari law)と呼ばれる法律が提案された。この法律はシーア派の思想を基にしており、女性の成人に達する年齢、つまり結婚が可能な年齢を9歳まで引き下げるというものである。このような法律が仮に議会で採決されると、イラクの女性の人権に関して、大きな損失につながるだろう。このように、イラクは50年代から70年代にかけては女性の権利に関して非常に先進的であったにも関わらず、2018年現在、イラクにおいて宗教家たちは女性の権利を脅かすような、非常に危険な状況を作り出そうとしている。
また、アメリカのイラク侵攻および支配は、イラクにおけるフェミニズム運動にも大きな影響を与えている。現在、イラクにおける女性のネットワークを形成する主要なプラットフォームに「イラク女性ネットワーク(Iraqi Women Network)」がある。同組織は多種多様なバックグラウンドの人々から構成されており、現在も活発に運動を行っている。しかし、宗派や民族による国家の分裂により、同組織や活動家たちの運動は物理的な面で非常に難しくなっているという。2003年以降、イラク社会は女性だけで集まって活動を行うことが非常に困難になっている。さらに現在、首都のバグダードでは宗派や民族のグループを隔てるように、各所にチェックポイントが設置され、武装した兵士が常時監視している。このように現在イラクでは女性の移動が制限されており、講演者はバグダートを「男性の街」と表現している。
今回の講演会における一連の議論を踏まえたうえで、講演者による結論は、以下のようになる。このように、宗教を単純な定義で捉えてしまうと、現実に起こっていることの意味が見えなくなってしまう。そして、現在起こっているような現象を宗教という非常に単純化した観点から見ると、その理解は不可能となってしまう。したがって、我々がイスラームというものを語るとき、よりインターセクショナルで相対的な分析方法を適用する必要性があると講演者は主張する。「イスラームと女性・ジェンダー」という問題を分析する際、一つ一つの要素を単純化して分析するのではなく、政治・経済・社会といった様々な観点から見ていかなければならない。
講演者であるザフラ・アリさんは第一線で活躍する活動家であり、彼女が研究のテーマとしているトランスナショナルなフェミニストの連帯をまさに体現する人である。彼女のような立場の人物から我々に投げかけられる主張や問いは、殊更に説得力を持ち、かつ刺激的だ。今回の講演のテーマである「イスラームと女性・ジェンダー」という問題を考える際、ポスト・コロニアルな文脈の中で、対象を単純化するのではなく、様々な要素について多角的に捉えていく姿勢が重要であるということが示された。そして、彼女の実践を通して、異なる国や地域で起こっている現象と、それに対する抵抗の空間的・時間的な連続性を理解するうえで非常に重要な示唆を得ることができた。彼女の活動および研究は、フェミニズムのみにとどまらず、社会における様々な思想や特定のグループに対する見方を脱構築し、理解を進めていくうえで非常に大きな意義を持つと言えるだろう。特に、日本というイスラームに対する理解があまり深くないと言える社会において、規模はさほど大きくはないが、このような機会を設けることができたのは大きな価値のあることである。このような機会が今後さらに増えていくと良いだろう。
(一橋大学大学院 社会学研究科 修士課程 阿部光太郎)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第42回(2018年 6月27日)
「感情を管理される日本軍兵士たち――軍事化されたマスキュリニティと戦争神経症」
講師:中村江里さん(日本学術振興会特別研究員)
司会:佐藤文香さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
第42回CGraSS公開レクチャー・シリーズは、「感情を管理される日本軍兵士たち ―軍事化されたマスキュリニティと戦争神経症」と題し、日本学術振興会特別研究員PDの中村江里氏にご講演いただいた。中村氏は日本近現代史を専門とする歴史学の研究者でありながら、軍事史、ジェンダー史、医学史と幅広く、学際的な研究に取り組んでこられた。現在は、ご自身の著書『戦争とトラウマ ―不可視化された日本兵の戦争神経症』(吉川弘文館、2017年)でも用いられた陸軍病院の病床日誌の資料集を出版されるなど(『資料集成 精神障害兵士「病床日誌」』第3巻(新発田陸軍病院編、六花出版、2017年)歴史資料のアーカイブ化に取り組まれたり、2017年2月には「海外派遣自衛官と家族の健康を考える会」の設立に携わったりと精力的に活動されている。
本講演で主要なテーマとなったのは、近代総力戦において各国で問題とされた「戦争神経症」である。とりわけ日中戦争以降の日本軍で問題化された、精神神経症患者に対する医学的解釈に、ジェンダーと人種・階級という文化・社会的構造がどのような影響を及ぼしたかについてお話しいただいた。
日本近代においては、兵役は徴兵検査やメディア表象、兵営にいたるまで「男らしさ」の規範と密接に結びつき、強固にジェンダー化されていたという。特定の男らしさが定義され、「男の中の男」という少年の理想像として軍人が称揚され、私的制裁をはじめとするあらゆる苦難も「真性の男子」を形成する軍隊には欠かせないものとされていた。それだけでなく、私的制裁に耐えられないものは「女の腐ったような」と罵倒されるなど、「兵士」としてのアイデンティティ構築と、感情等の「女性的なるもの」の排除といったミソジニーは不可分の関係にあり、軍隊はホモソーシャルな組織として成り立っていたという。このように兵役や軍隊が男らしさと切り離せない関係にあったことから、中村氏は戦闘への貢献度により、心身の犠牲の序列化がなされている可能性について考察されていた。戦中において、戦闘と最も近接性の高い犠牲である戦死はもっとも賞賛され、戦傷、戦病と続き、今回お話しいただいた戦争神経症はその末端に位置すると考えられるという。
さらに、その戦争神経症にもさらなる序列化が働いていたことを、中村氏は戦時期の軍事精神医療で用いられた病床日誌(カルテ)を元に分析されている。病床日誌では、戦争神経症は「ヒステリー(臓躁病)」と「神経衰弱」に使い分けられている。「ヒステリー」とは当時は通俗的に「女の病」とされ、女性化され侮蔑的な病名として用いられていたという。男性のヒステリーはジェンダー化されると同時に人種化され、戦時中、敵国を貶めるために相手を女性化する時の言い回しとして用いられることもあった。シェルショックの患者は自国内でも幼児性や非文明と結びつけられることがあり、戦時下の日本においても、同質で均一であることを求められる自国の軍隊において発生した男性ヒステリーは、「敵」と同じく「他者化」されることになる。ヒステリーとは自己中心的かつ感情的であるとして女性性や西洋と結びつけられ、戦時下の理想の男性像と相反する存在とされた。
このヒステリーという病名の与える侮蔑的な印象は、軍隊内でも罪悪的な響きを加えていたという。それゆえ、戦争神経症患者の存在が男性の軍人の権威を傷つけないよう、一般には流通していない医学用語である「臓躁病」という病名が用いられるようになった。さらに、下士官兵と比べると将校への配慮はより積極的になされており、兵士に「ヒステリー」や「臓躁病」という病名が用いられる一方で、将校にはその「将来の有用性」を考慮し、「神経衰弱」という病名が用いられることもあったという。ここに、軍事的・経済的に有用な男性のリスペクタビリティを保護しようとする精神科医たちの計らいが垣間見えると中村氏は述べる。
質疑応答では、これまで極端に語られることのなかった戦時下の戦争神経症について、中村氏が実際に見てこられた病床日誌の記録をもとに当時の軍事精神医療のありようを具体例を交えて説明されるだけでなく、その当時の状況を振り返った上で、現代における戦争とトラウマについて今後どのように考えていけるかについてもお話しいただいた。中村氏は以前、戦時下で「神経衰弱」と診断された方へのインタビューの中で、「あれはよく考えてみるとPTSDだったんじゃないか」と語られたという。その際に「言葉ができること」により、これまで語れなかった人々が語れるようになる可能性を感じ取られたようであった。さらに、戦時下では当然のようになされていた「戦争遂行のためのトラウマ治療」ではなく、「日常に復帰するためのトラウマ治療」のあり方を現在の日本でも模索していくべきであると語られ、講演は幕を閉じた。
戦争の苛烈化に伴い増加し続けた戦争神経症患者は、中村氏が冒頭で述べられたように、「男らしさ」と切り離せない軍隊や兵役においては「男らしさの理想への試練」であっただろう。それをどのように乗り切るかについて、戦時下では「ヒステリー」という女性化されたイメージを逆に利用して兵士の罪悪感を煽り治療にこぎつけたり、逆に聞きなれない「臓躁病」や「神経衰弱」という病名を用いることで兵士たちの女性化を避けたりという点は、ある時は戦争神経症患者を除け者にし、またある時は軍隊の傷として見られることのないよう軍隊という制度の中に取り込んでいくといった、巧妙な手段で軍事的なマスキュリニティを再構築しようとする軍医の奮闘と読むことができる。それだけでなく、当時の患者である兵士自身が傷病を恥じたり、「ヒステリー」という侮蔑化された病気に自分がかかってしまったことに罪悪感を覚えたりするというところに、戦時下の男性に理想とされた「男らしさ」が、いかに強靭な兵士たることを理想として軍事化され、感情などの女性的なものを除外することで構築されていったかがうかがい知れた。質疑応答でも中村氏が述べていたように、戦時下の戦争神経症に対する社会からの処遇から学び、自衛隊のメンタルヘルスをはじめとした現代的課題までを見据えて、戦争とトラウマの問題を考え続けることが肝要である。何が兵士たちの体験を語れなくさせ、不可視化させるのか。そしてどのような体制のもと、体験や思いは語り得るのかを、現代的な問題として問い続けなければならないと思いを新たにした講演であった。
(一橋大学大学院 社会学研究科 博士後期課程 関根里奈子)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第41回(2018年 1月19日)
「パリのフィリピン人家事労働者――カテゴリーとそこから零れ落ちるもの」
講師:伊藤るりさん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
シリーズ第41回となる公開レクチャーでは、伊藤るりさんが一橋大学・国際社会学プログラムに着任以来取り組んできた、フランス・パリのフィリピン人家事労働者についての調査研究についてお話いただいた。
伊藤さんが「パリのフィリピン人家事労働者」を研究のテーマとして取り上げた背景には三つの視点が交差している。ひとつめに、1980年代の日本において在留資格「興行」を取得して働いていたフィリピン人女性たちが「外国人労働者」としてはカウントされずにいた状況と、当時の日本では家事労働者の受け入れなされていないという状況に対する疑問。ふたつめに、同じく80年から国際移民研究において女性の国際移動が注目され始め、Parreñasの"servants of globalizations"や Hochschild の "global care chains" など、家事労働を担う女性たちの移動を概念化するような研究が登場してきたという状況。そして三つめは、伊藤さんの専門としてのフランス研究という視点からこのテーマをみると、フランスにおける家事労働は「職業化」され労働者の権利や休暇が整備された先進的なケースとしてとらえることができるという点である。このように女性家事労働者研究の重要性の高まりとあわせて、パリのフィリピン人家事労働者を労働の制度化、労働者としての権利保障や組織化という視点から捉えることから出発し、伊藤さんは、2008年より家事労働者、労働組合、フランス語教室関係者、自治体・省庁担当者、宗教団体等様々なアクターへのインタビュー調査と、参与観察を行ってきた。特に、フィリピン人家事労働者の移動の歴史を時間軸のなかで捉えることにより、「家事労働者」カテゴリーにおさまらない女性たちのすがたや、在仏フィリピン人コミュニティのあり方が明らかになってくる。なかでも、調査中に出会ったひとりのフィリピン人女性の「わたしは家事労働者ではありません」という発言をきっかけに、家事労働者カテゴリーは問い直しを迫られることになる。家事労働に就くフィリピン人女性たちには、家事労働を「仮の姿」と考える人々がいて、これまでの研究ではこうしたアンビバレントな感情は「母親アイデンティティ」へと回収されてきた(例えば、ParreñasやFresnoza-Flot)。しかし、伊藤さんは結論を急がず、このカテゴリーから零れ落ちるものを丁寧に押さえていくことを今後の課題として設定しつつ、この女性たちの非家事労働者アイデンティティを、「労働者」として制度化されることの重要性と合わせて考えていく。
フィリピン人家事労働者はしばしば「二重の非正規性」、つまり移民法上の非正規性と、労働法上の非正規性の両方をもつ。この状態から脱するには、まずは後者の非正規性からの脱却、つまり労働者としての制度化された地位を明確に獲得することが重要であり、サンパピエ(非正規移民)としてはこの労働者として雇用されているという事実の証明が、移民の地位の正規化のために必要になってくる。実際、多くの家事労働は闇経済の領域に存在する。雇用の事実を証明するためにあらゆるメモや、メトロのチケット、雇用者や周辺住民の証言などをかき集める努力が、労働組合によって80年代からなされてきたことが伊藤さんの発見した資料からわかっている。フランスは家事労働者の労働者としての制度化を整えてきたし、労働組合もこのように家事労働者たちをサポートする。しかし、先程の非家事労働者アイデンティティからもわかるように、正規化さえ上手くいけば、フィリピン人家事労働者は組合を離れてしまい、組合員として定着しないという課題をジタ・カバイス=オブラさん(CFDT、人身取引のサバイバーであり元家事労働者)は指摘する。フィリピン人家事労働者が特に必要とする支援があることを認識しているジタさんだが、フランス共和国の理念を受け継ぐ組合活動の中で特定のエスニック・グループに向けて活動することは難しい。このジレンマのなかでジタさんはCFDTとは別にフィリピン人のアソシエーションを結成し、組合とエスニックなアソシエーションの二本立てに依る組織化を図っている。
また、在仏フィリピン人家事労働者のコミュニティも決して一様ではない。コミュニティのつながりを特徴づける軸は、宗教や出身地域、看護学校同窓生など複数あるうえ、独立記念日、パレード、宗教的イベントから、誕生日のお祝いやピクニック、ギフトの交換などを通して絆を確認する"bonding" など、コミュニティの時間と空間は多様なレベルで存在し、また、その参加者の階層性もみえてくる。 パリのフィリピン人家事労働者がどのように生活し、再生産の権力関係の中でどのような地位にあるかということは引き続き伊藤さんの研究でより明らかになっていくであろう。
今回のレクチャーでわたしが印象的だったのは、パリのフィリピン人家事労働者を複数の時間と空間の軸でみていくことにより、参加者として研究の奥行きを理解していくような経験ができたことである。伊藤さんのお話から、パリのフィリピン人家事労働者について、移住を経験する人々、アンビバレントな感情と二重の非正規性をもつ集団、在仏フィリピン人コミュニティを形成し生きる人々としての多様な側面からその存在を理解しようとする試みが伝わってくる。特に、彼女たちの次の世代(フィリピンに残してきた子どもたちの子育て)と前の世代(年老いた元家事労働者のケア)の局面が示唆されたことと、さらに「屋根裏部屋の6階」(富裕層のオスマン風アパルトマンの屋根裏に位置する家事労働者が住み込みで暮らす小さな部屋)が、1960年代のブルターニュ地方出身者から、スペイン人、そしてフィリピン人へと世代交代されてきた国際的な再生産労働力が集まる場として示されたことで、この研究のなかで歴史、国境、エスニシティ、ジェンダー、世代の軸が交差し、また重なっていることを強く実感した。
また今回のCGraSS公開レクチャーは国際社会学プログラムとの共催で、伊藤るりさんの一橋大学退任を記念するイベントでもあり、第2部では国際社会学とジェンダー研究の「これまで」と「これから」が、伊藤さんの研究仲間・学生たちとの対談を通して存分に語られた。
(一橋大学大学院 社会学研究科 博士後期課程 工藤晴子)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第40回(2017年 6月30日)
「『裸足で逃げる』の若者たちの生育環境・ネットワーク・暮らすこと」
講師:上間陽子さん(琉球大学教育学研究科・教授)
司会:山田哲也さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
第40回CGraSS公開レクチャーは、「『裸足で逃げる』の若者たちの生育環境・ネットワーク・暮らすこと」と題し、琉球大学教授・上間陽子さんに講演していただいた。講演のテーマにも含まれている『裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』(太田出版)は2017年2月に刊行され、教育研究の世界だけに限らず、一般書としても注目を集めている著書である。同書は、沖縄の街で困難を抱えながら生きる6人の女性たちの生活の記録である。上間さん自身も著書のなかで「大文字の概念枠組みで彼女たちの人生を分析するということではなく、彼女たちの人生をできるだけまとまった『生活史』の形式で記すことを目指しました」(同書 p256)と述べているとおり理論的な分析や具体的な支援方法が同書の主軸ではない。同書を通じて、私たちは、この世界で生活困窮や暴力のなかでも生きている彼女たちがいることを体感させられる。
本講演は『裸足で逃げる』の執筆の経緯を中心としながら、沖縄の若者たちの実態、そして上間さんの今後の研究関心などについてお話いただいた。
「若い女性がどうやって大人になっていくのか」
上間さんの研究は、東京での女子高校の研究から出発する。現代の女性の性規範の変化について、学校内部に入りこみ、ライフストーリーや生育歴の丁寧な聞き取り調査を行った。調査中には、援助交際の場面を含めた性暴力の話も見聞きし、どうしたらよいかとまどい、被害にあったことや犯罪に加担したことは書かないということで研究を進めた。これが調査屋としての最初の経験だったという。上間さんが自身の一貫した研究テーマだと語る「若い女性がどうやって大人になっていくのか」という問いに通じる原体験といえる調査だろう。
その後、高校生から20代までの継続調査や小学校の友人関係のエスノグラフィーなどの調査、沖縄県の全国学習学力状況調査の分析などさまざまな調査に参加する。沖縄に研究拠点を移すと、沖縄の家族が抱える貧困・暴力などの困難とそうした困難を覆い隠す家族規範に直面する。そして2010年に起きた女子中学生の集団レイプによる自死事件が起きる。学校にも親にも、見過ごされるレイプ被害者の少女たち、加害者である男性コミュニティの暴力性や、被害者とその家族に対するバッシングを目にするなかで、上間さんが沖縄のリスクを抱えた若者たちを調査するきっかけとなる出来事であった。
「性暴力について書かないということはできないんじゃないか」
上間さんは、『裸足で逃げる』を書こうと思ったきっかけのひとつは、2016年に沖縄県で発生した元海兵隊員・軍属による20歳の女性殺人事件であるという。この事件は、沖縄県で女性支援活動をする人々に大きなショックを与えた。とくに、「沖縄の社会はとても狭く、性暴力の被害者は訴えないと思っていた」という逮捕時の加害者のコメントは、性暴力の被害者たちが声をあげられない、声をあげても届かない状況を改めて明らかにした言葉だった。
こうした事件を目の当たりにした上間さんは、性暴力について書かないということはできないと思ったという。それまで、性暴力の体験について書くことによる2次被害や、被害者のプライバシーを完全に保護することができるのか、といった観点から性暴力について書くことは避けてきた。しかし、「書かないままであるかぎり状況は変えられない、いまも性暴力被害にあうかもしれない場所で生き続けている人の被害を止めなければいけない」、こうした思いが、上間さんが女性たちの性暴力・性被害について書くことを決意したきっかけとなった。
また、『裸足で逃げる』は、支援に関わる人を対象に、わかりやすい文体で書くことを心がけたという。沖縄県は、2016年に子どもの貧困率が23.9%であることを発表し、全県をあげて貧困に取り組んでいる。一方で、支援員が困難状況の子どもに近づこうとしても、子どもたちは日頃馴染のない支援員に近づいてくれない、どのような困難を抱え、何を必要としているのか語ってくれないという状況にあった。どうかかわれば子どもたちは語ってくれるのか、支援員が悩む姿を上間さんは見聞きするなかで、子どもたちがどういう生育歴でどう語り始めたのかをわかりやすいかたちで書くということも重点を置いた。
「苦しすぎて語れない苦しさ」―それでも過去を語ること
上間さんのインタビューは何度も女性たちの語りを聞くことがひとつの特徴である。『裸足で逃げる』の優歌さんの第一回目のインタビューでは、沈黙も多く、「十分にきけなかった」と思ったという。一方で、インタビューを何度か繰り返していくうちに、彼女が「語ることのできなかった苦しみ」をもっていたことに気づかされたという。
このように、上間さんは何度も女性たちとやりとりをし、『裸足で逃げる』を書きあげた。彼女たちとのやりとりでは、プライバシーの保護の観点から書籍化する文章では匿名性を高くすることや、どこまで詳細にインタビュー内容を掲載してよいのかについて、詳しく説明・確認をしたという。一方で、彼女たち自身は、匿名性を高めた原稿について「そのままでいい」「自分の人生という感じがしない」と応えた。彼女たちにとって苦しい過去の経験は、一方で自分の人生の切り離せない一部である。苦しい経験を再帰的にナラティブに語ることは、自らの軌跡をたどることであり、彼女たちの安定につながると感じるようになった、と上間さんはいう。
「家族ってほんとにやっかいだと思った」
『裸足で逃げる』で中軸となっているのは、女性たちの身体、ネットワーク、家族である。 1つ目の身体について、上間さんは、調査のなかで、彼女たちの中絶や出産の場面に立ち会うなかで、女性たちが承認される場所がいかに存在しないかに直面したという。中絶手術に立ち会ったときには、医師から診察に必要のない、女性のプライバシーにかかわる内容を配慮なく質問され、説明を求められた。術後には安静する時間をとらず、帰されてしまう。『裸足で逃げる』女性たちのこれまでの経験において、いかに身体が大切に扱われず、承認が棄損されているかに直面する出来事だった。また出産した女性に差し入れをしたときには、「ふつうの家族像」を前提とした育児雑誌を見て、単身でお金も十分になく、これから子どもを抱えて必死に生きていこうとする彼女に渡せる雑誌がなかった。仕方なく買ったのは、彼女が好きなネイルの雑誌であった。彼女の子育て・家族の形成の仕方が、現代の子育てや家族像のなかに含まれていないことを思い知らされる出来事だったという。
ネットワークという点では、10代のときに学校でできた関係性そのものが危機的状況において効いているという。一方で、20代になると関係が持続的にあるわけではないが、女性同士の互恵的関係は、生まれ育った土地から移動の少ない彼女たちにとって重要な資源となっていることが明らかになった。
上間さんにとって3つ目の家族は大きな主題であった。『裸足で逃げる』女性たちは、定位家族にも生殖家族にも暴力を含めたさ まざまな問題がある場合が多かった。一方で、彼女たちは親や家族から暴力や育児放棄を受けても、親のことは悪く言わない、家族を見捨てることはしない。上間さんは、少し怒りをこめながらも、「なぜ自分のことを大切にしてくれなかった親を大切するの?」と聞いた。一人の女性は上間さんの問いに対し、「自分の、本当に命に替えがたい子どもがいるのは親のおかげだから。だから私は親の面倒を見る。」と応えた。彼女たちにとって、暴力や育児放棄を受けながらも家族は自身とは切り離せないものとなっていた。上間さんはこのやりとりのなかで、「家族って本当にやっかいだなと思いながらも、実践領域の感覚なんだなと思った」、そして「やはりケアを軸として家族を考えることが重要であると感じた」という。女性たちがどのような家族に生まれ、どのように家族を作ろうとしているのか、そこにおけるケアのありようとそのための資源の不徹底を描き、だからこそ家族を支援しなくてはならないという議論をするべきだと考えるようになったきっかけであったという。
「目の前の子どもが喜ぶから」―裸足で逃げたその後と沖縄の家族責任論
調査も5年目となり、『裸足で逃げる』で出会った女性たちのなかには、計画的な家族形成に向けてパートナーと歩み始める姿が 見えてきた。一方で、依然として家族や恋人関係といった親密圏に入りこむ暴力と生活せざるをえない者がいるのも現状である。とくに彼女たちは子育てをする際に、外部に委託できないために自分に暴力をふるった家族や恋人に子どもを預けざるを得ない場合も少なくない。
『裸足で逃げる』を通して、沖縄で困難を抱えながら生きる女性たちとかかわるなかで、沖縄で大きな力を持つ「立派な家族」像 がいかに沖縄の女性たちの多様な生き方や多様な家族のあり方を断罪しているかという問題が突き付けられた。沖縄県では、全国学習学力状況調査最下位という結果を受けて、早寝早起き朝ごはんといった家庭での生活習慣指導を徹底し、「家庭の教育力」を上げることが推進された。一方で、上間さんがかかわってきた女性たち、とくに子育てをしている女性たちは、「学力」や「家庭の教育力」の向上のために子どもをケアしているわけではない。またこうした「学力」や「家庭の教育力」の向上を掲げた取り組みでは、子どもをケアする女性たちに責任が帰属されてしまう。女性たち自身が本来守られるべき存在でありながら、守られていないことには目を向けず、さらにケアの内実を生活習慣指導と「学力」向上に矮小化することとなり、それは目の前の家族を断罪することになる。
「暴力を認める風景がそこにある」―今後の課題
上間さんは今後の課題として、1)軍隊との関係と2)セックスワーカーをめぐる議論に言及した。
『裸足で逃げる』彼女たちは、沖縄県の米軍基地のそばで暮らしてきた。上間さんは「占領軍があるというのは、暴力を認めるような風景がそこにある。そこで育っていることが、影響がないはずがないと思っている。」と述べた。基地近くに住む男性たちは、軍人のもつ暴力性をもった文化に親和的に育ち、成長過程で身につけた暴力性が女性に向かっていると上間さんは感じているという。現在、高江・辺野古でのヘリパッドや軍基地新設には沖縄の若い男性たちが多くかかわっている。彼らの軍基地反対運動に対する冷ややかな視線や、彼らが国家的なものに統合されて仕事をしているという感覚など、沖縄で育ち、暮らす男性たちにとって基地は大きな影響力を持っている。上間さんはこうした基地をとりまく景色を「グロテスクな景色」とも表現した。
今後の課題の2つ目は、セックスワーカーをめぐる議論である。沖縄には、未成年からセックスワーカーとして働き、いったん仕事を辞めるものの、その後子どもを持ち同じ業界に戻って働く女性たちがいる。彼女たちのなかにはセックスワーカーとして働いたことを「話せない」「うしろめたい」といったスティグマとして抱えている人もいるという。上間さん自身は、セックスワーカーの合法化は必要とする一方で、彼女たちの自己決定の選択不可能性や、また労働としてのセックスワーカーのリスクの低減、スティグマをなくすことなど、いまだセックスワーカーには取り組むべきさまざまな問題がとりまいている。こうした課題について今後整理していきたいとし、発表を終えた。
「吐きそうになりながら聞いている。でも聞かないといけない。」―沖縄の男性たちと暴力
質疑の時間に多くの質問があがるなかで、印象的だったのは「男性側の語りを書かなかった理由はなにか?」という質問だった。
上間さんは、『裸足で逃げる』での調査時点には、男性の語りは聞けなかったという。それは、上間さん自身が怒りを抑えられなかったためだ。「フロントガラスを割ってやろうかと思うくらい」、『裸足で逃げる』彼女たちに向けられる暴力、暴力を振るう男性自身に対する怒りが抑えきれなかった。
現在の調査では、『裸足で逃げる』の彼女たちの恋人や家族など男性側の聞き取りも行っている。そこでは、殴られながら育った男性たちの生育環境や、中学時代の暴力が組み込まれた先輩後輩関係が見られるという。上間さんは男性たちの語りを聞きながら、「暴力が本当に嫌いで、吐きそうになりながら聞いている。でも聞かないといけないなと思っている。」という。暴力を生み出し、受け継がせてしまうメカニズム。加害者側が暴力をどう継承し、用いてしまうのか、ということも今後の課題と今後の課題となっていくことが語られた。
講演を終えて
上間さんは終始穏やかな声であった。その声は、『裸足で逃げる』のなかでそっと彼女たちに寄り添い、語りに耳を傾ける著者像にぴったりとあてはまる。一方で、講演を聞いて印象的だったのは、彼女たちに振るわれるさまざまな暴力や、彼女たちを排除する社会に対する怒りであった。暴力や困難を生き延びた過去の苦しい経験は語る側はもちろん、聞き手にとっても相当な精神的負担だろう。上間さんは、怒りや苦しみといったさまざまな感情を抱えながらも、沖縄で『裸足で逃げる』彼女たちに向き合い続けた。そこには、沖縄という社会や「女性」をとりまく性規範によって生み出された暴力や困難がある。一方で、私たちが生きるその地続きに、裸足で逃げているひと、裸足で逃げようとしているひとが存在することをまざまざと見せつけられた講演であった。率直にいえば、私にはまだ彼女たちの引き受けた困難や、上間さんが抱く怒りに対して応答できる言葉を持っていないことを痛感させられる。『裸足で逃げる』彼・彼女らと地続きの社会で生きている私にとってできることは、彼・彼女たちから目をそらさず、ひたすら向き合い続けることだと改めて思った講演であった。
一橋大学大学院 社会学研究科 修士課程 渡邉綾
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第39回(2017年 5月12日)
「台湾の同志(LGBT)運動と文学―東アジアの基層文化と性のあり方を考える」
講師:橋本恭子さん(津田塾大学・非常勤講師)
司会:洪郁如さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
講師の橋本恭子先生は、仏文科からフランス系企業勤務を経て、台湾の清華大学と本学言語社会研究科で大学院を修了されており、これまでは主に、日本統治期台湾の比較文学者島田謹二を批判的に研究してこられた。御自身と島田謹二に共通する日本・台湾・仏語圏という枠組みの下、近年は新たなテーマとして、この3地域における性的少数者運動・文学の比較研究に取り組まれており、また「虹色とんちー」(「とんちー」は後述する中国語「同志」から)という団体を立ち上げ、LGBTや性の多様性について地域の理解を深める為の活動にも携わっておられる。
レクチャーの導入として、「学問の土着化」というお話があった。クィア・スタディーズの東アジアにおける受容を検討する中で、具体的な問題として「クィア」や「セクシュアル・マイノリティ」といった語が、日本ではカタカナで直輸入されて使われているのに対し、台湾ではそれらを包括する「同志」という語が用いられている例を挙げ、日本における外来概念の土着化に疑問を投げ掛けられた。そしてこの新たな学問が孕むアメリカ偏重主義と、「新自由主義的LGBT運動」vs「新しいホモノーマティヴィティ批判」という二項対立からの脱却を提唱され、その為には多言語・多地域間の運動・文学の交流が有効であると論じられた。
続いて、台湾の同志運動の大まかな流れを解説された。現在注目が集まっている同性婚法案を巡る動きに加え、日台の現状を表す象徴的な数字として、自治体による同性パートナーシップ制度の申請者数で、日本が52組(2016年8月時点)なのに対し、台湾は既に1,000組を超えていることを挙げ、文字通り桁違いの差に驚いたと話されていた。台湾の同志運動の特徴としては、日本統治時代/国民党独裁時代からの民主化・人権運動の流れの中に位置付けられる点と、フェミニズムや環境保護運動等、他の社会運動との結び付きが強く、社会全体に広がりを持っている点を指摘された。
そしてここまでのお話を踏まえ、日本にとって未踏の新たな可能性を切り拓き、多様な価値観を創出する手掛かりとして、台湾の同志文学を紹介された。胡淑雯の『太陽の地は黒い』において、異性愛者である主人公が性的マイノリティを語る構図が採られていることに関し、橋本先生は「問題はもはや『非-当事者』と『当事者』の間ではなく、私たちのセクシュアリティを支える諸構造に対する『無自覚』と『自覚』の間にある」という村上隆則の言葉を引用され、御自身もLGBT運動に関わる中で悩んできた「非当事者の役割」という問題に示唆を与える内容であったと述べられた。その他にも阮慶岳の作品や、日本語で書かれ群像新人文学賞にも選ばれた李琴峰の『独舞』を紹介され、この分野ではまだ成果の少ない日本文学にとって、台湾文学との交流が秘めている可能性を指摘された。
それぞれにとても興味深い内容のお話が沢山詰め込まれ、密度の濃いレクチャーだったが、橋本先生の軽快な語り口のお蔭であっと言う間の時間に感じられた。個人的に一番印象深かったのは、日本と台湾の違いについて最後に先生が語られた、「台湾は良い意味で「国」が小さいので、学問と運動の距離が近い」という言葉である。社会運動との距離の取り方は、人文・社会科学に従事する全ての研究者にとって難しい問題であろう。自分も台湾の少数言語復興運動について研究する中で、台湾の研究者の多くが同時に熱心な運動家でもある事実に少なからず驚かされた。結果として、台湾で書かれた論文の中では、感情が先行しやや論理性に欠ける記述にもしばしば出遭うことがあり、それは客観性の担保が不可欠な学問にとって、当然問題であるとは思う。しかしだからと言って、社会運動に超然的な態度を保ち、研究成果の実社会への還元のプロセスには手を染めないことが、研究者の正しい姿勢であるとも自分は思わない。今回のレクチャーでも触れられたが、本学で起きたアウティング事件のような痛ましい出来事が発生した場所が、正にこのレクチャーの開催場所であり、日々「高度な」学問が展開されているマーキュリータワーであったという事実に向き合う時、その思いを一層強くせずにはいられない。
また本題とはやや離れるが、冒頭で先生が、教え子の中に台湾がかつて日本の植民地であった事を知らない学生がいたと話されたのにはショックを受けた。台湾に関わる研究をする者として、日本人の台湾に対する理解の浅さについては、自分も責任の一端を担う問題として取り組まねばならないという思いを新たにした。昨今の斯様な状況は、日本人がかつての支配者側の人間であるという点から見て不適切であるばかりでなく、台湾人が現在日本の事をよく知ってくれていることを考えれば、甚だ不平等でもあると言えるだろう。日本はもっと台湾「を」学び、台湾「に」学ばなければならない、そう再認識させて頂いたレクチャーであった。
一橋大学大学院 言語社会研究科 博士後期課程 吉田真悟
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ/一橋大学国際交流セミナー 第38回(2016年11月18日)
「大学・教育とセクシャルマイノリティ(LGBT)―大学にできる支援について考えよう」
講師:遠藤まめたさん・松岡宗嗣さん
司会:ソニヤ・デールさん(一橋大学社会学研究科・特任講師)、大島岳さん(一橋大学社会学研究科・博士後期課程)
参加記
第38回CGraSS 公開レクチャー・シリーズは、「大学・教育とセクシャルマイノリティ(LGBT)―大学にできる支援について考えよう」と題して、性的マイノリティの若者支援に携わってきた遠藤まめたさんと、明治大学でオープンリーゲイとして活動する松岡宗嗣さんのお二方を講師としてお招きし、ご講演いただいた。
本学法科大学院の男子学生が自らの性的指向を同級生に暴露され自死に至った事件が広く報じられたのは、忘れもしない夏の盛りのことであった。事件の報に触れたときの心臓が凍るような感覚をいまもわたしは忘れることができない。驚き以上に、学部時代の4年間を同じキャンパスで過ごした身としては、件の事件は——こう言ってよければ——「起こるべくして起こってしまった」ようにも感じられた。多くの性的マイノリティ当事者がメディア等で述べているのと同じように、わたしもまた「彼はわたしだったかもしれない」と感じたひとりであった。本レクチャー・シリーズは、そのような事件の衝撃が多くの人びとの胸に刻み込まれたなかで開催され、大勢の参加者による活発な議論が交わされた。
まず遠藤さんのご講演においては、ご自身の経験を踏まえながら、性的マイノリティ——とりわけトランスジェンダー——の抱える問題経験や、周囲の人たちにどのような支援ができるのか、といった点についてご紹介いただいた。一口にトランスジェンダーといっても性別移行の状況等によって問題は人それぞれであること、学生簿や証明書における氏名・性別記載などの制度面の問題やトイレ・ロッカーなどの日常生活における問題のほかにも、語学系の授業における三人称の問題やシューカツの問題などがあることなど、性的マイノリティについて勉強しているつもりがまだまだ十分に分かっていなかった部分があるのだと思い知らされた。また相談前の全体対応と相談後の個別対応など、支援に携わってきた遠藤さんだからこその大学で可能な生的マイノリティ支援にかんする知見は非常に説得的なものであった。
松岡さんからは、アライ(性的マイノリティの支援者・理解者)を増やすための明治大学での取り組みについてご紹介いただいた。正直なところわたしはMEIJI ALLY WEEKにおけるファッションショーのような企画は、ある種のルッキズムに結びついてしまう危うさを感じて、やや懐疑的にみていた——これは講演後の質疑応答においても提起された問題でもある——のだが、多角的な取り組みを通じてアライになるための間口を拡げることの重要性を説く松岡さんのご講演を受けて、批判を覚悟の上でとにかくやってみることの大切さを痛感した。
「大学の大衆化」が言われて半世紀が経つ昨今、大学の成員は多様化し続けている。しかしながら、大学は——無論一橋大学も含め——はその学生や教職員の多様化にどれだけ向き合ってきただろうか?大学は性的マイノリティが安心して勉学に励むことのできる環境を整えられてきただろうか?忘れてはならないのは、これまでも——そして今現在も——大学には性的マイノリティは存在し続けてきたという極めてあたりまえの事実である。性的マイノリティは、今までもこれからも、大学にとって無関係の他者などではないのだ。
なお事件の報道を受け、CGraSSは「本学法科大学院における事件の報を受けて」と題した声明を発表している。本レクチャー・シリーズは性的マイノリティの問題を通して、大学がどうあるべきなのか考え続ける必要性を提起するものであったと言えるかもしれない。今回示された方途を参考にしつつ、これからもこの問題について考え続けなければなるまい。
(一橋大学大学院社会学研究科 博士後期課程 横山 陸)
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第37回(2016年 10月14日)
「現代ドイツにおけるフェミニズムと反フェミニズム運動」
講師:イルゼ・レンツさん(ドイツ ルール・ボーフム大学・教授)
司会:大河内泰樹さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
第37回CGraSS公開レクチャーでは、ルール・ボーフム大学よりイルゼ・レンツ先生をお迎えし、『現代ドイツにおけるフェミニズムと反フェミニズム運動』と題してお話いただいた。現代のドイツが直面しているジェンダーに関する状況とその歴史的経緯についてお話しいただくなかで、日本とドイツにおける反フェミニズム運動の比較などにも言及され、意義深く、新たな発見の多いレクチャーとなった。
はじめに、「反フェミニズム」とは何かを、「ジェンダー保守主義」との違いにも言及しながら説明してくださった。フェミニズムやジェンダー平等に反対する反フェミニズムは、ドイツで性差別のみならず人種差別とも結びつき、「ドイツ人女性を移民男性から守る」という文脈で用いられているそうだ。
続いて、ジェンダーをめぐるさまざまな分析概念についても解説していただいた。「ジェンダー・コンフリクト」とは、フェミニズム対反フェミニズムという図式のみに収まるものでなく、そこにはメディアや市民をはじめとする様々な要因が関わっている。現代における「ジェンダー秩序」の3つの潮流として、レンツさんは「国家による新家父長制」「生物学的な違いに基づく秩序」「柔軟なジェンダー秩序」をあげ、反フェミニズム論者とは「生物学的な違いに基づく秩序」に立ち返ろうとしているのだ、と強調された。
さらに、1968年から現代にいたるフェミニズムの歴史を4つのフェーズに分けて説明し、現代のフェミニズムが抱える問題として、「仕事の平等」「身体とセクシュアリティの自己決定権」「ドイツ人と移民のフェミニズム」があると指摘された。「仕事の平等」では日本とも共通するケアワークの担われ方の不均等、「自己決定権」では反フェミニズムに対抗し、中絶に対する自己決定権を主張した2015年のWhat-the-fuck-march、「ドイツ人と移民のフェミニズム」では、反フェミニズムと結びついた性差別・人種差別についてドイツ人と移民のフェミニストが連帯して戦い、性暴力についての法を改正したというお話が特に印象深かった。女性運動の成果として、ジェンダー、セクシュアリティ、家族などについて、ドイツの法・社会・文化が「より柔軟なジェンダー秩序」へと変遷してきたことがわかった。
しかし、その一方で、反フェミニズムの潮流も存在し続けている。インターネット・マスキュリニスト、メディア・アンチフェミニスト、超宗教的な人々、ネオリベ、ネオナチといった各集団はこれまでばらばらに活動していたが、2014年以降、オルタナティブという政党が台頭し、個々の運動をまとめあげる動きが起こっているという。このお話しの際に、比較対象として、日本における日本会議の存在にもふれられた。
最後に、ドイツにおいて男性や移民がフェミニズムに参加するという現状に言及しつつ、反フェミニズムに対抗していくためには、ネットワークを作り、反フェミニズムの主張の背景を見極めて声を上げていくことが大切だとイルゼさんはおっしゃっていた。
質疑応答で「ジェンダー平等が概ね達成されていく中で、フェミニズムはもういらないという声はあるのか」と伺ったところ、ドイツでは若い男女が連帯して、フェミニズムはまだ必要であると主張し、より進んだジェンダー平等を目指していく動きがあると教えていただくことができた。
全体を通じ、ドイツや日本におけるジェンダーをめぐる問題に対するイルゼさんのまなざしはポジジティブで、未来への期待が込められているという印象を受けた。「より柔軟なジェンダー秩序」が広がっていくために、今起きていること、そしてその背景を見過ごさないよう注意しながら、これからも考え続け、声を上げていかなければ、と改めて思うことができる貴重な機会となった。
一橋大学大学院社会学部4年 丁子幸
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第36回(2016年 7月6日)
「誘惑の舞台:夢を売る商売-東京ホストクラブ」
講師:竹山明子さん(米国 カンザス大学・准教授)
司会:ソニヤ・デールさん(一橋大学大学院社会学研究科特任講師)
参加記
第36回CGraSS 公開レクチャー・シリーズは、「誘惑の舞台:夢を売る商売-東京ホストクラブ」と題し、米国カンザス大学准教授の竹山明子さんに講演していただいた。竹山さんはジェンダー、親密さの商品化、新自由主義的グローバリゼーション等をテーマとして研究を行っている文化人類学者である。本講演では、今年3月に出版された竹山さんの著書「Staged Seduction: Selling Dreams in a Tokyo Host Club」(Stanford University Press)から、ホストクラブ現象について、ジェンダーを軸に新自由主義的構造改革下における自己実現がいかに商品化されるかという観点からお話しいただいた。
はじめに述べさせていただくと、竹山さんの研究の特徴は、感情や親密性など実証が難しく研究対象になりにくい側面を、自らAffective Ethnography「情動を駆り立てるエスノグラフィー」という方法論を提案し、明らかにしようとしている点にある。著書では、誘惑、焦燥感、不安など様々な感情の動きが感じ取れるよう、香りや音楽までも含んだその場の空気感が再現されている。深く精密なフィールドワーク、当事者視点への洞察、その場の人々の感情を掬い採らねば描くことができない叙情的な描写に、私自身も情動を駆り立てられずにはいられなかった。今回の講演は時間的な制限があったため、それを完全に再現することは難しかったかと拝察するが、2名のストーリーを中心に可能な限り丁寧に語ってくださったことに感謝したい。また、著書には本講演の内容も含め、より広い対象・時間軸の中での詳細な記述がなされているので、詳しい内容についてはそちらをご覧いただくことをお勧めする。
本講演の内容は、竹山さんが新宿歌舞伎町にある老舗ホストクラブで行った博士論文の研究、およびその後10年あまりにわたる追跡調査がもとになっている。竹山さんが博士論文のための予備調査を開始した2003年、日本に滞在し本格的にフィールドワークを行った2004年から2005年は、ホストクラブがマスメディアでも盛んに取り上げられ、社会的な認知度が高まっていった時期である。本講演では、主にこの時期に竹山さんが行った調査結果を中心に発表していただいた。
竹山さんはこの研究を行うにあたり、ホストクラブのオーナーに直接許可を得て、調査者としてフィールドワークを行った。しかし許可が下りたのは、1部という深夜24時までの合法な営業時間帯に限られる。そのため、顧客は若いホステスやセックスワーカーを中心とする2部とは異なり、主婦やキャリアウーマンなど30~40才代を中心とした比較的年齢層の高い女性たちが中心となっている。本講演ではこのような特徴をもつフィールドから見えてきた知見を語ってくださった。
竹山さんは研究開始以前、マスメディアが描くホストクラブに関する表象から、「女性が男性を買う時代」と女性の活躍をもてはやす言説、「女性を食い物にする卑劣な男性、および商売」という加害者としての男性・被害者としての女性を強調する言説、そして疑似恋愛に酔った女性の札束が飛び交うという一見相容れないイメージを見聞きしていたという。
だが、実際にフィールドワークを開始してみると、竹山さんはそのような言説やイメージでは集約しきれないホストクラブの側面を発見する。特に当事者の語りの中で注目した言葉が「夢」である。ホストは、ホストとは「夢を売る商売」だと語り、女性客はホストクラブは「夢を見させてくれる」と語る。竹山さんは参与観察や聞き取り調査を通じ、「夢」という言葉を紐解いていく中で、その根底にあるものが「自己実現」(将来から現在を見据えて行動を決定し目標を実現すること)のプロセスであることに気づく。ホストクラブにおいては、男女ともに「男らしさ」「女らしさ」と密接な関係にある将来の「理想的な自己像」を心に描き、その自己実現を図る。つまり、「理想的な自己像」が目標になり、そこに向かうプロセス自体が「事業」・「プロジェクト」として捉えられ、ホストクラブに関わるあらゆる労働や消費が自己実現に必要な投資として捉えられる。そして、この自己実現のためのホストの労働や女性客の消費活動、すなわち自己実現のプロセス自体が、ホストクラブでは資本化されているのだという結論に達する。竹山さんは、このように個々人が理想像を打ち立てて実現するプロセスがどのように舞台仕掛けの誘惑(Staged Seduction)の中で誘導され方向付けされているか、そして資本化されているのかを説明してくださった。
説明にあたり、竹山さんは典型的な特徴を持つ男女それぞれのインフォーマントの例を挙げてくださった。まずは女性客のAさん(2003年夏当時31才、3児の母)のケースである。Aさんは大工である夫の事業を事務員として手伝いながら、家庭では妻・母として家事と育児をこなす。彼女は高校卒業後、会社の事務員をしながら夜は地元でホステスのアルバイトをしており、20歳を過ぎた頃、高校の同級生であった現在の夫と恋愛結婚したという。Aさんは第一子誕生後10年ほどは、家事や子育てに追われ自分の時間がとれない日々が続き、自分の衰えた身体や垢抜けないファッションを目にすることで、オンナとしての自信が持てなくなっていったという。また、夫からも性的対象として扱われないようになり、自分も夫を性的な対象としてみることができなくなっていった。そして、周囲の人からも夫の妻、子供の母としてみなされる中、一人の女性としてのアイデンティティを失ったかのように感じるようになったという。30才を超え時間的にも金銭的にもゆとりができたのと時を同じくして、「自分のオンナとしての人生が終わりゆく」危機感を持ち始めたことがAさんをホストクラブ通いに駆り立てたようである。Aさんは、「ホストクラブ通いはオンナを取り戻すための手段だ」と説明する。そして「オンナ」という言葉を「魅力ある一個人として扱われる女性」のことだと定義する。それはAさんが結婚後喪失したと感じる、若くて可愛いというだけで男性から言い寄られもてはやされた自らの過去の記憶に基づいた女性像であり、それを懐かしむものだった。Aさんにとって、このオンナを取り戻すということが、ホストクラブ通いを通じて遂行する自己実現のためのプロジェクトとなったのである。
ホストクラブにおいて、Aさんはホストたちと騒ぎ楽しむ中で一人のオンナとして扱われる喜びを得る。そして、疑似恋愛(疑似とはいえAさんは浮気の存在は否定しない)を通じてトキメキを感じ、オンナとしての自分を意識するようになる。その関係性の中で益々キレイなろうとすることで、サロンやエステ等、他では得られない自分の内側から醸しだされる若々しさやオンナとしての魅力を取り戻す効果を体感したそうだ。さらに、日常生活でも、趣味や活動の幅が広がり、おしゃれや自分の時間を楽しむ一方で、夜遊びへの罪悪感と家族への感謝の気持ちから退屈な家事も気にならなくなる。その結果、明日への活力が生まれ活き活きとした生活を送ることができるようになったと語る。
このようにAさんにとって、ホストクラブ通いの代金はホストクラブでの飲食・サービスに加え、日常生活をより充実したものにするために必要な経費となる。これは、Aさんが「いつまでも若々しく、美しく、輝く」女性であり続けるという理想像を実現するための自己投資と捉えることもできる。こうした当事者の肯定的な解釈に対し、ホストクラブ通いする女性への社会的偏見は依然根強い。Aさんは次のようなロジックでそれを払拭する。他人に迷惑をかけることなく自ら稼いだお金で息抜きをしていること、夫との約束の門限を守り家庭や職場に支障をきたさぬよう努力していること、恋愛相手にプロの男性を選ぶことで家庭崩壊やその他のリスクの回避を図っていること、そして美しく輝く母や妻を家族が喜んでいること等を理由に挙げ、自らの行動を正当化する。
もちろんAさんのケースは夫や家族の理解がある場合だが、そうでないケースもある。惚れ込んだホストとの将来を夢見て莫大なお金を貢いだり、自らセックスワーカーになってホストを金銭的に支える女性など、いわゆる「見返り」を得られない女性も多く存在していることを竹山さんは指摘されていた。
では、男性ホストはどのような「夢」をもち、自己実現像を持っているのだろうか。竹山さんがフィールドワークをしたクラブのホストは、社会的な資源、人脈や学歴など社会で成功するための要素を持ち合わせておらず選択できる職業が極めて少ないケースが多かったという。だが彼らは、女性に恋愛感情を抱かせ、格好良さと夢を女性に提供することによりビジネスで成功し、社会にメッセージを発信していく影響力のある男性、といった理想像を思い描いていたようである。その理想像を目指し、根拠のない自信と自らの頑張りとでホストとして成功しようと日夜努力する。その結果、実際に一握りの人間は成功するが、その背景には膨大な数の成功できないまま低賃金で日々働き続け、性的なサービスを提供するホストが多く存在している。
竹山さんは彼らの姿をBさんの事例と、ホストクラブの仕掛けから説明する。Bさんは2004年当時24歳、難波のホストクラブでNo.1になり、「歌舞伎町でNo.1になればすなわち日本一になれる」という夢を持って大阪から上京したと語るホストである。Bさんによると、彼は高校を中退し前科持ちという経歴から選べる職業が少なく、介護職やバーテンダーなど様々な仕事を転々としていたようである。バーテンダーをしている際、「女の子を何人か連れて、かっこいい服を着て、いい車で乗り付けてくるホスト」を見て、「遊びながら酒が飲めて、金ももらい、有名人にもなれる簡単な仕事」だと思い、ホストになったという。そして、ホストクラブは幸い来るもの拒まず、誰でも受けてくれる職場であったので違和感なく入れたとBさんは語っている。
だが、実際に働いてみると、ホストはイメージしていたような簡単な仕事ではなく、Bさんは仕事中もプライベートの時間も、接客の技術を獲得することに専念することになる。しかしホストになるには、技術だけでなくホストとしてのマインドセットも確立せねばならなかった。Bさんはホストになりたての頃、控えめで女性客に電話番号を聞くことすらできなかったという。そんな入店直後の彼を、自営業を営む50代の客が大金を払い店のNo.1にした。Bさんはある時その客の自宅でキスを迫られるも、それをかわしてしまった。その出来事を店の先輩に話したところ、同情を買うどころか、「この世界にいたらそんなきれいごとを言っていては駄目だ、ちゃんと対処しないといけない」と喝を入れられる。自分の母親の年齢以上の客と性的な関係を持つことを想像だにしていなかったBさんであったが、それを機にホストとして乗り越えるべき壁を認識し、プロ意識をもって対処していくようになる。具体的にはあいさつ代わりのキス、感謝の気持ちを表すキスなどと様々な意味付けをすることで力まずにすむようになり、今まで出来なかったような性的なサービスにも慣れていった。そして複数の上客(業界用語で「太い客」)と性的関係を持ち同棲をするようになる。こうした職場以外での交流も、売上No.1の地位を維持しビジネスで成功するのに必要なことであったと説明する。また、自ら確立したプロ意識から店での正規の労働だけでなく、閉店後の複数客への性的サービスも含めたインフォーマルな労働にも昼夜精を出す。その結果、Bさんの生活は一日24時間、ホストクラブでのNo.1を目指すための労働に占められるようになっていった。
ここで興味深いのは、外部者は、Bさんの様な客に性的サービスを提供しているホストをセックスワーカーであると捉えるだろうが、当事者であるホストはそれを否定するという点だ。自分たちは、客を拒むことなく誰とでも性行為をする男娼やセックスワーカーではなく、あくまでもプロのエンターテイナーでありホストであって性的対象とする女性は自分たちが選んでいる、というような説明をする。そして、選択の理由の中には自分の好みの女性であったというものも含まれるが、多くは自分の目標を達成するためのビジネスとしての戦略だと捉えることによって「枕営業」を正当化し、そのサービスを提供していく。
そして、ホストを性的サービスも含めた24時間労働に駆り立てる背景としては、ホストクラブというステージの巧妙な仕掛けを見逃すことはできないと竹山さんは指摘する。店の表向きの舞台は、あくまでも客が非日常のファンタジーを味わうための煌びやかな舞台である。だが、裏舞台は売り上げを競う戦場であり、そのための仕掛けが多く施されている。清潔で大きな鏡がある女性用トイレに対し、狭く汚い男性トイレには目線の位置にビジネス標語と罰金規定が貼ってある。ビジネス標語には「人はお前の負けを笑っている、途中で辞めたらお前は敗者だ」「人は成功した後についてくる」「売り上げがないなら自分の女を連れてきてでも売り上げろ」といった言葉が並ぶ。ロッカーに向かう狭い通路には売上ランキング表が貼りだされ、指名本数、売上総額の記載から自分の立ち位置とライバルホストの成績、あといくら売りあげればトップランキングに仲間入りできるかが常に可視化されている。月末締めの際にはこの表は数時間ごとに更新され、ホストの競争を煽る起爆剤となっている。このようなステージの様々な仕掛けに促され、ホストは月末の売り上げ競争で勝利をおさめるよう日頃から客に辛苦のともなうサービスも行い、その対価として客も無理をしてでも自分の担当ホストに表舞台でいい格好をさせようと、金を使うような仕組みになっている。
では、このような人間ドラマを一歩退いて見た場合、現代日本社会のどのような姿を映し出しているのだろうか。竹山さんはその背景にある社会の風潮と構造、そしてその底流にある新自由主義的価値観に視点を向ける。
まず、選択の自由、起業家精神、自己実現といった価値観が重要視されるようになり、「勝ち組」「負け組」という階層意識が形成されるようになった日本社会において、将来の目標を実現するよう煽られる社会的風潮があること。そして、日本のバブル経済崩壊後の長引く不況の中、製造業を中心とした右肩上がりの成長期に描かれたような夢や明るい未来が影を潜めた現代に彼らが生きていることが挙げられる。自己実現を煽られるものの具体的な将来像が描けない、そしてサラリーマン中心の企業社会で成功する要素を持ちあわせない男性にとって、ホストクラブはわかりやすい競争原理で自己実現を果たす「夢」を与えてくれる舞台として魅力的に映る。その舞台提供と引き換えに、ホストクラブは彼らから搾取に近い形で労働力を得ていると考えることができる。
男性が個人事業主・起業家として労働に駆り立てられる一方で、女性は消費する主体として消費活動を通じて「自己実現」するよう導かれる。歴史的にロマンチックラブイデオロギーや家父長制家制度の下で女性には性的規範が課せられてきた。とりわけ母親には性的対象ならざる存在として家族への献身が課せられてきた。だが現在、ホストクラブ通いをするAさんのように、結婚後も若々しく性的な存在であり続けたい、オンナとして認識される存在でありたいという女性が多く存在する。これは従来の男性が作りあげてきた女の性というものへの反抗、またはそこからの解放とも捉えることもできる。また、そうした観点からは女性が生きやすい社会になったと肯定的に捉えることもできる。確かに高度消費社会の中で称揚される女性達が自己実現の手段にする婚外恋愛は、日本の近代化における家父長制のもと否定的に概念化されてきた不倫とは区別化されたものであり、新たな倫理観を作り出しているとも考えられる。婚外恋愛・アンチエイジングの言説(恋愛はセルフプロデュース術を身に着ける格好の教材であり、自己承認を取り付け、若返る効果もあり、日常に活力を与えてくれるといったもの)は婚姻後の女性の性を肯定的に捉え直したものと見ることもできる。こうした言説を内面化した女性たちにとって、金さえ払えば理想の恋愛をプロの男性が提供してくれる便利な恋愛市場が、ホストクラブであるといえるだろう。だが別の視点からは、女性は消費する主体として称揚されることで、結婚後も性的な存在として自らを位置づけ、身体を客体化させ、法外なサービスを消費し続けざるをえない存在となることで巧妙に資本制に取り込まれているという見方も否めない、と竹山さんは警告を鳴らす。
さらに、このようなホストクラブを取り巻く人々の労働や消費に関する語りと、1980年代以降、新自由主義改革の下で重要視されてきた価値観や倫理観との共振を竹山さんは指摘する。ホストは性的サービスを客に提供する時もセックスワーカーと差別化を図り、自らの語りの中で主体性を維持する。セックスワーカーは客を選べないが自分たちは性の対象を選んでいるのだと説明し、サラリーマンが他人の下で働かされているのに対し、自分たちは個人事業主として自ら采配を振るのだと強調する。そして一見搾取ともとれる働き方も夢の実現のための手段であると認識している。一方の女性客もこれに似た語りをする。従来の研究者達は女性の身体や性が客体化されることを問題視してきたが、ホストクラブの女性客は、自ら進んで客体化することによりオンナとしての自己価値を高めようとする。そして、そのオンナを武器に社会で活躍していくこと目論む女性もいる。だが、彼ら、彼女らが自らの意思と責任の下行っていると信じる自己実現に向けたプロセスそのものが、ホストクラブでは商品化され新自由主義経済の枠組みの中に納まってしまうのである。
1985年のプラザ合意以降、加工貿易を軸とした製造業中心の社会から、サービス産業を中心とした国内消費に頼る社会経済へと日本は急速に変化した。同時に新自由主義改革の下、より良い将来の構築は国家に依存するのではなく個人個人が自らの将来を思い描き、それぞれの人生選択をし、リスクを負うことも恐れず創造力を活かして自己実現を図ることが求められてきた。男性ホストも女性客もまさにそのような時代の申し子といえる。自己実現のプロセスまでもが資本として新自由主義経済の中に取り込まれかねないようなプロジェクトを、労働者として、消費者として「自由意志」の名において果たそうとしているのがホストクラブを取り巻く人々であると捉えることができるであろう。そのように考えると、この誘惑の舞台はホストクラブという特殊な空間に限られたものではなく、まさにこうした現代の日本社会のあり方そのものがこの誘惑の舞台にほかならないと捉えることもできるのである。
以上が竹山さんに講演していただいた内容である。私個人としては、過剰に消費やリスクのある生き方をもてはやす風潮や本人たちがそれらを美談として語る傾向は、一時期よりはなりをひそめたものの、現在でも決して無くなったわけではないと認識している。そして、本講演で論じられたような構造は日本社会に依然として残存しているだろう。そのような中、フィールドワークに加え、色眼鏡で捉えられがちなテーマと新規性のある手法の選択というリスクを背負いながら、時代背景とフィールドの実態を踏まえ、自らの意思で誠実に研究を遂行する竹山さんからは非常に感銘を受けた。もしかしたら、そのような竹山さんに情動を突き動かされた私も、やはり、誘惑の舞台に上っている一人なのかもしれない。
一橋大学大学院社会学研究科博士課程 荒井悠介
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第35回(2016年 6月17日)
「錯綜する<男らしさ>のポリティクス―プロ・フェミニスト男性運動の可能性と課題」
講師:多賀太さん(関西大学文学部教授)
司会:佐藤文香さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
第35回CGraSS公開レクチャーは、「錯綜する<男らしさ>のポリティクス―プロ・フェミニスト男性運動の可能性と課題」と題し、関西大学教授の多賀太氏にご講演頂いた。多賀氏は教育社会学の視点から日本の男性学をけん引してこられ、近年は日本におけるホワイトリボン・キャンペーンの設立に取り組み、精力的に活動されている。
今回のご講演で主なテーマとなったのは、「男性運動(men’s movement)」である。「男性運動」とは、フェミニズムや女性学の主張を意識しながら、男性たち自身で「男というジェンダー」を意識して展開されてきた社会運動のことであると多賀氏は述べる。つまり「男性運動」の基盤は、フェミニズムにおける「男性は女性に対する『抑圧者』であったり『権力者』であったりする」という主張、また「女性は社会的に作られた『女らしさ』に縛られているのだ」という主張に対する、男性たちからの様々なリアクションであるという。そこには、フェミニズムに反発する男性たち、フェミニズムに納得して自らの在り方を反省・自己変革しようとする男性たち、さらには「自分たちも社会的に作られた『男らしさ』に縛られているのではないか」と思い至り、「男らしさ」から解放されようと考える男性たちなど、様々なフェミニズムに対するリアクションをする男性たちの姿がある。
中でも今回、多賀氏は、フェミニズムに納得し、「女性たちの声を受け入れて、どう男性たちが変わっていけるのか、変わっていくべきなのか」という考えのもと行動する、「プロ・フェミニスト」という立場の可能性と課題について述べられた。「プロ・フェミニスト」とは、フェミニストに親和的な男性たちや、フェミニズムに共感する男性たち、フェミニズムとともに歩もうとする男性たちを指す。しかし多賀氏は、「女性の犠牲によって男性に利益をもたらす社会において、男性が男女平等のために行動することは、自らの利益を失うために行動することを意味する」と述べた上で、以下の問いを立てる。果たして、こうした「プロ・フェミニズム運動」を多数派の男性が行うだろうか。男性が主体的に男女平等の担い手になることが可能だろうか。可能だとすればいかにして可能なのか。そして、彼らを男女平等へと動機づけるものは何なのか。これらの問いに答えるために、多賀氏はこれまでアメリカや日本で展開してきた数々の男性運動と、「ホワイトリボン・キャンペーン」を事例とした「プロ・フェミニズム運動」について紹介され、男性たちを「プロ・フェミニズム運動」へと動員するためにはどうすれば良いのか、ということについて述べられた。
まず、男性運動の布置関係をとらえるために、多賀氏は、アメリカの社会学者であり男性研究者であるMichael Messner(1997)による、「男性の制度的特権」「男らしさのコスト」「男性内の差異と不平等」という3つの視点を紹介された。男性運動は一様ではなく、この3つの視点のそれぞれに敏感であったり無関心であったり様々な立場があるという。それらは「保守派」「メイル・フェミニスト(ラディカル・プロフェミニスト)」「男性の権利派」「マイノリティ派」などのイデオロギー的立場に腑分けされるが、多賀氏は、いずれかの視点に偏るのではなく3つの視点をバランスよく考慮することを、あるべき男性運動の形、つまり「プロ・フェミニスト」のとるべき形として提示する。
日本における男性運動へと視点を移すと、日本における男性運動は1970年代後半から、フェミニズムに対するリアクションとして起こったという。それらの運動は主に、仕事中心であった男性の人生の問い直しや、家事・育児への参加に関する問題意識から発展していった。1980年代になると、男性の性のあり方を問いなおす団体や、「少数派」男性が抱える問題について考える団体が発足する。こうした運動の流れを受けて、1990年代から日本における「メンズリブ」が誕生することになる。多賀氏は、「メンズリブ」はフェミニズムにおけるコンシャスネス・レイジング(個人の悩みを共有することで共通の問題を見出すことにつながり、個人の悩みは個人的なものにとどまるものではなく、社会的な問題なのだという気づきをもたらす処方箋として捉えることができる)の男性版としての性格を強く持っていたと述べる。1991年に関西で「メンズリブ研究会」が発足したのち、1995年には東京でも「メンズリブ東京」が発足、1996年からは男性運動の全国大会が展開されるなど、男性運動の拡大・拡散が進んでいったのが1990年代であった。
しかし、構成員を男性に限定する「メンズリブ」は、フェミニストから「男性だけで集まることは結果的に女性の解放にはつながらないのではないか」、「男性の特権性を見つめ返していないのではないか」という懐疑のまなざしを向けられることになる。だが、多賀氏は、男性の抱える問題を見つめなおしたり、女性の目線を気にせずに、まずは男性の抱える本音をさらけ出してもらったりすることが、大多数の男性たちにジェンダーの問題に気付いてもらうことにつながるのではないかと指摘されていた。一方、男性たちだけで構成された組織内では、これまでの男女における差異にとって代わる形で年齢による差異が生じるなど、新たな問題が散見されることもあったという。2000年代には、メディアや行政がそれまでメンズリブが担ってきた機能を一部代替し始めたことや、「父親世代」と「息子世代」における男性問題の捉え方の違いなどメンズリブに対するスタンスにも内部で様々な差が顕在化していったことなどが影響し、「メンズリブ」は衰退の道を辿ることとなる。
これまでの男性運動の流れについて説明されたのち、多賀氏は現在の男性運動として「ホワイトリボン・キャンペーン」について紹介された。これは、男性が主体となり、女性に対する暴力をなくすことに取り組む世界的な運動である。「ホワイトリボン・キャンペーン」の設立の背景には、1989年、カナダのケベック州にあるモントリオール工科大学において、女性の権利拡張への反対を叫ぶ男性によって引き起こされた虐殺事件がある。この事件を受け、1991年にマイケル・カウフマンらカナダの男性たちが中心となり、「女性への暴力反対」の意思表明として男性たちに白いリボンを身に着けようと呼びかける。こうして誕生したのが「ホワイトリボン・キャンペーン」であった。
多賀氏は、これまで男性の女性に対する暴力の問題については、「自分が責められているようで」積極的には考えることができなかったという。しかし多賀氏は、「暴力を振るわない男性が、暴力を振るう男性の代わりに罪の意識を感じる必要はないんだ。罪悪感からは何も生まれない。だけども、暴力を振るわない男性にも、女性に対する暴力をなくすためにできることがあるんじゃないのか。できることがあるのに何もやっていない。そのことを問い直してほしい」、というマイケル・カウフマンの講演会での言葉に心を打たれ、その後の日本における「ホワイトリボン・キャンペーン」を展開していくことになる。「この活動をすることでどれくらい社会が変わるのか」「男性中心の活動が女性たちの活動の妨げになるのではないか」との懸念は常にあるものの、大多数の男性たちに関心を持ってもらうためにと、この活動は男性主体で運営されている。
上記の問題意識をふまえた上で、最後に「プロ・フェミニズム男性運動」の可能性と課題について述べられた。男性をフェミニズムへの動員に動機づけられる可能性として、「男性の正義感や倫理観」、「身近な女性の受ける不利益について考える」、「男性の受ける『制度的特権』を放棄し、かわりに『男らしさのコスト』から解放されることの利益」、「リスクヘッジとしての男女平等」、「ジェンダー以外の側面における女性との共通性に基づいた男女の共闘」などの方途を提示された。また、研究・啓発における観点から、男性をフェミニズムへ動員するためには、「男らしさのコスト」と同時に「男性の得ている制度的特権」についても意識してもらう必要があると述べられた。また男性といっても一様ではないため、男性内の権力関係についても考慮し、さらに男性が抱いている可能性のある「本来持てるはずのものを持てていないはく奪感」をくみ取っていく必要もある。なおかつ「ホワイトリボン・キャンペーン」のように、女性が抱える問題に対して男性が主体的に、しかし反省的に関わっていくことができるように、男性たちをバランスよく運動に取り込んでいくような方法を提案された。「どうすれば社会が変わるのか」という問いは、「どうすれば男性が実際に変わるのか」という問いに、ひいては「どうすれば女性が実際に変わるのか」という問いもつながるという。研究者には、男性たちに向けて実用的なメッセージを出し、まずは運動に参加してもらうことを目指したアプローチを考えていくことが求められるのではないかと、多賀氏は結論づける。
今回「プロ・フェミニスト男性運動」について述べられた多賀氏のご講演に参加できたことは、男性が参加した形での男女平等の可能性について考える貴重な機会となった。「男性が主体的に男女平等の担い手になるためにどうすれば良いのか」という問いに対する答えは実に明快で、大多数の男性たちにまず興味を持ってもらうためにと、男性の持つ問題意識を逆手に取るように提案される戦略的な方法は、非常に魅力的であった。さらに、男性を中心に形成される「プロ・フェミニスト男性運動」が、いかにして女性たちやフェミニズムと共闘する可能性を有するか、ということについても深く考えさせられる、刺激的な内容であったと感じる。男性の問題が女性の問題へとつながり、女性の問題が男性の問題へとつながる。入口はどうであれ、そのことについて女性・男性ともに真摯に向き合い行動することが、社会全体における男女平等への第一歩となる可能性があるのだという、一つの希望を抱かせてくれたように思う。
一橋大学大学院社会学研究科博士課程 関根里奈子
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第34回(2015年 10月23日)
「何を怖れる―フェミニズムを生きた女たち」
講師:上野千鶴子さん(立命館大学特別招聘教授)
司会:佐藤文香さん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
第34回CGraSS公開レクチャーは、「何を怖れる―フェミニズムを生きた女たち」と題して、1970年代のウーマン・リブ運動に始まるフェミニズムのパイオニアたちを描いた、同タイトルのドキュメンタリー映画(松井久子監督)を鑑賞した。そして上映後には、映画の出演者の一人でもある上野千鶴子氏(立命館大学特別招聘教授)と聴衆とのあいだで議論が交わされた。
映画「何を怖れる―フェミニズムを生きた女たち」は、1970年代のウーマン・リブ運動当時、20~40代であり、現在60~80代になった故人も含め15名のフェミニストたちのインタビューで構成される。ウーマン・リブ運動の思想を生みだしたリーダーたち、女性学を育てた研究者、戦争・軍隊・暴力が女性に何をもたらすかを問い続けてきた研究者と活動家、雑誌・書店・女性センターそれぞれのかたちで女性たちのネットワークを築いてきた活動家…。“年齢を重ね、回顧の季節を迎えた彼女たちが生きてきた歴史と、人生の厚みを、まだ間に合ううちに記録に刻み、次の世代に手渡したい”という松井監督の強い想いがこもった映画であった。
上映後は、フェミニズムに関する意見が取り交わされた。フェミニズムとレズビアンの関係/日本のセックスレスについてどう思うか。フェミニストはなぜ中絶ピルの導入を反対したのか…。男性解放運動はなぜ起こらないのか…。これらの聴衆からの質問に対する上野氏の応答は、「自分の問いを自分のために解く」というフェミニズムが提示してきたメッセージで貫かれていた。女性学もフェミニズムも当事者が自分自身を救済する運動であり、「女であることを愛する女たち」の運動である。社会は当事者が変えようとしない限り何も変わらない…という強いメッセージが込められていた。
さて、この公開レクチャーには、私の母も参加していた。ここで、映画「何を怖れる」に出演したフェミニストたちの同年代であり、異なる視点をもって同時代を生きていた母の感想を紹介したい。
***
私は上野千鶴子さんと同年代です(1947年早生まれ)。ウーマン・リブ運動については、冷ややかに一線を画していました。階級闘争の視点がなければ、また、組織的に運動しなければ、ただの女権拡張闘争ではないかと思っていたのです。
ただし、ウーマン・リブ運動の参加者と同様、学生運動に対する違和感は抱いていました。私は、地方の国立大学教育学部で社会科学を専攻していました。その大学の学生自治会は全国で唯一、反代々木系であり、あるひとつのセクトが執行部を握っていました。そのため、まわりには学生運動をしている人が大勢いました。当時、セクトの様子を見ていると、結婚している男性は経済的にも、育児も全部女性に任せて、“自分は世の中のためにやっているんだから偉いんだ”“女性が支えるのは当たり前だ”という空気がありました。口では平等を言うけれど、実生活は抑圧だ。こんな人たちに革命を起こさせては大変だと私は思っていました。
ジェンダーと接点を持ったのは、40才半ばでした。教員をしていた私は、転勤先の小学校で男女平等教育に出会ったのです。目から鱗が落ちるとはこの事でした。混合名簿、男女わけない並び方、呼び方(全員“さん”づけ)、男女関係なく、混ざった風景。“男として”“女として”を意識する事ないジェンダーフリー教育を目指していました。学校運営も、役職を校長が任命するのではなく、教員の希望や互選や輪番で学級担任、教務主任、生活指導主任等を決めていました。実に民主的で居心地のいい職場でした。
今日の映画を見て、ウーマン・リブ運動に対する誤解が解けた気がします。女であることを否定している訳ではない。男を否定している訳でもない。つまり、人間としての解放を目指していたのだという事。それは、私が学生時代に抱いていた疑問と同じでもあり、40代半ばで出会った職場で目指していたものでもあったのです。
映画の後の議論の中で、日本は変わったのかという話がありましたが、私は大きく変わった面もあると思います。少し長くなりますが、私が「女は損だ」と思わされたエピソードを2つ紹介します。
最初は、高校受験のときでした。県立高校を学区外から受験するのを許された年で受験枠がありました。私は、旧制中学の流れを組むA高校を受けたいと思っていたのですが、中学校の先生から「女だからB高へ行け」と言われ、旧制女学校の流れをくむ事実上女子しか入学していないB高校へ進学しました。私がA高に行かない事で、男子が一人助かり、中学校の進学率も上がったと後で分かりました。この時、初めて「女は損だ」と思いました。
二回目に思い知らされたのは、就職の時でした。中学社会科の募集は皆無。高校は、近隣県では募集がなく、唯一、東京都で募集していました。教員採用試験の合格通知は来ましたが、年度末近くになっても、なかなか採用通知が来ないので、東京都教育委員会に出向いて、理由を聞くと「女の社会科の教員は採用しないよ。高校闘争をどう収拾するんだ。あんたが、国語か英語なら採るよ。」と言われました。この時は、そんなものかと思っていました。まだセクハラという言葉もなかった時代です。仕方がないので、その後、通信教育で、小学校教員の免許を取り、就職しました。
今、この2つの事件が起きれば、明らかに「男女差別」であると言われるでしょう。40~50年という期間を長いとみるか短いとみるかは人それぞれだと思いますが、私はずいぶん変わったと感じています。映画そして上野千鶴子さんのお話し楽しかったです。
***
ちょうど、戦後の女性労働運動をテーマにした博士論文をまとめている最中だった私にとって、この公開レクチャーを通じて、ウーマン・リブ運動のパイオニアたちの経験だけでなく、偶然にも同時代にリブと一線を画しながらも女性解放を考えていた母の経験とを同時に知ることができたのは、非常に刺激的であった。40年後の世代である私は何を受け取るか…。そして、1970年代の女性たちの経験を研究者としてどのように受け止めていくのか。この問いに対する重厚な返答はできないのであるが、ひとつ、確実に言えることは、「自分の問いを自分のために解く」というフェミニズムの提起を心に留めていきたいということである。以前、研究プロジェクトでのフェミニズムのパイオニアたちへのインタビュー調査の中で、「正論を言うと相手は身構えるから、ビジネスの場では正論を言わないのがマナーだ」といういわゆる男性社会の論理に翻弄され「どんな言葉を投げかけたらいいのか…」と悩んでいた私に対して、“言葉でなくとも、生き方が言葉になる”と励ましてくださった方がいらっしゃった。映画に登場する彼女たちの生き様は、まさに強烈なメッセージを私に与えたように思う。松井監督と映画の出演者たちのメッセージを胸に、これからの人生を歩んでいきたいと決意を新たにした。
一橋大学大学院社会学研究科博士課程 跡部千慧
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第33回(2015年 7月15日)
「ヴェールの政治学―ジェンダー・身体・植民地主義―」
講師:サミア・シャラさん(映像作家)/アブデラリ・アジャットさん(パリ西大学准教授)
司会:森千香子さん(一橋大学大学院法学研究科准教授)
参加記
第33回CGraSS公開レクチャーは、「ヴェールの政治学―ジェンダー・身体・植民地主義」と題して、サミア・シャラ監督『マダム・ラ・フランス—私はなぜムスリムになったのか』(2013年、52分、フランス)の上映を行った。そして上映後に、監督である映像作家のシャラ氏と社会学者のアブデラリ・アジャット氏(パリ西大学准教授)と聴衆とのあいだで議論が交わされた。本レクチャーは科研費「EUにおけるレイシズムの新展開と社会構造の比較研究」と 一橋大学国際交流セミナーとの共催でおこなわれた。
現代のフランスにおけるイスラーム教徒女性のヴェールに関する「問題」は、本レクチャーの表題である「ヴェールの政治学」と同題のジョーン・スコットの著書の李孝徳氏による翻訳をはじめ、多くの研究書や映像作品などにより日本でも知られている。しかし、本作「マダム・ラ・フランス」は、これらの先行する「スカーフ問題」を紹介する諸著作と別の視座を与えている。その鍵となるのは「対話」と「旅」である。以下では、映画と上映後の議論を振り返りたい。
本作は二つの対話により構成されている。まず、作家と「マダム・ラ・フランス」、そして作家と彼女の叔母との対話である。
「マダム・ラ・フランス」、フランス語ではフランス(la France)は女性名詞であり、「自由・平等・博愛」というフレーズとともにマリアンヌという女性が共和国の象徴とされている。そのため、移民一世は女性に対する敬称であるマダムをつけ、この国のことをこう呼んだ。第一の対話は、作家がアルジェリアにいる時から始まっていた。だが作家は、独立後のアルジェリアで成長したため、ゾラやユゴーのような文学作品やボーヴォワールに代表されるフェミニズム思想などの影響を受けたものの、彼女にとってフランスは未知の国でもあった。両者の関係は、イスラーム復興運動の台頭をめぐるアルジェリア社会の変化により転換する。イスラーム救国戦線の選挙での勝利と軍のクーデターによる「暗黒の十年」と呼ばれる内戦の勃発により、作家はフランスに亡命する。作家は、彼女と「偉大なる貴婦人」との関係を「付き合い始めて20年、ケンカばかりしてきた」と評している。そしてそれは、多くのアラブ系移民が共有するこの貴婦人との関係である。しかし、亡命アルジェリア女性はフランスに「歓迎」された。ただ、それはフェミニストであり、民主主義者であり、非宗教的であり、反原理主義者であるという条件の下での寛容であった。その寛容の閾を踏み外すとき、つまりムスリムとして在るときに、彼女をはじめとするアラブ系移民は「ケンカ」せざるを得なかった。その過程をつうじて、彼女はアラブ人でありムスリムとなった、と言う。ムスリムで在ることは、非宗教性を要求するフランスにおいて寛容の閾からはみ出す要因となりやすいが、状況は9・11により悪化した。
9・11事件以後、フランスでは原理主義者あるいはテロとの戦いにおける「敵」は、ムスリム一般に敷衍され、特に「スカーフ問題」により事態はより悪化する。「マダム・ラ・フランス」は訳知り顔で、饒舌に、そして一方的に「イスラーム」や「ムスリム」について語る。作家は、マダムとの対話の扉をいったん閉じ、故郷アルジェリアのカビール地方へと第二の対話のため旅に出る。作家の家族のうちで最長老である叔母の昔話——文字を解さない老女は歌により語る——は、貴婦人が誇る歴史、つまり植民地主義の暴力を詳細に作家と私たちに示している。この老女が語ったことは、植民地主義の暴力はアルジェリアの土地を収奪のみならず、アルジェリアの女性へと顕著に働いたということである。植民地主義は内面から破壊する。そして、その最初の対象が女性であった。そしてこの暴力が対象とする女性は、植民地主義の男性性により構築された幻想でもあった。作家はマダム・ラ・フランスに問いかける。「私にとっても、〔あなたが描く植民地の女性像が〕珍妙な世界だと分かる?」と。そして、作家はヴェールをまとう。色とりどりの、そしてさまざまなスタイルのヴェールだ。これらのヴェールの多様性は、私たちに「スカーフ問題」において問題とされるヴェールがいかに実際に女性(とりわけ少女)たちか着用するヴェールと異なるかということだけでなく、「スカーフ問題」が否定しようとする多様性が、まさに植民地主義の暴力が破壊しようとした多様性であるということを私たちに告げている。ヴェールを脱げと植民地主義の暴力は要求し、その要求に応えた女性を統治に利用した。「マダム・ラ・フランス」は、今日再びヴェールの着用を禁ずる。そして、植民地主義以来脈々と引き続いている寛容の閾の内に「移民」とされる人々が在ることを求めている。
作家は、終盤に以下のように語っている。「アルジェリアではスカーフの強制と闘った。フランスでは着用の自由を訴えている。不思議?私には同じ闘い。国家は法で女性の身体を縛る。「女性解放」と言うけれど当事者の声は聞かない」。この語りは、作家のこれまでの闘いを明瞭に示すとともに、「マダム・ラ・フランス」と移民たちの対話を不可能にしている状況を鋭く指摘している。この語りをフランス社会が理解すること、そのことこそがムスリムたちがもとめる「平等」の可能性の条件である。
さて、このように本作を振り返ってみると、本レクチャーは第三の対話と位置づけられる。この対話の意義は、従来日本語圏で理解されてきたように「スカーフ問題」やフランスにおけるムスリムという存在の問題化がフランス社会に固有あるという理解以上の理解が共有されたことである。シャラ、アジャット両氏のさまざまな背景を持つ日本語話者の聴衆に対する熱心な対話的な姿勢により、本レクチャーはこの問題がフランス的な性格だけではなく、普遍性も理解する機会となった。植民地主義の暴力の行使者としての歴史を持ち、かつその歴史を「誇り」に改変する試みが顕在化する日本という国で、シャラ、アジャット両氏がフランスの状況や二人の経験を語ることは意義深いことであった。そして、この対話が成立した条件は、媒介である映画作品への字幕作成者たちの努力とさまざまな観点からなされた質問とその回答を正確にシャラ、アジャット両氏と日本語話者の聴衆に伝えた通訳の高野勢子氏の仕事があったことを最後に指摘したい。
付記:本レクチャーと関連した著作、映画として以下があげられる。
ジョーン・W・スコット『ヴェールの政治学』李孝徳訳、みすず書房、2012年。
ジェローム・オスト監督『スカーフ論争——隠れたレイシズム』(フランス・2004年・75分)
一橋大学大学院社会学研究科博士課程 南波慧
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第32回(2015年 6月24日)
「Narcopolitics, Necropolitics and Femicide/麻薬政治、死政治、女性殺人—メキシコからの教訓—」
講師:メリッサ・ライトさん(ペンシルベニア州立大学地理学科/女性学科教授)
司会:伊藤るりさん(一橋大学大学院社会学研究科教授)
参加記
CGraSS公開レクチャーシリーズ第32回は、「麻薬政治、死政治、そして女性殺人:メキシコからの教訓」というテーマで、ペンシルベニア州立大学地理学科、並びに女性学科教授のメリッサライト先生をお迎えした。フェミニスト、そして地理学・政治経済学の研究者であるライトさんは、米国とメキシコの国境沿いフアレス市における女性に対する暴力と不処罰の実態、そしてそのような不正義と闘う反女性殺人の社会運動について「ウーマン・イン・ブラック」という女性グループの活動を取り上げ、講演を行った。
まずレクチャーの冒頭で、反女性殺人への抗議行動として黒い服に身を包み、ピンク色の十字架を掲げた女性たちがフアレス市の通りを練り歩く写真と共に、問題の背景と運動の状況が示された。フアレス市は、グローバル化の進展とともに工業化が進み、多くの農村地域出身の女性労働者によってその発展が支えられてきたが、1990年代以降から多くの女性や少女らが日常的な暴力や殺人の対象となってきた。このような危機的状況において何の対策も講じてこなかったメキシコ政府に対して懸念の声をあげたのが、女性活動家たちによるローカルな反女性殺人運動「ウーマン・イン・ブラック」である。
本レクチャーで、ライトさんは「女性殺人」、「不処罰」そして「死政治」といった幾つかの重要な概念を提示した。「女性殺人」とは、本来女性が女性であるがゆえに殺される犯罪を意味してきたが、メキシコの反女性殺人の運動で用いられた「femicidio(女性殺人)」というスペイン語の概念は、従来の意味に留まらず、犯罪者が国家によって保護され、処罰が下されないという「不処罰」の意味を含んでいる。これは独裁政権を引き摺り下ろす際にラテンアメリカの社会運動家たちが使った考えであり、現在では、先住民、貧困層、そして女性たちが日常的に直面する国家のテロ、労働搾取、そして政治的腐敗を説明するために広く使われている。
次に「死政治」という概念は、南アフリカの学者アキーユ・ンベンベがフーコーによる生政治の概念を補足修正的に提示したものである。この生政治の議論を出発点としながら、ンベンベはポストコロニアルな文脈における、より政治的に不安定な国家を引き合いに出しながら、政治とは、誰が死に、またその一方で誰が生きるのかという決定を通じて主権が表出する、恒常的な闘争の一形態として理解できると主張した。ライトさんは、本レクチャーを通じて、このンベンベの死政治の概念を念頭におきながら、女性に対する暴力を矮小化し、女性殺人を正当化する政治的戦略とその裏にある死政治による統治に対して、「ウーマン・イン・ブラック」の活動がいかに抵抗してきたかを示そうとした。
まずライトさんは、「ウーマン・イン・ブラック」の女性たちが運動を展開するにあたって直面した困難と矛盾について述べた。女性たちは、抗議行動を通じて女性が公共空間に存在する権利を主張したが、「あばずれ」や「売春婦」を意味する「パブリックな女」すなわち不適格な市民として見做され非難された。そのため「ウーマン・イン・ブラック」の女性たちの多くは、すでに政治家や運動家としての公共のアイデンティティを持っていたにも関わらず、この運動の正当性を高めるために、家族の行方について心配する「家庭的な女性」としての自己表象を選択せざるをえなかった。女性たちは、売春婦を「汚れた女性」であるとする性差別的な認識が広く共有される社会において、その言説的文脈の制約から完全に自由であることはできなかった。
こうした女性たちの戦略は、アルゼンチンにおける「5月広場の母親たち」の運動――軍事独裁政権に対して「私たちの子供はどこ?」という問いを「喪に服す母親たち」として突き付けた――から示唆を受けたものだった。ライトさんは、このような非暴力的な母親としての像を用いることが、メキシコ政府に対して一定の効果を発揮し、ラディカルなものであったと指摘した。なぜなら、子供たちが家に戻るのであれば、抗議行動を行う母親たちもまた家庭へと戻ることになるが、行方不明になった、あるいは殺された女性や少女たちは既に亡くなっていることが明らかであったので、実質上この女性たちは家に戻らない革命戦士として、永遠に抗議を継続するということが含意されていたからである。
ライトさんのもう一つの重要な指摘として、被害者の女性に対するスティグマ化とそれに対する運動側の戦略が挙げられる。政府の役人は、被害者らが昼間は工場労働者、そして夜は売春婦として二重生活を送っていたという疑惑をまき散らすことによって、女性殺人の問題を矮小化しようとしたのである。被害者を「売春婦」と名指すことによって、被害者に責任を転嫁し、その暴力的な死を正当化する戦略はパブリックな女性に対する言説に深く根ざしている。このような女性に対する犯罪の重要性を退けようとする動きに対抗するために、「ウーマン・イン・ブラック」の女性たちは、女性殺人の被害者を「無垢で純真な娘たち」、そして自らをその娘たちを探す「母親たち」であると描写する以外に選択肢は無いと考えた。ライトさんは、被害者を教会へ行くような「無垢で純真な少女」であったという公のレトリックを使わざるを得なかったことは、運動家の女性たちにとって残酷な難問であったが、公共における女性の存在を正当化するためにプライベートなアイデンティティを源泉としたこの戦略は、メキシコ政府に対する国際的な圧力を高めることに成功したと指摘した。
では、このような「ウーマン・イン・ブラック」の運動は、世界における他の運動にどのような教訓をもたらすことができるだろうか。例えば、現在メキシコでは「麻薬戦争」によって多くの命が奪われている。2014年9月に、師範学校で学ぶ若者たちが、政府への全国的な抗議行動に参加しようとした際に、政府のエージェントによって殺され誘拐された。ライトさんは、この学生たちをあたかも麻薬ギャングの一員であったかのように見せようとした政府のやり方は、まさに被害者に責任を転嫁する死政治そのものであり、「パブリックな女性」言説が、麻薬戦争で死ぬ者はみな麻薬組織の関係者であったとする言説と同型であることを指摘した。ここに女性殺人に対する闘いが、他の社会的浄化を意図する死政治に対する闘いにもたらす教訓を見て取ることができるだろう。
レクチャー終了後、会場からは多くの質問や感想が挙げられた。その一つに、現在メキシコの麻薬政治の文脈における政府への抵抗運動に、女性殺人に関する展開との類似が見出されるとするならば、いったいその運動にはどのような矛盾が秘められているのかという問いがあった。ライトさんは、現在の師範学校の学生に対する攻撃を発端とする政府への抵抗運動が、メキシコにおける国の将来を担う「学生たち」への攻撃であることを強調することで、広く世論の支持を受けてきた一方で、被害者を「学生」というフレームで捉えることによって、そこからどのような被害者がこぼれ落ちてしまうのかという問いを立てる必要があると述べた。
本レクチャーは、メキシコでフィールド調査中に大変世話になっていたご家族の息子が殺されるという出来事に遭遇した私個人の経験を振り返る上で貴重な機会であった。19歳という年齢で身を粉にして働いていた青年は、無残に命を絶たれただけでなく、警察から犯罪者の一味であったという嫌疑をかけられていた。結局、家族らは彼の死の真相を追及できないまま泣き寝入りせざるを得なかった。メキシコにはこのようなライトさんが指摘した死政治が蔓延していることを、身に染みて実感する辛く苦い経験であった。このようなメキシコの現実に対する簡単な処方箋は存在しないかもしれないが、ライトさんの講演を拝聴し、死政治に抵抗する社会運動の持つ可能性にわずかな希望を見出した。
一橋大学大学院社会学研究科博士課程 飯尾真貴子
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第31回(2015年 4月24日)
「Slavery, Islam and the Making of Race and Sex in South Africa/南アにおける奴隷制、イスラム、そして人種と性の構築」
講師:ハベバ・バデルーンさん(ペンシルベニア州立大学女性学科准教授、詩人)
司会:中井亜佐子さん(一橋大学大学院言語社会研究科教授)
参加記
第31回CGraSS公開レクチャーは、「南アにおける奴隷制、イスラム、そして人種と性の構築」と題し、ペンシルベニア州立大学准教授のハベバ・バデルーン氏にご講演頂いた。バデルーン氏はケープタウン大学で博士号を取得し、詩人としても活躍されている。今回の講演では、氏のご著作Regarding Muslims: From Slavery to Postapartheid (Wits University Press, 2014) から、南アにおけるムスリムの表象とその歴史的考察を、ケープ植民地支配を支えた奴隷制と性暴力の観点からお話し頂いた。
まず、導入として、現代の南アの大衆文化におけるムスリムのイメージを紹介された。ムスリムの人口に占める割合は2%以下で、マイノリティであるにも関わらず、漫画や大衆的な絵画・料理本の中では、ケープマレーと呼ばれるムスリムの像であふれているという。しかし、一般的に流通しているイメージは、親切なマレーの洗濯女や料理人、そして従属的なマレー男性といった偏ったムスリム像である。このような温和なムスリム像は、17世紀のケープ植民地にイスラム系の人々が連れてこられた奴隷制のトラウマを消去するものであり、南アにおいてムスリムの可視性と不可視性をめぐる緊張関係を表していると氏は指摘する。
そのため、まず、南アにおける奴隷制とムスリムの関係を歴史的にひもとく必要がある。ムスリムは、1658年に初めてケープ植民地に奴隷やオランダ人の使用人として連れてこられた。オランダ東インド会社は先住民の奴隷化を禁止したため、その代わりとして、奴隷労働力を輸入して使用することにした。当初西アフリカから運ばれてきた奴隷は、その後はインド洋のオランダ領地から調達することになる。 そのため、ケープ植民地の奴隷となった人々の過半数は、東アフリカを含むインド洋地域、インド洋のアフリカの島々や南アジア、東南アジアから連行された。彼らはアフリカとアジアの様々な言語を母語に持ったが、マレー語をリンガフランカとして用いた。その後徐々に「マレー」という単語が、ケープ植民地においてムスリム一般を指すものとしてつかわれるようになった。ムスリムを表すようになった「ケープマレー」という言葉は、奴隷の出自の歴史に影響を受けているのである。
次に、バデルーン氏はイスラムと人種の関係について詳述する。先述した奴隷制の歴史は、その後、オランダとイギリスの帝国主義による人種主義的な要請と、アパルトヘイトによって書き換えられることになる。1950年には、国民党政府は人口登録法を通過させ、アパルトヘイトを築くが、この法律の下で、白人・カラード・ネイティブ、という3つの法的な人種分類が作り上げられた。1959年の人口登録法の改定によって、今度は4つの集団が作られる。その際には、白人・カラード・インド人・ネイティブという分類に代わり、カラードの下に、サブカテゴリーとして「ケープマレー」が加えられた。 ムスリムをカラード・インド人・ケープマレーとして人種化することは、植民地の南アフリカで176年間にわたって中心的な社会勢力だった奴隷を、マイノリティに変容させる効果があった。その結果、奴隷制は、南ア史の中で、それぞれの人種集団の例外的な問題だと考えられてきたのだ。このマイノリティとしての位置は、彼らが建国期に重要な役割を果たしたことを歴史からかき消してしまう。奴隷は、南アフリカにおける「最初の近代的な人々」として記憶されるのではなく、エキゾチックで「時間を超越した」存在へと変えられ、ピクチャレスクで美しい過去のものだと考えられるのだ。
その後、バデルーン氏は、南アにおける奴隷制・人種・セックスの関係性を分析する。奴隷を美しくピクチャレスクに描くことの最も重要な問題点の一つは、奴隷制が南アのセクシュアリティと人種の概念に強い意味を与えたことを、忘れ去ってしまう効果がある点であり、さらに、体制的な性暴力という奴隷制の遺産に、意識が全く向かなくなることだと彼女は論じる。
南アのジェンダー状況は、奴隷制と強い関わりがある。1830年までに、ケープ奴隷の2/3は家庭内労働に従事しており、奴隷の主な役割となっていた。加えて、奴隷制がしかれた時期は、常に植民地のジェンダーが不均衡だったため、植民者にとって、奴隷女性と自由黒人女性が結婚相手の候補となった。白人男性にとってマレー女性がエキゾチックで官能的だとみられていたことは、様々なアーカイブから読み取ることが出来るとバデルーン氏は述べる。例えば、ケープの19世紀から20世紀初頭の新聞のアーカイブを読むと、「マレー少女」の魅力が、新聞にしばしば掲載されている。このようなマレー女性の魅力に対する植民者の熱狂やステレオタイプ化は、植民者のマレー女性に対する性的搾取を自然なものにした。
最後に、ケープにおいて、性的搾取が体系的に行われていたことは、都市の名前にもあらわれていると彼女は述べる。オランダ語で「ケープの」という意味を表す、「van den kaap」は、ケープで生まれた奴隷の名字として使われ、異人種間の結婚によって生まれた子どもであることを示唆した。この名前を持つ人々は、しばしば、所有者による奴隷女性のレイプ、または、強制的に売春させられた奴隷女性の妊娠の結果であることがほとんどだった。そのため、この名前は、ケープの奴隷制を特徴付けた性暴力の存在を証明するものとなった。この都市の名前が、オランダ支配下において奴隷女性が経験した性奴隷の歴史を証言するものであり、ケープの奴隷を表象する際の美しく、ピクチャレスクな伝統の根底にある暴力の記憶を呼び覚ますのだとバデルーン氏は結論づける。
私は南アフリカの現代文学に関心があり学んでいるのだが、バデルーン氏の講演に通訳として参加できたことは、中心的に論じられることが少ない南アのイスラム系の人々について詳しく知る貴重な機会となった。また、アパルトヘイトの人種政治において見られた本質主義的人種観の矛盾を、ムスリムの人種的不安定性からも確認でき、刺激的な講演であった。
一橋大学言語社会研究科修士課程 西あゆみ
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第30回(2015年 2月 2日)
「親密な関係にかんする市民権――異国籍同性カップルが日本で子どもを産み育てる場合」
講師:青山薫さん(神戸大学文化学研究科教授)、リル・ウィルス(心理カウンセラー)
司会:宮地尚子さん(一橋大学大学院社会学研究科・教授)
参加記
第30回CGraSS公開レクチャーシリーズは、「親密な関係にかんする市民権――異国籍同性カップルが日本で子どもを産み育てる場合」というテーマで、青山薫さん、Lil Willsさんのお二人にお話しいただいた。青山さんはセクシュアリティの研究者でLilさんはカウンセラーであるが、今回は同性カップルとしてのお二人の経験から親密な関係にかんする市民権についてお話をしていただいた。まさに個人的なことから政治的なことを考える企画であったと思う。
お二人は2009年にイギリスで市民パートナーシップ(Civil Partnership)【※】に登録し、日本で暮らすことになった。異性愛者で同じ国籍の者同士であれば当人の意志で済むかもしれないこの決断にも、法制度が関わってくる。周知の通り日本では同性間の法的な関係が認められずLilさんは青山さんの配偶者としては入国できないため、学生としてビザを取得したそうである。2010年以降、子どもを産み育てるために(生物学的な)「父親」を探すことになった。女同士で子どもを持つには、養子縁組やマッチング・サイトを通じた友情結婚などの手段もあるが、日本で同性カップルが養子縁組を利用することはできず、友情結婚も名前を継ぐ・墓を守るなどの条件があるため、精子提供者を見つけて妊娠出産するという方法をお二人は選択された。青山さんは既に最初の結婚時に産んだお子さんが成人しており、当初「なぜ同性同士でそんな面倒な事をしなければならないのか」と思ったそうである。しかしLilさんが子どもを望んでおり、またイギリス滞在中にゲイ・レズビアンカップルの間で子どもを望むことが「当たり前」となっているのを実感して「随分意識が変わった」とおっしゃっていた。こうした変化は、青山さん個人だけでなく社会の中でも起きているというお話が印象的であった。青山さんは、最初に英国に行った1999年と、市民パートナーシップや同性婚に関する様々な法が整備された現在とでは、同性カップルに対する社会的な眼差しが全く異なるとご指摘された。
お二人のお子さんは2014年に誕生したが、そこに至るまでのプロセスにも様々な制度が関わっていたことを教えていただいた。まず、同性カップルは法的な保証がないため、「父親」との間で契約書を交わしたそうである。そして、これも子どもを持ちたい同性カップルにとっては有益な情報なのだと思うが、お二人は出生後認知ではなく生まれる前に「胎児認知届」を区役所に出した。出生後認知だと裁判所を通らなければならないため、より手続きが煩雑になるそうである。お子さんは英国人のLilさんから生まれたため自動的に英国国籍は取得するが、日本国籍も取得するために日本国籍の父親の認知が必要だった。そうすると、Lilさんも「日本人の配偶者等」というビザで日本国籍の子どもの親として留まることができるとのことである。Lilさんのビザについてもこれまで様々なご苦労をされ、それでもLilさんが英語ネイティブで白人であることで「同性カップルの中でも恵まれた方だと思う」と青山さんはおっしゃっていたが、私も含めて上記のような煩雑な手続きをする必要がない異性愛者はどれほど「恵まれている」のかと考えさせられた。
日本国籍男性と結婚していない外国籍女性の間の子の胎児認知は、2006年にフィリピン女性が裁判を起こして可能になったそうである。お二人はまず、胎児認知する日本国籍の男性を見つけるのにも困難を経験された。その男性が良くても、認知すると戸籍に載るため家族の問題になってしまうからである。また、認知届けを出すためには、子の母が子の父ではない別の男性と法的に婚姻関係に「ない」事を証明しなければならない。結局どのような経緯かは明かされなかったものの胎児認知は受理されたが、これも同性カップルの法的な地位が保証されていれば悩まなくて済む問題だろう。
最後に、青山さんは親密な関係にかんする市民権(Intimate Citizenship)についてご紹介された。これは、「人がどんな親密な関係をもっても社会的に排除されたり不利益を被ったりしない権利」である。青山さんは、ケン・プラマーの『セクシュアル・ストーリーの時代』(桜井厚ほか訳、新曜社、1998)を参照して、市民社会において犯罪者や精神病者とされてきたホモセクシュアルの人々が、同じ境遇の者同士で苦しみや悲しみや怒りを言語化して共有し、自らの「個人的な問題」を市民社会の公の議論に転化させてきた歴史の中で生まれた考えであるとご説明された。この権利に基づいて、パートナーシップや同性婚の制度が近年確立されてきている。こうした制度には批判もあるが、お二人が直面した困難は、まさに同性カップルの関係が制度的に保証されていないために生じたことである。また、異国籍のカップルでもあるために英国と日本における同性カップルの法的な地位の違いも影響を与えている。研究者が個人的な経験をこうしたレクチャーの場で語ることは珍しいことかもしれないが、同じような問題を抱えている人にとっては、情報や感情を共有できる場であり、またそうではない人にとっても普段考えることの少ない(考えずにすんでいる)現状や近年の変化を知ることができる場であったと思う。多くの事を教えていただいた青山さんとLilさんと、素晴らしいレクチャーを企画してくださった関係者の皆様に御礼申し上げたい。
※2005年12月21日施行。16歳以上の同性パートナーが登録可能で、異性夫婦と同等の権利義務があるが「結婚」とは異なる。2013年3月13日施行のMarriage(Same Sex Couple)Actにより、イングランド・ウェールズでは同性婚が可能になった。(スライド資料より)
関東学院大学等非常勤講師 中村江里
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第29回(2014年12月12日)
「いま、男子の性は~私は大学生に何を学ばせようとしたか」
講師:村瀬幸浩さん(日本思春期学会名誉会員、"人間と性"教育研究協議会幹事、季刊『SEXUALITY』副編集長)
司会:坂なつこさん(一橋大学大学院社会学研究科・教授)
参加記
第29回CGraSS公開レクチャー・シリーズは「いま、男子の性は~私は大学生に何を学ばせようとしたか」と題し、本学で26年にわたって共通教育科目の「ヒューマンセクソロジー」を担当された、村瀬幸浩氏にご講演いただいた。
氏が教育者、また研究者として性教育の現場に携わるようになった当時は、産婦人科医を中心に性トラブルに巻き込まれないための知識を教えることが主な目的であった。具体的には、第1に予期しない妊娠を防ぐためのピルやコンドーム等の避妊に関する知識、第2にAIDSなどの性感染症や性病に罹るのを防ぐための知識、第3に性暴力の被害に遭わないための知識である。しかし科学的知識の伝達だけでは学ぶ側がその知識を使えないという問題があった。氏は、それらの知識を無意味なものとしない為には、それを関係性の中で表現しなければならないということに気づく。その際、次の2点が重要になる。第1に関係の質である。男女の関係は平等・対等か、望ましい性関係とは何かということであり、この点はジェンダー研究において深められてきた。第2にセクシュアリティの問題、換言すればセックスに関する教育である。セックスについて語ることは下品なことでは決してなく、人間にとって有意義なことであるという前提を確認した上で、そもそも人間にとってセックスとは何かを問うと、以下3点が挙げられる。まず生殖、そして快楽、最後に支配である。3点目は他の動物にない現象であるとともに、2点目と3点目の違いは紙一重であることを自覚しながら、氏は2点目を徹底的に肯定する立場をとる。つまり、性を人権、アイデンティティ、文化として捉えるのである。
以上のように、氏の性教育の主要テーマは知識→関係性→快楽へと移行して来た。それに伴い、氏は“男性が変われば関係が変わる”という考えの下、“男性の意識改革”に取り組み始めた。いかに男性の意識改革をするのか。それには、体の仕組みを理解することに立ち帰る必要があった。それは一方で、男性が家庭や学校、社会において、自身の性についてまともに学習したり、教育を受けたりすることがほとんどないまま育って(育てられて)きたからであり、他方で、「男子の性」が少ないながらに語られる際は、話題がセクハラやDV、レイプなど攻撃的・暴力的・自己中心的なものに偏っていたからである。前者のように放置された環境の中では、男子はアダルトビデオ(AV)などを通じ手探りで性に関する情報を集め、根拠のない「確信」を積み重ねる結果、更に孤立を深めるという状況があった。また後者のように“性の豊かさ、あたたかさ、コミュニケーション”について聴く・語る・学ぶ機会がほとんどなく、自らの性や性そのものをよきものとして認識しながら育つことが困難な環境では、男性が自分の性や相手の性を大切にしたり、優しく慈しんだりするという柔らかな性関係を紡ぐ力が培われない状況にあった。これらの問題点を克服し、体の仕組みの理解に立ち帰る上で課題に挙がったのが、自らの性を卑しんだり不潔視したりすることから解き放つということである。その具体的実践の1つが射精学習のすすめである。提示された調査結果からは、男性の中には射精を白くて粘っこくて膿みたいで汚いもの、また尿道を通ることを不潔と感じたり、気持ちのいいことも何か卑しく後ろめたく思ってしまい、マスターベーションに自己嫌悪を抱いたりする人がいることがわかった。そうではなく、マスターベーションを“セルフプレジャー”として積極的・肯定的に受け入れることが目指される。つまり、性的欲求を自己管理することで自信をつけ、健康やセルフケアの視点から自身と他者の体や性器への愛着・扱い方を学ぶことで、主体者として性に関わっていく力を培い、性の快楽性への認識を深めることが求められるのである。また、男性の意識改革を進める上での課題として、「男らしさ」という男性ジェンダーが男性自身を苦しめ、縛るという点も挙げられる。具体例の第1が男性の性被害である。いたずらや悪ふざけとして無視・軽視されやすいが、本人にとっては虐待・屈辱であり、自傷や引きこもり、更には加害に向かうこともある深刻な問題である。第2は、AVに代表されるポルノ情報が性意識、性行動、セックス観、女性観を規定し、性が幻想化・記号化されてしまうということである。男性の中にはそのような幻想化・記号化された性に嫌悪感を抱く人もおり、“柔らかい性”の関係づくりの阻害要因となっている。この点に関して男性のメディアリテラシーを育むことが必要であることが強調される。男性ジェンダーをめぐっては、メディアを中心に(元々が「肉食」だったかは別として)「草食化」という現象が語られている。伝統的規範としての「マッチョ」と「草食系男子」という二分化の進行は男性ジェンダーが男性自身を縛るという問題と無関係ではないだろう。最後に、氏は改めて男性への性の学習について問い直し、その目的を4点指摘された。第1に自らの性に対する自信と安心を取り戻し、科学性・関係性・多様性を基軸に据え、男性が女性と関係を紡ぐ力を培う新たな学び、第2に女性の性への理解を深めること、第3に生殖の可能性を持っていることへの自覚を促す、そして第4に多様な性のあり方に対する認識を育むことである。講演後の質疑応答では、「臨床性護士」(*性を人権として捉え、障がい者の性に関わる問題解決を支援する団体ホワイトハンズによって提唱されている)との比較で、売買春や風俗を利用することをどう捉えるか等の質問が出され、活発な意見交換が行われた。
ジェンダー研究の門外漢である自分が今回の講演で印象的だったことは、氏が授業のコメントペーパー等を通じて学生(特に本学では過半数が男性)の声に耳を傾け、研究と教育を相互に密接に結び付けながら活動を進めてきた点である。本学の卒業生としては、珍しく「ヒューセク」を受講していなかった者として、氏のお話を伺う機会に恵まれ大変嬉しく思った。というのも中高一貫の男子校で保健の授業がなく、思春期に性教育を受けたこともなかった。その結果、氏が言及した多くの男子のように、AVや友達との会話などを通じ手探りで性に関する情報を集め、快楽よりはむしろ嫌悪感を抱き、生殖を目的としない性に関する行為の意義に疑問を持ったこともあった。今回のようなお話をもっと早くに聴けたらと思った。尚、今回の講演は、2014年に大修館書店から上梓された『男子の性教育 柔らかな関係づくりのために』をベースに行われた。また2011年2月4日の第13回CGraSS公開レクチャー・シリーズでも「性と愛をめぐる不安と学び-大学生たちの今-」という題でご講演され、参加記が掲載されている。併せて参照されたい。
一橋大学社会学研究科博士課程 熊澤拓也
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第28回「日本占領と性 ―性暴力、売買春から親密な関係まで」(2014年11月21日)
第1レクチャー 「日本占領とジェンダー―米軍・売買春と日本女性たち」
講師:平井和子さん(一橋大学社会学研究科特任講師:近現代女性史・ジェンダー史)
第2レクチャー「パンパンとは誰なのか-キャッチという占領期の性暴力とGIとの親密性」
講師:茶園敏美さん(京都大学学際融合研究推進センターアジア研究教育ユニット(KUASU)研究員:ジェンダー史・他者表象)
司会:佐藤文香さん(一橋大学大学院社会学研究科・准教授)
参加記
11月21日に開催された第28回CGrass公開レクチャーのテーマは「日本占領と性、売買春から親密な関係まで」である。講師には、平井和子さんと茶園敏美さんをお迎えし、それぞれ『日本占領とジェンダーー米軍・売買春と日本女性たち』、『パンパンとは誰なのかーキャッチという占領期の性暴力とGIとの親密性』というタイトルで講演が行われた。ほぼ同時期に、同様の対象について研究を行っているお二人は、異なる視点から占領期における性暴力・売買春・親密な関係性まで幅広い議論を展開した。
まず、平井和子さんの『日本占領とジェンダーー米軍・売買春と日本女性たち』では、①男性神話と慰安施設の設置、②米軍の性政策の変化、③御殿場の事例から見る「パンパン」たちと住民との共生関係、④女性たちの分断を超えた「出会い直し」という四つのテーマで講演がなされた。本論に入る前、平井さんは、橋下大阪市長が2013年5月に発言した軍基地売買春に関する男性神話ー軍人の性的コントロールのため必要・他の国もやっていた・住民を守る防波堤ーを取り上げ、敗戦を迎えた日本において存在した神話が現代にも綿々と引き継がれてしまっている現状を鋭く指摘した。
はじめに、占領軍「慰安施設」の開設についてである。1945年8月18日、内務省警保局長から特殊慰安施設を開設するように全国の知事や警察に無電秘密通牒が出された。この通牒には米軍から守るべきものとして、「日本人の保護」=良家の子女が、米軍に差し出すものとして、「芸妓、公私娼妓、女給、酌婦、常習密売淫犯罪者」が設定されていた。さらに同日、GHQの到着に合わせて、「特殊慰安施設協会(RAA:Recreation and Amusement Association)」が設立された。8月28日のRAA「宣戦式」における声明文では「『昭和のお吉』幾千人かの人柱の上に、狂瀾を阻む防波堤を築き、民族の純潔を百年の彼方に護持培養する」と述べられた。米軍側もそれまでの売春禁圧方針を転換し、「禁欲」から「性病予防策」を採用することで、これら慰安施設の女性に対して健康証明書を発行し、「疑わしい」とおもわれる女性に対しては強制連行(「狩り込み」)と強制検査が行われた。慰安施設にかかわる当時の言説からは、設置した日本の男性側は「兵士には性的慰安が必要」「性の防波堤」「女性たちは自発的に応じてくれた」という男性神話を主張し、米軍側もそれに応じたことがわかる。そして、施設を「受容」した女性側では「こういう汚れた体で国の役に立つなら…」というように内面化された自己卑下とナショナリズムが利用されていた。敗戦国ー戦勝国の男性間での「良好な占領」体制づくりのために、元公娼や下層の女性の身体が取り引きされ利用されたのである。
次に米軍の性政策の変化について説明があった。初期にはMPと日本警察による「狩り込み」やコンタクト・トレーシングなど強制的な性病管理対策が徹底されたが、占領中期になると禁欲政策が展開された。しかし朝鮮戦争期になると、兵士が増加するのにあわせて基地周辺の売買春が激化した。
売買春をおこなう施設が基地周辺地域にできることで、もともと居住していた地域住民と、雇用された「パンパン」との間に複雑な関係性が生まれることとなった。御殿場の事例では、「パンパン」に英語を教える男性や、子ども(「混血児」)を育てる大家の女性、里親を支援する産婦人科医や助産師などの存在があり、「パンパン」との共生が築かれていた。しかしその一方で、関係町村の婦人会や小中学校、青年団などのような「パンパン」に依存しなくてもすむ階層もおり、「パンパン」との緊張関係が語られた。
このように人々の間に引かれた分断線を越えて、女性同士は「出会い直す」ことができるだろうか。日本キリスト教婦人矯風会や女性議員、地域婦人会などの女性団体は、占領軍に対する売買春を禁止する運動を展開したが、この売買春禁止運動において、兵士には性的慰安が必要という男性神話は女性たちにも共有され、兵士に「充て」られる売春女性への視点と軍事組織そのものの問題性を問う視点は欠落していた。
平井さんは最後に、近代家父長制によってジェンダー化された軍事主義のもと、「良家の子女」と「性の防波堤」に二分化された女性たちは、日米男性同盟の「策略」の下、連携する道を築くことができず、その分断線こそが、現在でもRAAの女性たちや狩り込みの被害者たちが軍隊による性暴力の被害者であることをカムアウトできない要因となっていると強調した。
次に『パンパンとは誰なのかーキャッチという占領期の性暴力とGIとの親密性』というテーマで講演された茶園さんは冒頭で、これまで「パンパン」と呼ばれた女性たちがGIに抱いた親密性を有するような気持ちやGIとの間の経験が個人的な問題として封印されることで、彼女たちへの性暴力(性病検診)という問題が看過され、一方的な他者表象が続いているという現在の問題点を指摘した。講演内容は①「パンパン」と呼ばれた女性たちとGIとの関係をコンタクトゾーンという視点で捉え、圧倒的な暴力にさらされながらも彼女たちがどのような交渉を行ったのかに着目する、②GHQ内部の性病対策をめぐる対立に注目し、関係各位の連帯性を分析するという二点に焦点化されて報告された。また各用語の説明として、「コンタクトゾーン」をMary Louise Prattの概念に沿って「植民地という空間において、支配/被支配という非対称的な関係が存在するなかで、異質な文化が互いに出会い、衝突し、格闘する場」、さらに報告においては「占領地日本を、あらゆるひとたちが相互交渉し(コンタクト)対処する場(ゾーン)」と設定すると述べた。この視点によって、異なった立場のおんなたちを支配する者/される者といった一義的な力関係を前提としてみるのではなく、さまざまな立場のおんなたちが互いに交渉し交流しているという豊かな関係性を見出せるのではないかと指摘した。「パンパン」と呼ばれた女性たちは「キャッチという性暴力を被ったおんな」であると同時に、「GIとの親密でかけがえのない時間をも経験していたかもしれない」アンビバレントな存在である。また「GI」も、米軍内部のヒエラルキーを考慮すると、支配者として単一にまとめることはできず、かれらも軍の組織においてはどちらかというと末端に位置する独身男性であった(田中雅一,2011,「コンタクト・ゾーンとしての占領期ニッポン ―『基地の女たち』をめぐって」田中雅一・船山徹編『コンタクト・ゾーンの人文学1』晃洋書房,p.204)。「 パンパン」とGIとの関係性は一枚岩的に捉えられるような単純なものではない。「パンパン」の他者表象についても、「パンパン」を性的にスティグマ化されたステレオタイプによって描く男性・女性知識人の言説が多かったものの、彼女たちとGIとの親密な関係性についてのべる言説も存在したという。
さらに、「パンパン」と呼ばれた人々にたいする認識の違いはGHQ内部にも存在していた。GHQにはSCAPとAFPACという二つの命令系統があり、それぞれに性病問題に対処するPHWとMSという組織があった。PHWでは兵力維持と占領地対策が、MSでは兵力維持と軍事技術がそれぞれの担当分野であった。MSは米兵を相手にするおんなたちを米兵に性病をまきちらす「犯罪者」とみなして警戒していたが、軍人と民間人で構成されていたPHWでは性病を伝染病ととらえているため彼女たちを患者とみなしていたため、双方の意見は対立し合っていた。おんなたちへの強制的な性病管理であるキャッチとコンタクト・トレーシングは結果的に内部の衝突によって収束に至るが、この要因として、占領地のおんなたちが兵士たちの信頼と協力を得ることに成功したためとも考えることができる。
このような性病管理の暴力にあいつつも、同時に米兵との親密性を築いてきた女性たちは、決して過去の問題なのではなく、現在にも引き継がれている。茶園は最後に、「パンパン」だったことを沈黙している状況こそ、暴力が目下継続中であることを示すものであると述べて講演を締めくくった。
質疑応答の時間ではお二人に多くの質問が寄せられ、それぞれに丁寧なコメントをされ、現在にも社会に浸透する男性神話を徹底的に解体すること、「パンパン」と呼ばれた女性たちを一元的ではなく多様な視点から見つめることによって連帯の可能性を開いていくとこが重要であることが、再度強調された。
私自身も、祖母が米兵と関係を持つことで、私の母が産まれた。正式な婚姻届を提出していないため、「祖父」と呼ぶことができるかも分からない男性について、祖母はあまり話したがらない。このように私の祖母のような女性や、母のように米兵との間にうまれた人びとが自ら自身の言葉を語るためには、私を含め、この問題に関心を持つ人々一人一人がこの問題に向き合う姿勢を再度問い直すことが肝要である。連帯を紡ぎたすための問いかけである「語ることができるか?」という、かつてスピヴァクが発した疑問符は本講演のテーマにも通底しており、お二人の提示された論点はこの問題についてさらに考察を進めていくうえで重要な手がかりとなるだろう。
一橋大学社会学研究科博士課程 田口ローレンス吉孝
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第27回「戦時、日中映画のモダニズムとジェンダー」(2014年6月13日)
第1レクチャー 「モダン・ライフ映画が提起するもの-見えない中国・日本社会の二重構造」
講師:宜野座菜央見さん(明治大学・大阪芸術大学兼任講師:近代日本史)
第2レクチャー「越境する映画、引き裂かれた表象-戦時日中映画交渉に見るジェンダー」
講師:晏妮さん(本学社会学研究科客員教授:比較映画史、映像学)
司会:坂元ひろ子さん(一橋大学大学院社会学研究科・特任教授)
ディスカッサント:島村輝さん(フェリス女学院大学文学部教授:日本近代文学)
参加記
第27回CGraSS公開レクチャーは、『戦時、日中映画モダニズムとジェンダー』と題し、宜野座菜央見氏、晏妮氏のお二方による報告と、島村輝氏によるコメントという形式で行われた。
まず、宜野座報告「モダン・ライフ映画が提起するもの」は、中国との戦争がなぜ長期化したのかを、対中国意識の変容という視角から探るという関心のもと、当時の大衆メディアのなかで最も大きな影響をもった映画における中国の不在と、モダン・ライフ映画の隆盛とを一対の現象としてとらえようとするものであった。日本ファシズムが台頭する「暗い谷間」の時代としてイメージされる1930年代は、他方では順調な経済のもとで大衆文化が花開き、満州事変後の「平和と繁栄」を謳歌した時期でもあった。報告では、1930年代をめぐるイメージの分裂を統合すべく、モダン・ライフ映画と戦争との親和性に着目する。すなわち、日本社会の現代性・先端性を描くモダン・ライフ映画は、脱政治化をもたらすとともに、不断に“いま”を更新し続けるという点において資本主義社会に親和的であることが指摘された。
“いま”=「モダン」を追いかける映画製作者は、日本社会の活力や産業化・近代化の進展、あるいはスポーツにおける日本人選手の活躍を描きだす一方で、後進性に結びつくものには無関心であった。「東洋一」の日本という自意識を形成する一助を担ったモダン・ライフ映画には、遅れた存在とみなされた中国への関心や共感が欠如しており、中国との接触が増えるはずの事変後のスクリーンから、中国が消えていくことになった。こうして、正当に振る舞う日本という自己肯定感と、日本に抵抗する遅れた中国という都合のよい“日華親善”の大衆意識が形成されていったという。
また、「映画観客の二重構造」とモダン文化の「でこぼこ」な拡大を示すものとして、大都映画が取り上げられた。土建業者「河合組」の設立者であり、丸山眞男が大正末期の民間右翼の一人としてその名を挙げる河合徳三郎によって設立された大都映画は、評論家や主要映画会社から蔑視されながらも、労働者層の根強い支持を獲得していた。大衆映画としての大都映画の強みは、女優のファッションや男性アクションスターに体現される「表層的な「モダン」」にあったが、他方で、看板女優の琴糸路が演じる劇中の女性は、主体性はあっても、状況に翻弄され、紋切型の悲運な運命に終始するものであったという。
さらに報告の後半では、女性中心のモダン・ライフ映画と男性主役の戦争映画の「協調効果」が指摘された。日中戦争前期にあたる1938-39年は、「統制半分」とも呼ばれ、娯楽や消費を含む日常生活が何とか継続していた。戦場と銃後をつなぐ戦争映画が製作されるものの、それらがスクリーンを占拠することはなく、『愛染かつら』の大ヒットに象徴されるように、モダン・ライフ映画のなかの「平和な日常」が継続していたのである。この銃後のモダン・ライフ映画と戦場を描く戦争映画との「協調関係」、およびそこでのジェンダー役割という主題は、時間の関係で充分に展開されなかったのが残念であった。
続く、晏報告「越境する映画、引き裂かれた表象」は、日本人でありながら戦時下に中国女性を演じ続けた李香蘭(山口淑子)を、ジェンダー的越境現象とみる問題提起ではじまった。満州、上海、華北、日本、台湾などアジアの広大なエリアを移動しながら、中国女性の記号としてのキャラクターを数多く産出した李香蘭は、戦時日本の文化政策によって製作された一つのテクストであり、支配者(男性)に征服された女性と、侵略者に抵抗する女性を演じ分けただけでなく、映画俳優というカテゴリーを越えて演劇や音楽の分野にも進出した。また、上海映画が生んだスターとの競争や、満映の新人女優を牽引する役割をも与えられた李香蘭は、「チャイナドレスの姑娘」という支配側が創り出したチャイナモダンの先端に位置しつつも、最終的には大東亜共栄圏の文化政策が必要とするヒロイン像への変身を要請された。
報告では、李香蘭から、日中両国の女優たちの表象と、彼女たちが出演した日中映画の交渉に関わるテクストへと視点を広げ、モダニズムとジェンダーポリティックスとの融合および拮抗関係、帝国主義とモダニズムとの共犯関係が検証された。言及された映画や女優は多岐にわたったが、中心的に分析されたものの一つが『木蘭従軍』(1939年)である。陳雲裳主演の『木蘭従軍』は、日本支配下におかれる被占領区(淪陥区)、国民党政府統治区(国統区)、日本国内とで、その受容のされ方が大きく異なっていた。上海ではメガヒットを記録し、隠喩的に抗日を呼びかける作品としてマスコミから絶賛されたのみならず、「借古諷今」(昔のことに託けて現在を諷刺する)の時代劇ブームを引き起こした。しかし、重慶で上映された際には、「太陽一出満天下」(太陽がひとたび出れば満遍なく照らす)という歌詞が太陽=日の丸と解釈され、観客らが激昂する騒動が起った。主演した女優の陳雲裳が、上海では抗日の英雄となり、重慶では悪魔と非難されたことから、称賛/非難のいずれの場合においても人々の視線は女優に向けられていたことが指摘された。
また、李香蘭の役割に関しては、1941年頃から母親またはそれに準じる役が多くなっていくものの、母親のイメージが終始投射されることはなかったという。「日中提携」や「共存共栄」、さらには「大東亜共栄圏」が唱えられながら、優生学的な大和血統論の言説が台頭するなかで中国女性を演じ続けた李香蘭には、子どもを産むという役割は与えられなかったのである。李香蘭は、戦時中の観客の植民地的、領土的、男性的な欲望を満たすために、現実と表象との間に位置する遊動的、曖昧な被写体であり、同時に、日中の非対称の交渉においては国家間の衝突と局部地域的な「提携」を具現した女優であった。帝国主義、植民地主義と共犯関係にあるモダニズムは、被占領側にとっても、ソフトな語り口や身振りで協力を回避するための有効な手段となったが、いずれの場合も、女性の身体のみが恰好の対象として突出することになったという。
両報告の後、プロレタリア文学を中心とした日本近代文学を専攻する島村輝氏によるコメントがなされた。宜野座報告に対しては、「15年戦争」という括りのなかにも、小林多喜二の拷問死に象徴されるような何かを決定的に踏み越える一つの転換点として1933年があるが、他方では好景気や文芸復興があり、そうした複雑な様相をみていくことの重要性に気付かされたと述べたうえで、戦争が映画に入り込んでいないと本当にいえるのかという問題提起がなされた。晏報告については、李香蘭が出演した『支那の夜』が、1944年までに三度にわたって中国を慰問した渡辺はま子による歌謡「支那の夜」(1938年)が元となっていることに触れ、戦地慰問における女性の影響や役割の問題が提起された。さらに両報告に対して、東京の女性/上海の女性というモダンガール表象の継続性を指摘し、15年戦争の時期を一括りにできないとはいえ、モダンガールの描かれ方の背後にあるものは何か、映画以外の他のメディアとの関連ではどのように位置づけられるのか、という問題提起があった。
この映画と他メディアとの関係性という問題は、フロアからの質問でも取り上げられ、ポスト事変後のスクリーンにおける中国の不在に対し、文学や美術の分野では中国への関心が高いことから、こうしたメディア間のずれがなぜ生じたのか、受容層の問題などを総合的にみたときにどのように考えられるのかという意見が出された。また、中国表象に対する検閲の問題や、各地のモダン・ライフ映画の相互関係などが議論された。 戦時の日中映画におけるモダニズムとジェンダーの表象を鮮やかに分析された両氏の報告を通じて、テクスト分析のみでは見えてこない、大衆映画を検討することではじめて明らかとなる歴史の断面があること、また対外意識を検討する際、欠くことのできない分析対象の一つとして大衆映画があることに、改めて気づかされた。公開レクチャーの冒頭で司会の坂元ひろ子氏が述べられたように、決して良好とはいえない昨今の日中関係を思うとき、戦時日中映画にみられる自他表象やジェンダー役割を検討する作業は、現在の日本社会における対中国意識や中国をめぐる表象の問題を考えるうえでも重要な意味をもつ。本レクチャーは、そうした意味においても意義深い試みとなったのではないだろうか。
一橋大学社会学研究科特任講師 小野百合子
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第26回 (2014年2月27日)
第1レクチャー <家族と企業社会>をジェンダーでつなぐ
講師:木本喜美子(一橋大学大学院社会学研究科・教授)
司会:佐藤文香さん(一橋大学大学院社会学研究科・准教授)
第2レクチャー 中国近現代思想文化史研究とジェンダー
講師:坂元ひろ子(一橋大学大学院社会学研究科・教授)
司会:貴堂嘉之さん(一橋大学大学院社会学研究科・教授)
参加記
第26回CGraSS 公開レクチャー・シリーズでは本校社会学研究科の木本喜美子先生と坂元ひろ子先生をお迎えし、特別企画として2013年度をもってご退官されるお二方にこれまでの研究や教育における活動やこれからの研究内容などについてご講演いただいた。
まず第1レクチャーでは木本先生に「<家族と企業社会>をジェンダーでつなぐ」というタイトルで、先生が家族と労働の社会学を専門とするに至った経緯や研究の3つのステージについてお話をいただいた。木本先生の経歴を簡単に紹介すると、広島大学総合科学部助手、立命館大学産業社会学部助教授を経て、1990年から一橋大学に着任された。以来、20年以上社会学部、社会学研究科において社会調査、教育などに尽力してこられた。ご専門は家族と労働の社会学だが、これは労働と生活の統一的把握や労働者状態論への問題関心や労働と家庭をつなぐ研究分野に対する課題が出発点にあったそうだ。そして、家族内部だけではなく家族と外部社会のダイナミックな関係性や両者の相互浸透過程を捉えることや労働と生活のリアリティを追究することを課題として研究を進めてこられた。その第1ステージにあるのが家族賃金を媒介として家族と企業社会との関連構造を把握する実証研究である。この研究成果は1995年に刊行された『家族・ジェンダー・企業社会――ジェンダー・アプローチの模索──』(ミネルヴァ書房)にまとめられ、これは翌1996年に社会政策学会奨励賞を受賞された。第2ステージでは労働組織におけるジェンダー関係に関する調査研究をおこない、流通小売業におけるケーススタディをもとに特に女性労働をめぐる職場内の労働関係を実証的に研究しそこにおけるジェンダー規範の構築を明らかにしてこられた。この成果は2003年に『女性労働とマネジメント』(勁草書房)として刊行され、これは“gender and Japanese management”という洋書としても翻訳されている。そして、現在は第3ステージにあり、<家族と女性労働>の史的再構成として歴史的に家族と女性労働をどのようにつなげていくのかという課題に取り組んでおられる。本講演ではこの3つのステージのなかでも第1ステージにおける<家族と企業社会>という着想をどのように得ていったのかということを中心にお話しされた。
先生はまず1980年代の自動車産業(トヨティズム)が国際的に着目されるなかで、トヨタの現場労働者、つまり「豊かな労働者」とされる一方でその引き換えに単調・高密度・不規則・長時間労働の担い手である労働者と家族生活との関係性をどう捉えるかという課題のもとに調査研究を進めてこられた。この時、家族と労働のリアリティを探索すると同時にフェミニズムの文献を講読することによってこの課題にアプローチし、家族と社会を結ぶために理論的、方法論的としてマルクス主義フェミニズムに着目された。当時1980年代の家族をめぐる議論として布施晶子氏の「家族擁護論」(「『兼業主婦』主流の時代」、『講座/現代・女の一生 第四巻 夫婦・家族』、岩波書店、1985年)の立場と水田珠枝氏の「家族解体論」(「家族の過去・現在・未来」、『講座/現代・女の一生 第四巻 夫婦・家族』、岩波書店、1985年)の立場があったが、この二つの議論が対象とする家族とは近代家族論を前提にしていた。近代家族論とは、近代家族、つまり近代に出現した家族で主婦を抱え子供中心主義が重要な課題になっている家族が歴史的な制約性を持っているという議論を指す。これは落合恵美子氏が「<近代家族>の誕生と終焉―歴史社会学の眼」(『現代思想』第13巻6号、1985年、青土社)でいち早く提起し、家族社会学が近代家族を家族の本質として概念化していると指摘したことでも家族社会学に内蔵されているパラダイムの限界を打ち破る視点を提示したと言える。木本先生はこれを評価しつつ、しかしながら、階級差の問題、つまりミドルクラスの家族像を労働者家族がどのように受容したのか、階級・階層を越えて近代家族がどのように波及したのか、このメカニズムが明らかにされていなかったと指摘された。そして、階級とジェンダーを架橋するものとして「家族賃金」という観念に注目するに至ったという。次に、この点について「家族賃金」をめぐるイギリスでの研究を紹介された。
Barrett,M.&Mclntosh,M.(Barrett,M. &Mclntosh,M.,1980, Women’s Oppression Today, Problems in Marxist Feminist Analysis. Verso.)によれば、19世紀のイギリスの工場によって労働時間が短縮され、女性が「保護」という名のもとに稼得現場から排除されたが、このことによって「家族賃金」観念が構築された。これは女性を低賃金職種に周縁化し、他方では労働者階級のなかに専業主婦願望を出現させた。しかし、専業主婦は一時的な不安定なものに過ぎず、結果、「家族賃金」は女性労働に決定的な制約をもたらすことになった。「家族賃金」は主にミドルクラスや労働組合の男性によって推進されたが、「家族賃金」成立の余地は特に労働者階級にとってはきわめて狭く不安定であるとBarrettらは強調した。これを引き継ぐ形でHartmann(Hartmann. H., & Markusen,A.,1980,Contemporary Marxist theory and the practice: A feminist critique, The Review of Radical Political Economics, summer.)とHumphries(Humphries,J.,1981,Protective legislation, the capitalist state and the working class men: The case of the 1842 mines regulation act, Feminist Review,No.7.)によって「家父長制第一主義」対「階級第一主義」とされる論争が起こった。Hartmannは「家族賃金」の導入は組織された男性労働者が決定的な役割を果たしたと強調し、女性労働者との競合を嫌うことから女性を労働市場から排除し主婦にすることで家庭内の男性の権威と特権を確立することが可能になった、つまり家父長制との動機が随伴したと述べる。これに対して、Humphriesは炭鉱労働者に関する歴史的事例を挙げ、まず炭鉱において性と年齢に応じた職務分離がされていたため男女の競合はあり得なかったと指摘し、また家族労働団を組んで働く習慣があったため「家族賃金」は成立していなかったと述べる。そして、家族労働団にとって収入を最大化する方法は娘と妻を就労させることであるにも関わらず、それを犠牲にしてまで女性の地下労働を禁止しようとしたのには次のことがあると問題提起として挙げている。一つは、労働の特殊性である。肉体的に過酷な労働から家事に専念してほしい、したいという願望が男女ともにあったのではないかということ。もう一つは、家事に専念する主婦を擁する家族モデルがすでに存在し、そのミドルクラスの家族像を労働者階級は知っていて自分たちもそれに近づきたいと考え、そして、同時に誰からも指図されない個人生活を実現したいと男女ともに願ったのではないかということ。Humphriesは労働者階級も個人生活を願望すると同時にそのことが結果として性役割分業を自ら家庭のなかに導き入れることになったという歴史の複雑な側面を提示してみせた。木本先生はこのHumphriesの解釈の仕方に共感し、これはミリアム・グラックスマン(M.グラックスマン著、監訳木本喜美子、『「労働」の社会分析―時間・空間・ジェンダー』、法政大学出版局、2014年)の方法としての「二者択一(either-or)」ではなく「両方とも(both-and)」という解釈に通ずるものだと述べた。これらの研究の後、Lewis(Lewis,J.(ed.),1986,Labour and Love: Women’s Experience of Home and Family 1970-1918,Basil Blackwall.)はブルジョア家族モデルの推奨過程として福祉国家の存在を捉え福祉国家のなかに「家族賃金」を埋め込んだ家族像が制度として形成されること、また「家族賃金」が国家レベルで再生産されていくことを指摘した。Seccombe(Seccombe,W.,1986, Patriarchy stabilized:The construction of the male breadwinner wage norm in nineteeth-century Britain, Social History , Vol.12,No.1.)は「家族賃金」は第一次世界大戦までにすべての発達した資本主義国において、労働者階級の理想として信じられるようになったと述べている。ただし、木本先生は日本に関してはもう少し遅い時期と捉えている。そして、最後に日本における「家族賃金」観念の展開について述べた。
木本先生は日本での「家族賃金」は福祉国家の成立過程ではなく雇用慣行(終身雇用、年功賃金、企業内組合)との関係で考察し、これを「家族賃金」の具現化と捉え生活給賃金に着目する。生活給賃金とはライフサイクルの展開にそくして右肩上がりの年功型賃金を指す。この原型は電器産業の労働組合が提起した賃金体系「電産型賃金」(1946年)で、これは戦後ほかの産業にも波及していった。「電産型賃金」は生活保障給(労働者の年齢と家族の人数から算定)、能力給、勤続給の三要素からなり、うち生活保障給が80%を占めた。企業福祉は「生活補助的機能」(戦後まもない時期の社宅や医療などの提供)から「労働者の中産階級化をはかる財産形成策」(1960年代以降の持家制度、持株制度の導入)へと展開する。また、日本型福祉国家体制は企業福祉と公共事業や補助金・各種保護政策をあてにしていたと言える。1970年代初頭以降には大企業は厳しい経済状況のなかで現有社員を解雇しないことが会社への忠誠心を高めていく根拠となり企業社会化が進展していった。したがって、木本先生は日本こそ「家族賃金」が賃金体系としても物質的基盤をともなって強固に定着したと考える。そして、男性はこのもとで「会社人間」へと傾斜し、他方で女性は専業主婦かパート主婦のパターンに収斂していく流れが形成されていったと指摘された。また、ここで重要なのは第二波フェミニズム運動と同時代に企業社会化の進展や「家族賃金」観念の受容、それを基盤とする豊かな生活の推進が行われていたということをきちんとおさえておくことと、1980年代の国家レベルの主婦優遇政策が今なお根強く存在することを念頭におくことであると強調された。
現在の問題としては、年功システムは依然としてありつつも、一方では非正規雇用が拡大し晩婚化・未婚化が進んでいることを挙げ、この背景のもとで日本型の「家族賃金」観念を共有する基盤を変えうる層が形成されつつあることを指摘された。そして、近代家族の縛りから自由な家族像や生活共同体の兆しをどこに見出せるのか、また親密性を担うユニットの問題と、社会的連帯関係によるケアの組織化をどのように考えていくのかという問題が重要になってくると強調された。
最後に、現在、第3ステージとして1960年代の<家族と女性労働>について歴史的に再構成することに取り組んでおり、具体的には結婚後も継続就業してきた織物女工のライフ・ヒストリー調査を実施していることについてお話いただいた。この調査では「良き妻良き母」という「主婦化」規範が社会階層差や地域差を越えてどのように展開したのか、また彼女たちが日々の労働・生活にどのように立ち向かい、この「主婦化」規範をどのように読みかえ自らを価値づけたのか、あるいはこれに反発・抵抗したのかを描き出そうとされている。今後はこれをまとめる段階に入り、「日暮れてなお道遠し」などとおっしゃりながら講演を締めくくられた。しかし、講演後の先生と学生との会話からは「先生、まだ全然日は暮れていない。お昼くらいではないか」といった声が聞こえ、私も全く同様に感じた。先生の今後のますますのご活躍に期待すると同時に、先生が最後に家族の現在について提示された問題について私自身、どのように取り組むことができるか真摯に受け止め向き合っていきたいと考えた。つまり、結婚・出産・育児・介護などを経験したりしないなかで、日本型の「家族賃金」観念や「主婦化」規範、近代家族像に対する変革を担うアクターとしてどのような実践があるのか、この問題には研究に携わる者としてだけでなく身近な問題として関わっていきたい。
第2レクチャーでは坂元ひろ子先生に「中国近現代思想文化史研究とジェンダー」というタイトルでご講演いただいた。坂元先生の経歴を簡単に紹介すると、山口大学教養部哲学分野、ハーバード大学フェアバンクセンター、東京都立大学人文学部中国文学科を経て、1998年から一橋大学に着任された。ご専門は清末・民国期における思想文化史でこれまで多くの成果をご著書にまとめられ、単著では『連鎖する中国近代の“知”』(2009年、研文出版)、『中国民族主義の神話―人種・身体・ジェンダー』(2004年、岩波書店)、共著では『モダンガールと植民地的近代』(2010年、岩波書店)など多数で、編者としてのご著書は40冊以上にもなる。
まず始めに先生がどのような経緯で今日のご専門にたどり着いたのか、それと密接に関わる当時の時代背景についてお話いただいた。1960年代末から1970年代初めには水俣病などの公害病の問題や冷戦構造下で拡大する核兵器の問題、原発への反対運動、ベトナム反戦運動や学生運動があり、中国では文化大革命が起こっていた。当時、大学生だった先生ご自身の周囲でも70年安保反対運動や三里塚空港建設反対闘争、出入国管理法制定阻止運動、狭山差別裁判糾弾闘争、沖縄返還協定をめぐる闘争などが盛んだった。なかでも日本のアジアにおける植民主義の問題と深く関わる入管闘争と被差別部落解放運動である狭山差別裁判闘争に影響を受けたそうだ。後者については先生のご出身が大阪であることから小学・中学・高校時代に経験した在日の同級生たちとの交友関係や近辺の被差別部落の人たちとの関わりが潜在的な問題としてあったと述べられた。これらの問題意識から中国語と朝鮮語を選択するに至り、また中国語を選択したことで今日の専門へと導かれた西順蔵先生(宋学、後に日本での中国近現代思想研究の道を切り開く)およびそのご著書との出会いがあったそうだ。
次に中国史、中国思想の分野での女性の先輩学者である小野和子さんについてのお話をされた。小野さんは1978年に『中国女性史―太平天国から現代まで』(平凡社選書)という先駆的なご著書を発表され、1991年には当時最初の女性教授として京都大学に着任された。小野さんは京大女性教員懇話会の代表を務め、1993年の日本の大学における初めてのセクハラ事件とされる矢野事件でもご活躍され、ご著書に『京大・矢野事件―キャンパス・セクハラ裁判の問うたもの』(1998年、インパクト出版会)がある。この裁判以降、全国の大学でのセクハラ対策の流れが出てくるようになった。
また、専門領域にジェンダー視覚を組み込んでいくことはとても難しい問題だったことについてお話された。大学院では清末の譚嗣同や章炳麟など社会変革を考えた人物の思想をめぐって、気による天地万物一体論形式の世界観をもつ儒教にエーテル理論や仏教の唯識論を組み入れていく様相、また儒教を初期グローバル化の思想や個と共同性、精神と肉体、男女の関係性の再定立という意味での近代思想に組み替えていく様相、そのプロセスにおいて西欧や日本の思想との連鎖の様相を捉えることがテーマだった。その過程で問題視したのは文化差別を本質としていた華夷意識が人種論的社会進化論とともに受容されていくことについてだった。この点に対して中国思想の分野では抵抗ナショナリズムを重視する研究では軽視され、西洋的近代化論の側からは高く評価されるといった二極化した傾向があった。先生はこのこと自体に問題があると考えるようになり、ポスト構造主義理論やポストコロニアル理論から示唆を得たという。歴史学自体のジェンダー化を指摘したジョーン・スコットの考えやバトラーなどにも触発され大きな刺激を受けられた。そして、システムなどへの洞察を深めるために必要な階級や民族、地域といった多くの軸の一つとしてジェンダーを捉えるようになった。それによって文字から遠ざけられていた女性の声を直接取り上げるのが難しいなかで中国思想史分野において「女性思想史」という問題の立て方ができるのか否かという悩みからも解放されたそうだ。
1990年代頃からは中国の学者、例えば李小江、孟悦、戴錦華、チョウ・レイなどによって中国学におけるジェンダー視覚の導入に成果が見られるようになった。一方、日本では坂元先生が中心となり1997年に中国社会文化学会の年次大会シンポジウムの共通テーマに「中国社会・文化とジェンダー」を挙げたが、ジェンダーは時期尚早ではという意見もあったそうだ。2013年にも同学会大会で「中国のジェンダー構造の歴史的変容」というテーマで開催したが、男性性やセクシュアリティなどに関する報告もあり広がりのある研究成果を示すことができた。今後もこのようにジェンダーをテーマとした内容を続けていくべきだと強調された。
最後に、先生のご著書である『中国民族主義の神話―人種・身体・ジェンダー』とそれに関わるものとしてドロシー・コーの論文「明末清初における纏足と文明化過程」(ドロシー・コー、「明末清初における纏足と文明化過程」、アジア女性史国際シンポジウム実行委員会編、『アジア女性史―比較史の試み』、明石書店、1997年)の内容について説明され、纏足とナショナリズムの問題や明末清初から清末、民国期にかけての纏足観の変容などについて話された。続いて、纏足の女性や中国女性が視覚的なメディアおいてどのように表象されたかについて近年の研究内容とともに論じられた。纏足の女性は画報というグラビア・メディアで表象され、女性は結婚制度とともに進化を展望する主体として託され、辛亥革命期には女性は男性に同一化し兵士にすらなった。また主に描かれたのはファッションリーダーとされる妓女だが、彼女たちは新聞などを読み知的進化を遂げた。女工や女子学生も描かれ始め、女工については主体的に集団行動をとる女性として現れる。この女工の存在が二つの大戦期でのモダンガールの登場の展望となっていたと言える。男性によるモダンガールは裸体で描かれ揶揄の対象とされたが、そのなかで女性漫画家である梁白波はそれに抵抗するモダンガールを作り出した。また、上述したモダンガールを描く男性漫画家グループは「救亡漫画」や「抗戦漫画」のなかで全く違う画風で日本兵に凌辱された自国の女性を描いた。つまり、日本の悪を糾弾するために自国の女性が凌辱された場面を強調したのだ。このことは慰安婦にされた女性がその後自分が悪いかのように思ってしまうことと通じる問題があるのではないかと先生は指摘された。今後は1950年代の建国期に同じ漫画家たちがどのような漫画を描いているのかを連続的に見ていき、そうすることでジェンダーが思想文化史にとって重要な視点になりうることを示しうると述べられた。
以上、木本先生、坂元先生による講演からはそれぞれのライフ・ヒストリーを垣間見ることができ非常に刺激的だった。自らの専門にジェンダー視覚を取り入れ先駆的な研究を成し得るには、その背景に多くの闘いあるいは「事件」を乗り越えてこられたのだと知り、改めて今日私たちの目の前にある道に深く感謝した。特に、このお二方はジェンダー社会科学研究センターの代表を務められ、一橋大学の全学的なジェンダー教育プログラムがより豊かなものになるよう尽力してこられた。私は修士課程から本学に進学したが、ジェンダーに関連する科目の豊富さに興奮し、また同じ関心を持つ仲間と議論を重ねられる喜びを日々感じてきた。先生方の懸命な奮闘によって築き上げられたこの素晴らしい環境に重ねて感謝するとともに、ここで学び得てきたものを今度は私たちが自分の置かれている場所において還元していきたいと強く感じた。
一橋大学言語社会研究科博士後期課程(現在は博士研究員) 上村陽子
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第25回 (2014年1月20日)
<サバルタン女性>はいかにして公共圏の担い手になりうるか?―在日朝鮮人女性による夜間中学独立運動から―
講師:徐阿貴さん(お茶の水女子大学ジェンダー研究センター研究協力員)
司会:伊藤るりさん(一橋大学大学院社会学研究科・教授)
参加記
CGraSS公開レクチャーシリーズ第25回(2014年1月20日)は、お茶の水女子大学ジェンダー研究センター研究協力員の徐阿貴さんをお迎えして、「<サバルタン女性>はいかにして公共圏の担い手になりうるか?――在日朝鮮人女性による夜間中学独立運動から――」と題したご報告をいただいた。
本レクチャーでは、2012年に出版され、山川菊栄賞、ことばとジェンダー賞特別賞を受賞した『在日朝鮮人女性による「下位の対抗的な公共圏」の形成』(御茶の水書房)の内容の一部をもとにしたものである。この書籍は徐さんの学位論文の一部をまとめたもので、帯には「命がけや」「ここは、うちらの学校(ウリハッキョ)」という、レクチャーの表題にある夜間中学独立運動のフィールド調査で得られた在日朝鮮人女性の言葉が載せられている。
冒頭では、徐さんがこのような研究に取り組むに至った経緯について語られた。それは、ご自身の出自に深く起因していた。日本で生まれ育ち教育を受けながら、日本国籍ではなく韓国籍をもつ在日朝鮮人三世である徐さんは、自身が育った家族のなかで、一世である祖母らとの使用言語の違いに気をとめた。少しの日本語しか使えない祖母らと、日本語しか話せない徐さんの間には、徐さんが成長し、年齢を重ねるにつれて少しずつ溝ができていった。このような経験をもとに取り組まれた夜間中学独立運動についての研究には、在日朝鮮人女性の言語/日本語/識字の獲得をめぐる深い考察が展開されていた。
夜間中学独立運動とは、1990年代に東大阪市立長栄中学校および太平寺中学校の夜間学級をめぐって展開された夜間中学開設を求める運動である。当時の長栄夜間中学では、在日朝鮮人一世女性をマジョリティとする生徒数が昼間の全日制学級のものを大きく上回ったため、近隣の太平寺中学校に分教室を設置することになった。しかし、狭い教室、暗い運動場、越境通学の禁止など、教育環境が大きく悪化したため生徒らの不満は続出した。結果として、分教室を独立したひとつの夜間中学にし、教育環境を改善することを訴えた運動が始まった。この背景には、地域に根強くある在日朝鮮人への民族差別が存在しており、生徒らである在日朝鮮人女性らはそこに敏感に反応したといえる。その差別のあらわれとして、第1に、夜間中学の生徒らは2校目の夜間中学の設置を市教育委員会に要望しており、それが長年対応されていなかったにもかかわらず、新聞報道をきっかけとする全日制学級の視点に立った要請には早急に対処されたこと、第2に、分教室の環境があまりにも学習に適さず、生徒が日本人である場合に市教育委員会が同じような対応をするとは到底考えられないことが挙げられた。
徐さんの夜間中学独立運動にかんする資料収集、フィールドワーク、生徒当事者であった在日朝鮮人女性へのライフストーリーの収集およびインタビューによって明らかになったのは、この運動を通して、在日朝鮮人女性のサバルタン(下位の対抗的な)公共圏が形成されたことである。具体的には、(1)在日朝鮮人女性という独立し可視化された運動主体が獲得されたこと、(2)運動によって学校の外部と関わる活動拠点が展開されたこと、(3)かのじょらが長年奪われてきた文字(とりわけ日本語の識字)がコミュニケーション手段として主体性の獲得に大きく貢献したことなどが挙げられる。
まず、(1)では、これまでの在日朝鮮人による解放を求める運動では女性の姿が見えにくいものとなっていたことについて述べられた。これまでの民族運動では、在日朝鮮人女性らは民族運動で重要な役割を果たしていたにもかかわらず、それはあくまで男性が主体である運動を支える形であったことが指摘され、このことから、徐さんは在日朝鮮人女性らを「みずからの声を持つことができず、自身を代表できない存在」である「サバルタン女性」と位置づけた。その一方で、夜間中学の設置をめぐる運動では、在日朝鮮人女性らは自分たちの学ぶ権利を自分たちの手で主張していった。夜間中学での学習によって日本語の識字を獲得し、また、生徒会をもとにした集合体の形成によって、自身の体験を自身の言葉で公共の関心事として訴え、可視化してゆくことが可能になった。
(2)については、自主教育機関である「うりそだん」、デイサービス「さらんばん」の設立について言及された。いずれも2001年の独立校化の後に設立されたもので、年齢、世代、背景がさまざまな地域の在日朝鮮人女性が活動する拠点として、現在はNPO法人となっている。「うりそだん」は、高齢ゆえにゆっくりと時間をかけて勉強したい在日朝鮮人女性の学習の場となり、さらんばんは世代をこえた在日朝鮮人女性の交流の場となっていった。これらの設立により、学校のなかだけでなく地域社会での活動が可能となり、他の関西や韓国にある運動団体との連携も展開した。このような機関に集うことは、在日朝鮮人女性が地域社会に対して自らが在日朝鮮人であることをほとんどはじめて言明するに等しく、夜間中学での教師らによるかのじょらの民族名の尊重などとあいまって、在日朝鮮人女性としてのアイデンティティ形成に寄与した。
(3)については、在日朝鮮人女性らが日本語の識字を獲得することで主流社会に対して、そしてお互いのなかで発話することのできる主体になっていくことが明らかにされた。これについては、質疑応答のなかで、「なぜ母語である韓国語の識字ではなく、日本語の識字であることに解放の意味があるのか」という質問があった。徐さんはこれに対して、まず、日本社会での生活言語としての日本語の読み書きができないことにより在日朝鮮人女性らは自尊心を傷つけられてきたが、それが学習によって回復可能となったことを指摘した。そして、在日朝鮮人向けのハングルを学ぶためのテキストは本国の家父長制的なナショナリズムに影響されがちで、朝鮮語の文字を獲得できても民族集団の主流である在日朝鮮人男性の言説にからめとられ、「母」や「妻」規範によらない在日朝鮮人「女性」としての主体性が獲得しにくいことを挙げた。他方で、このことは夜間中学における日本語学習のテキストのイデオロギー性を、運動を通じ形成された女性主体との関係において検討する必要性をも浮かび上がらせている。
民族運動が活発な集団の在日朝鮮人でありながら、その夫、息子など家族内の男性にあくまでも付随した存在として運動にかかわっていた女性たちが、自分の手で自分のために夜間中学独立運動を展開していく姿は、民族差別やジェンダー差別といった一方向からのアプローチだけではとらえることができない問題を提起していた。また、このことは在日朝鮮人女性だけでなく、民族運動を大きく展開するに至っていない在日外国人、そして在日外国人女性全般にも共通する含意のある問題といえるだろう。筆者自身は、ニューカマー生徒が大多数である東京都の夜間中学にて調査を行ってきた。夜間中学の存在を知り、通学を継続し、日本語とその識字を獲得していくことのできる在日外国人らは多いとはいえない(この点については、徐さんも著作のなかで、夜間中学生の在日朝鮮人女性らが、この世代の中では「エリート」のような存在と指摘している)。徐さんの行ったような、夜間中学に通うことができた存在とその周辺の人びとへの深い聞き取りを布石にし、今後、声なきまま日本で暮らしている在日外国人にも光をあてていくことがよりいっそう望まれるだろう。本レクチャーは、多角的に物事をとらえていくこと、複雑にからまった網の目を丁寧にときほぐし、見えなくなっていた事象を可視化していくことの重要性をあらためて考えさせるものであった。
一橋大学大学院社会学研究科修士課程 金海翔
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第24回 (2013年12月9日)
フェミニスト魂を捨てずに、研究者としてのキャリアを追求できるか?―Can One Make an Academic Career and Keep One's Feminist Soul?―
講師:シンシア・エンローさん Prof. Cynthia Enloe(クラーク大学)
司会:佐藤文香さん(一橋大学大学院社会学研究科・准教授)
参加記
第24回CGraSS公開レクチャー・シリーズでは、長年フェミニスト国際政治学者として第一線を走り続けるシンシア・エンロー先生が、フェミニストとしてアカデミズムを生き抜いていく方法について約三時間にもわたって講演してくださった。1989年に出版されたBananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politicsから最新刊のSeriously!: Crashes and Crises As If Women Matteredに至るまで、「個人的なことは政治的なことであり、国際的なこと」というフェミニストの議論を柔軟に受け入れてこなかった男性中心主義的な国際政治学の領域において、エンロー先生は世界各国の事例をもとに、人種・民族・階級・ナショナルアイデンティティが絡み合いながら、軍事目的のために女性らしさ/男性らしさが形成され、利用されてきたことを考察してきた。
壇上に立つと、まずエンロー先生はフェミニストの魂をアカデミズムで維持してゆくためには、教える、ということが重要だと説明した。共存させるのが困難な「フェミニスト」「アカデミア」「キャリア」「ソウル」という四つの要素を同時に持つことにより、フェミニストの学者としてなんとか生きていくことができる。それらの共存を維持する方法が教えることである。本講演では、エンロー先生の母親ハリエットとエンロー先生自身の経験から、フェミニストとして生きるなかで教えることの重要性が述べられた。
まずエンロー先生はハリエットの個人史を語り、歴史的文脈に位置づけながら彼女の人生が社会的に規定されたものだったと説明した上で、ハリエットにとって教えることが生きてゆくための方策だったと解説した。ハリエットは1907年生まれで、幼少期をカリフォルニアで過ごした。カリフォルニアは、白人、ネイテイブ・アメリカン、ラティーノ、アジア系アメリカ人、黒人などの多人種多民族によって構成される社会だったが、所属する人種や階級グループごとにジェンダー規範が異なっていた。ハリエットの所属する白人アッパーミドルクラスの文化では、女性の高等教育も賃労働も一般的に認められていなかった。しかしハリエットの母親が早くに亡くなったために、父親がボストンから教育係として呼んだ女性から、彼女は進歩的な考えを身につけ、ミルズ・カレッジへ進学した。制度としての大学は、社会を変化させる原動力を持つ一方で、現状を維持する力も併せ持っている。その上女子大学であるミルズ・カレッジは、男性しか進学できない他の大学と相互補完関係を形成しながら、ジェンダーイデオロギーを維持させていた。そのため、ミルズ・カレッジで推奨されていた女性の賃労働は女性的な仕事に限定され、卒業後ハリエットは幼児教育の教師になった。妻となった女性は家庭にいるべきとする中産階級のジェンダー規範に背かないよう、数年働いた後、結婚を機に彼女はその仕事を辞めた。しかし何らかの形で教育に携わりたいと考えたハリエットは、女性の社会的活動が認められていた教会で、無給のボランティアの教師として働き続けた。このように大きな歴史的文脈からハリエットの人生を辿ることによって、エンロー先生は「個人的なことは政治的なこと」というフェミニズムの考えを実践しながら、女性の自由が完全に保証されていない社会において、教えることがハリエットにとっていかに重要だったのか示した。
さらにエンロー先生は、自身の経験からフェミニスト研究者にとっての、教えるということの意義を指摘した。エンロー先生は、こうしたハリエットの生き方に対し疑問を持つことなく成長した。しかしエンロー先生は女性の賃労働を要求する1970年代から始まった第二波フェミニズム運動に参加し、さらに大学教授としてのキャリアを積み、今に至る。エンロー先生自身は大学に籍を置き、教えることをその生活の核としてきた。大学でキャリアを積むということは、そこでの昇進の機会が与えられるということであり、そのためには専門家としての知識や技能だけでなく、昇進するための戦術が必要になる。しかしそれらを追求すると、従来フェミニストが批判してきたエリート主義に陥り大学組織内のヒエラルキーに組み込まれる危険性が増す。そうした相反する場で、エンロー先生は教えることを中心に据えることによりフェミニストとして、そして研究者としてのバランスを維持してきた。教えることは、知識を一方的に学生に伝授することではない、むしろ学生とともに学んでゆく過程である。それによって研究者は謙虚な学習者としてあり続けられるし、さらに相互作用的な人間関係を築くことができる。こうしてエンロー先生は、教えることによって「フェミニスト」「アカデミア」「キャリア」「ソウル」を共存させてきたのだ。
約一時間半の講演を終え質疑応答に入ると、講演内容に即してアカデミズムにおけるフェミニズムあるいはフェミニストのポジションについての議論が交わされた。最初に、指導教員がフェミニスト的な関心に基づく研究を、「アカデミックではない」「瑣末なことだ」「実証できない」と批判し、そうした問題を捨象しようとするとき、どうすればいいのかという質問が出された。エンロー先生は米韓関係において韓国の売春婦が果たした役割を考察したキャスリン・ムーンが著書Sex among Alliesを執筆中に、彼女の指導教員がその研究を否定したこと、そしてその後に彼女が史料を元に「実証」してみせたことを例にあげた。この実例に基づき、エンロー先生は緻密な検証に基づく女らしさ・男らしさの分析を通し、ジェンダー的視点が政治学をより豊かなものにすること、そして政治学者が自然だと考えている事例にこそ権力関係が埋め込まれているのだということを、研究を通じて示す重要性を説明した。同時に学内で同じ知的関心を持つ人々とネットワークを作り、個人ではなく集団で意思を表明することも大切だと、エンロー先生は指摘した。学科内でグループを作り、自分のキャリアを追求するだけでなく学科の文化を変え、さらに学科に限定されない学際的な研究センターを設置し、様々な考えを交換してゆくべきだと提案した。次に出た質問は、フェミニストが蓄積した研究業績を、本来意図した形とは違う方法で現実社会の政治目的に利用されることに、いかに抵抗したらいいのか、というものである。その具体例として、第二次世界大戦時のフランスで地元の女性が米兵に性的サービスを提供したことを考察したメアリー・ロバーツの研究(Mary Louise Roberts, What Soldiers Do: Sex and the American GI in World War II France)を参照しながら、現大阪市長の橋下徹がアメリカも女性を性的に搾取したのだから、日本の慰安婦制度だけが批判されるのはおかしいと主張したことが挙げられた。この問題に対し、エンロー先生は各国の戦時政策の比較研究は重要だが、それは政策の酷さを格付けするようなものではあってはならない。それよりも各国固有の戦争責任を提示することの重要性を指摘した。最後にジェンダー研究をしていない研究者と議論するとき、ジェンダー視点からのコメントを「感情的だ」「批判として正当ではない」と言って周縁化されるときはどうすればいいのか、という質問が出された。エンロー先生は他分野の研究者と議論するとき、自分の意見を正当化させるために専門用語を使って議論を制限してはいけないと助言し、それに加えて専門用語を使わないための訓練としても「教えること」が重要だと指摘した。
本講演は、エンロー先生がフェミニスト研究者として生きてきた人生について語る非常に貴重な機会だった。講演中彼女はシンプルかつ力強い言葉で、聴衆にジェンダー研究の意義を説いてくれた。そして聴衆もその意見に元気づけられたのだろう、とても生き生きとした表情で講演を聞いていた。教えることを通し、私たちフェミニストは双方向的に新たな知を得ることができるのだ。だからこそ私たちフェミニスト研究者は孤独ではない、そう実感させてくれる講演だった。
一橋大学大学院社会学研究科博士課程 三好文
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第23回 (2013年11月16日)
「生殖技術—不妊治療と再生医療は社会に何をもたらすのか—」
講師:柘植あづみさん(明治学院大学・教授)
司会:宮地尚子さん(一橋大学大学院社会学研究科・教授)
参加記
CGraSS公開レクチャーシリーズ第23回(2013年11月16日)は、明治学院大学の柘植あづみさんをお迎えして、「生殖技術—不妊治療と再生医療は社会に何をもたらすのか—」が開催されました。司会は、一橋大学教員、精神科医であり文化人類学者の宮地尚子先生でした。講師の柘植先生、司会の宮地先生とも、理系を修めた後に文系へと学問領域を広げ、新たな分野を模索し挑戦し続ける研究者です。お二人は、以前より交流があり、医療と社会を包含する学際的な視点を培った「若き時代」の話から、レクチャーは始まりました。この瑞々しい話が、これから始まる生殖を巡る袋小路のような現実を照らし出す「光」になったことは言うまでもありません。
本編は、2012年に出版された「生殖技術」の内容を基礎に、近年、アメリカでの生殖技術を取り巻く諸問題を調査した事例やそこから導き出された知見をお話しくださいました。
冒頭で、柘植先生の主な研究テーマである「生殖技術」の定義について、「生殖を本人の意志(will)で制御しようとする技術、生殖を本人とは異なる第三者の意志で制御しようとする技術」と解かれました。そこに横たわる問題として「生殖技術」は、主体と客体が固定されず、常に揺れ動く社会事象だということです。当初は、個人が自分自身の生殖を操るための様々な「技術」でした。次第に「技術」を扱う側(医療者)も受ける側も、自分たちの意志通りにはいかず、他方では、技術に対する信頼が欲求を生成し、意味そのものを改編し続けています。また、これらの現象を医療者側は、技術の進歩を正当化するロジックの一部にして活用していく姿も垣間見えます。そして固定されないからこそ、特に直接関与することが多い女性たちは焦りながら技術を追い、医療者(主に医師)は「患者の要望」と「技術の発展」の両輪から技術を追う現実が、「生殖技術」にはあると述べていました。この他にも「生殖技術」には、生殖の量と質を管理する技術、医療技術と民族技術、医療技術とは何か、医療ではない技術とは何か、女性の尊厳、子どもを持つことと社会、制度と法律、市場などとの関係を考察する必要がある、と提示されました。
次にフィールドワークから得た知見から、生殖(補助)技術によって変化した事象について分析・考察です。第一番目に、家族形態の変化から見る「生殖技術」です。具体的には、アメリカに住む、代理出産で「日本人」の子どもを持ち、育てているフランスの男性の事例、オーストラリアに住む、第3者の精子と女性の妹の卵子でその妹に出産してもらった、不妊症が出会いのきっかけであった男女のカップルの事例などが話されました。生殖技術があるから可能になる、家族形態の変化であり、誰が親で、誰が子であるか、というシンプルな問いに大きな視座を与えました。 第二番目は「生殖技術」が作り出した市場と女性たちとの関係です。特に卵子提供は、提供者と被提供者が必要です。その場合に、かなりの経済格差、階級格差、階層格差が存在します。そこに「誕生」するのが受容と供給の不平等性です。この市場の主役である女性たちは、多様な「思い」を持ちながら、卵子を提供し、卵子を受け取っています。提供者の女性は、学費稼ぎの学生、不妊を憐れむ出産経験者の女性、など個人の事情は多様です。そこに、“子どもが持てる技術”として生殖補助技術が横たわることで「欲望」が生産されています。
第三番目は「生殖技術」と保険制度の関係です。日本では医療保険には入っていませんが、諸外国では医療保険に組み込まれている場合が珍しくはありません。このことは、技術を受ける女性たちの経済的な背景など、技術を受ける「動機」にも大きく影響してきます。それにも関わらず、日本では、「生殖技術」の背景にある経済構造や社会保険制度と「生殖技術」を関連させて議論することはあまりありません。むしろ社会問題として検討するよりは、医療の中の一事象として有耶無耶にしてしまう傾向があります。このことは、卵子が人の手から、医療の手へ、市場の手へ、その先へ移行していることを意味し、それらを検証することを困難にさせています。
第四番目は「生殖技術」と再生医療との関係です。「生殖技術」は子どもを持つための技術であるとともに、再生医療にはなくてはならない技術です。とりわけ、卵子は不可欠な「材料」です。つまり、卵子は「不治の病」を治すそうとするための技術を支える「材料」になっているのです。従って、「生殖技術」とは、ある特定の人々だけが関係する問題ではなく、誰もが考えなくてはならない問題であることが理解できます。
最後に、この4つを貫く課題として「卵子を提供する意味とジェンダー」です。卵子は、女性しかないものであるため、神秘的なものとされ、女らしさの象徴としても作用しています。一方で、女性の手を離れることが多いのも、事実です。そして、卵子を提供する女性は“若い・健康・妊娠能力”、卵子を提供される女性は、“経済力・教養・教育能力”を象徴資本としてそれぞれが意味づけると同時に、女性たちに見えない分断をもたらします。そこには、可視化されない卵子提供の多様な意味があります。個人の動議は、自分のため・他人のため・社会のため・国家のためなど個人によって異なります。しかし背後にある「自己尊重感を欲する現代社会」は共通するとし、レクチャーを締めくくりました。
私たちの社会は程度の差はあれ、「技術の進歩」に対して寛容です。もちろん、技術の進歩によって救われた人々も多くいます。一方で、ある集団を救うために、ある集団が何らかの犠牲や奉仕を積極的/消極的、直接的/間接的にせよ、行っていた歴史も見過ごすことはできません。これの代表が、卵子提供に象徴される「生殖技術」です。これに対して立ち止まり、思考停止せずに、考察することができる、学際的な研究が今後ますます求められます。
女性の生物学的特徴が故に起こる問題でもあり、可視化されにくい事象でもあります。今私たちが考えるべきことは、その場の判断や欲望ではなく、少し先を見据えることでありながらも、現在起きている問題を多角的に捉える視座の重要性であることを、学びました。
一橋大学大学院社会学研究科博士課程 永山聡子
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第22回 (2013年10月25日)
「政治的代表制とジェンダー-韓国の女性大統領をめぐって-」
講師:申琪榮さん(お茶の水女子大学大学院准教授)
司会:伊藤るりさん(一橋大学大学院社会学研究科・教授)
参加記
公開レクチャー・シリーズ第22回はお茶の水女子大学大学院准教授の申琪榮氏を迎えて、昨年の韓国大統領選で当選した朴槿恵の選挙戦略とジェンダーについて、「政治的代表制とジェンダー-韓国の女性大統領をめぐって-」というタイトルでお話をいただいた。講師の申琪榮氏は比較政治学を専門とし、もともと女性運動に関心を持ったことから、日本と韓国の家族法改正についての比較調査を出発点とし、最近では女性の政治的代表制/性(本レクチャーのタイトルでは「代表制」と表記されているが、以下では当日のレクチャー内容から「代表性」の表記を用いる。これらはともにrepresentationの訳語であり、その意味するところの複雑性については冒頭で言及された)について関心を寄せてきたとのことである。本レクチャーでは、朴槿恵の略歴、政治的代表性から見た朴槿恵、朴槿恵のジェンダー戦略、朴槿恵の支持層といったトピックからなっていた。
まず、前提として、彼女の政治家としての歩みについて概観し、その中で2012年の大統領選が位置づけられた。朴正煕の娘として1952年に生まれた朴槿恵は、1974年に母親の死を経験し、そこから政治家としての歩みを始める。最初は父である朴正煕大統領(当時)のファースト・レディとして、1979年の父の死後、一旦政治の表舞台から去るものの、1998年からは国会議員として国政に参与した。2007年の大統領選ではハンナラ党予備選で李明博に敗れるものの、敗北を認めたことで「信念のある政治家」としての評価を得て2012年の大統領選に挑むことになった経緯について言及があった。 続いて、2012年の大統領選における朴槿恵の政治的代表性について検討された。政治学において、代表性はstanding forとacting forの二つの視点から説明がなされる。前者は「代理人」としての立場であり、「似ている」ことが求められる。それに対して、後者は「リーダー」としての立場であり、「特別の能力」が求められる。一般的に女性はこの両者においてその「代表性」が不十分であるとされる。前者について言えば、特定の性の代弁者となることはできるが国民全体を代表することはできない、後者について言えば、国家をリードすることができないという主張がその根拠とされる。そうした中で、朴槿恵も女性であるがゆえに「代表性」の観点から「困難」を抱えていた。主に女性からは(女性であるのに)女性を代表できない「名誉男性」であるといった声や、主に男性からは(女性であるから)分断国家である厳しい状況にある国家を率いることはできないといった声が上がっていた。
そうした背景を踏まえて、朴槿恵がどのようにしてそれを「克服」することになったかが次に考察された。朴槿恵の選挙戦略においては政策で大きな差がつかない中、ジェンダーがポイントになっていたことが強調された。そこで取り上げられたのが、朴槿恵の資質、革新性、女性としての規範の三点である。まず、資質については、朴正煕の娘としてこどもの頃から帝王学を学んだことである。第二に、革新性については、女性性が変化と発展、つまり民主主義の「最先端」と評されるアメリカが実現できていない女性大統領を、韓国が実現することの意義である。第三に、女性としての規範については、朴槿恵が「大韓民国と結婚」するという擬態をとることで、国家の妻、国民全体を支える母としての規範を獲得したという点である。これらにより、朴槿恵は「国家のブランド」という地位を手に入れたという考察がなされた。朴槿恵のジェンダー戦略の巧みさは対立候補の安哲秀、文在寅と対比させることで際立つとのことで、それぞれの候補が選挙戦において用いられた写真の分析が行われた。まず、朴槿恵と安哲秀の写真を比較することで、朴槿恵が男性的女性を示しているのに対して、安哲秀が女性的男性をイメージさせていると指摘された。その両者の写真の性格を踏まえた上で、次に文在寅の写真が分析され、それが彼のそれまでのイメージ、つまり彼が補佐した盧武鉉大統領の「妻」的役割というイメージと異なる男性性を強調した写真が用いられたために、そのギャップからジェンダー戦略に失敗したという考察が導き出された。
では、一体誰が朴槿恵を支持したのであろうか。選挙は秘密投票なので正確なデータを取ることは不可能であるが、投票率をみると大統領選全体の投票率では女性が男性を上回った。2011年の韓国大手マスメディアによる調査の結果によると、朴槿恵の支持層は、女性が男性を上回っていた。世代別では年齢が高くなるほど朴槿恵を支持する傾向があることが指摘された。また、職業では主婦層に朴槿恵の支持者が多かったことが強調された。そうした朴槿恵支持層の支持理由としては「女性であること」が最多であり、政策よりも個人に注目が集まったことが指摘されていた。しかし、「女性である」という点で支持を集めながらも、大統領就任後の朴槿恵の政権運営は必ずしも支持者の期待に応えるものではなかった。特に女性閣僚の少なさ(二人)が際立っている。
最後に、ジェンダー・ギャップ指数について言及があり、世界的に政治的分野でのジェンダー・ギャップが顕著であることが指摘された。
その後の質疑応答では、極めて活発な議論がかわされた。提起された論点は多岐にわたるが、主なものとしては以下のトピックがあげられる。まず、韓国政治の特性について考慮する必要があるという指摘である。特に階級、地域差、世代、ソースとなるメディアのバイアスの四点が挙げられた。その中でも世代の問題とメディアの問題は複数の参加者から提起された。また、分析に用いられた写真や「国家と結婚する」という言説など、選挙戦で用いられた戦術・メディアについての異なる解釈の可能性も指摘された。また、より広い視点からは、アジア各国で「建国の父の娘」が国家リーダーとなっている文脈の中での朴槿恵の位置づけ、アングロ・サクソンの政治文化とフランスの政治文化それぞれと対照させた時の韓国の政治文化についてなど多岐にわたる切り口で議論が展開された。
白熱した質疑応答からは、このテーマが2時間ほどのレクチャーでは議論され尽くせない大きな問題であることがうかがえた。本参加記執筆時点で朴槿恵による政権運営は現在進行中であるが、これが歴史となった時点で再検証した際、ジェンダーの観点から果たしてどのような歴史的評価がなされるのか、本レクチャーでの議論から、そうしたことに思いを巡らせた。
日本学術振興会特別研究員 松岡昌和
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第21回 (2013年7月5日)
「「不法移民」収容キャンプ内部のジェンダー構造」
講師:マルク・ベルナルドさん(ルアーブル大学社会学部教授)
司会:森千香子さん(一橋大学法学研究科・准教授)
参加記
第21回公開レクチャーは、2013年7月5日、ルアーブル大学のマルク・ベルナルド社会学部教授をお迎えし、講演会『ジェンダー・アプローチによる外国人収容所の分析』が開催された。ベルナルド氏は、フランスにおける移民の住宅問題、また外国人収容施設に関する社会学的調査研究を精力的に進めるとともに、外国人支援、反人種差別運動の人文科学、社会科学の専門家によるネットワークのTERRAを運営し、提言活動も行っている。
ベルナルド氏は、収容所の分析にジェンダーの視点を反映させる試みの新しさに言及しつつ、戦犯捕虜、移民、強制労働で暗黙裡に「男性」が想定されているように、ジェンダーの影響が伺える点を指摘した。被収容者である男性は、当局にとって脅威とみなされ隔離され、労働力を提供する資源として労働を強いられる一方で、現代の難民のための人道援助キャンプは、脆弱者を受け入れるという意味で女性の空間と捉えられることが多い。このジェンダーの観点を生かすためには、収容所の空間をより広義に捉える必要があると説く。「収容所」という言葉は、全体主義的な絶滅収容所を想起させるが、その制度化は19世紀以前から存在している。本セミナーでベルナルド氏は、収容所の定義として物理的定義とは別に、物理的な条件に限定されない「収容所状態(forme-camp)」という概念を提起した。前者は、刑務所制度の外部にありながら、壁などによる外部からの遮断、監視体制、有刺鉄線、仮設住居などに特徴付けられる空間に、人々を収容して自由を奪い、文化的同化、強制労働、制裁、破滅、殺人等が実施される。後者の「収容所状態」とは、収容所と思えるような状態のことを指し、建物などの物理的な空間がなくても状態としての収容所が存在しているという見解が示された。「収容所状態」は、複数の機能を具備しており、合法性と非合法性の境界が曖昧で、かつ世界を善悪に分類した時に不均衡に見える場合、このような考え方が出てくると言う。本セミナーの講演は、収容所とジェンダーの問題に関する歴史的背景、現代社会における問題群、保護や解放の空間としての収容所の可能性と3つの部分から構成されていた。
最初の歴史的考察では、収容所形態の発展には植民地と奴隷制度が深く関与している点が強調された。収容とジェンダーが交差する現象は、植民地のプランテーション及び人身売買が盛んになった頃に出現した。収容所形態の発展における要因は、プランテーションの黒人女性奴隷の管理における労働搾取と性的搾取、ヨーロッパから植民地に送り込まれた女性、「原住民同化政策」におけるネイティブ女性の管理が特に重要であった。また、プランテーションという空間ではジェンダーを軸とした権力構造があり、女性への暴力が頻発し、植民地の女性は性と人種、植民地支配の秩序を乱す脅威として表象された。
次に現代におけるジェンダーと収容所の問題に関しては、「収容所状態」の観点から女性が経験している特別な構造的問題について言及された。まず、女性に特化された「収容所状態」とは、広義な意味における性的搾取であり、それは性的サービス、人口増加を行うためのものや婚姻関係を持つことをも含んでいる。そして、相手の人種に対する好悪の度合いにより女性に劣等感を抱かせる表象を鑑みながら行われる。例えば、軍隊が設ける売春婦、大衆向けのセックス観光、紛争下での収容所における性的暴行、レイプ、民族浄化、名誉戦争などがある。また、地域紛争における女性の強制的な借り出し、人質、後方部隊としての家事、性的慰安の提供者という女性の軍事化の問題もある。ベルナルド氏はまた、グローバリゼーションの元での移民女性を、マルクスの産業予備軍に倣って、グローバリゼーションにおける快適さ、慰安をもたらす予備軍であると指摘する。グローバルな移民労働市場の拡大は、グローバルエリートに家事労働、性的労働を提供する存在としての移民女性労働者の移動を誘発し、その結果移民女性労働者は、「快適さ、慰安をもたらす予備軍」となっているという。そして、現代における収容所は、移民政策の厳格化、軍事化を推進する中核的措置として、新しい形態の性の生政治の一部を形成している。この「新しい管理制度」は、植民地時代の本土や植民地で見られた西洋人と現地人の間の性関係の延長線上にある。移民女性は、労働問題、人口問題の解決の一端を担うとともに、性的欲望として対象化され、また人種の純粋性を汚す下級女性として忌む者とみなされ、女性、外国人、プロレタリアと幾重ものハンディを負っており、「捕獲政策」のターゲットとなっている。また、国際結婚の下で南側諸国から北側諸国へ嫁ぎに来るという移住形態での女性は、受け入れ国の家族以外の人には会えず、一種の軟禁状態に置かれている。ベルナルド氏は、この厳格化した移民政策の目的は、移民の数を減らすことではなく、市民の中に下層市民を作り、常に強制収容が執行される可能性のもとで彼らの定着の可能性を管理することであると強く主張された。
最後に、収容所自体が移住女性の解放と保護の空間となり得るか否かについて、主に3つの視点から言及された。1つは、ジュネーブ条約で定められた女性の保護規定の効力と問題点である。移民女性の保護は、出身国文化への批判を通じてなされることが多く、結果的にポスト植民地移民の子孫の男性を罪人化し、移民は生物学的脅威であり善良なる社会を脅かすものという認識を生み出している。2つ目は、人道支援目的キャンプにおける女性支援活動の成果で、キャンプ内で提供される教育や労働の機会を通じて、また女性を中心とした家族が構成されることにより、収容の長期化は女性が社会復帰や地位向上を果たすきっかけを提供している。しかし、移住先社会での家父長制の復活や帰還後の生活条件の悪化により、残念ながら女性の保護や解放はキャンプ内に限定されがちである。また、UNHCRやNGOがキャンプの女性を介して運営原則や人道および道徳に関する説明を行うため、女性は被害者、弱者のレッテルを貼られ、その結果彼女らの政治的主張が困難になるという。3つ目は、非正規滞在移住女性による運動であるが、不法移民であるがゆえに組合を作れず、結束が緩く、働く時間の違いによる結集が難しく、メディアの無関心等多くの障害が存在している。しかしながら、21世紀のグローバルなネオリベラリズムの進展と保守の革命という潮流の中、非正規滞在者の運動は中心的存在である。ベルナルド氏は、難民、移住女性の自由を確固としたものにするには、どこに住んでいようと十分で確実な市民権の付与が必須である点を強調し、講演を締めくられた。
質疑応答では、南の人道支援キャンプと北の外国人収容所の保護と抑圧という対立軸や、「収容所状態」の物質化がいかなる現象に当てはまるかという点など、「収容所状態」という概念について質問が多く投げかけられた。ベルナルド氏の説明では、キャンプ自体が保護の機能をある時点で失ったり、権利付与も恣意的で待機が制度化しており、収容所という制度が潜在的、個別経験的で不可視化されたりしている。この概念の非物質化、潜在化、不可視化といった特徴は、国際結婚による移住女性や人身取引に巻き込まれた女性等、「収容所への収容」を経ない多くの搾取の現実を射程にしており、会場の参加者にはジェンダー分析における概念の有効性について希望を抱かせるものであった。
一橋大学大学院社会学研究科博士課程 鈴木美奈子
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第20回(2013年 6月19日)
「フランス・フェミニズムの両義性と隘路」
講師:ナシラ・ゲニフ=スイラマさん(パリ=ノール大学准教授)
司会:伊藤 るりさん(一橋大学社会学研究科・教授)
参加記
CGraSS公開レクチャーシリーズ第20回では、フランス・パリノール/第13大学から社会学者のナシラ・ゲニフ=スイラマ氏を迎え、フランス、ヨーロッパ、さらにはより広い地域で今日重要な問題となりつつある、フェミニズムにおける人種主義とナショナリズム、それに起因した運動の分断とジレンマ、これらを乗り越える連合の可能性について、フランスのケースから豊富な事例をもとにお話を伺った。
フランスには、戦後多くの旧植民地出身者が移住し(ゲニフ=スイラマ氏自身もアルジェリア出身の両親をもつ)、今日までに子どもや孫の世代がフランス市民として定住している。その人々のなかにはイスラム教徒が含まれるが、ゲニフ=スイラマ氏によれば、今日のフランスでは、イスラムが(個人の信仰のレベルを越えた)「浮遊するシニフィアン」(S.ホール)となり、様々なナラティブと結び付けられているという。「内なる他者」、脅威としてのイスラムというナラティブにくわえて、彼女が注目するのは、女性や女性性と関連づけられたイスラムについてのナラティブである。ゲニフ=スイラマ氏はまず、これらのナラティブを、性的分断線のなかに埋め込まれた人種的分断線の問題として位置づけ、これらの分断が、同性愛憎悪とイスラム憎悪を連合させると同時に、フェミニズムやジェンダー平等の闘争に深い打撃を与えているのではないかと提起した。
分断と(憎悪の)連合の事例として、彼女がまず取り上げたのは、2011年7月にノルウェーで起きた銃乱射事件である。この事件の犯人である白人男性A.ブレイヴィクは、公共施設を爆破した後、ウタヤ島での集会に参加していた数十名の左翼活動家の若者たちを殺害した。この事件の予告文書において、彼は、ノルウェーや欧州が「イスラム化」していることを指摘し、それを「女性化」として表現した。このオリエンタリスト的な表現には、過去にナチズムにより動員された、正常/異常なセクシュアリティについてのアーリア主義的レトリックが含まれ、同性愛憎悪と異性愛憎悪が結びつけられているという。
二つ目の事例は、2013年6月にフランスで起きた、左翼活動家でパリ政治学院の学生、C.メリックの殺人事件である。右翼男性との衝突において死亡したこの学生は、同性愛嫌悪主義者への対抗運動とムスリムの女性たち(公共の場でのスカーフ着用禁止が制度化され、スカーフを着用した状態での子どもの送り迎えや課外学校への参加が許されない状況への反対を訴えているムスリム女性たち)の反人種差別運動を同時に支持していた。ゲニフ=スイラマ氏は、「(ムスリム)女性の救済」というナラティブのもとに、イスラムの家父長制を、「普遍主義」的に批判するフェミニストと「白人男性優位」の視点から批判する左右の保守政治家たちの間で、(イスラム憎悪を軸とした)あり得ない連合が見られる点を指摘すると同時に、この若い学生の取り組みに、二つの分断された闘争を結びつける新たな連合の可能性を指摘した。
ここで、フェミニストと保守男性政治家のあり得ない連合の背景として、ゲニフ=スイラマ氏が指摘するのが、フランスのフェミニズムに潜む「ホワイトネス(whiteness)」と「ホワイトニング(whitening)」である。「ホワイトネス」は女性のなかの弱者(権利を求める女性/集団)をディスエンパワーさせる権力を伴い、「ホワイトニング」の手続きにより助長される。「ホワイトニング」の手続きにおいては、第一に、様々な社会現象が(一定の側面から)着目されたり、逆に退けられたりする。この例として、当時IMF専務理事だったドミニク・ストロス=カーンが、ニューヨークのホテルで売買春の容疑で逮捕された事件が挙げられた。この事件にたいして、フランス・フェミニズムが、(相手女性がギニア出身の女性であった点において)植民地主義の文脈を考慮する可能性を排除し、性暴力の問題としてのみ扱う構えを見せたという。
次に、「ホワイトニング」の別の側面として、「パッシング(passing)」が指摘された。これは、褐色・ブラックの肌の女性が、フランス共和主義フェミニズムへの正当な地位を手に入れるために、西洋的価値観と呼ばれるものへの忠誠を示すだけではなく、自らの非白色性をかき消す、ないしは無視することを意味する。例として挙げられたのは、2012年に社会党内閣で若くして大臣職についたナジャット・ヴァロー=ベルカセムの出自の掻き消し/無視、すなわち「パッシング」である。自らが大臣職についたことへの「気後れ」について、「女性であること(女性の「劣等性」を内面化しているための発言)」を理由に挙げる一方で、「非白人」としての出自に言及しない「パッシング」を通して、彼女は「ホワイトニング」の手続きをとっているという。
こうした議論をふまえ、レクチャーの後半部分で、ゲニフ=スイラマ氏は、性的分断線・人種的分断線と憎悪の連合に対抗するものとして「肌の政治(skin politics)」とそれを作動させる「裸体のレジーム(regimes of nudity)」という概念を提示した。その事例に挙げられたのは、ウクライナ生まれの反教会フェミニスト集団フェメンとメキシコ原住民男女の運動である。
フェメンは、国家の政治的弾圧に抵抗するための「乳房露出パフォーマンス」で知られる。彼女たちによる裸体での政治的パフォーマンス、しかも(授乳の表象と結びついて)処女性や国家への奉仕といった意味合いを暗示する乳房を露出し、そこに政治的なメッセージを書くというやり方は、(女性の性を商品化する)ネオリベラルかつ(女性に処女性や奉仕を求める)家父長的な権力への全面戦争として捉えられるという。
他方で、メキシコ先住民男女の運動の事例は、同じ「身体の政治」でも、異なる「裸体のレジーム」のあり方を示している。この事例は、自分たちの土地を強制的に退去させられた男女が、メキシコシティの中心部で裸体でのデモを行ったというものだが、先住民男女の裸体は「無防備で、脆い」ものとして示され、「あたかも潜在的な暴力を招き入れるような裸体のレジーム」であるという。かれらはこのデモにより、土地を取り戻すことに成功した。
ゲニフ=スイラマ氏によれば、両者の事例を考える場合に、どの主体が、どのような目的のために、どのように身体をいかすのかを考える必要があるという。フェメンによる「裸体のレジーム」は、ヨーロッパからブラジル、さらにアラブ世界へと輸出されているが、フェミニストによる「裸体のレジーム」がどれほどの/どのようなインパクトを持つのかという点について、ポルノグラフィや商品化されたエロスとの関わり、人種主義・ホワイトネスとの関わりで考えていく必要があるということだった。
結論としては、分断の政治から抜け出す道を「サブ/オルタナティブな連合」として位置づけ、考えていく必要性が提起された。そのためには、様々な問題を名付け直し(ホワイトニングなどの表現は彼女独自の名付け直しの一例だろう)、様々な分断戦を撹乱していくことが求められるという。
長時間に及んだレクチャーのあと、フロアからはいくつもの質問(日本における在日の運動の文脈や、オランダにおける極右の台頭などの文脈との関わりにおいて「サブ/オルタナティブな連合の可能性」についてより詳しく聞きたいという声、フェメンの運動と人種主義の関わりについての問い、スカーフ禁止法のインパクトについての問い)があがった。
フランスで留学生として彼女の指導を受け、彼女と身近に接している私としては、活き活きと質問に答えるゲニフ=スイラマ氏を前にして、この「分断から連合へ」という議論を、彼女自身の認識論的闘争に重ねて見た。アルジェリアからの移民の子どもとして社会学者になり、「エスニシティ」という講義科目を大学で設置することすら難しい、共和主義的保守のフランス学術界において、「人種」の問題を主要な研究テーマとし、しかもフェミニズムやLGBT運動のなかの人種主義を告発することは、なかなか精神的なタフさを強いられる。さらに彼女は、他の教授たちから「テーマが『繊細(sensible)』すぎる(つまり、政治的に挑発的である)」という理由で断られた院生たちを進んで受け入れている。扱うテーマも、学生も「パッシング」せずに全面的に闘うことを選ぶ彼女が、フランスからイギリスやアメリカ、そして中国や日本にまで好んで講演に出かけていこうとするのも、彼女自身が「分断から連合へ」の実践を行う意味があるのではないだろうか、と考えさせられた。
パリ=ノール大学、一橋大学大学院社会学研究科博士課程 田邊佳美
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第19回 (2013年1月18日)
「金融化された資本主義と新たな収奪の形態――横奪=嵌取dispossessionによる蓄積とジェンダー」
講師:足立眞理子さん(お茶の水女子大学大学院教授/ジェンダー研究センター長)
司会:伊藤 るりさん(一橋大学社会学研究科・教授)
参加記
シリーズ第19回となるレクチャーは、グローバル化とジェンダーの議論の中で不足している部分について、政治経済学だけでない視点からも議論を活性化させたい、という足立眞理子さんの熱いことばから始まった。グローバル化のジェンダー分析においては、生産領域、そして再生産領域に関する議論がなされてきたが、「金融領域のグローバル化とジェンダーの問題」は十分に問われてこなかった(Diane Elson 2012)。足立さんによれば、生産、再生産、金融の諸領域の問題を結合させていく必要があるが、特に金融領域については、資本の蓄積とジェンダーに関わる「dispossession収奪(※)」の新たな形態を捉えることが、現代グローバル資本主義を捉えるうえでのジェンダー研究の課題なのである。
「ディスポゼッションによる蓄積」はデヴィッド・ハーヴェイの用語である。ハーヴェイはローザ・ルクセンブルグが示した、再生産の問題(非資本主義的社会関係と特定の社会層に依拠してのみ資本主義そのものが再生産される)と二重の蓄積過程(搾取と収奪の同時並行的継続によって資本主義的蓄積が起きている)についての理論を評価しながら、「ディスポゼッションによる蓄積」概念を現代グローバル資本主義理解のために用いる。足立さんは、ハーヴェイのローザ・ルクセンブルグに対する評価については、ハーヴェイが、原始的蓄積過程の継続と資本主義の外部の必要性を評価しつつ、ローザ・ルクセンブルグの過少消費説恐慌理解に疑問を投げかけるという点で、概ね妥当とみなす。しかし、彼が同時に示した、現代資本主義における恐慌の理解(資本の過剰蓄積)では、90年代以降のアメリカ金融自由化の中で起きた収奪の形態に、的が絞れてこないことを指摘する。特に、2008年のサブプライム危機以降に焦点を当てながら資本主義の性格を考える際に、新たな収奪による蓄積について、金融化された資本主義の仕組みについてはより緻密な議論が必要だということだ。
そこで足立さんはアメリカでの予備調査に基づく、地域信用組合の仕組みの解説を通して、金融化された資本主義とは、商業信用―銀行信用―中央銀行というこれまでの信用機構論の意味の変化、あるいはその機構生成そのものの問題として理解することが重要であると解説する。新たなディスポゼッションは、自由/不自由賃労働の収奪の問題を越え、ある種の自発性を伴いながら債権―債務関係への巻き込みのシステムの中で起きているのである。シャドウ・バンキング・システムの中では、個人のクレジットリスクのスコアは、過去の「利子つき返済」の実績にのみ左右される。例えば、ある女性が住宅ローンを組むのに、正規雇用者か否かは関係ない。しかし同時に、一度でも返済に失敗すれば、他の消費者クレジット支払いの利率も連動して上がり、全てを個人が負うはめになる。サブプライムローン以降のこうしたシステムの中で、銀行信用の機能は本来の信用をモニタリングするという形から、信用を販売する側に転じた。つまり、証券化商品の発行体が間に複雑に挟まったことで、銀行は住宅ローンの借り手の債権を、証券発行者へと売り渡し、資金を調達するという機能を持つようになった。また、社会的な属性に縛られることなく経済活動・構造に参加し、そして収奪されるという過程と結果にはフェミニスト・イデオロギー上の問題も発生している。
特に、「自営」という形態で働く者(=正規の雇用関係の外部で働く者)が、グローバル資本主義の最大のターゲットとなり、債務奴隷に陥るというケースが顕著であり、まさにここに、新しい形の収奪があると足立さんは注目する。具体的な例として、アメリカにおけるエクアドル出身の家事労働者女性のケースが紹介される。彼女がサブプライム危機後にショートセール(任意売却)で購入した家は、その後も大幅に価値が下がり続けているのだが、「自分が所有した(させられた)」という事実を与えられることによって、彼女は利子を払い続け、収奪されているのである。足立さんによれば、「所有する/させられる」、すなわち「私的所有者とであるとみなされる身体」ということから派生する収奪のありかたは、厳密な意味での銀行の信用機能の変化とともにしか理解できない。これが金融化された資本主義における新しい収奪の形態だが、この関係はまだ十分に解明されておらず、今後ジェンダー分析の視点から、議論する必要性がある。たとえば、従来のジェンダー論では、所有からの排除/包摂が問題となるが、今浮かび上がってきているのは、まさに境界線を飛び越えて巻き込みが起きるとき、「あなたは今や所有していると名指される」ことから生じる。「何を?」と「主体」は答えてしまっている、これこそが問題なのだとレクチャーは締めくくられた。
質疑応答は、収奪される資本主義を社会、個人、貨幣のどの水準から切り取るべきなのか、資本の蓄積形態はどう変化したのか、所有していると思わされる新しい身体とは誰か、という疑問をオーディエンスと足立さんとで解きほぐしていくような作業であった。金融化されたグローバルな資本主義による搾取の実態と、その実態を理解するための概念と理論についてはいまだ手探りの段階であるため、ディスカッションにはすれ違いもあったが、何かが起きていてそこにジェンダー分析が必要である、という確信は共有されていたといえる。
限られた時間ではあったが、わたしは重大な議論の入り口を覗くことができたと感じた。帰途の道すがら、ふと、何年も顔を見ていない親戚を保証人として返済を誓約した「奨学金」という名の学生ローンを、自分がウン百万と抱えていることを思い出した。自分が新たなディスポゼッションからそう遠くない位置にいるような気がしたとき、今回のレクチャーの重みがずしっと増したのである。ディスポゼッションに抗う可能性についての議論も期待される。
Elson, Diane. “Finance, production and reproduction in the context of globalization and economic crisis,” ジェンダー研究 : お茶の水女子大学ジェンダー研究センター年報15 2012. 3: 3-12.
※“dispossession” の訳語については、「横奪」、「嵌取」も検討されているが、ここではレクチャー中に口頭で最も使われていた「収奪」を用いた。
一橋大学大学院社会学研究科博士課程 工藤晴子
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第18回 (2012年12月14日)
「外国籍女性たちの3・11『以前・以後』と改定入管法」
講師:鄭暎惠さん(大妻女子大学大学院・人間文化研究科教授)
司会:伊藤 るりさん(一橋大学大学院・社会学研究科教員)
参加記
2012年12月14日、鄭暎惠先生をお招きして公開レクチャーシリーズ第18回「外国籍女性たちの3・11『以前・以後』と改定入管法」が開催された。今回の講演では、震災「以前・以降」と呼ばれる移り変わりにおいて、外国籍住民がどのような状況におかれていたのかを、東日本大震災で被災した外国籍住民に対する先生ご自身の活動経験や資料から明らかにするとともに、2012年7月に施行された改定入管法がもつ意味や影響についてお話しいただいた。以下、三つの点に分けて要点を記す。
第一に、東日本大震災で被害をうけた外国籍住民についてである。震災における死者・行方不明者は住民基本台帳をもとに算出されていたため、何人の外国籍住民が被害をうけたか、正確な数値は分からない。外国籍住民総数のうち韓国籍・朝鮮籍の人々の割合が高く、中には独居老人や無年金生活者がいることも想定される。また、避難所生活では支援物資が届くかどうか、分からない中で精神的な不安を抱える人が多くいたに違いない。ある外国籍女性のケースでは、避難訓練の経験がなく、買い占めによる食糧不足で子どもに十分に食事を与えられず、周囲からも孤立し、母国の家族に迷惑をかけることを懸念して帰国することもできずに苦悩するという状況だった。震災をきっかけに、これらの外国籍住民が地域社会ネットワークにつながれたという見解もあるが、震災「以前・以降」で外国籍住民の状況がなにか劇的に変化したというよりも、むしろ以前からの深刻な状況が継続・悪化したと考えられるのではないか。
第二に取り上げられたのは、外国籍女性への支援のあり方についてである。日本での支援は、往々にして日本人主導のもとで支援が進められ、外国籍女性自身が主体的に支援活動に従事することはむずかしい。日本語能力が厳しく問われ、外国籍女性は当事者であるにもかかわらず、補助的、あるいは従属的な立場に置かれがちである。また支援者としての処遇も日本人と対等に扱われないことがある。「支援」という名の支配が生じる。これに対して、たとえば韓国では、移住労働者の労働組合は、現在、フィリピン人移住者が委員長となっていて、韓国人はあくまで通訳などの後方支援にまわっている。 なぜこのような差が生じるのか。いくつかの理由が考えられるが、問題を支援者内部の問題として捉えるだけでは不十分だろう。「支援者の貧困」の問題も考慮にいれなければならない。日本では、NPOや支援団体に対して、国は十分にサポートをしない。このため、日本人支援者も経済的に困難な中で活動を展開しているのである。このことが、支援の体制にも影響してくる。
最後に、新しい在留管理制度の施行の問題が取り上げられた。2009年に成立し、2012年7月に施行された改定入管法は、アメリカにおける住民管理システムを一部取り入れている。今回の法改正は、外国籍住民と日本国民の双方をより効率的に支配するための施策の一環であるにもかかわらず、日本国民の危機感は薄い。申請を拒否したり、規則に違反したりすれば厳しい罰則が科せられる。こうした状況を捉えるうえで、鄭先生はJ.バトラーの『生のあやうさ』を引用しながら、プライバシーや自由への権利を侵害するかたちで、近代国家が崩れ、専制的な監視社会が形成されつつあるとの見方を示した。
まとめとして、①「支援」という名の支配から解放されるにはどうすればよいか、②外国籍女性が自立し、「分離独立」をめざすとすればどう行動していくべきか、③もし近代国家が崩壊しつつあるのだとすれば、その後にどのような社会が来るのか、という三つの問いを会場に投げかけて講演を締めくくった。 ご自身がフィールドの最前線で活動された経験に基づき、詳細な情報も交えながらの報告は、臨場感にあふれ、論点も明快であった。講演後、フロアから「差別の問題は深刻きわまるのに、どうして暗くならずにやっていけるのか」との質問があった。「わかりませんねー(笑)」、「でも、本当に変わらないと思ったらやってられません」――こうした応答の中に、先生の実践や活動の背後にある熱い思いを、ひしひしと感じとることができる講演であった。
一橋大学大学院社会学研究科修士課程 田口ローレンス吉孝
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第17回 (2012年5月31日)
「Filipino Nurse Migration: Histories, Geographies, and Ethics」
講師:Prof. Catherine Ceniza Choy(University of California at Berkeley)
司会:貴堂 嘉之さん(一橋大学大学院・社会学研究科教員)
参加記
第17回CGraSS公開レクチャー・シリーズでは、カリフォルニア大学バークレー校のキャサリン・セニサ・チョイ先生が現在のフィリピン人女性看護師の国際移動に関する講演を行い、重要な分析視角を提示し問題提起を行った。チョイ先生はニューヨーク育ちのフィリピン系アメリカ人であり、かの女の母親はまさにフィリピンから移民してきた看護師である。このチョイ先生のバックグラウンドに基づく関心から、かの女は『ケアの帝国-フィリピン系アメリカ人史における看護と移民-』を2003年に出版し、数々の賞を受けている。
最初にチョイ先生は現代の医療従事者の国際的移動をめぐる状況と、その中でも顕著なフィリピン人女性看護師の移住に関して解説した。現在起こっている医療従事者の国際的移動は広範囲かつ多種多様であるが、一方で変化しない兆候が三つある。それは医療従事者の移動が貧困で植民地だった「南」から富裕で宗主国だった「北」へ向かうものであるということ。次に国際移動する医療従事者の大半が医者や看護師であること。最後に移住者はより良い生活を求めて移動してゆくということ。この潮流において、フィリピン人看護師の国際移動は最も顕著な現象である。だが看護師の国際移動が始まった20世紀初頭から今日に至るまで様々な歴史的変化を経ており、フィリピン人看護師と一口に言えども、実態は世代によって多様性に富んでいる。その中で今日のフィリピン人看護師の国際移動の特徴として以下の点が挙げられる。かれらは合衆国で働くのを望んでいるということ。そして多くは最初に中東諸国、シンガポールや英国で働き、合衆国で働くための必要経費を蓄えること、またその第三国経由のシステムが人材派遣会社によって制度化されているということ。かれらが合衆国で働くのを望むのは、一定期間働けば市民権を取得できるためであること。ならびにフィリピン人医療従事者の国際移動は合衆国とフィリピン共和国の政策によって促進されていることも、かれらの移住を語る上で重要な点である。
フィリピン人看護師は国際移動する医療従事者のモデルとして語られることが多い。しかし一方で、その移動に付随する頭脳流出や差別の問題は注目されてこなかった。フィリピンの看護師不足を示す証拠として2004年の調査は人口十万人に対し合衆国や英国は約八百人の看護師がいるのに対し、フィリピンでは約四百人しかいないことを明らかにした。さらにフィリピン人医師も合衆国で働くことを希望しているため、看護師資格を新たに取得し、フィリピン国外で働いている。問題はこれが単なる第一世界による人材の搾取ではなく、フィリピン政府の一向に成果を挙げない失業者対策や移民からの送金への依存体制がそれを加速させていることだ。次に看護師が強固に女性化され人種化されていることもポイントである。自律的かつ多芸でありながら男性または雇い主に従順な理想的労働者/母親/娘というイメージに基づき、フィリピン政府や職業紹介事業者は理想的フィリピン人看護師像を作った。その独立独行のイメージは各種メディアが看護師の直面する諸問題に注意を向けることを妨げたため、かの女たちの苦境は報道されてこなかった。しかし実際1960年代からフィリピン人看護師が合衆国で低賃金、無保険、無補償、人種差別、フィリピンと異なる英語の発音や表現、過重労働などの問題を抱えてきたことは事実である。以上の問題整理を受けて、チョイ先生は五つの政策提言を行なった。フィリピン人看護師の問題を歴史的文脈で捉えること、看護師の採用確保と仕事の満足度を決めるものを見直すこと、国際的な看護師採用の倫理的問題だけでなくプッシュ要因となる送出国の貧困、失業、政情不安についても考察すること、医療従事者の受ける抑圧に目を向け労働環境の改善を図ること、受け入れ国における医療従事者の移民の貢献を周知させるための制度を検討することである。
レクチャー終了後、フロアからは多くの質問がだされ活発な議論がなされた。歴史的文脈に関する質問として、合衆国の植民地政策によってフィリピンに看護学校が作られた理由、20世紀初頭にはフィリピン人男性看護士がいたにも関わらず数が減少した理由、合衆国におけるフィリピン人の社会的地位の変化などが問われた。また現代のフィリピン人看護師の状況に関するものとして、看護師自身の社会的地位や家族形態、医者が看護師に転身することが看護師のジェンダー規範に与えている影響、インドネシアの看護師との異同、フィリピン人看護師が受けた差別と黒人差別との相似性などが指摘された。全ての質問がジェンダー、あるいは人種の問題に関わっており、チョイ先生がレクチャーの中で提起した問題関心に沿うものであった。
本レクチャーは約二時間半にもおよび盛況を呈した。学部生、院生、学外生など学校の境を超えて参加者が集まり、質疑応答だけで一時間以上とった。これもチョイ先生の研究への関心の高さを示しているといえるだろう。現在チョイ先生は合衆国で行なわれてきたアジア系の子どもの養子縁組に関する研究を進められているそうである。多様な人間のアジア-アメリカ間の国際移動に関する研究領域は注目分野であり、チョイ先生の次回作Global Familiesの刊行が待ち遠しい。
一橋大学大学院社会学研究科博士課程 三好文
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第16回 (2012年1月20日)
「「人間天皇」の表象――「天皇ご一家」像から見えるもの 」
講師:北原恵さん(大阪大学大学院・文学研究科教員)
司会:坂元ひろ子さん(一橋大学大学院・社会学研究科教員)
参加記
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ第16回は大阪大学の北原恵先生を招いてのお話だった。北原先生は、アートとアクティヴィズムに関する著作を出版されるなど、美術、政治、そしてジェンダーの重層的な関係を対象として幅広い執筆活動をなさっている。今回のレクチャーでは、天皇一家の図像の変遷を、「国民統合の象徴的役割を担ってきた家族写真」(ブルデュー)という視点から読み解き、そこに見られるジェンダーの揺らぎを、豊富な資料をもとに提示されていた。
地震・津波の被災地や避難所を訪問する天皇一家、死者に祈りを捧げる天皇一家、正月の参観日に小振りの日の丸を左右に振る観衆に微笑む天皇一家。大メディアに頻繁に顔を出すこの特異な一家は、近年、女性天皇の可否をめぐる議論など、ジェンダー役割をめぐる議論がつねにつきまとう。しかし、ジェンダーとセックスの固定化(産む存在としての女性性)を前提として話題にされるばかりで、その前提となる天皇のジェンダー表象自体が問われることは少ない。北原先生は、明治以降の家族制度と天皇制の相互的に規定しあう関係に焦点を当て、当然視されている「ご一家」の図像のジェンダーが決して一貫したものでもなく、また当初から目的論的なものとして構築されてきたのでもなく、むしろ、新聞など付される写真=図像を通して、遂行的に想像され、構築されてきたのではないかと問う。レクチャーの構成としては、戦前の家族像の形成、占領期の「人間」天皇の形成、現在につながる戦後「ご一家」像の形成と、三つの次期区分をもとに、新聞に掲載されてきた正月写真を中心として(第二期に関しては、写真集『天皇Emperor』と雑誌『ライフ』をも読解対象として広げつつ)読み解く作業だった。
とりわけ、第二期の占領期における「幾重にも錯綜してジェンダー化される」天皇という論点は、現在の天皇制とジェンダー体制の錯綜する相互規定的関係を相対化する視点として重要だと思われる。敗戦直後のメディアで天皇の非人間的な暴力性が批判される中、中野重治が1947年の雑誌『展望』で発表した『五勺の酒』において「女性的なやさしさ」について描いているが、図像においては単純に女性化されるわけではない。例えば、戦前までは、立ち姿で鞘に手をあてている写真が主だったが、1946年の朝日新聞では、皇后とともに散歩する写真、女性が鶏に餌をやっている写真、などが登場する。あるいは1950年(当時裕仁46歳)には老人として孫と戯れているように表象されている写真が掲載される。このジェンダー表象を北原先生は、「女性化」や「老人化」など揺らぎがみられるだけでなく、家族と同一空間に描かれつつも女性領域と切り離されて表象されることで、完全な女性化を免れているという(マッカーサーとのツーショットにおける裕仁の限定的な女性化については、北原恵「表象の"トラウマ"―天皇/マッカーサー会見写真の図像学」森茂起編『トラウマの表象と主体』所収、新曜社、2003年で論じられている)。
唯一心残りがあるとすれば、最後に紹介され、また、ご自分でもまだ整理がついてないと語っておられた、植民地における「ご一家」写真と「内地」におけるそれとの連環について、より詳細に展開していただきたかった(これは質問しそびれた私の責任でもあるのだが)。北原先生は、『台湾日日新報』と『京城日報』の元旦新聞における皇后写真の使われ方の差異について触れ、「植民地といっても一括りにはできない」と指摘されていたが、天皇一家の図像、とりわけ、そこでの女性性の使用が、帝国の拡大期にいかに編成されてきたかを明確にすることは、ドメスティックな興味・関心にとどまりがちな天皇制議論の射程を広げることになるだろう。同時に、そのような作業は、戦争責任への批判的精神を喚起し続ける富山妙子氏の作品への、あるいは、大浦信行氏の天皇コラージュ作品が2009年沖縄県立美術館で開催された「アトミックサンシャイン展」において検閲にあったことで浮き彫りになった、天皇制、検閲、そして植民地主義のそれぞれの共犯的関係に対する何度目かの批判的検討への、アカデミズムからの応答となりうるのではないだろうか(北原先生はこの事件に関連して、以下の論集にも論考を寄せているので参照されたい。「<<遠近を抱えて>>の遠景と近景?戦後美術における天皇表象」『アート・検閲、そして天皇?「アトミックサンシャイン」in沖縄展が隠蔽したもの』沖縄県立美術館講義の会・編、社会評論社、2011年)。
一橋大学大学院社会学研究科博士課程 吉田裕
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第15回 (2011年7月15日)
「20世紀前半のモンゴル族(内モンゴル)女性の伝統と現代」
講師:包英華さん(内モンゴル大学・専任講師)
司会:坂元ひろ子さん(一橋大学社会学研究科・教授)
通訳:呉忠良さん(早稲田大学大学院文学研究科・博士課程院生)
参加記
包英華さんの今回のレクチャーは、中国のなかのモンゴル族という、エスニシティーの立場からアジアの女性史を考える視点が提起され、普段知ることのできない貴重なお話に知的刺激をうける内容であった。報告は日本語、質疑応答は呉さんの通訳によった。
包さんは、20世紀の初頭にモンゴル独特の伝統が「近代」のなかに組み込まれつつ女子教育が立ち上がり、そこで自立をめざした女性たちに注目する。当時の内モンゴル地域は清朝の支配下にあり、科挙も共通しており「漢化」する部分もあったが、モンゴル各部族はそれぞれの王族による地域統治を維持し遊牧民としての生活習慣や文化も続けられていた。清朝改革派の漢人官僚や、新たに台頭した日本などが、これらの王族との関係を持つようになったことが、近代的な女子教育が導入されるきっかけとなっていったという。
興味深いことは「高原の母」と呼ばれたモンゴル独特の伝統――遊牧民として外へ出ていく男性たちのかわりに、日常の生産活動のほとんどをひきうけていた女性たちが、次代を担う子どもを育てる母親として尊敬を集めていたこと――と、近代化をすすめる日本の「良妻賢母」及び中国の「賢妻良母」思想とが結び付いたという指摘である。
実はこうしたモンゴル族の近代的女子教育を最初にはじめたのは、内モンゴルでも北京に比較的近い東部のカラチン右旗(部族単位であり、清朝の行政区分でもある)の王族グンサンノルブであり、彼は1903年日本へ秘密裏に視察に訪れて、日本の近代教育に影響をうけ、下田歌子と面会、女子教育のための人材派遣を要請した。これに選ばれたのは日本の華僑学校・上海の女学校での教職経験者、河原操子であった。河原は日露戦争直前という情勢を反映し、半分は情報工作の任務を負わされた。内モンゴルへ赴任後、最初の女子学校である毓成女子学堂の設立と運営をまかされ、河原の帰国の際には3人のモンゴル女学生が日本へ留学し、彼女らの帰国後は各地で教育に従事したとのことである。20世紀初期からの日本の対外進出政策との関係の深さがうかがえる。
質疑応答では、「高原の母」について、チンギスハンの母親などの歴史的な人物モデルがあり、それを母から子へと伝えられるという話、内モンゴルでの研究状況に関して2005年にはじめてモンゴル女性のモダニティーをナミヤ氏が提起したこと、などが紹介された。また戦争と女性の教育のかかわりについては今後さらに検討が必要であり、包さんはナミヤ氏が触れていない女性たちの社会的な背景や「革命女性」のあり方について研究を深めたいとのことであった。このような研究交流が、相互に影響を与えあって、アジア地域におけるジェンダーやエスニシティーをめぐる多様な議論がさらに深まることを期待したい。
一橋大学大学院社会学研究科博士課程 鈴木航
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第14回 (2011年6月24日)
「ジェンダー、労働、ケア――フランスの研究動向――」
講師:エレナ・ヒラタさん (フランス国立科学研究センター 研究ディレクター)
司会:木本喜美子さん(一橋大学社会学研究科・教授)、伊藤るりさん(同上)
参加記
第14回のCGraSS公開レクチャーは、エレナ・ヒラタ先生を講師に招いて行われた。ヒラタ先生のご専門は、労働社会学・ジェンダー研究である。パリ・社会学・政治学研究センター内研究チーム「ジェンダー・労働・移動(GTM)」所属であり、現在は国際交流基金フェロー、一橋大学外国人客員研究員として来日され、日本の看護労働について研究されている。今回のレクチャーでは、フランスの労働社会学を拠点としたジェンダー研究の展開について報告していただいた。
フランスにおけるジェンダー研究には、ふたつの分析概念が並存している。ひとつは、1970年代に登場した社会学的概念の「性分業」(la division sexuelle du travail)である。今日では性分業研究は複雑化し、新たな課題も生じている(これが今回のレクチャー後半の課題である。)性分業研究は、労働社会学における労働概念そのものへ問い直しを迫った。一方で、2000年代以降の性分業研究におけるカルチュラル・スタディーズやクィア理論の導入は、ジェンダーの複数性や不安定性への着目を促し、従来の性分業概念の二分法的性格の批判もなされている。
もうひとつの分析概念は、「性の社会関係」(les rapports sociaux de sexe)である。これは英語のgenderに対応する概念ではあるが、あえてフランスではrelationとの違いを意識して使われている。rapportとrelationの区別はフランス語特有のものであり、rapportには「支配・抑圧の関係」という、英語のrelationにはない含意がある。これはマルクス主義の問題とする「階級関係」との係わりの中で、フランスの研究者たちがrapportという語を手放さなかったという背景があり、「性の社会関係」を「階級」や「人種」の問題との重なりにも留意しながら分析しようという試みとも関連している。ここにフランスのジェンダー研究の豊かさがあるようにも感じられた。
レクチャー後半では、フランスでの性分業研究の新たな課題として、グローバリゼーションと性分業、不安定雇用の増加、ケア労働と移民の問題の紹介がなされた。時間の関係上、ケア労働と移民の問題を中心にレクチャーは進行した。
意外なことに、フランスにおけるケア労働への関心の高まりは、2000年代半ば以降であったという。それまでも家事労働やヘルパーなどの職業研究の研究蓄積はあったものの、ケアの視点からの研究はあまりなされていなかった。例えば、ギリガンのIn a Different Voice(邦題『もうひとつの声』)の2008年の改訳は非常に話題になったものの、1986年に訳されたものはあまり注目を集めなかった。また、フランスにおける影響力の大きいケア労働研究として、ジョアン・トロントのMoral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care(1993=仏訳2009)があげられる。ここでは、ケアは活動であると同時に道徳的・倫理的なものであるとして、「ケアの二重性」への注目がなされている。トロントの議論は、ケアという労働への注目を促し、他の労働とケア労働の比較などの重要な問題提起をもたらした。
ケア労働研究の次なる課題は、性分業や家事労働研究との接続であるという。ケア労働の有償化や市場労働化のような可視的問題と、無償労働としての家事労働のような不可視的問題との関係などにも留意しつつ、ケアをめぐる問題の把握をしていかねばならないとのことだった。
また、ケア労働と移民、国際移動の問題は密接に関わっている。既に知られているように、フランスは移民社会である。女性移民はケアの分野で働こうとする者が多い。ケア労働の多くは低賃金の不安定就労であり、民族間格差の拡大の問題とも通底していよう。さらに、ケア労働のグローバル化は、私的領域や親密圏に属するとされてきた問題を、公的領域の問題として考える契機にもなる。この指摘は、ケア労働の国際的移転にともなう日本的状況を検討するにも非常に参考になるだろう。
一橋大学大学院社会学研究科博士課程 丹羽宣子
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第13回 (2011年2月4日)
「性と愛をめぐる不安と学び―大学生たちの今―」
講師:村瀬幸浩さん(一橋大学・講師)
司会:尾崎正峰さん(一橋大学社会学研究科・教授)
参加記
2011年2月4日に、村瀬幸浩先生をお招きして、公開レクチャーシリーズ「性と愛をめぐる不安と学びー大学生たちの今」が開催された。村瀬先生は、高校で教諭勤められた後、一橋大学で20年以上の長きに渡って「ヒューマンセクソロジー」の講座を受け持っておられる。今回はその「ヒューマンセクソロジー」の授業を通し、またその授業内のコメントペーパーやレポートなどから見えてきた、まさに生の「大学生たちの今」について報告をしていただいた。まず、「性」のもつ意味とは、「生殖性」、「快楽性」、「支配性」の三つであり、この三つは極めて近い、紙一重のものであると考えられとのことである。今回の報告では「快楽性」(快楽としての性)について学生に何を考えさせようとしたか、にしぼってお話をいただいた。
そもそも「快楽性」に関しては、性を考える上でも、無視され、軽視され、蔑視されてきたものである。しかし、一方で人間にとって「核」となるものでもある。そこで、性欲を"性的な快楽を求める欲求"と解釈し、性的な快楽を「生理的な快感」と「心理的な快感」に仕分け、マスターベーションとメイクラブの違いは何かを考え、そして「快楽」を性産業やAV任せにしてはいけないとお話された。「快楽」というとき、先に述べたように、ともすれば無視され、蔑視されがちなものである。しかしその結果、男性は思春期に、性産業やAVから性交渉や性の快楽というものを学ぶことになってしまう。これらから快楽を学ぶということは、創作された暴力的な快楽こそが、性の在り方であるということを視聴者に学ばせる。つまり男性には暴力的な態度を教え、強いることとなるし、女性にはその暴力的な態度を受けなくてはならない、ということを規定してしまう、ここからジェンダーバイアスが生み出されているというお話をされた。この性の幻想と現実を区別することが大切であり、そのためにこそ、「快楽」を性産業やAV任せにはしてはいけないと、力強く言及された。
一方で、ふれあう安心感、一体感、快感を生み出す「生」の共有共感こそが大事であるとお話された。からだ(性器をふくむ)や性を卑しむ偏見、誤解、先入観、意識を解き放つことだ大事であるとのことである。ここで、自らの性を卑しみ、忌避する傾向は、学生の反応から見る限りでは、男性の方が強いようであり、それはとても不幸なことであるということを指摘された。また、互いが楽しくなれるための意識と関係性の変革こそが、性の健康であるとされた。例えば、性の快楽といっても、手をつないでいるだけでも幸せである、というのであれば、それはそれで「性」の快感であり、健康であるという旨をお話された。これらのことは、「性的に健康であるとは」という13項目を挙げられている。(個別項目については、紙面の都合上割愛する)
その後、学生のレポート課題をご紹介され、学生の生の声からの報告や、女子大において性に関する授業を行った際に週刊誌に揶揄されたことから、逆にその週刊誌の記事を「君たちの周りは性に関してこんな意識である」という観点から授業の題材にされたという報告もなされた。
本報告を伺った中で最も印象的であったのは、「男性」は特に自らの性に対して卑しい、汚いと思わされている、という点であった。(もちろん男性に限ったことではないというのは当然であるが)このことと、報告や学生のレポートで触れられていた同性愛の問題は、交差する問題であるのかもしれないと感じた。私自身、思春期に自らの性を受け入れられなかった時期があり、性の快楽を感じることは「汚い」ことで、その都度後悔する、ということが往々にしてあったように思う。そうした時、少女漫画やBLによる自己肯定(藤本由香里さんなどが論じておられるが)「君は君のままでいい」というメッセージを繰り返し繰り返し浴び、自己を保っていたことを思い出した。村瀬先生はこの自己肯定のメッセージを、きちんと授業で実践され、学生に発信してきたのであろう。
今回のレクチャーシリーズは、村瀬先生のように、一人一人の様々な性に様々な時、場面で、出会い、向き合い、それぞれの価値観や状況に想像力を働かせ、お互いが豊かに生きられるように努力していきたいと感じた、素晴らしい報告であった。
一橋大学大学院社会学研究科修士課程 佐藤太郎
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第12回 (2010年10月20日)
「広告とアートからみた近代中国の女子スポーツ」
講師:游鑑明さん(台湾中央研究院近代史研究所研究員・一橋大学外国人客員研究員)
司会:洪郁如さん(一橋大学社会学研究科・准教授)
参加記
新聞と雑誌が民衆生活の一部になった後、計算高い商売人は新聞・雑誌の流通性を見越して、定期刊行物に様々な商品の広告を掲載し、その結果これら設計されたコピーライティングは、商品販売を促進する重要な方法となった。本講演では30年代から50年代にいたるまでの中国における広告、漫画、映画を主たるテクストとし、近代中国が商業広告と視覚媒体などの芸術文化を通して、女子スポーツがいかにして人々の日常生活に浸透したかを明らかにする。一般大衆が見てすぐ理解できるように、広告と視覚芸術は簡潔で分かりやすい方式で表現された。
当時、女子スポーツがイメージとして利用されるには、いくつかのパターンがあった。例えば、女子学生の運動する姿(強国強種)、有名なスポーツ選手(スターによる商品使用)、運動のポーズをとる女性(一種の視覚効果の表現)、女性が自転車にのりスケートする(自由の雰囲気)などが挙げられる。
一方、1930年代には、西洋製作のスポーツ映画が上映されると、中国の映画会社もスポーツ映画に取り組みはじめ、女子スポーツと関係のある様々な映画が製作された。「健康美」の概念が世の主流を占めていた時代にあって、これらの映像は二つの製作様態を呈した。一つには曲線美やセクシーさといった類の極めて性的誘惑の強いことばを使用した広告で、これに対し甚だ不満を感じる観客もいた。もう一つには、スポーツの普遍化と大衆化を重視したもので、褒め称えるに値するとして広く大衆によって肯定的に受け入れられた。このような真逆の観念によって、当時の大衆における受容のあり方がある程度明らかにされた。伝統と新しい価値観のお互いに衝突し妥協する様相は、変動し続ける時代の容貌と見ることができよう。
様々なスポーツ競技が盛んになるに連れ、女子スポーツも徐々に都会の流行文化と化した。女性もスポーツに取り組むようにとの宣伝が政府のプロパガンダや世論によって行われただけでなく、民衆の日常生活と関係する消費文化、芸術文化もまた競ってこの新たな潮流に乗ろうとした。制作者らは女子スポーツと関連する概念や流行語をその製品や作品に巧みに持込み、あらゆるところで消費者と視聴者に女子スポーツを目の当たりにさせた。別の角度から言えば、彼らは大衆の視点から、自らの女子スポーツへの認識に解釈を与えたのであり、それがまさに商業広告、漫画、映画なのである。
ただこれらの映像を見れば見るほど、それにはさまざまな疑問を喚起されられる。例えば、特殊な目的を持った女子スポーツ(武術など)は当時、社会の大衆の普遍的な支持を得られるのか。当時の女性自身はこれらのスポーツ、映像に対してどのような考え方を持っていたのか。その次世代の女性選手の服装、身振りはどこから学んだものなのか、或いは彼女らはそれを他に学んだのではなく、自ら流行のパイオニアたりえたのかどうか。30年代からの女性は社会で大いに活躍し、開放的な存在であったと言うことができ、現代女性とあまり差異がない様子である。この現象は女性スポーツ選手に限られるのか、或いはその時代に社会的に普遍な現象であったのか。もし女性側の角度からその時期の社会規範、中国政府の体育政策などをもう一度考察すれば、新たな視点を構築できるかもしれない。 最後に、これらの資料、映像を見る/読むと、当時女性映像の持つ魅力は男性のそれを遥かに凌ぐものがあると感じられる。特に商業的な活動の下で、女性のイメージは常に利用され、買い物の動機を強化させる効果を持つ点では、現代社会とあまり変わらない。それは30年代ころから本格な都市消費社会が生まれつつあったこととも関わっていようが、こうした女性イメージの消費/被消費概念の背後に隠された、社会学、情報学、心理学などの深い意味については、更なる探求が期待されよう。
一橋大学大学院言語社会研究科博士課程 黄耀進
CGraSS 公開ワークショップ(2010年7月2日)
「ジェンダー領域で学位論文を書く――『Racing Romance』を語る――」
講師:根本宮美子さん(ウェスターン・ケンタッキー大学社会学部・准教授)
司会:木本喜美子さん(一橋大学社会学研究科・教授)
参加記
2010年7月2日、根本宮美子さんを講師に招き、院生を対象とした公開ワークショップが開催された。根本さんは、テキサス大学オースティン校でジェンダーと人種問題に関する博士論文を執筆され、現在ウェスターン・ケンタッキー大学で教鞭を執られている。本ワークショップのテーマは『ジェンダー領域で学位論文を書く』であり、主に、博士論文のテーマ設定と研究をすすめる上で重要と思われることについて、ご自身の経験に基づいて語っていただいた。本ワークショップは、1)米国の大学院博士課程のプロセス、2)テーマ設定に必要な作業、3)博士論文執筆のプロセス、4)博士課程でやるべきこと、という4つのトピックに従って展開された。
はじめに、米国の大学院(社会学)博士課程の仕組みと技術的側面について説明いただいた。日本の博士課程と異なり、調査を開始する前に3年におよぶコースワークを修了させなければならない。コースワークとは、方法論や関連分野の授業の履修である。その後、研究計画書を提出し、面接試験を受ける。(面接試験の際に、食べ物を持参し先生方に振る舞うというユニークな儀礼に関するエピソードが印象的だった。)面接に合格し、IBPというインタビューの内容や倫理性、質問項目に関する承認を経て、はじめて調査にとりかかることができる。コースワーク、研究計画書の作成と提出、面接、IBP、調査、博士論文執筆、最終面接というのが、米国の大学院博士課程の大まかな流れとなっている。根本さんは、コースワークの利点として関連分野の知や様々な分野の専門家から助言を得ることができる点を挙げられた。他方、非常に長い期間(6、7年)を費やさなければならないは難点である。それに伴う金銭問題、解決策としてのリサーチアシスタントやテーチングアシスタントの実情などについても言及された。
博士論文の作成には、非常に多くの時間とエネルギーが費やされる。では、長年向かいあうことになるテーマはどのように設定すべきなのか。まず問うべきは、自分はその分野に関して本当に専門家になりたいのか、そのためにはどのような作業が必要か、という問いだという。テーマ設定に関し根本さんが強調されたのは、研究テーマを客観的にみることである。そこで必要となるのは、先行研究との関連から興味の対象を相対化し、社会科学全体のなかに位置づける作業である。その際、自身の研究の貢献を意識することも大切であるという。同時に、不可欠となるのは、自己の位置の認識と相対化である。すなわち、「~(日本人、女性)という立場である自分」がどのように対象にアプローチするのか。その問題点や将来の可能性を意識することの重要性について強調された。そして、なぜそのテーマに取り組むのかということを研究者としてだけでなく、社会で生きるものとして時代や社会を相対化しながら意識することが重要だという。
つぎに、論文執筆のプロセスに関し、ご自身の経験からお話いただいた。根本さんは、ラディカルフェミニズム、結婚や家族のあり方、当時の時代的背景へのご関心から博士論文のテーマを選定された。『Racing Romance』と題された博士論文では、アジア系移民と白人間の結婚において作用する権力構造をジェンダーと人種の視点から研究された。約1年間の質的調査では、42人にインタビューを実施している。論文は、指導教官との綿密なやりとりのなかで、一章づつ執筆されたという。ここでは紙面上、内容に関する事柄は割愛させていただくが、論文執筆プロセスにおける困難や論文に対する周囲の反応、米国における出版事情、についてもお話いただいた。
最後に、指導教官や大学院の友人、多くの専門家の助言を得ることの重要性について言及された。学会は、他者のサポートを得る場であるだけでなく、共同研究の機会を得る可能性に拓かれている。根本さんは、コミュニュケーションと伝達の場の活用、学会への積極的な参加を奨励された。質疑応答では、根本さんのご研究に関する質問や、IBP、所属学会、出版経緯の詳細に関する質問など様々であった。根本さんは院生からの質問全てに対し、丁寧かつ真摯な態度で応答して下さった。質疑応答のみならず、本ワークショップは全体を通して、講演者と参加者の間に誠実なやりとりが行われていたという印象を受けた。
本ワークショップに参加し、研究過程における自己の位置の認識と相対化する作業、研究意義をディフェンスし続けることの重要性を再確認することができた。一見すると、これらはごく当たり前のことのように聞こえるかもしれない。しかし、将来に対する不安や焦り、苛立ちや孤独感を抱えながら研究生活に挑む院生にとって、「常に(・・)研究意義をディフェンスし続けること」、「何年費やそうと素晴らしいものを創るという意識をもつこと」は決して容易いことではない。そのような意味で本ワークショップは、参加者にとって、自身と研究の関係(研究生活や態度、意識)を再考する良い機会となったであろう。『Racing Romance』の語り――根本さんの博士課程入学から論文の書籍化までのプロセス――を伺ったいま、少なくとも私にとって本著は、ジェンダー研究に貢献する重要文献というだけでなく、「博士論文を書くこと」それ自体に対する希望を感じさせてくれる文献となった。参加した院生の多くは、根本さんの語りに刺激され、自身の研究に再び希望を見出したに違いない。
一橋大学大学院社会学研究科博士課程 深海菊絵
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第11回 (2010年6月18日)
「イタリアのフェミニズム――「家事労働に賃金を」から「プレカリアート」へ」
講師:ジャクリーン・アンドールさん(バース大学ヨーロッパ研究学部上級講師、一橋大学外国人客員研究員)
司会:伊藤るりさん(一橋大学社会学研究科・教授)
参加記
今回のCGraSS公開レクチャー・シリーズは、イギリス・バース大学ヨーロッパ研究学部上級講師・一橋大学外国人客員研究員のジャクリーン・アンドールさんをお迎えした。ジャクリーンさんは、今最も注目すべき、若手研究者で、専門はイタリア地域研究とフェミニズム研究である。最近の研究「National Belongings: Hybridity in Italian Colonial and Postcolonial Cultures」などが挙げられる。さらに、イギリス・社会主義フェミニズムの流れを代表する雑誌 「Feminist Review」の編集委員としてもご活躍されている。ヨーロッパ地域の中でも「男女平等」と「規範意識」が絶妙なバランスを保ちながら入り組んでいるイタリアにおいて、フェミニズムの歴史的展開を「移住女性のケア労働」という分析軸を使って報告をされた。
イタリアにおけるフェミニズムの歴史的展開を見ることは、現在ヨーロッパの主要先進諸国が抱える「移住(移動する)女性」における再生産労働問題の核心を問うことを意味している。さらに、「歴史的に誰が再生産労働を担って、この先に誰が担うのか?」に一つの答えを提示している。それはどういうことを意味しているのだろうか。
イタリアフェミニズム勃興時期を1960年とし、1974年を大きな転換期として捉えていた。世界の潮流と同じくしての大きな転換期であるこの年に「主婦労働に賃金を」のスローガンが生まれたことが、その後のイタリアにおける「家事労働」(再生産労働)の概念規定に大きな影響を及ぼしたことが伺える。
現在イタリアは、他のヨーロッパ先進諸国と同じくアフリカ系移民を多数抱えている。その中でも、移民女性たちの多くはイタリア人家庭にて「家事労働(再生産労働)」を担っている。「家事労働」から"解放された"イタリア人女性は、社会の中で才能や努力を発揮することが可能になった。だが、それは問題の解決になったのだろうか?ジャクリーンさんは、「結局、女の中でもより地位の低い女に担い手が代わっただけではないのか?」という鋭くも、現実のやるせなさを、イタリアの現状に合わせて述べていたことが、大変印象的であった。象徴的な出来事として「女性問題を取り扱う会合においても、移住家事・介護労働者とイタリア人女性が同じテーブルで、問題を共有し議論することは少ない」ことをあげていた。この現象は、大変興味深く、再生産労働問題の核心をついているといえる。
大量の不安定就労層(<プレカリアート>)、移住家事・介護労働者の急増という状況のなかで、「女性」というひとつの枠では捉えられない問題の出現でイタリアのフェミニズムは新たな展開を求められていることを強調された。 誰かの解放が誰かの抑圧を前提としているのであれば、それは、本当の解放とは言えないことを改めて考えさせられたレクチャーであった。
一橋大学社会学研究科修士課程 永山聡子
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第10回 (2009年12月18日)
「ジェンダーと家族の可能性」
講師:牟田和恵さん(大阪大学大学院人間科学研究科・教授)
司会:木本喜美子さん(一橋大学社会学研究科・教授)
参加記
今日それ以外のあり方をイメージできないほど自明に思えたジェンダー家族が、牟田氏の歯切れのいい口調であっという間に解体されていった。清々しさのなかで覚えた一瞬の躊躇は、それがあまりにも「自然な」姿でそこにあることを物語っている。
近代以降の社会では、一対の男女の(性的)結びつきを核とする家族に特権性が付与され、排他的に存在してきた。そこではケアの唯一の責任者とされた女性(妻、母)が私的領域に囲い込まれて孤立し、生涯にわたって男性(夫)に経済的に依存せざるをえない。こうした家族の仕組みを特権化することこそ、男性優位の二元論的ジェンダー秩序をめぐる政治に他ならない。
これを「性的家族」と呼んで、それにかわるケアの単位としての家族のかたちを提示したファインマンを念頭に置きながら、牟田氏は新しい家族のイメージを描く。そこでは、従来の「家族」構成員を含む大人と子どもの小集団が、ケアの単位として社会的に特権化される。大人たちはケアを分担することで経済活動との両立も可能となり、ジェンダー家族では私的に賄われていた「保護」「扶養」が社会的に賄われることで男性の経済的優位は霞む。ケアと依存の悪循環から解放された女性にとって「愛情」によって夫をケアする理由はもはや存在しない。
さらに、「自然」に思えたジェンダー家族の根拠にメスを入れることで、「男女平等主義」の危うさもまた暴かれる。「親性」の男女平等は父親の経済的優位という前提の上に成り立っており、生物学的説明は後付けに過ぎない。「科学」の名を借りて捏造された「父性」は、「自然」という聖域に留まることを許されない。性行為における男女平等のまやかし、男性優位に働く公的年金制度…牟田氏の追究は続いた。非対称な二元論的ジェンダー化に内包された権力の温床としてのジェンダー家族の解体は、生殖技術の進歩とも連動しながらジェンダー/セックス/セクシュアリティの三位一体の体制を突き崩す。そしてケアの絆を中心とした新しい家族が、人と人とのつながりの新たな可能性を開く。
レクチャーを通じて、ケアの家族のイメージに対して抱いた解放感は何であったか。それは、ジェンダー化された存在として生きる呪縛から不完全ではあれ抜け出せる可能性を見出せたことであろう。確かに、多くの個人や社会にとってそれは非現実的であり、「不必要」とされるかもしれない。ジェンダー家族のなかで「満たされている」女性(男性)にどう説得的たりえるのか。しかし、そのことは牟田氏の理論を曇らせるものではない。われわれはジェンダー家族以外の家族のありかたを、既に知ってしまったのである。
一橋大学社会学研究科修士課程 鈴木楓太
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第9回 (2009年11月6日)
「宗教とフェミニズムの不幸な関係?―バックラッシュを超えて―」
講師:川橋範子さん (名古屋工業大学・准教授)
司会:深澤英隆さん (一橋大学社会学研究科・教授)
参加記
CGraSS公開レクチャーシリーズ第9回「宗教とフェミニズムの不幸な関係?―バックラッシュを超えて―」は、川橋範子さん(名古屋工業大学)を講師にお招きして佐野書院にて行われた。本レクチャーで主なテーマとなったのは、日本のアカデミズムにおける女性の宗教経験に関する研究の問題点、川橋さんも含めた日本の仏教界の女性たちの実践、そしてフェミニスト・リサーチの方法的立場である。順を追って整理していくと以下のようになる。
川橋さんは、女性の宗教経験に関する研究の立ち遅れとその理由を、宗教学とジェンダー・フェミニズム研究の二分野を対象に検討した。まず宗教学に対して、川橋さんは宗教学におけるジェンダー視点の導入への無理解を厳しく批判する。例えばどんなに信仰が厚く修行を積んでいても女性の地位は男性より必然的に低くなるといった、仏教界やキリスト教界などにおける女性の周辺化と不可視化を明るみにするためには、ジェンダーの視座を持つ宗教研究が必要である。にもかかわらず、特に日本の宗教学においては他の学問分野に比べてジェンダー視点の導入が依然として立ち遅れているという。宗教学者は、宗教を文化や歴史を超越した普遍的なものとみなす認識のもと、ジェンダー視点を用いた研究を、客観性や中立性を欠く偏った還元主義的な研究として批判し、ジェンダー視点の導入に強い抵抗を示してきた。しかし川橋さんは、宗教も文化的・歴史的なものであり、神のような絶対的存在の下に教義や儀礼を通じてジェンダー・人種などを作り上げる装置であると述べ、ジェンダー視点の導入のためには、客観性の神話を手放し宗教に対する認識を転換する必要性を説く。
一方ジェンダー・フェミニズム研究においても、宗教への一面的な理解が女性の宗教経験を捉え損ねていると川橋さんは指摘する。宗教をめぐるジェンダー・フェミニズム研究者は、宗教の家父長制的性格を批判してきた。しかしもっぱら宗教がジェンダー差別の現状維持に加担しているとするその論理は、宗教を男性中心主義の砦として切り捨てるのみならず、宗教教団内にいる女性たちをジェンダー差別に無自覚な、自立能力を欠いた存在へと回収してしまう。女性の自己理解を視野に入れ、行為主体としての女性の宗教経験を捉える必要性を川橋さんは主張する。
このようにアカデミズムが「宗教とフェミニズムの不幸な関係」に足を取られている一方、実際の日本の宗教界で現在起こっていることを、川橋さんは自身の学術的・社会的実践でもって次のように説明した。それは、宗教を家父長制として解体するだけでなく、それに新しい意味を付加し再生させるという試みである。このような例としてよく知られているのはフェミニスト神学の実践であるが、日本の仏教界においても、フェミニズムを通して女性を解放し平等へと導く真理のメッセージを宗教の中に再生しようとする女性たちが存在すると、川橋さんは述べる。仏教教団内において、宗教はジェンダー差別的であるという彼女たちの見解は「信仰を理解できていない」として退けられがちで、最近ではバックラッシュも起きている。しかし彼女たちは、フェミニズムを通して再生した宗教が社会の差別性を揺さぶるエネルギーを持ち、精神的な希求を満たすと信じるがゆえに教団内にとどまる。そして『ジェンダーイコールな仏教をめざして』を書きあげるなど、自らの声と意思でもって仏教を公正なものに作り直そうとしているという。禅宗僧侶の妻として禅宗の寺に住む川橋さんもまた、そのような女性の一人として内部からこの運動に携わっている。つまり、自らを含めた仏教界の女性たちについてのフェミニスト・エスノグラフィーを書くことによって、宗教学の男性中心的な語りを解体しつつ、仏教界の女性たちとともに仏教を再創造していこうとしているのだという。
共に宗教を変革しようとしている仏教界の女性たちとの関係について、川橋さんは、自分は「部分的当事者」であり、仏教界の女性たちの「代弁者」では決してないと述べる。このようにネイティブ・アンソロポロジストとしての自らの立ち位置により繊細であろうとする理由として、川橋さんは自身の多文化的背景に言及する。高校時代に渡米し、高等教育もアメリカで受けた(プリンストン大学で宗教学の博士号を取得)川橋さんは、自分が絶えず「東洋の女」として、より力のある存在によっていとも簡単に表象されてきた。そればかりか、「東洋の女」が第一世界のフェミニストたちの解釈を検証したり異議申し立てをしたりしても、多くの場合却下されるだけであったという。
このような自身の「原体験」と学術的・社会的営みをふまえ、川橋さんはフェミニスト人類学をはじめとしたフェミニスト・リサーチの基本理念を次のように明言した。研究者は、アカデミズム内の議論と現代女性の政治社会的苦闘の両方に応答責任があるということ。他者を一方的にまなざすことに安住することなく、他者からたえず見つめ返されるということを自覚すること。研究者が排除されている人々を代弁するのではなく、その人たちが語れる場を広げようと共同すること。そして常に自分がどこに立ち誰に向かって発話しているのかを問いかけていくこと、である。
以上が川橋さんの主なレクチャー内容である。会場からは、行為主体性を過度に強調して女性の宗教経験を論じることが孕む問題や、解放を必要とする宗教のあり方それ自体に内在する問題などが提起された。私自身は、川橋さんのレクチャーの中でも、「自らの声と意思でもって仏教を公正なものに作り直そう」とする川橋さんや仏教界の女性たちの営みが、フェミニズムをよりどころとしながらも、ジェンダー・フェミニズム研究や宗教学などアカデミズムの知をも問い返そうとする点が印象的だった。フェミニズムがアカデミズムの垣根を越えるものであり続けること、より多くの女性や男性、マイノリティによって絶えず鍛え直されていくことの重要性を改めて認識した。宗教を変えていこうとする女性たちの向こうには、そのように声をあげることなしに宗教界を生きる女性やマイノリティがいる。宗教界には属さなくとも、女性も男性もマイノリティも絶えず宗教と関わりあいながら日常生活を営んでいる。「宗教とフェミニズムの不幸な関係」の罠から抜け出るためにも、こうした人々の存在を常に視野に入れながら川橋さんや仏教界の女性たちの実践に学んでいきたいと思った。
一橋大学大学院社会学研究科博士課程 浦田三紗子
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第8回 (2009年7月17日)
「戦争とジェンダー ~フェミニストによる根源的問い直し」
講師:シンシア・コウバーンさん Prof. Cynthia Cockburn(英国 ロンドン・シティユニバーシティ・客員教授)
司会:足羽與志子さん(一橋大学社会学研究科・教授)
参加記
2009年7月17日、第8回目のCGraSS公開レクチャーシリーズとしてロンドン・シティ大学客員教授のシンシア・コウバーン氏による講演会『戦争とジェンダー フェミニストによる根源的問い直し』が開催された。労働過程のジェンダー分析の第一人者として知られるコウバーン氏は、60歳の誕生日を機に、その後の人生をフェミニスト平和運動と軍事化のジェンダー分析に捧げることを決めたそうだ。本講演もパレスチナから東アジア、コロンビアまで世界12カ国/地域?日本も含めそのどれもが軍事化の問題に直面している?でのフェミニスト平和運動へのアクション・リサーチに基づいている 。
本講演でのコウバーン氏の主張は、「家父長制的なジェンダー関係は戦争と軍事化の「根源的要因(root cause)」であり、それらを世代から世代へと継続させていく動員力である、そしてそうであるがゆえに、平和を追求するプロジェクトは既存のジェンダー関係の改革を志向する必要がある」とまとめられる。「根源的要因」という用語はブライアン・フォガーティの戦争の原因分類に基づいている 。フォガーティは戦争には、直接的原因(経済的な動機など)、先行的原因(ナショナリズムや自国の安全保障問題など)とともにそれらを支える根源的要因があるとする。戦争は、石油や国家の自治権の「ために」戦われるようなかたちではジェンダー問題の「ために」戦われることはない。しかしながら、家父長制は社会を戦争に向かわせ、軍事化を促進し、平和の持続を難しくするという意味で、戦争と軍事化の根源的要因であるとコウバーン氏は主張する。
コウバーン氏は、このことを自らが出会ったフェミニストの反軍事主義/反戦活動家たちから学んだという。コロンビアからイタリアまで、セルビアからインドまで、彼女が各地で出会った女性たちは平和主義とともにフェミニズムを自らの活動の根拠としており、自分たちの生きるシステムを「家父長制」と呼んでいた。そして、そのような軍事化の暴力と家父長制の暴力に脅かされている女性たちの立場(スタンドポイント)に立って眺めるとき、戦争は連続的な軍事化という姿をあわらにする。各地に広がるフェミニストたちは、他の地域の仲間たちと問題を共有し、自らが取り組むものが突発的な戦闘行為などではなく、連続的な軍事化であることを認識しているのだ。
この連続性こそが家父長制的ジェンダー関係が戦争の根源的要因となる理由である。コウバーン氏が出会った女性たちは、戦時にもいわゆる平時にも似たような形で男性による強制と暴力を経験していると述べる。家父長制は、男性性と権威、強制、暴力を結びつけ、女性性と男根中心的な関係を築く。そしてそのような結びつきは、軍事化の過程においてこそ隆盛する。そして、このことは男性性が戦争の前準備する(pre-dispose)機能を果たすだけではなく、男性性の達成のためにこそ軍事化が求められることを意味するとコウバーン氏は述べる。そして、そのように家父長制と軍事化が根源的に結びついているがゆえに、平和を追求するアジェンダにはジェンダー関係、特に男性性の変革が書き込まれる必要があると述べ、講演は終えられた。
以上の家父長制と軍事化の根源的な結びつきについてのコウバーン氏の議論は大変に刺激的なものであった。特に、主流派の戦争研究者たちが、戦争を「別の手段でする政治」であり、むき出しの暴力などではなく、制度化されたものとすることで、戦時を平時の延長線上におくこととちょうどパラレルに、女性たちが、戦時性暴力といわゆる平時での暴力を結びつけているという指摘には深く説得された。しかしながら、フロアからコウバーン氏のいう家父長制概念(氏は暴力を「戦場から町へ、街頭から寝室へ」と連続しうるものとして捉えている)が近年のフェミニストが問題としてきた差異を矮小化する危険性があるのではないか、という指摘もなされた。コウバーン氏からはいわゆる交差性(インターセクショナリティ)や男性性の多様性といった点についての言及もあったが、個人的には、家父長制と軍事化を(本質的にとは言わないまでも)根源的な結びつきに注目するがあまり、男性性や男性主体のそれこそ根源的な脆弱性と他者依存性を見失わないようにしたいとも考えた。そのような性質と暴力が男らしさの名の下に召還されることにもまた結びつきがあるように思うからである。軍事化とジェンダー暴力の連続性を見据えつつも、その具体的なプロセスの分析においては繊細な吟味が求められていると言えよう。
追記
講演後にはコウバーン氏と参加者を交えての懇親会が開催された。コウバーン氏は、私を含め学生のぶしつけな質問に、おそらく世界各地の紛争地域でそうであったように、真剣に向き合い、そして鋭い質問を返してくださった。一橋大学の教員と学生以外の多種多様な参加者を迎えることができたのもそのような氏のパーソナリティと研究スタイルに由来するだろうと感じた。
一橋大学大学院社会学研究科博士課程 川口遼
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第7回 (2009年4月28日)
「ジェンダーと女性心理学の功績と課題 ~今、何に注目をすべきか~」
講師:キャロル・エンズさん Carolyn Zerbe Enns Ph.D.(米国 コーネル大学・教授)
司会:柘植道子さん(一橋大学法学研究科・留学生専門教育教員、臨床心理士)
参加記
社会をある一定の方向に作り上げてしまうのが科学であるならば、それを変革するのもまた科学である。そんなことを考えさせる講演だった。
「心理学は、女性とは本当は何なのかについて言うことができない」。会の冒頭を、エンズ氏は1968年のNaomi Weissteinの言葉を紹介することから始めた。心理学は当時、男性を「標準」なものとする一方、女性を劣ったものとして扱い、その理由を生物学的な説明に求めていた。そうして「科学性」を通過した見解は、同時に男女の様々な差別を強化する一翼を担っていただろう。
Weissteinの批判から40年が経ち、心理学は大きく変わったとエンズ氏は説明する。初期のフェミニズム心理学は、男女に能力の違いがあるという「常識」に、調査を通じて異を唱えることに力を注いできた。けれども、やがて男女の能力そのものではなく、男女の置かれる社会的文脈の違い、そしてその文脈に添った形でのステレオタイプの内面化の問題を探ることの方の重要性が次第に認識されるようになってゆく。その様なステレオタイプの内面化こそが、実験の結果として得られる個々人の能力の違いをもたらすからだ。
例えば、ある実験の被験者に対して、そのテストは(a)ジェンダーによる差異はないという場合と、(b)ジェンダー差が確認されている、という場合とでは成績は異なるとエンズ氏は言う。実験の手続きのちょっとした差異で、「男女の能力には差がある」という「科学的証拠」が生まれてしまったり、正反対の知見が得られたりするのだ。
フェミニスト心理学のこうした努力により、こんにちフェミニストだけでなく心理学者一般に、心理学者はジェンダーバイアスや社会的文脈に意識的であるべきだと考えられるようになっている。これらの知見の成果は、2007年に発表された“Guidelines of Psychological Practice with Girls and Women”(「少女・女性に関する心理学的実践のためのガイドライン」)にも表わされている。
科学は社会へ知識を流通させるものだが、生み出される過程がどのようなものなのかによって、社会で共有される知識もまったく異なるものになる。そして、社会にどのような知識が流通するのかによって、社会のさまざまな領域での行為も変化していく。フェミニスト心理学の成果は、その意味で、間違いなく社会を変えていったのだろう。
ところで、私たちは一般に、科学者は自身の研究の成果によって社会を変えてゆくということのみを想像してしまいがちだが、先に挙げたガイドラインでは科学者個々人が社会を変革しようと実際に行動することが奨励されているのが興味深い。いったい具体的にどのような行動が想定されているのか聞いてみると、エンズ氏の答えは、「リサーチをする」ことに加え、「ボランティアをしたり、政治家に手紙を書いて意見を表明したりすること」だそうだ。
一橋大学大学院社会学研究科修士課程 佐藤圭一
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第6回 (2009年1月30日)
「台湾女性の相続権をめぐるジェンダー・ポリティクス」
講師:陳昭如さん(国立台湾大学法律学院・助理教授)
司会:王雲海さん(一橋大学法学研究科・教授)
参加記
今回の報告の概要について述べる前に,まずは報告者である陳昭如氏の経歴について簡単に紹介しておこう。陳氏は国立台湾大学の法律学院を卒業後、同大学の大学院へと進学、博士課程在学中にアメリカのミシガン大学ロー・スクールへと留学し、当地でフェミニズム法理論などの研究で日本でも令名の高いキャサリン・マッキノン氏の指導の下で法学博士号を取得した後に台湾へと帰国し、現在では国立台湾大学法律学系の助理教授を務めている。専門は台湾およびアメリカ合衆国の法制史やフェミニズム法理論、ポストコロニアル法学である。
本報告は、現代の台湾における相続制度をめぐるジェンダー・バイアスの存在を析出した上で、そうしたジェンダー秩序の下での女たちの抵抗の姿を描き出そうとしたものだといえる。報告の冒頭では、最近、台湾のメディアを賑わせた事件の紹介が行われている。それは亡くなった夫=父の遺産相続をめぐって、六人の娘たちが妻=母と二人の息子=兄弟を刑事告訴したという事件であるが、この事件の背景には,相続法上では男女同権が保障されているのにもかかわらず、女子には相続放棄を迫るという社会的抑圧の存在がある。
陳氏はこの抑圧の問題を論じるにあたって、かのじょが「二元論的な認識構造」と呼ぶカテゴリー化の具体的な内容について、「相続を放棄する娘―親孝行・無私―父権的伝統下における犠牲者―遅れた社会・法制度 対 遺産争いをする娘―親不孝・貪欲―父権制に挑戦する行動者―進歩した法制度」と定式化した上で、この定式化を乗り越えるための理論的な試みを行っている。その成果についての詳細な報告は、紙幅の都合で省略せざるをえないが、重要なことは以下の諸点にまとめられよう。
一つめは他家に嫁いだ娘たちをよそ者とみなすという、日本でもみられる典型的で排除的な文化的風習があること。二つめは娘による相続放棄を家族的共同体に対する忠誠心の表れとみなす考え方が根強く残っているということ。三つめは大部分の妻=娘が親の介護をするという社会的実態があるのにもかかわらず、夫=息子が介護の中心的な担い手となるのであり、したがって、遺産はそうした扶養の義務を担っている息子だけに相続されるべきだ、という考え方もなかなか変わらないということ。四つめは同じ女性ジェンダーに属する者でありながら、母と娘たちとの間でも厄介な対立がみられるが、アメリカの人類学者マーガレット・ヴォルフの「子宮家族」という概念を用いることにより、母による息子を通じた家族の支配という要因の存在を明らかにでき、その結果、こうした対立が生じる理由を説明しうるのだということ。そして最後は、法制度上の「平等」が達成されたはずなのにもかかわらず、社会的な不平等がなおも残存しているのはなぜなのか、という批判的法理論上では馴染み深い問題の存在だけではなく、一見支配的にみえる「構造」への服従を強いられているはずの被支配者たち(今回の報告では女性)がどのようにしてそれに抵抗しているのか、ということである。
残念ながら、当日は時間の関係上,最後の点について詳細に論じられることはなかったが、今後も陳氏の手によってさらに継続されるであろう精緻な判例分析と、フェミニズムなどの社会理論との接合により、われわれが法というものに対して抱いている固定的な観念から解放され、ひいては社会変革への途を切り拓くための契機が与えられることを期待したい。なぜなら、「フェミニズムはみんなのもの」(ベル・フックス)というように、女たちの闘いの成果はわたしたちみなが享受できるはずのものなのだから。
北海道大学大学院法学研究科博士課程 綾部六郎
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第5回 (2008年12月19日)
「“ホモエロティシズム”とポストコロニアル沖縄の関係」
講師:新城郁夫さん(琉球大学法文学部・准教授)
司会:鵜飼哲さん(一橋大学言語社会研究科・教授)
参加記
第5回の公開レクチャーは琉球大学の新城郁夫氏を講師に招いて行われた。新城氏は、現代沖縄文学を論じさせたら右に出るものはない批評家であり、研究者である。その鋭く豊かなテキストの読解によって、沖縄文学の読解可能性は、その都度、更新されてきた。具体的には沖縄文学を出発点として現代思想との豊かな対話をしつつ、他の研究領域との橋を架ける仕事をされてきた。とくにジェンダーとセクシュアリティの問題系は初期の仕事から問われ続けており、豊かな関係がきり開かれてきたといえるだろう。今回の報告はその延長にある。以下の参加記では新城氏の報告の要旨を中心にして、最後にごく簡単な感想を述べたい。
まず新城氏は問題意識として、テレビや映画など沖縄のメディア表象にはらまれている政治性への言及からはじめた。「沖縄」という表象は、さまざまなメディアによって女性ジェンダー化されて語られることがある。この語りの欲望の根底には集団自決や米軍基地の問題ともかかわる政治的暴力が潜在していることが指摘でき、現在の「沖縄」が置かれているポストコロニアルな政治状況を透かして読むことができる。そして、その有効性は認めなければならないとも語った。
だが他方で、この表象と政治の問題は、女性ジェンダーの動員だけではとらえきれないのではないのか、沖縄の女性ジェンダー化は、むしろ歴史的なスパンをとったとき、より大きくは男性間の欲望の交換、つまり、ホモソーシャルな権力関係を作動させるホモエロティシズムの問題系の内部にあるのではないか、と新城氏は指摘する。こうした観点から、戦後の沖縄を代表する小説家である大城立裕の自伝的小説『朝、上海に立ちつくす 小説「東亜同文書院」』の読解が試みられる。
「東亜同文書院」は1944年から敗戦にかけて大城が学んだ実際に存在した大学である。小説では主人公の「沖縄人・知名」、学友である「朝鮮人・金井」「台湾人・梁」「日本人・織田」の民族的な葛藤が、「沖縄人女性・新垣幸子」「中国人女性・范淑英」との関係の中で描かれる。しかし奇妙なのは、男性主体間の精液を授受するという「夢」が執拗なまでに反復されていることである。もちろん、この「夢」を「沖縄人・知名」の青年期特有のアイデンティティの不安と彼の民族的なマイノリティとしての葛藤から生じたものとして考えることは十分可能である。実際に、この小説はそのように論じられてきたし、それは作者が述べてきたことでもある。
しかし、新城氏はこれを作者の意図とは、「さかさまに」読むことを試みたいとする。この「夢」を、精神分析的にそこに「抑圧されたもの」を読んでいくのである。そこから注目されるのは、第二次世界大戦中の「大東亜」のビジョンが「同文」のカテゴリーで結び付けられた「植民地」の上海で見られた「夢」であるということだ。このとき、男性間の精液の授受という「夢」に抑圧された「大東亜」の理念の象徴としての「血盟の成立」という潜在的な主題系が浮かび上がってくる。
実際の小説では、人物配置において「血盟の中心」に「日本人・織田」が存在しており、また、「知名」は無意識的なレヴェルで「日本人」である「織田」との近さを何よりも気にしていることがわかる。そして、実は「知名」の「夢」の中には「織田」が隣に控えており、「知名」は彼をこそ欲望の宛先としていると読めるのである。そして同時にこの「中心」との近さによって生じる「序列化」の中で、「新垣幸子」「范淑英」など女性の登場人物たちは周縁化されてもいる。新城氏は、ここに明瞭な形でホモエロティシズムと結びついた男性間でなされるホモポリティクスの構図を見ることができるとする。
さらに興味深いことに敗戦を迎えた「知名」は、その動揺の最中に足を踏み入れた「上海のフランス租界」において「織田」とは違う人物との同性愛セックスを行い、そのことを恥じ、同性愛的欲望を代理的に否認する。このエピソードは以上の脈絡でとらえたときに、単に「若気の至り」といった言葉ではすまない問題が背後にあることがわかる。この恥辱化のメカニズムによってこそホモエロティシズムは否認され、それと軌を一つにして「大東亜」というホモポリティクスの理念が否認されるのである。新城氏は、こうした形で小説に見られるホモエロティクスの動員と否認において「大東亜」という歴史的なビジョンの忘却がなされているのではないか、と述べ、この読解を起点に「大東亜」の歴史の再考をしたい、それを夢のように考えているのです、と報告を締めくくった。
続いて質疑応答がなされた。きわめて豊かな質問のやり取りが50分近くなされていたが、発表と同程度に内容が豊かであったため、残念ながらこの参加記では割愛させていただく。しかし、小説の「夢」の読解を通じた新城氏の、別の意味で「夢」に満ちた読解は、ジェンダーの領域に限らず、多分野の研究者と学生の発言を喚起し、その場が熱気に包まれていたことは付け加えておく必要がある。おそらく分野は違う参加者のそれぞれの思考の間に橋が架けられ、さらに「夢」を見させる程に、充実した報告だったからだろう。また、おそらくそれは未来になんらかの応答という形で実を結ぶ「夢」でもあるに違いない。
一橋大学大学院言語社会研究科修士課程 小田剛
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第4回 (2008年11月29日)
「フェミニズムとリベラリズムの拮抗――新しい<家族>の可能性」
講師:岡野八代さん(立命館大学法学部・教授)
司会:平子友長さん(一橋大学社会学研究科・教授)
参加記
公開レクチャー・シリーズ第4回は、岡野八代さん(立命館大学)を講師にお迎えして、2008年11月28日に行われた。報告の題目は「政治『学』批判としてのフェミニズム―フェミニズム理論からの社会構想の可能性を問う」、報告・質疑応答は2時間半におよび、活発な議論が交わされる有意義な会となった。全体のテーマとされたのは、近代的な主体に対する批判、ケアの倫理をめぐる考察、社会的なるものの理論化、家族や社会の再構想などである。これらは社会科学の複数の分野でいま注目されている問題群であると思われるが、岡野さんはご専門の政治思想の立場からこれらの問題にアプローチされた。また、これまでに発表された論文や著書、関心をお持ちの運動などへの言及から、研究者としての岡野さんの思想の軌跡のようなものをかいま見ることができたのは、レクチャー・シリーズならではの貴重な機会であった(本稿内の「 」は報告レジュメおよび口頭での発表からの引用、『 』はレジュメ内で「 」に括られていた部分、〈家族〉の〈 〉はレジュメに従うものである)。
報告は岡野さんの近年の研究の大きな構想を支える三つのステップに沿って進められた――1)伝統的なリベラリズムにおける理想の市民像の批判、2)家族とケアの倫理への注目、3)フェミニズム理論からの非‐暴力的で自由な社会構想へ、である。なかでも中心に据えられたのは、2)の家族とケアの倫理をめぐる理論展開であった。
1)伝統的なリベラリズムは、自立した「自由な主体」や「責任ある市民」を前提にしており、また、個人の自由や愛の領域として私的・家内的な領域(家族や家庭)を囲い込んできた。この枠組みに対して岡野さんは、市民や国民への包摂過程や人びとの主体化の過程においてこそ、個々の生きられた経験や多様な生の構想が剥ぎ落とされる暴力がはたらくのではないかと疑問を呈し、さらに、リベラリズムが、(子どもを含む)依存する他者というものと、その他者への応答責任・ケアについてはほとんど語ってこなかったことを指摘された――ケアは政治的な領域の外部にあるものとされ、歴史的に周辺化されて「ジェンダー支配」のみなもとになってきたのである。
2)そこで岡野さんが注目するのは、家族の機能――多様な人びとや異なる時間性を「出会わせる場を提供する」機能や、「社会的弱者、公的な存在としては認められない者たちのケア」の機能――の再考である。それによれば、家に暮らすことは、ケアされる者にとって自分を受容され解放される場所を得ることであり、ケアする者にとっては、(生まれてくる子どものように)予め知ることのできない「『非決定の他者』」を受容し、そのニーズに応答して保護する場を作り続けることである。したがってこのような「依存と相互承認」による他者同士の平和な共存が日々実践される〈家族〉こそ、まさに「社会的な」場なのである。少し言い方を変えるならば、家族とケアの場は、ケアする者とされる者との多面的な非対称関係ゆえに、愛や共感だけでなく暴力の可能性をも潜めさせている。しかし、だからこそ倫理と責任が要請され、支配的にも暴力的にもならないかたちでの対話や同居や接触が重ねられ得る場なのであり、そのような〈家族〉は「公共のもの」・「開かれたもの」・「社会的なもの」として示されるのである。
3)「なぜ〈家族〉から出発することが国家権力に対抗することになるのか」。これは報告の最後に、今後の展開として改めて述べられた問いである。そこで示唆されたのは、開かれた家族を社会的なものとして捉え直す試みが、「国力や国史、国益の人質となってきた『家族』を取り戻す」ことにつながるということ、また、ケアの倫理が含意する非暴力と自由で平等な共存とは、国家の戦争や武力衝突を回避することや、暴力が起こってしまった後の傷ついた人びとへのケアへとつなげていくべきものであるということであった。
続く質疑応答は、より大きな・異なる視座から報告の位置づけが確認される運びになった。このことは、岡野さんの取り組まれる家族とケアの理論化の重要性を示していたと思われる。主要な話題を三つ挙げると、第一には、岡野さんの報告も含むケアをめぐる今日的な議論と、1970年代以降のフェミニズム理論とのより詳細な関係である(たとえばなぜ「家族」なのか、母性や母子関係をいかに再考するのかといった問い)。第二に、今日のグローバル化やケアをめぐる社会の動きを考慮するものである(たとえば、トランスナショナルな契約も含めケア労働の女性化や人種化が進むとともに、家庭や病院などケアの現場での暴力が止まないなかで、ケアの価値や愛といった論理を国家権力の側も用いていることへの懸念)。第三には、ホームとケアの再考における愛や希望の語り直し・非暴力の試み・倫理の要請などに関して、学問という領域がどこまでアプローチできるのかという問いである。
これらに対する岡野さんの回答では、母性や母なるものに関して、養育者という役割や家事の価値の読み替え・自然と「本質主義」とをめぐる議論の見直しの必要などが指摘され、〈家族〉という言葉の意味がさらに説明された――それは、ともに生活する人びと・住居・家事から、人びとの想いや心のなかにもある故郷、人びとと生活の記憶や語りなどを広く含意する「ホーム」であり、物質的なものと抽象的なものをつなぎ、横の(同時代の)つながりと縦のつながり(世代や歴史)の両方に開かれたものである。そのような〈家族〉の語にこめられているのは、これまで価値を貶められてきた(あえて言えば女性化されてきた)領域や言説化されずにきたものの回復であり、支配的なものを批判するとともに異なる視座をも提示するフェミニズムの創造的な可能性であるという(回答のなかで、ケアギバーの社会的地位の向上および手厚い経済的保障の必要性への言及がなされたが、これはフェミニズムの社会構想において国家との交渉ごとに含まれると言えるだろう)。
国籍や生活の場所やこころの在り処などのいくつものホーム。生物学的なつながりや血縁によるとは限らず、また、セクシュアリティやロマンスが必須なわけでもなく、友愛や意思や必要、偶然などによっても結ばれる人びとの関係性。そこで未知なる他者を受け容れること、同化や完全な理解を自明視しないこと、非対称であっても支配的でなく暴力的でもない関係をはぐくむこと。岡野さんが家族とケアという場で議論されたこれらの問題は、たとえば国民と移民と難民の関係や、(代理母を含む)母の身体における母と子の関係などにも共有され得ると思われる(国家なるものの再構想や語り直し、ひととその身体や生の捉え直しである)。また、これらの背景には、まさにこれまでフェミニズム理論が批判してきた近代的な主体や、家父長制的な家族とジェンダーの役割分業などを、具体的な歴史として可能にしてきた社会的・経済的な条件が変容しつつあるということがある。そこでは従来のジェンダーや人種、階級といったものもまたトランスナショナルに、そして植民地と帝国の複数の歴史を呼び起こしながらさらに組み替えられてきている。ホームとケアをめぐる議論を重ねていくことには、さまざまなフェミニズムの歴史化や継承の方法から学問的研究の自由や責任というものまでふかく関わっているだろう。
一橋大学大学院社会学研究科博士課程 松村美穂
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第3回 (2008年6月13日)
「領域分離とジェンダー史研究」
講師:姫岡とし子さん(筑波大学人文社会科学研究科・教授)
司会:坂元ひろ子さん(一橋大学社会学研究科・教授)
参加記
本講演では「領域分離」というキーワードをもとに、ジェンダーの壁を越えるべきという問題提起がなされた。姫岡氏はドイツを中心とするジェンダー史研究家であり、『ジェンダー化する社会-労働とアイデンティティの日独比較史』(2004)では、労働の場でジェンダーの差異化と領域分離が構築される姿を日独比較のかたちで提示している。こうした内容に加え、本講演ではジェンダーを基礎に、ネイションのなかに女性の存在意義を求める右派運動について語られた。
まずは姫岡氏がこうした問題意識にたどりつくまでの経験談から講演が始まった。姫岡氏が研究を始めたのはフェミニズム運動が盛んな頃である。氏は市民的女性運動穏健派と称されたボイマーに注目し、ドイツではじめての内務参事官というエリートである彼女がなぜ「女性の使命は母性」と主張したのか、母性にこめられた意味を考え始める。そこで領域分離を基礎に、女性の社会進出、女性にしか出来ない仕事へ焦点が当てられているのではないかと考えたという。
そこで氏は女性労働を論点とし、就業労働だけを切り離さず私領域も労働に関連することの重要性を感じる。また女性労働を男性中心の労働史の補完とするのではなく、男性=一般/女性=特殊という一般史の書き直しの必要性に取り組むようになる。たとえば、同じ労働を異なるジェンダーが担うとき、その労働にはどのような意味が付与されるのか。その疑問にこたえるため、氏は繊維工業織物業に関してのドイツ・日本の比較に着手した。
世紀転換期ドイツの繊維工業織物業は男性職工が手織、技能、職人、有資格者として扱われているのに対し、女工は逆に力繊維、機械織り、補助労働力、無資格として存在した。いっぽう、同時期の日本においてはやや趣が異なる。日本の繊維工業織物業では男性が手工業職人、技巧、強健で親方とされていたのが、女性の場合は一家の嫁が担う未発達な技術者であり、微弱な労働力としてとらえられていた。氏はここに労働のジェンダー化を発見し、本質的ととらえられることもある労働の中のジェンダーが、地域によって異なることを指摘した。
こうした労働のジェンダー化をさらに深く分析するため、氏は近代的な意味での女性労働者/男性労働者の差を明確にする女性保護法の制定に注目する。女性のみを保護し、女性=脆弱、意志薄弱、家庭中心、家政教育が本分だとする女性保護法は、男女両者の差異化をはかり強化するものである。こうした差異化により、行政や雇用者から女性は二流の労働者とみなされてゆく。氏はこれらの分析をとおし、しだいに言語を現実の反映ではなく、現実を作り出すものととらえるようになったという。つまり歴史資料を実体の反映としてではなく、テクストとして読む必要があるということだ。かつ実態調査においてもどのような問題設定によって調査をするのか「現実」の構築を考えるようになったのである。
こうした研究成果を出したのち、2000年以降はバックラッシュを契機として、姫岡氏はナショナリズムとジェンダーにも関心を抱き始める。姫岡氏はネイションの中でジェンダーによる居場所の違いと相互補完が行われていると指摘する。その例として、時代はさかのぼるが、ナポレオン戦争期のドイツにおけるジェンダーによる労働分担が補完的に機能した例を挙げた。そこでは女性がネイションのために社会活動を行うことが許され始め、領域分離にのっとった活動が行われた。男性は破壊、殺戮、先頭、征服、国家形成として語られ、女性は再建、治療、出産、維持、民族形成を担った。そして男女の愛と補完性が、ネイションの強化のためにいかに重要かが強調された。ここではまさにジェンダーの構築・強化は言説によってもたらされている。この例を見ても、必ずしも一定ではない体験・行為から生まれるジェンダーを考え、領域分離というキーワードをもとにジェンダーの壁を越える必要性をさらに感じるようになったという。
これら特筆すべき研究成果に留まらず、現在の問題意識につながるご自身の大学院生時代のご経験もふまえ、本講演ではより長いスパンでの問題意識が語られた。研究成果だけではなく、氏の研究生活の中で通底する問題意識や、大学院生時代の着眼点についても聞くことができたことは参加者にとっては非常に有益な機会であった。姫岡氏の「労働のジェンダー化」―世紀転換期のドイツでは繊維業の職工は主に男性が担い手であり、専門職とみなされていた―という指摘は、現在の女性労働を考える上でも非常に貴重な発見であるといえよう。歴史研究の中で様々な分野での「ジェンダー化」の過程を明らかにする試みは、固定的なジェンダー規範を覆すものとなる。姫岡氏の研究に学び、歴史研究の分野でジェンダーそのものの再考を行うことは、ジェンダー研究の深化に寄与するのではないだろうか。
一橋大学大学院社会学研究科博士課程 黄綿史
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第2回 (2008年1月25日)
「フィールドワークの『ジェンダー化』をめぐって-ジェンダー人類学の視点から」
講師:中谷文美さん(岡山大学社会文化科学研究科・准教授)
司会:石井美保さん(一橋大学社会学研究科・専任講師)
参加記
本講演において中谷文美先生が問題にするのは、フィールドワークの「ジェンダー化」である。フィールドワークの実践の中で、「ジェンダー」という差異が重要であるのは何故だろうか。中谷先生は、本講演において、文化人類学における研究者と対象者との関係性や他者概念を整理しながら、「ジェンダー」という差異を見つめることによって、フィールドワークやエスノグラフィーを再考する。
中谷先生は、フィールドワークの実践において、「ジェンダー」の視点は、「ただのトピック」であるのかという、根元的な問題から本講演をはじめる。中谷先生が問題にするのは、「調査者は誰であるのか、そうして、フィールドにおいて、どんな人であると受け止められているのか」という点である。調査者が男性なのか女性なのかという区別だけではなく、年齢やセクシュアリティ、階級や国籍など、調査者が「誰」であるのかということと、「ジェンダー」というトピックを扱うことは切り離して考えることはできないと述べる。
「ジェンダー」という視点は、フィールドワーカーがインフォーマントとの関係を築く上で重要であり、データの性質やエスノグラフィーにすら影響を与える。調査者は、自由にジェンダーを選べず、当該社会のコードに沿ってジェンダーを規定されている。しかし、ジェンダーは固定的なものではなく、フィールドでどのように振る舞うかによって、対象者との関係性を規定していくような実践なのである。
では、フィールドワークを重ねて描くエスノグラフィーに、ジェンダーという差異はどのように影響するのだろうか。
フェミニスト・エスノグラィーは、「一方的・搾取的な関係ではなく、対等で相互信頼に基づいた互恵的な関係を重視する調査と記述」をすることを目指しているという。しかし、女性だから男性に見えないものを描きうるというような、本質的な属性に還元してフェミニスト・エスノグラフィーを定義することは、ともすれば、女性を本質化し、女性の内部の差異を消し去ることに繋がるだろう。中谷先生はそれに対して、チャンドラ・モハンティの、「コモン・ディファレンス(共通の差異)」という概念を参照し、フェミニスト・エスノグラフィーは、単に女性同士の感情移入によって成り立たつものではなく、問う必要があるのは、何が共通していて、何が違っているのかであり、違いを見えなくしているのは何か、それでも共通していることは何かという問いであると述べる。
中谷先生が繰り返すのは、自己と他者の関係性をどのように捉えるかのという関係性への問いであるといえるだろう。女性や男性といった抽象的な概念ではなく、個別具体的な、顔を持った調査者と対象者とが出会うフィールドにおいて、絶えず関係性を切り結びながら調査し描くエスノグラフィーは、ジェンダーという差異をなおざりにしてはおけないような繊細さを必要とするだろう。その際、中谷先生は、フェミニスト・エスノグラフィーへの疑義として二人の研究者を取り上げる。ジュディス・ステイシーは、「研究者と対象者との間の親密性によって対象者を搾取」することは「二重の背信行為」であると述べ、L.アブー=ルゴドは、「自己と他者の連続性を強調することで相互理解を追求するべきではない」と述べる。二人の研究者は、研究者と対象者の差異よりも同質性を重視する方法への疑義を突きつけているのである。しかし、エンパワーメントを重視するE,エンスリンの実践に触れ、調査地の人々に対する政治的な応答責任を考慮しながらフェミニスト・エスノグラフィーを実践することについても触れる。
これまでの文化人類学研究が、男性偏向であり、男性中心的な産物であったならば、「中立な視点」は、もしかしたら、「男性の視点」の別名であるかもしれない。ジェンダー人類学が思い描くのは、「女性の視点」を取り入れることのみならず、漠然とした男性/女性といった固定的なジェンダーを再度、フィールドワークとエスノグラフィーの実践から問うてゆくような試みだろう。それならば、ジェンダー人類学の試みは、逆説的ではあるが、差異の総体として、フィールドを包括的に理解するための足がかりになるのではないだろうか。
早稲田大学大学院文学研究科・修士課程 岩川大祐
CGraSS 公開レクチャー・シリーズ 第1回 (2007年11月28日)
「オーラル・ヒストリーとジェンダー研究-イギリスにおけるオーラル・ヒストリーの展開を振り返って」
講師:酒井順子さん(成蹊大学ほか非常勤講師)
司会:濱谷正晴さん(一橋大学社会学研究科・教授)
参加記
CGraSSの第一回公開レクチャー・シリーズ「オーラル・ヒストリーとジェンダー研究-イギリスにおけるオーラル・ヒストリーの展開を振り返って」は、ポール・トンプソン著『記憶から歴史へ オーラル・ヒストリーの世界』の訳者で、オーラル・ヒストリアンの酒井順子先生をお招きしました。ポール・トンプソンの本は、濱谷先生の大学院ゼミで最初にテキストとして使用した思い出ある一冊でもあり、講演当時、私は日本仏教の抱える性差別問題を僧侶の配偶者たちへの聞き取りなどから描き出そうと収集したインタビュー・データを整理し、それを修士論文としてどう纏め上げようと悩んでいる最中でしたので、訳者である酒井順子先生のお話を聞くのを非常に楽しみにしておりました。
以下、講演の簡単な内容と、質疑応答での様子を記したいと思います。
オーラル・ヒストリーとは何か。それは、研究法、研究領域、民衆の歴史運動など、様々な領域にまたがって広がっていくもので、人間を軸に展開するヒューマン・サイエンスであると、酒井先生は言います。その研究法は、周辺領域のいくつかの研究法と組み合わされてつかわれ、本質的に学際的でもあります。しかしこの研究方法としてのオーラル・ヒストリーをめぐっては、「理論化されていない」との批判を受けることもありますが、トンプソンは『口述の歴史』の第4章において、口述資料の信頼性を以下のように説明しております。すなわち、文書資料および統計資料と口述資料は相互に入り組んでおり、文書・統計資料にもバイヤスや誤謬がある。また、口述資料は文書資料を残し難い人々の声、社会から隠されていた側面に光を当てることができる、と。口述の史資料は、文書・統計資料の下位に位置づけられるものではなく、対等に相互に参照・分析され得るべきであると。
また、イギリスにおけるオーラル・ヒストリーの展開を、酒井先生はMore history/Anti-history/How history/Public historyの4つにわけて考察されました。そのうちMore historyは文書記録を残し難かった女性や労働者層の埋没した歴史を救い出し、Anti-historyは口述の史資料から既存の定説を覆す力を持ち、トンプソンもここがオーラル・ヒストリーの醍醐味であると指摘しています。
講演では、酒井先生ご自身の研究内容や調査経験についても紹介がありました。何よりも驚いたのは、100人もの人にインタビューを行ったというご経験です。ジェンダー化されていた在英日系金融コミュニティの研究において、何人もの人の話を聞き、そこから、ジェンダー・アイデンティティとエスニック・アイデンティティが交差されながら形成される様に迫ったことを、ご自身の体験や当時思ったことなどを織り交ぜながらお話していただきました。この中で印象深かったのは「オーラル・ヒストリーをやる人は内気な人が多い」という一言です。会場は大爆笑に巻き込まれましたが、しかし、オーラル・ヒストリアンは人の人生を聞き、それに寄り添って研究を進めていきます。我が強くては、その人の人生に静かに耳を傾けることも難しいかもしれません。普通の人間のフリをして、一対一で聞く、また大事なことは、語り手を対象化しない緊張関係を保ちつつ話を聞く、このようにインタビューを重ねてきたという酒井先生のお話は、オーラル・ヒストリアン見習いとして学ばせていただくことがたいへん多かったです。
質疑応答でもオーラル・ヒストリーの手法、インタビュー・データの整理の仕方、フィードバックや調査倫理の問題、フェミニスト的アプローチの問題など、白熱した議論が展開されましたが、その全てを書くことは難しいので、強く印象にのこっているお話と、そこから考えたことを簡単に書かせていただきます。
酒井先生がインタビューの聴き取りにこだわるのは、そこには人々の主観が入り組んでいて、その主観の向こう側に見えるものを探しているから、というお話がありました。私も修士論文執筆にあたり、女性仏教徒たちにインタビューを何度も何度も繰り返したのは、教義経典解釈のような宗教集団内の上意下達的な理解からではなく、宗教活動の現場での女性たちの生きた声から彼女たちの仏教観の理解を試みる必要性を感じたからでした。宗教的エリート層にのみ独占された教義に偏重した議論に拘泥するばかりでは、活き活きとした日々の宗教生活に迫れないどころか、そこから排除されていた女性たちの声が無化されてしまうのではないか。その彼女たちのことばから、ダイナミックな「フェミニスト仏教」の萌芽に迫れないだろうか。そのような想いから女性仏教徒たちの声そのものに接近すべくインタビューを重ねていた当時の私にとって、酒井先生のお話は勇気付けられるような思いでした。
私がオーラル・ヒストリーの調査研究手法に惹かれるのは、やはり「人の話を聞く」という人間的営みからそれまで看過されてきた豊かなリアリティに接近する面白さに魅了されているからに他なりません。優れた宗教的感性を持ちながらもマージナルな存在として追いやられていた仏教女性たちの話を聞くたび、その面白さと力強さに圧倒され、夢中になりインタビューを重ねてきました。 私の手元にある『記憶から歴史へ』は、付箋や挿まれたメモで膨らんでしまっています。自分自身のインタビュー調査の計画と実施に関しては何度も読み返し参考としておりました。酒井先生の講演に参加できた幸運に、心から感謝しております。
一橋大学大学院社会学研究科修士課程 安達宣子